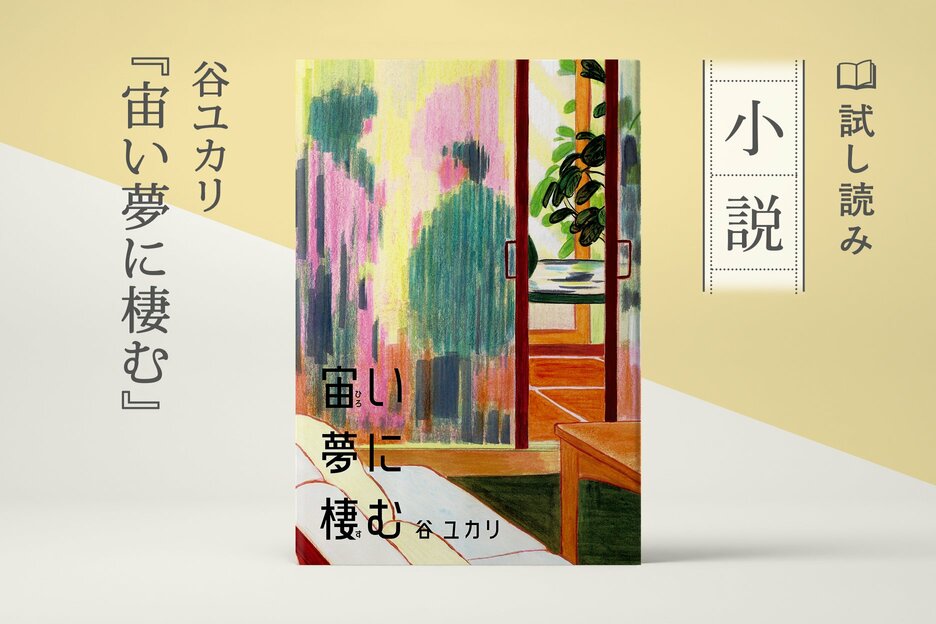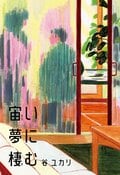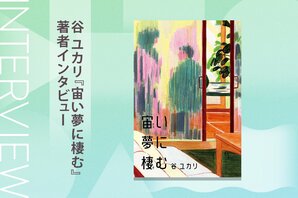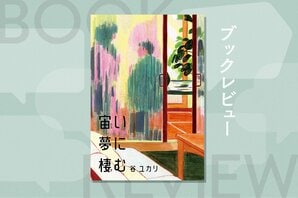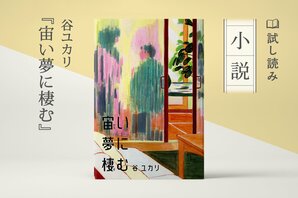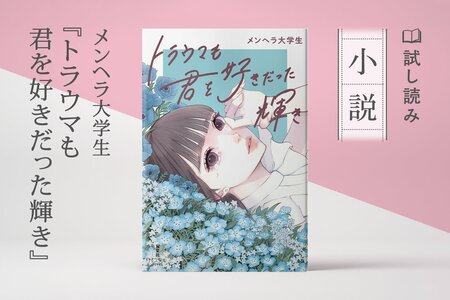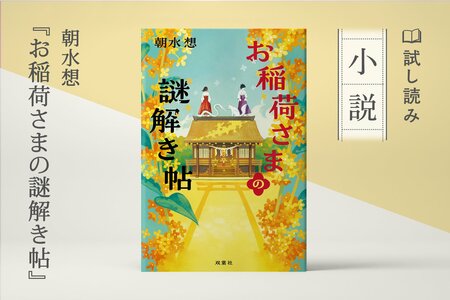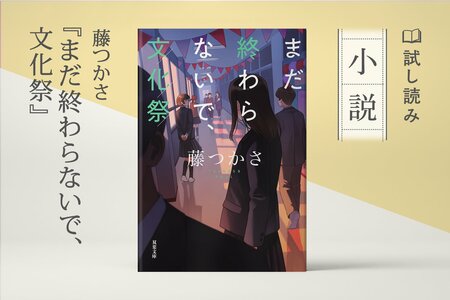*******
「絵里。世界児童絵画展、本当に素晴らしかったよ。君にも見せたかったな」
「一緒に行きたかったな」
伸朗はダイニングテーブルの私の隣に来て、図録を開いて見せた。
それぞれの作品の写真の横には、作者の顔写真と年齢、国籍が記載されていた。
「どの子にも、みんなとても素敵な世界観があるんだ。ほら、このトルコの少年が描いた家族の絵を見てよ。ドキッとするような配色でしょ」
「本当だ。個性的で魅力的。それぞれの表情がいいね」
「そうなんだよ。この子、特徴を捉えるのが天才的に上手いんだ。まだ九歳だよ」
「あ、この女の子の絵もいい。フランスの子ね。十一歳」
「うん、これも本当に素晴らしかった。家族の笑い声まで描かれているよね。それから、ほら、中国の子が描いた虫採りをする兄弟。八歳だって。どっちが本人かな。二人の好奇心と感動がガンガン伝わってくる」
「うん。何だか涙が出そう」
「どうしたらこんな絵が描けるんだろう……こういう風に考える時点で、もう違うんだろうな」
「違う?」
「どうしたらって考えること自体が違うような気がする。描くって、そんな頭で考えてやることじゃない。感動の反応として自然に出て来るんじゃない? 僕らは知識や経験に縛られている。一旦こういうものだと覚えてしまったら、目の前のものをそのままに受け取ることが出来なくなってしまう。やり方を学んでしまうと、体の中から溢れ出て来るものを無意識には出せなくなってしまう。もう、何も知らなかった頃には戻れないんだ……学んだ全てのことを捨て去れたら、どんなに自由になれるだろう」
「もう一度、子どもになってみたいと思うこと、ある?」
「ある。僕はもう一度、小さい人になりたい」
「もっと目線が低かった頃?」
「うん」
伸朗はダイニングテーブルの下に目をやった。
「昔、よくテーブルの下にもぐり込んで遊んでたんだ。テーブルや椅子の脚に囲まれて森の中に居るみたいだった。あの感覚が時々無性に恋しくなるんだよ。世界は広くて、高くて、綺麗で、不思議で、怖いものだらけだった。それなのに、今、怖いと感じているものが全然怖くなかった」
そう言った時の伸朗が好きだった。
扉を閉じた時の彼が抱く、その恐怖のことを語っているのだと思った。
*******
もしかしたら、私が口にすべき言葉は「どうして」ではなくて、「やっぱり」だったのかも知れない。夫をずっと放っておいたのだ。自分のことでいっぱいだったのだ。
伸朗の向こうの、顔の見えない女に「だって仕方ないじゃない。伸朗が人一倍淋しがり屋だと知ってたくせに」と言われたような気がして、頭を振った。体に力が入らず、ソファーに沈み込んでぼんやりと本棚に目をやった。『おせっかいねこミミ』の背表紙が目に留まった。
*******
結婚して四年ほど経った頃、伸朗は初めて童話の翻訳のチャンスを掴んだ。勤めていた会社からではなく、たまたま知り合った編集者からの依頼だった。
原稿の提出前に伸朗は私に読ませてくれた。
「ミミって可愛いわね。大切なお友だちの役に立ちたくて、一生懸命頑張る姿が本当に健気。でも、ちょっとピントがずれてて、実際には役に立つどころか、問題を複雑にしちゃってる。こういう人ってさ、現実に結構いるかも」
「いっぱいいるよ。善意しか持たない、ちょっと煩わしくて愛おしい人たち。でも、ミミのしていることは罪がなくて微笑ましいけど、実際の善意の人たちはなかなか厄介だよ。自分の善意しか見えていないから、相手の戸惑いに気づけない」
「善意でしてくれていることだから、文句も言いにくいしね。そういう時には、善意を受ける側の度量が試されるのかもね」
「君は優しいからなぁ、笑って受け入れるんだろうなぁ。いいママになるよ」
「伸朗も、とってもいいパパになると思う。このお話さ、読み聞かせのことも考えて訳してるでしょう」
伸朗の目が輝いた。
「分かる? 僕ね、子どもができたらたくさんのお話を読んであげたいんだ。その為にリズムを大切にしてる。声に出して読んだ時に読みやすくて、分かりやすくて、音も楽しい文章にしたいんだよ」
「成功してると思う。何だか朗読してみたくなる文章だもの」
「本当? 君にそう言ってもらえると嬉しいなぁ」
「いつかこのお話、私たちの子どもに読んであげたいね」
私たちはそれが実現可能な夢だと信じていた。だって、周りの人たちは自然に手に入れていたものだから。
*******
結婚後、数年しても妊娠の報告をしないと、私たちは周囲から不妊外来の受診を勧められるようになった。
出産を経験した友人が増える度に、助言が増えていく。不妊外来を受診して子どもを授かった友人たちは、他の人にもこの幸せを掴んで欲しいと、より熱心に話を聞かせてくれる。
友人たちの話は開けっ広げで、遠慮がない。どんな検査を受けるのか、どんな治療を受けるのか、どんなに辛くて神経のすり減る日々が待っているのかを事細かに教えてくれる。親切心からプライベートな質問をする。長くて先の見えないトンネルの向こうに、どれほど輝かしい幸福が待っているのかも伝えてくれる。
だが、子どもを欲しがる人の中には、その治療を自分の心と体に他人が土足で踏み込んでくるようで耐えられない、と感じる人もいる。最初に受けるという検査の内容を友人から聞かされた時、私はひどく気分が落ち込んで受診を怯んだ。伸朗は私の気持ちに理解を示し、私の盾になってくれた。
私たちは自然に任せることにした。
そうして月日は流れ、いつの頃からか、私たちはお互いに子どもの話題を避けるようになっていった。
父親になれなかったことを伸朗はどんなに残念に思っているだろう。想像するだけで胸が締め付けられる。そして母親になれなかったことは、私にとっていつまでも瘡蓋にならない生々しい傷だ。
もしも、相手の女性が「妊娠」していたとしたら……
伸朗が離婚を口にしたことも納得がいく。そして、その言葉が喉の奥に貼り付いてしまったことも十分理解できる。
その日の午後、梅雨のまとわりつくような小糠雨の中、伸朗はあの本とスーツケースひとつを持って、ターコイズブルーの愛車でどこかへ消えてしまった。彼が口にした言葉は「ごめんね。また連絡する」だけだった。
この続きは、書籍にてお楽しみください