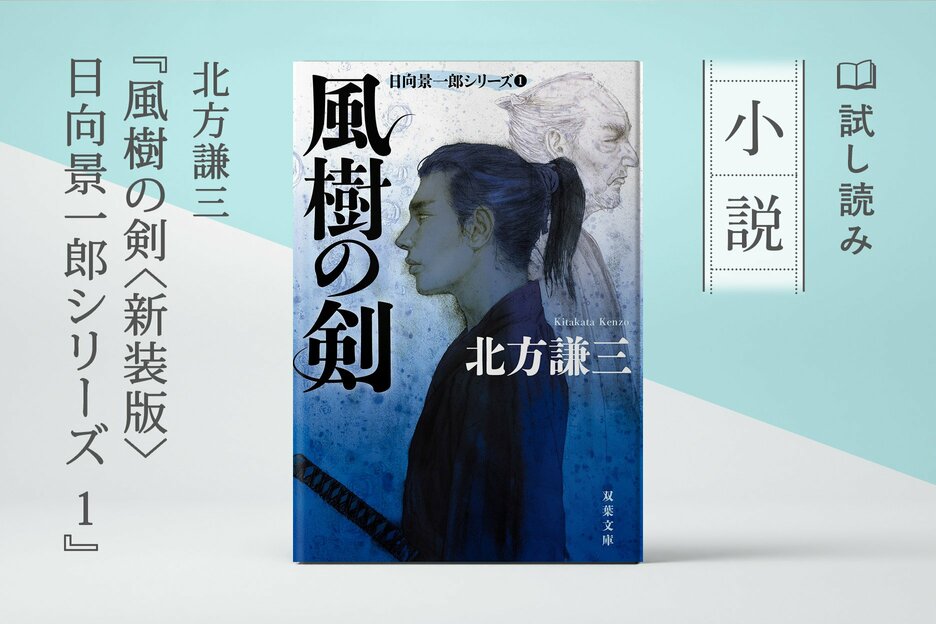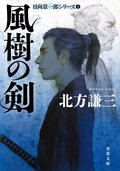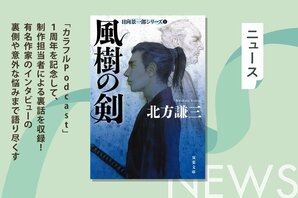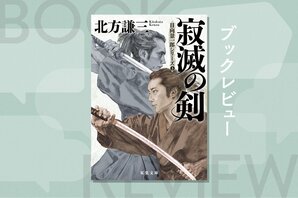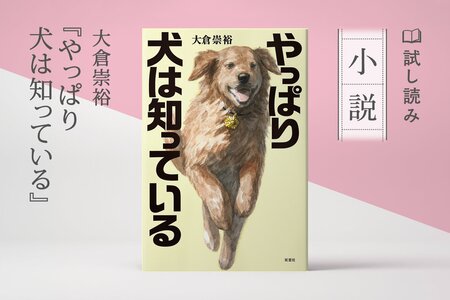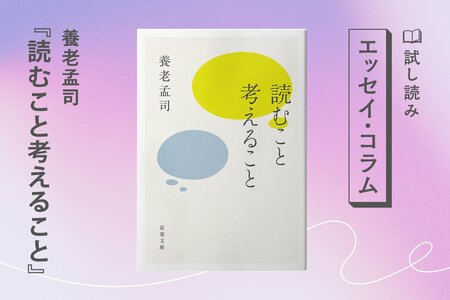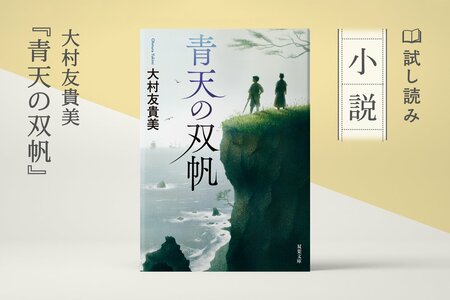芳円が、音をたてて粥を啜った。
なにか、いまわしいことがある。母の死については、祖父にも訊いてはならないことがある。昔から、景一郎は漠然とそう感じていた。そして、ことさら理由を知ろうとはしてこなかったのだ。
「死ぬのが怕いか、景一郎殿は?」
そう問いかけられて、景一郎は箸を止めた。
「いや、私も坊主だからな。たまには、坊主らしいことを話題にしたくなる」
「わかりません」
「わからぬとは?」
「死ぬことがほんとうに怕いかどうかは、死んでみなければわからないと思います。誰でも死にますが、生き還ってきて、死ぬことは怕くないと教えてくれる人間はいません」
「なるほどな」
「なぜ、そんなことを訊かれます?」
芳円は、景一郎を見てかすかにほほえんだだけだった。嗤われているとは思わなかった。芳円のやさしさのようなものが、景一郎を包みこんでいる。それがたまらなかった。やさしさほど、いまの景一郎にとって残酷なものはない。それを気色には出さず、景一郎はつとめて闊達に振舞おうとしていた。
「怕さを克服する方法を、持っているかね?」
「方法があるものなのですか?」
「さあな。私は、あまり怕いと感じたことはない人間なのだ。だから、教えてはやれぬ。鈍いのかもしれぬな」
「鈍くなれ、と言われているのですか?」
「違う。言葉通り、私が鈍いということだ。だから、鋭敏な人間の心の動きが、時として不思議に見えることがある」
やはり、嗤われているような気分にはならなかった。
「景一郎殿は、まだ若い。私がその歳頃には、暴れることしか知らなかった」
芳円が箸を置いた。
「母上を亡くされ、いま先生も亡くなろうとされておる。私などより、はるかに深く考えることがあろうな」
「祖父でも、死ぬのでしょうか?」
「死なぬ人がいるわけはなかろう」
「頭では、わかっているのです。それでもなぜか、驚きなのです」
「それでいいのだ。その驚きは、多分大切なものなのだろうと思う。先生でさえ、死ぬ。言われてみれば、私にとっても驚きだ」
話は終りだというように、芳円は腰をあげた。景一郎は、膳を片付けはじめた。
「村まで、使いを頼まれてくれんかのう。縫いものができあがっているころなのだ」
「わかりました」
あの武士に会うかもしれない、という思いがよぎった。また、斬りかかってくるだろうか。そうなれば、なった時のことだ。
景一郎は、椀を洗うと、すぐに村へ出かけた。青林寺から村まで、半里ほどの道のりである。村の近くになると、農家も散在していた。途中から街道に出るので、人の姿も多くなった。
村へ入る時、束の間ためらった。頭をよぎったのは、やはりあの武士の姿である。
気負いはなかった。怯えているのかどうかは、会ってみるまでわからない。村に入らないで使いを済ませる方法がないかは、考えないことにした。濡れた袴で泣いている自分とは、いずれはむかい合わなければならないのだ。それから逃げるのは、生きたまま死ぬことと同じだった。
教えられた家は、すぐに見つかった。
代金を払い、縫いものを受け取ると、景一郎は同じ道を帰っていった。
村のはずれのところに、十人ばかりの男が待っていた。構わずに、景一郎は歩き続けた。六人の男を、夢中になって打ち据えた。あれも、匕首などを出したからだ。素手か竹の棒だけなら、自分を失うことはなかっただろう。刃物が怕い。その先にある、死が怕い。そういう心の動きをしてしまうのだろう、と景一郎は歩きながら考えた。
十人ばかりが、道を塞いだ。賭場へ出入りする顔見知りも混じっていたし、この間打ち据えたうちの二人もいた。
「どういう顔で、歩いてくるかと思ったが、おっかねえな。食いつきそうな顔だ」
「道を、あけてください」
立ち止まり、景一郎は言った。
「それからもうひとつ、頼みがあります」
「頼みだってよ、おい」
ひとりが言うと、二、三人が笑い声をあげた。
「あなた方のためになる、頼みですよ。どうか、私に刀を抜かせないでください」
「抜けるのか、その刀を」
「そこの人」
まだ竹で打ち据えた傷が残っている二人にむかって、景一郎は言った。
「この間は、竹だった。傘の柄になる竹です。あなた方も、匕首や竹を持っていた。そして、六人もいたのに私の躰に触れることもできなかった。あの竹が、真剣であったらどうなるか、考えてみてください」
二人が、たじろいだようだった。
「おい、おめえにやられた政は、まだ立てねえんだぞ」
「いずれ立てます。いくら強く打ったといっても竹で、真剣ではありませんでしたから」
言って、景一郎は歩きはじめた。男たちが身構える。
「抜きますよ。私に触れた瞬間に、私は刀を抜きます。できるなら、抜かずに済ませたい。だから、頼んでいるのです」
歩き続けた。景一郎とむかい合う恰好になった男の顔に、怯えが走った。それだけだった。男たちの中を通り抜け、ふりむかずに景一郎は歩き続けた。
6
なにかが、近づいてきている。
芳円には、それがはっきりと感じられた。
青林寺は、いつもと同じ夕刻である。しかし、なにかが近づいてきていた。
暗くなる前に、芳円は境内をゆっくりと歩き回った。格別、意味があるわけではない。そういうことを、やる日もあればやらない日もある。
「かわりに、髭を当たってくれぬか」
離れのそばを通りかかった時、そう言っている将監の声が聞えた。景一郎が酒を運んできたが、いらないと言ったらしい。
離れを通り過ぎて戻ってくると、横たわったままの将監の髭を、景一郎が屈みこんで剃っていた。将監の髭は、ほとんど白い。
「いい月が出そうです、先生」
声をかけたが、将監は返事をしようとしなかった。そのまま、芳円は庫裡へ歩いた。
見ているしかあるまい。庫裡の縁に腰を降ろし、芳円は呟いた。宿業を負っている。はじめて寺を訪ってきた将監を見た時に、芳円が感じたことだった。
「般若湯は、私に回してくれぬか」
離れから戻ってきた景一郎に、芳円は言った。将監に出すはずだった酒が、縁に置かれた。
「めずらしいな」
「はい。一緒に旅をはじめてから、こんなことは一度もありませんでした」
「いやな感じがするな」
「私もです。村への使いから戻って、はじめて感じましたが、ずっと消えません」
「もうすぐ、陽が落ちる」
なにかが、すぐそばまで来ている。景一郎が、同じことを感じて言っているのかどうかは、よくわからなかった。
それ以上なにも言わず、芳円は酒を飲みはじめた。景一郎がなにをしているか、もう気にしなかった。
月が出てきた。満月に近い。酒はもうなかった。酔ってはいない。
境内の、虫の鳴声が熄んだ。風はあるが、空には雲がなく、かすかな樹木の戦ぎがそれを教えているだけだった。
五人か、芳円は思った。景一郎が、境内に立っている。庫裡と離れの中間あたりだ。気配を感じてそこに立っているとしたら、肚を据え直したと見てよさそうだ。
「日向森之助の、居所を教えてくれ。ここにいるのが、森之助の父親と伜だということはわかっている」
闇からの声だった。
「病人や子供を、斬ろうとは思わぬ」
その病人に呼ばれてきたのだ、おまえたちは。芳円はそう言いそうになった。
「日向森之助から、預かっているものもあるだろう。合わせて、それも頂戴したいのだ」
闇の中から、人影が五つ出てきた。
芳円は、縁に立ちあがった。
なにかが、闇の中を走った。そういう気がした。芳円は息を止めた。苦しくなるほどの間、なにも動かなかった。息を吐き、吸う。不意に、闇になにかが迸った。
芳円の眼が捉えたのは、ひとりの男を肩から胸まで斬り下げた、将監の姿だった。四人が、一斉に抜刀した。倒れかけていた男が、ようやくうつぶせに倒れた。ほんの短い間のことに違いなかったが、芳円にはひどく長く感じられた。
将監と四つの影は、固着して動かない。何度も、背中に冷たいものが走るのを、芳円は感じた。月の光まで、冷たかった。
景一郎が、喚きながら刀を抜いた。正眼に構えているが、構えたままで四対一の対峙の中には入れないでいる。
ひとりが動き、将監の横に回ろうとした。しかし、途中で凍りついたように動かなくなった。将監の構えは、下段である。ひとりの将監の方が、明らかに押していた。四人は、四人とも手練れである。それも、見ていて芳円にはわかった。
息を呑んだ。緊張が破れそうな気がしたのだ。しかし、固着は崩れなかった。息が苦しくなってくる。
ひとりが動こうとし、横に回りこもうとしていたもうひとりが、やっと将監の横の位置をとった。そう見えたのは、一瞬だった。
将監の刀が舞いあがった。それが振り降ろされた時、横に位置をとった男は、声もなく倒れていた。刀身の動きが、ひどく遅いもののように芳円には見えた。しかも、斬ったようには見えなかった。それでも、斬っているのだ。遅く見える動きは、多分錯覚なのだろう。斬られた男は、受けようとして刀を動かしかけただけなのだ。
三対一の対峙になった。
三人が、追いつめられているのがわかる。一歩も動いてはいないが、気持は追いつめられている。どこから、動揺しはじめるのか。芳円は、肩で息をしていた。
将監の躰が、月の光の中に躍りあがった。真中の男が、袈裟に斬り降ろされていた。首筋から男の躰に入った刀は、股の近くから抜けてきたように見えた。
異様な音がした。ぶつかるとか、打つとかいうような音ではない。将監の口から、血が噴き出す音だと、しばらくして芳円は気づいた。夥しい血を噴き出しながら、将監は構えを崩していない。ただ、静止していた刀が、別のもののようにふるえはじめている。
「景一郎」
芳円は叫んでいた。二人が、将監に斬りかかろうとしたのだ。
景一郎が、叫び声をあげて突っこんでいた。二人の刀が、景一郎の方へむかった。崩れるように、将監は膝を折っている。
いきなり、激しい動きになった。
二人が、次々に景一郎にむかって斬撃を加える。景一郎は、それをかわしていた。しかし、刀は正眼に構えたままだ。まるで見えない力に掴まれてでもいるように、刀だけが動かなかった。硬直した肩から先と較べて、景一郎の腰や膝は柔軟だった。斬られた、と何度も芳円は思ったが、景一郎はきわどくかわしていた。
月の光が、凄惨なほど必死な景一郎の形相を照らし出している。
芳円は、思わず縁から飛び降りた。
景一郎はまだ、刀を正眼に構えたままだ。それで動けば、当然隙が出る。そこに斬撃が来る。将監が、天稟と言ったわけを、芳円ははじめて理解した。どう崩れようと、ほんとうの隙は作っていない。一瞬、隙に見えるだけだ。すべてかわせる。つまり、無意識に斬撃を誘っている。
これで、刀を動かせれば、と芳円は思った。正眼に構えたまま動き続ければ、やがてはほんとうの隙が出る。なにしろ、斬撃を加えているのは二人なのだ。
しかし、どうやればいいのか。
「小便を洩らすな、景一郎」
とっさに、芳円は叫んでいた。瞬間、景一郎の全身が静止した。内側から、ふくらみはじめたように、芳円には見えた。すざまじい雄叫びがあがり、呪縛の縄が断ち切られていった。その音が、聞えるような気がした。
景一郎の刀が頭上に舞いあがり、溜めに溜めていた力を一気に吐き出すように、振り降ろされた。闇がふるえた。男の躰が、頭頂から胸まで断ち割られていた。脳漿と血を頭から浴びた景一郎が、もうひとりに斬りかかる。左一文字に胴を薙ぎ、二の太刀で両腕を斬り飛ばし、三の太刀で真向から斬り降ろした。
ほとんど人間のかたちをしていない物体が、しばらくしてから地面に倒れた。
芳円は、将監に駈け寄った。
吐き出した血が口につまり、すでに死んでいた。血まみれだが、将監の傷は体表にはなく、胸の中のものだった。
景一郎が、呻きをあげて屈みこんだ。刀がふるえている。左手が、柄から離れないようだ。
「落ち着け。鞘に収めてから、指を開けばいいのだ」
景一郎が、泣きながら右手で帯から鞘を引き抜いた。泣いている割りには、刀身の収め方は鮮やかだった。ようやく、左手も柄から離れたようだ。
景一郎が、地面に両膝をついた。月の光を浴びた周囲の情景を、しばらくぼんやりと見ていた。不意に、景一郎は狂ったように地面を転げ回った。椎の木の根方に腰をぶっつけると、その場でうずくまって吐きはじめた。
芳円は、将監の躰を抱きかかえると、離れの床に運んだ。悲しいほど、軽い躰だった。あの斬撃が、この躰のどこから出てきたのか、と芳円は思った。
行燈に火を入れ、晒で血をきれいに拭った。眼は閉じている。こうして見ると、どこにでもいる老人だった。
躰にも、着物にさえも傷はひとつもなかった。
「景一郎、井戸で血を洗ってこい。それから、昼間取ってきた小袖に着替えるのだ。あれはおまえのために縫わせたものだ。早くしろ。先生が亡くなられた」
外にむかって、声をかけた。
月の光の中に、景一郎が立ちあがる。まだ泣き続けていた。母親の血だな、と芳円は思った。日向森之助は、たとえはじめてでも、人を斬って泣く男だとは思えなかった。
満乃の、多感さを受け継いでいる。そう思うと、不意にいとおしさに似たものがこみあげてきた。森之助は、将監と諍をして、何度か家を飛び出した。芳円は、そのたびに満乃と二人で江戸を捜し回ったのである。
水を使う音がした。
芳円も、動きはじめた。事をこじらせて、代官所に睨まれると、面倒なことになる。本堂では、賭場も開かれているのだ。
景一郎が、新しい小袖を着てきた。躰に傷は受けていないようだ。顔面は蒼白だが、それはそれでいいだろう。
芳円は鐘楼へ行き、早鐘を撞いた。緊急なことは、そうやって代官所へ知らせることになっている。
離れへ戻ると、景一郎のそばに座った。
「境内で五人の男が斬り合いをやって、みんな果てた。理由はわからぬ。そういうことだぞ、景一郎」
黙って頷き、景一郎は立ちあがろうとした。
「吐きたくても、耐えろ。先生の前ではないか。三人を斬り倒したあの剣を、おまえは見たであろう」
もう一度、景一郎は頷いた。
役人がやってきて、境内が騒々しくなった。
芳円の説明で、役人たちは納得したようだった。斬られ方が、半端ではない。離れに病人がいることを知っている者は役人の中にも何人かいたが、その死と、境内の屍体を結びつけられはしなかった。景一郎がひとりで斬ったなど、さらに思いも及ばないだろう。
騒ぎが収まったのは、明け方だった。
「景一郎、おまえの刀は、私が預かろう」
「なぜです?」
「先生の遺言だ。これからは、この刀を遣うのだ」
「これは」
「来国行。先生が遣われていたものだ。山城来派の祖で、二尺六寸近くある古刀だ。知っていたか?」
「長いとは思っていました」
「これで、父を斬れ。そう言い遺された」
「父を。なぜです?」
「わからぬ。わかっているのは、これからはひとりだけの旅だということだ」
「父を、斬るのですか」
「そうしなければ、おまえの生きる場所が、この世にはないのだそうだ」
外は明るくなっていた。残っていた役人たちも、引き揚げはじめたようだ。屍体は、とうに運び出されている。
長い時間、景一郎は喋らなかった。
「もう行け。先生との別れは済んだであろう。旅の仕度は整えてある。路銀も、先生が遺されたものがある」
「わかりました」
「私は、この寺で待つ。おまえが、いつか帰ってくるのをな」
「いいのですか、帰ってきても」
「待っているよ」
二度小さく頷き、景一郎は腰をあげた。
「芳円殿、父と立合われたことは?」
「ある。勿論道場でだが、毎日のように立合っていた」
「強かったのですか、父は?」
「私よりはな。先生と立合うのは、見たことがない」
しばらく立ち尽していたが、諦めたように景一郎は庫裡の方へ歩いて行った。父を斬る気になったのかどうかは、わからない。将監に言われたままを伝えただけだ。
この続きは、書籍にてお楽しみください