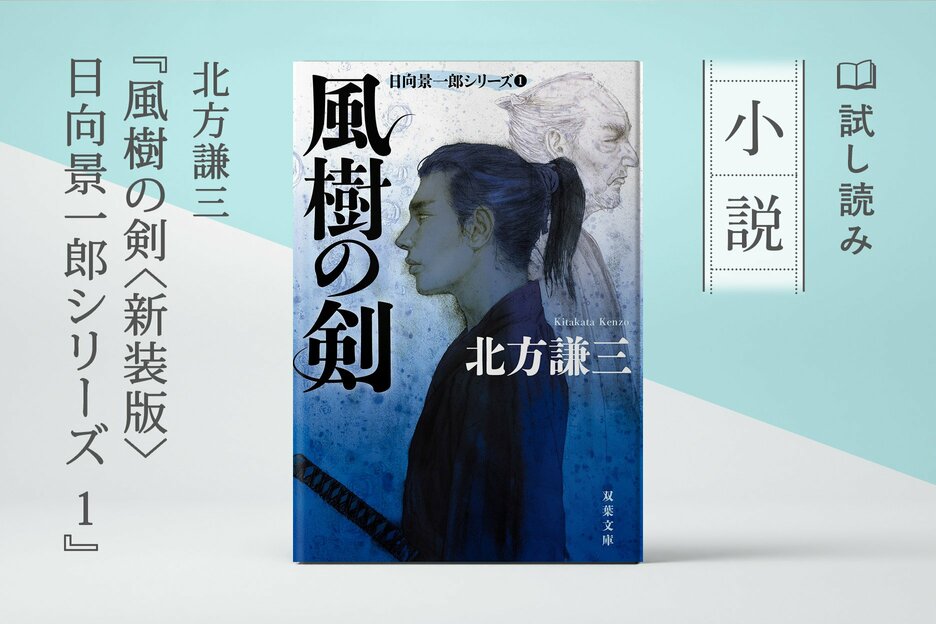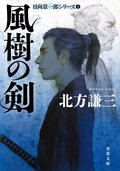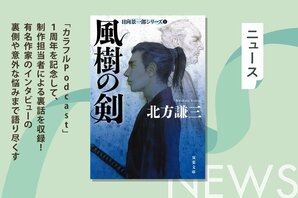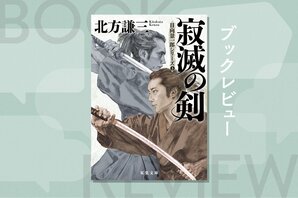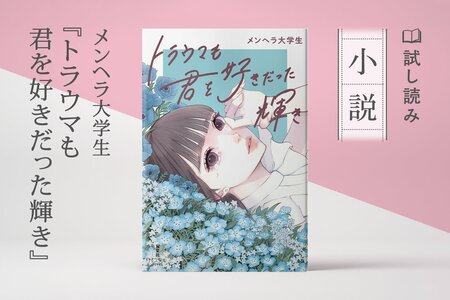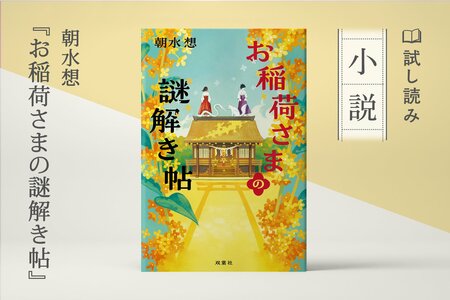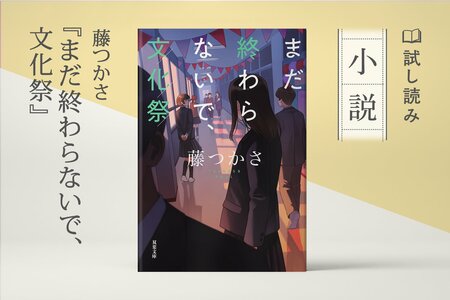4
芳円が入っていくと、将監は眼だけを開いた。芳円の方は見ようとせず、天井を睨んだままだ。
「このところ、具合がよろしいようですな」
「別に、よくはない。変らぬな」
「書状は、そろそろ先方に届くころだろうと思います」
「いつ届こうと、そんなことはどうでもいい」
「気になります。私はまだ俗から離れきれておりませんので」
「だいぶ、余計なこともしたようだな」
「わかりましたか」
将監は、死を前にして、五感を研ぎ澄ましているようだった。近づいてくる死の足音でも聞こうというのか。寝具から出た腕は、骨と筋と血管が浮き出して、ほとんど肉というものは見てとれなかった。それでも、半刻は太刀を構えて立っていられる。
気力とか執念とかいうものとは、また違うように思えた。倒れまいと決めたら、死んでも倒れはしない。将監は、自分をそのように作りあげたのかもしれなかった。芳円には、窺い知ることのできぬ、剣客の境地だ。
武芸がもてはやされていたころに将監が生まれていたら、一代の剣客として名を馳せたかもしれない。薬研堀の道場に通っていたころから、芳円はそう思っていた。時代が、剣客などを必要としなくなっていた。江戸には多数の道場があり、一見武芸が盛んだと思えなくもないが、そこは門弟を強くしてくれるところではない。そこに通えば、強くなったと思いこめるだけのことなのだ。
将監の道場では、弱いということをいやというほど思い知らせてくれるだけだった。
「やはり私は、景一郎殿を道連れになさるのは、やめられた方がよいと思います」
「道連れか」
「先生は、やがて亡くなられます。もう遠くないでしょう。景一郎殿は、十八です」
「あれには、剣の天稟がある」
芳円は、将監の顔から眼をそらした。将監ほどの剣客でも、孫の力量となると見誤ってしまうものなのか。
天稟どころか、ひどい臆病者である。二日前に、それを試した。
村にひとつだけある道場は、結構繁盛していて、そこの主とは旧知だった。この村で道場を開こうとした時、村人の中でただひとり、芳円に眼をつけてきたのである。立合を所望されたが立合わず、束の間睨み合っただけだった。
僧が剣を執ったとしても、不思議はなかった。僧で一流を立てた者も少なくない。しかし芳円は、出家の身であることを理由に立合を固辞し、道場の邪魔をすることも決してしないと約束したのだった。その時から八年、道場主との仲は続いている。景一郎の腕を試したのは、その道場主だった。
景一郎は、明らかに真剣に怯えていた。道場破りを多くこなしてきた男とは、とても思えない無様さだった。表情はひきつり、眼は恐怖に満ち、追いつめられると失禁したのである。
「臆病者だ、と思っておるな、喜重郎」
「確かに、そういうところは見うけられると思います」
「おまえには、あれの天稟はわかるまいな」
「わかりません。失礼ながら、先生の血を引いているとは思えないのです」
「おまえは、はじめての真剣の立合で、相手を倒した。それもひと太刀でな」
「私ですら、それぐらいは、と思います」
「おまえには、天稟はない。はじめての立合で、習った通りに剣を遣える者は、駄目なのだ。自分より弱い者には勝ち、強い者には負ける。そこまでなのだ」
いつになく、将監は饒舌だった。時々、口を拭う。大抵は軽い咳をしたあとで、やはり血の痰が出ていた。
「真剣を執らせると、あれは強いか弱いかもわからぬ。逃げ惑うだけだろう」
「どこに、天稟があるのですか?」
「臆病さにだ。臆病だから、相手の剣先を見切ろうとする。それができるようになる。人間が、なぜ臆病なのだと思う。生きのびたいからだ。他人よりずっと臆病ということは、ずっと生きのびたがっている、と言ってもよい。それで、身を護る術を覚える。生きのびたいという思いを、克服できるようにもなる。つきつめれば、剣とはそういうものだ」
「わかりません、私には」
「わからなくてもよい。ただ、真剣を握ったあれを、斬れる手練れは少なかろう」
追いつめられ、失禁するような男を、斬れる者が少ないというのかと、芳円は腕組みをしながら考えた。
ひとつ気になるのは、戻ってきた道場主の言葉だった。初太刀は別として、次の斬撃からは、本気で斬ろうと思ったというのである。なぜそう思い、なぜ途中でやめてしまったか、自分でもわからないと言っていた。斬撃は、ことごとく紙一重のところでかわされていたという。
将監が、軽い咳をした。痰を拭いとっている。胸の中が破れ、そこから絶え間なく出血が続いているという感じだった。
「死ねば、それはあれの天命ということだ」
「僧の私が言うようなことを、言われます」
「あれの天稟も見抜けぬ、馬鹿な男だ」
景一郎が失禁していたことを、芳円は言おうかどうか束の間迷った。死ぬ前に失禁するかしないか。それは肚の据り方で、失禁するようなら刀は持つべきではない、と芳円は思っていた。しかし、言わなかった。あの道場主の意地になったような斬撃が、ことごとくかわされていたのも事実なのである。不意にやめたのは、剣を持ってむかい合った人間にしかわからぬ、なにかを感じたからかもしれなかった。
自分は、ただ見ていただけなのだ。
「おまえは、十年わしの道場にいてくれた」
「よく、置いていただけたものだ、といまにして思います」
「その縁で、わしをこのように扱ってくれている。孫の心配までさせてな」
「先生らしくない、おっしゃり方です」
「恩に着ている」
言って、将監は眼を閉じた。
熱にうかされたような眼が見えなくなると、将監の躰はほとんど屍体のようにさえ思えた。そばにいて感じられる気が、まるでないのだ。
芳円は腰をあげ、庫裡へ戻ってひとりで考えこんだ。
武士を捨て、剣の勝負を捨てた自分に、なにかわからないものがあるのかもしれない。芳円は、一度将監に打ちかかってみようかと考えた時のことを思い出した。武士を、いや剣を捨てきっていないのかもしれない。中途半端なところで、自分は景一郎を見ようとしているのではないのか。
庫裡の裏では、景一郎が薪を割る音が聞えた。それが、どこか悲しげなもののように、芳円の心に響いた。
この二日、景一郎は働き続けている。なにもやることがなくなると、雑木林の中に駈けこんで、刀を振っている。腕ほどの太さの木を、斬り倒しているのである。切口を見ると、見事な刃筋だった。無理なく刀を遣えるのは、稽古によるのだろうが、芳円は驚嘆せずにはいられなかった。自分には、とてもこんなふうには斬れない、という思いがどうしてもこみあげてくる。
将監に仕込まれただけあって、技倆は一流なのだ。その技倆を、真剣の勝負では生かせないでいる。そこで生きてこそ天稟、と芳円には思えるのだった。
薪を割る音が、不意に熄んだ。駈け出して行くような気配がある。
芳円は、腰をあげて外を覗いてみた。斧が放り出されたままだ。
また雑木林に駈けこみ、憑かれたように木を斬っているのだろう。ちょっと不憫な気もした。腕を試そうとしたのは、自分なのである。それでも、いまからどうしてやりようもなかった。
芳円は、憎らしい仕草でちょっとうなだれると、庫裡の居室へ戻った。
5
景一郎は、じっと祖父の姿を見ていた。
毎夜、境内に出て刀を構える。やめてくれと言えば、叱られるに決まっていた。だからいままで、あまり気にしないようにしていた。
それが、このところ違ったものに見えてきた。祖父は、ただ刀を構えているわけではない。なにかと闘っているわけでもない。早く死のうとしているわけでもない。
なにか、掴みかけているのだ。それはまた、剣の極意とも違う。
祖父の躰からは、殺気も覇気も感じられなかった。もっと根の深いところで、景一郎の心をゆさぶるなにかがある。それを見極めようとしても、なにも見えてはこないのだった。立っている姿を、ただ見つめているしかなかった。そうすることが苦痛ではなく、むしろ意味のあることに思えた。
いままで、修行ということについて、考えたことはなかった。祖父が言うままに、竹刀を執り、振っていた。道場では、ほとんど負けることはなくなった。それでも、修行を積んだということではなかった。もの心がついたころから竹刀を持たされ、八歳で道場の板を踏んだ。これまで、竹刀を振ることが生きることだったのだ。それは修行でもなんでもなく、大工の子供が鉋の扱いを自然に覚えるのと似ていた。
道場破りも、結局は同じことだったのだ。真剣の勝負とはまるで違う。
微動だにしない祖父の姿を見つめながら、景一郎はそんなことを考え続けた。
やがて祖父は、刀を鞘に収め、静かに床に戻ってきた。
なんのためにやっていることかは、やはりわからない。わかる必要もないのだ。言葉で言えるぐらいなら、祖父も重病の身をおして無理なことはしないだろう。
やってみて、わかることがある。真剣を抜いて、ただひとつわかったのがそれだ。わかったことはあまりに惨めで、思い出したくもなかった。思い出さなくても、心にしみついてしまっている。
床に横たわった。隣の部屋から、祖父の気配はまったく伝わってこない。庭の秋の気配だけが、強くなった。
つん、と躰になにかが走った。全身に粟が生じていて、それがひくと冷たい汗が残った。それだけのことだった。汗も、やがてひく。ここ数日、しばしば見舞われていることだ。いまは、じっとしたままそれが通りすぎるのを耐えることができる。
死に身を晒してみることが必要なのではないだろうか、と景一郎は考えはじめていた。真剣が怕いのではない。死ぬことが怕いのだ。生と死の、ぎりぎりの境のところまで、自ら踏みこんでみる。一歩誤れば死、というところを歩いてみる。そうやって克服できる恐怖感かどうかは、わからない。結局は、死ぬことでしか克服できないことかもしれないのだ。
眠った。考えているうちに、眠りに落ちた。眠ってしまった自分が浅ましいと、眼醒めた時に景一郎は感じた。
縁に出て、境内に降りていく。裸足である。秋の夜明けは、快いほどの冷気に満ちている。
景一郎は、腰の刀の鞘を払った。
いつものように、すぐに素振りには入らなかった。
正眼に構え、闇を凝視した。
闇のむこうに、見えてくるものはなんなのか。はじめは、さまざまな人の顔が浮かんだ。八歳の時に、いなくなった父。十歳の時に死んだ母。道場破りで立合った道場主たち。祖父との旅で出会った人々。絡んできた、青梅村の男たち。いきなり斬りつけてきた武士。そして芳円。祖父。
顔のむこうに、また別のなにかがあった。
眼を凝らすと、それは自分の姿でしかなかった。袴を濡らしながら喚いている、弱々しい男の姿。それから、すべてが闇になった。
気づいた時、周囲は明るくなりはじめていた。射しはじめた光を斬るような思いで、景一郎は一度だけ刀を振った。朝の空気が鳴る。光が交錯する。
全身に、つんとなにかが走った。正眼に構えたまま、景一郎はそれに耐えた。
なにかが見えた。景一郎は、とっさにそれに斬りつけた。空気が鳴っただけだった。ゆっくりと、静かに息を吐いた。二度の素振りだけで、全身に汗が滲んでいる。
朝の粥。いつもの通りだった。
祖父は、箸をつけただけで椀を返してきた。その間は床に端座していて、横たわると急に病人らしくなる。
「一緒に、粥を啜らぬか、景一郎殿」
離れから椀を下げてきた時、いつもよりは長い朝の勤行を終えた芳円が声をかけてきた。わざわざそう言わなくても、朝食はともにすることが多い。
「お父上が、なぜいなくなったのか、景一郎殿は知っているか?」
膳を挟んでむかい合うと、箸を取りながら芳円が言った。
「芳円殿は、父をよく御存知ですよね」
「そうだな。十年近く、一緒に稽古をした。だから知っている、とは言えぬかもしれぬ。いなくなった時の事情は、実際に知らぬ。私はその少し前に、斬り合いで人を殺した」
「父がいなくなってから、私は道場へ出るようになりました。それまでも、祖父に竹刀の扱いは仕込まれていましたが、道場に入ることは許されませんでした」
「景一郎殿を、よく見かけた。大抵は、母上に手を引かれておられた」
景一郎は、高久喜重郎といったころの芳円を、憶えてはいなかった。景一郎が道場の板を踏んだ時は、すでにいなかったということになる。
道場で、はじめて門弟のひとりとむかい合った時、恐怖などはなかった。すでに、竹刀の痛みは祖父から教えられていたのだ。父になにかを教えられた、という記憶はない。
「あれから二年で、母上は亡くなられたそうだな。その時、私はもうこの寺にいた」
「父がなぜいなくなったかを、祖父は語ろうとしません。母が生きていれば、語ってくれたでしょうが」
「病か?」
「はい」
嘘だった。母は、懐剣をのどに突き立てたのだ。景一郎は、それを見ていた。理由は、いまもわからなかった。
『風樹の剣〈新装版〉 日向景一郎シリーズ 1』(第一章 斬撃)は全4回で連日公開予定