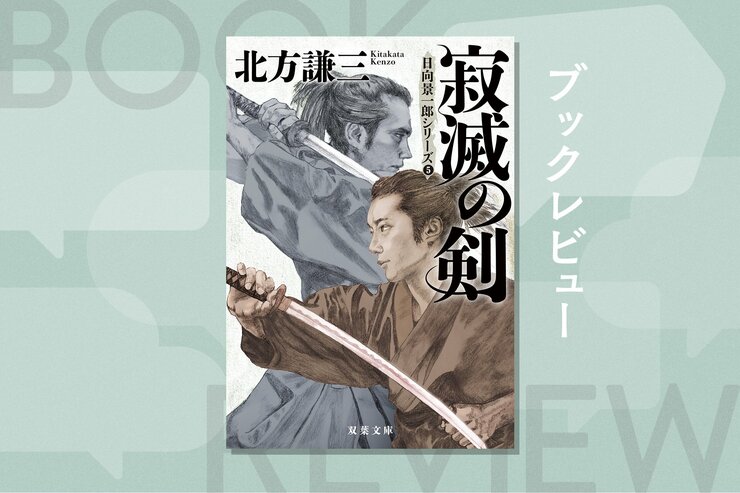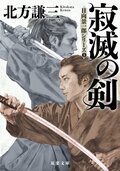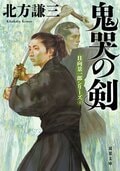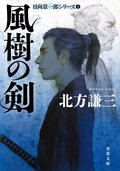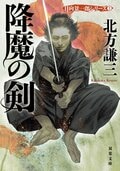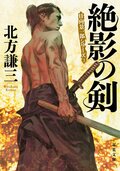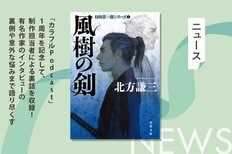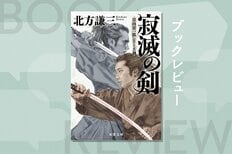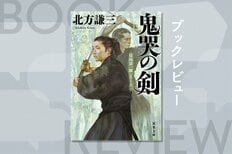今年1月から5カ月連続で刊行中の北方謙三さんの時代小説「日向景一郎シリーズ」がついに完結しました。兄・景一郎と弟・森之助の20年に及び因縁が、本作にて幕を下ろします。手に汗握る剣戟、人間同士の因果。傑作シリーズの完結編を文芸評論家・池上冬樹さんのレビューでご紹介します。
■『寂滅の剣〈新装版〉日向景一郎シリーズ 5』北方謙三 /池上冬樹[評]
日向景一郎シリーズの最終章である。全五作のシリーズはこれで終わる。
もうすでに読み終えた読者は、ラストの対決にしびれているのではないだろうか。こういう完結なのかと感じ入っているのではないかと思う。そして意外と悲壮感や寂しさとは異なる、不思議な読後感に浸っているのではないか。
第二作『降魔の剣』の解説から予告してきたように(シリーズの中でも触れられてきたように)、本書の最後の最後に景一郎と森之助の対決が用意されているのに、おののくような昂奮と衝撃とともに、読後には緊張感から解放されたような気分もある。気持ちがやわらぎ、何かある種の清々しさのようなものすら感じ取れるのは、生きることも死ぬこともさほど違いはないという死生観をしらずしらず体得してしまっているからだろうか。
個人的なことになるが、『チンギス紀 七 虎落』(集英社文庫)の解説の仕事で、積読だった『チンギス紀』全17巻を速読したのだが、昨年暮れからの日向景一郎シリーズとあいまって、もうどっぷりと北方謙三の世界に入ってしまい、現代を舞台にした他の作家の新作が読めない、もう読まなくてもいいという気分にもなってしまった。それほどの物語を読む幸福感がつまっている。
といっても、北方謙三の中国小説群および『チンギス紀』と、日向景一郎シリーズの剣豪小説には大きな違いがある。だが、その話に触れるまえに、本書をまず紹介しよう。
物語は、森之助が暴漢3人をこらしめる場面からはじまり、日向兄弟が暮らす薬種商・杉屋清六の薬草園に舞台を移す。
小関鉄馬が営む道場に、居合を使う男があらわれ、真剣勝負を挑む。景一郎がいなかったので、鉄馬は森之助を指名する。森之助は格の違いを見せつけながらも挑んでくるので、男の片腕をきりおとしてしまうが、それで終わらなかった。その男の兄を名乗る湯浅弥兵衛が登場し、難癖をつけて帰っていく。
不穏な気配があった。元武士の清六はまた剣術に励みだしている。清六が出かけるときは必ず、森之助が護衛についていた。“おかしなことで、恨みを買ってしまった”という。やがて湯浅がふたたび二人の前に現れて、清六の暗殺を請け負った話をする。
そのあとも軽業を使う剣客集団、奇抜な技を使う二人組の刺客など、次々に襲撃を受けるようになる。そんなおり、病気の母親を背負った諸橋了右が薬草園を訪ねてくる。清六の知り合いだったが、彼もまた何者かに命を狙われていた。いったい清六のまわりで何が起きているのか。買った恨みとは何なのか。
冒頭から、剣吞な空気が流れている。前作までの面倒みのいい明るい商人のイメージだった清六とは異なる荒んだものがのぞいて緊張感を醸しだしている。恨みとは何かという謎が、襲いかかる刺客がいっそう数を増してきて(数十人にも膨れ上がる)いちだんと深まっていく。今回もまた壮絶な抗争劇が展開されるのだ。
シリーズの前作までの解説では、時代背景についてあえて触れてこなかった。断定できるように書かれてなかったからだが、本書でははっきりと書かれている。「老中の水野忠邦が罷免されて、ふた月が経っている」(129頁)というから、天保14年(1843年)11月となるだろう。天保年間には凶作によって米価や物価の高騰が起き、大飢饉による百姓一揆なども頻発した(これは第三巻『絶影の剣』の背景でもある)。天保の改革(1841年から43年)自体は悪くはなかったが、すべてを急ぎすぎた。領地や支配権を召しあげる上知令は「江戸に権力を集中させる、最初の試みになるはずだった」が、それに気付いた大名や旗本がいたかどうか。「とにかく、この国は古い。政事のかたちを変えず、長い間、太平を謳歌してきた。その間に、清国は阿芙蓉に蝕まれ、列強は日本という国そのものを狙いはじめた」(356頁)と清六の視点から語られる。阿芙蓉に蝕まれ、列強に狙われているというのは、第二作『降魔の剣』でも語られていたが(アヘンの輸入をめぐる清とイギリスとの戦争、いわゆるアヘン戦争は1840年から42年)、その影響が、本書の物語の背景にもなっているといっていいだろう。
しかしこれは物語の主たるストーリーではあるのだが、シリーズ全五作の完結編においては、繰り返しになるが、景一郎と森之助の戦いが中心となる。本書の中で、関係者たちが何度も言及しているように、景一郎と森之助はなぜ戦わなければならないのかがわからない。そもそも二人は兄と弟なのかもはっきりしない。自分と兄の関係は本当は何なのか、兄弟ということで斬りあうのかという森之助の問いに、「どうでもいいことだろう、森之助。どちらかが死ぬのだ。おまえは、自分が死ぬ理由を、それほど知りたいのか?」(102頁)と景一郎が答えるように、斬る理由、死ぬ理由などないのである。森之助が20歳になったときに、景一郎と森之助が立合うということだけが決められてきた。それを二人の宿運として景一郎は森之助を育ててきたし、森之助もそう思い込んで自らの剣を磨いてきた。
日向景一郎シリーズ第一作『風樹の剣』は、「父を斬れ。斬らねばおまえの生きる場所は、この世にはない」という謎めいた祖父の遺言を胸に、18歳の青年剣士・日向景一郎が旅に出る話で、最終的には熊本で父親と対決することになるが、何故父親を斬らなくてはいけないのかも語られない。景一郎はそこで父親の子供とおぼしき赤子を拾い、父と同じ森之助と名付けるが、これも何故なのかは語られない。「自分が斬る相手を、景一郎は20年間育てたのか。それとも、自分を斬ってくれる相手を育てたのか」(195頁)とまわりが不思議がる関係なのである。森之助は自分の父を殺した相手なので斬るべきだと考えているのだが、亡き父親のための戦いと深く考えているとも思えない。
ここで思い出すのは、『チンギス紀』である。この景一郎と森之助の戦いのあとに、『チンギス紀』を読むとおどろくほどロマン主義というか、生と死、友情が高らかに謳いあげられていて、これはこれでいいという思いにかられる。
『チンギス紀』(全17巻)の物語は、12世紀、史上最大の大帝国を築いた英雄チンギス・カンの激動の生涯を描く大作である。大帝国を築くまでにはさまざまな敵がたちふさがるのだが、なかでも生涯のライバルがジャムカであり、ジャムカの息子のマルガーシである。モンゴル族の有力氏族キャト氏の長・イェスゲイの嫡男として生まれたテムジンと、ジャンダラン氏の長・カラ・カダアンの長子のジャムカは、第一作の『火眼』ではともに13歳。二人の話が並行して描かれるように、重要な存在であり、二人はやがて盟友となるものの、金国を支援するかどうかで、二人の立場が鮮明になり、敵対することになる。第七巻『虎落』では戦いがはじまり、第九巻『日輪』で区切りはつくけれど、その後は、ジャムカの息子マルガーシとの戦いとなる。マルガーシは片腕をなくしながらも、果敢にチンギス・カンに戦いを挑み続け、最終巻『天地』で相まみえることになる。
俺は戻ったぞ、爺。
あんたの剣については、俺はかぎりない敬意を払う。あんたほどの男と、五分に闘ったという親父を、俺はいま、はじめて全身で感じている。
礼を言う。親父を、自分の誇りだと感じさせてくれた。
しかし、あんたと俺との結着はついていないようだ。もう一度、見えるしかないぞ、テムジン。お互いに、命がなにかを教え合おう。感じ合おう。そして、死のう。(略)
命があるかどうか。どうでもいい。死など、ただいなくなるだけのことだ。
生きていて、死んで行く。どれほど果てしないことなのだ。生きることも死ぬことも、あんたと俺にとっては、ほんとうは意味すらもないことではないか。
殺し合うのだ、ただ。
行くぜ、爺さんよ。俺はそう言いたい。あんたの懊悩のすべてを、俺の手が飛んでいったように、飛ばし、消してやろう。(『チンギス紀 十七 天地』296~297頁)
マルガーシは“テムジン”とよびかけ、チンギス・カンも、「死のうか、ジャムカ。/戦とは、ほんとうは、ただ死ぬことだ」(327頁)と応じるのである。なんと恰好いいのだろう! なんと格調高い戦いだろう。それは戦ったあとにもいえて、敗退する敵軍の兵士たちに、首領の体は置いてゆけ、「魂は持ち帰れ」というのである。屍は地中深く埋められ、どこに死体があるかわからないよう丁重に弔うのが礼儀だった。この終盤の戦いが熱き昂奮をよび、もうたまらないのである。
北方の『水滸伝』もそうだった。全19巻を2週間かけて読み終えたことがあるが、もう読んでも読んでも終わらないのが、愉しくて仕方なかった。面白くてわくわくしたのだ。スパイ小説、脱獄小説、冒険小説、青春小説、恋愛小説、戦争小説など、あらゆるジャンルをとりこんで終盤へとなだれこんでいく。とくに第18巻、第19巻が凄い凄い。梁山泊と官軍の童貫軍との全面戦争に心を奪われてしまうのだ。目の前で両親を殺されて言葉を失った少年の楊令が、宋建国の英雄、楊業の子孫の楊志に育てられ、梁山泊に馳せ参じ、最前線にたつ。その凜々しき颯爽とした姿に、読者は目頭をおさえて声援を送ることになるのだが、しかし童貫軍の何たる強さ! 次々と梁山泊の要衝を崩していき、豪傑たちが次々と戦死していくのだ。
北方『水滸伝』は、旧体制に縛られた社会と精神の解放がテーマであり、(『絶影の剣』の解説でも触れたように)“キューバ革命がもっていた変革へのロマンチシズム”を『水滸伝』に移しかえたと、作者がある対談で語っている。いわば壮大な革命小説を意図し、至るところで、国の形、ありかたが論議される。それは『楊令伝』シリーズでもかわらないし、『チンギス紀』でもかわらない。
北方謙三はまた、中国小説の先駆けとなった『三国志』を振り返ったときに、こうも述べている。『三国志』とは「結局は男の夢が潰えていく、すべての夢が潰えていく。すべて、誰も勝利しない。誰も勝つことはない。そういう小説だった」と。「これは、ある意味では滅びというものが、男と同義みたいになって、男というのは滅びの中に生きていく。滅びを目指して生きていく。滅びを夢見て、生きていく、という部分があったと思います。そういうものは、僕が書いているハードボイルド小説で、ずっと書いてきたものなんですよ。それをもっと明確に、鮮やかに書くことができたのが『三国志』だったと思いますね」(『三国志読本 北方三国志別巻』ハルキ文庫より)というのだが、もちろん北方の現代小説だって鮮やかである(詳しくは『降魔の剣』の解説参照)。その鮮やかさが劇的なストーリーの中にはないだけの話だ。
“明確に、鮮やかに書くことができた”というのは、肉体と肉体が激しくぶつかりあう壮大な戦いを通してだろう。さまざまな男たちが出会い、熱き感情をともに味わい、たぎるほどの生の輝きをはなちながら潰えていく姿は、物語的にも“明確に”なるし、雄々しい行為とともに“鮮やかに書く”ことができる。それは壮大な革命小説を意図した『水滸伝』でもかわらない。日本を舞台にした歴史・時代小説でもそうだが、時代や状況が厳しければ厳しいほど滅びはより鮮やかに、ときに美しく捉えることができる。
「滅びる時は、人は滅びる。思いなど、もっとたやすく、時が瓦解させる」(265頁)とは景一郎の言葉である。「死とは、なんなのだ。それを考えていたのは、ずっと昔だった、という気がする。いなくなること。いまは、ただそう思う。自分が死ぬ時は、自分がいなくなるだけのことだ。そして、早かろうが遅かろうが、いずれいなくなる」(401頁)とは森之助の言葉だ。日向景一郎シリーズ全五巻(1993年から2010年)が完結するまで、『三国志』全13巻(1996年から98年)、『水滸伝』全19巻(2000年から05年)、『楊令伝』全15巻(2007年から10年)が並行して書かれている。中国小説や近年の『チンギス紀』と比べれば壮大とはよべないが、でもこれほど生と死を凝縮したスリリングなシリーズもないだろう。
もう一度、先の『チンギス紀』の引用を見てほしい。マルガーシからすれば父の仇をとる物語になる。森之助にとっても景一郎は父の仇であり、『チンギス紀』のように最終決戦はもっと謳われてもいいのに、そういう風にはならない。むしろひたすら謳わないようにしているといったほうがいい。一言でいうなら、中国小説はロマンチシズム、日向景一郎シリーズはニヒリズムとなるのだろうか。前者は男たちの志や夢など格調高く叙情的に描くのに対して、後者は不条理と無意味を即物的に描いていく。にもかかわらず、日向景一郎の物語に深く引き込まれてしまうのは、弁解も謝罪も言い訳も一切ない(一切許されない)、救済なき虚無主義ともいうべきものが、読者ひとりひとりのあるがままの生の根源をひたすらのぞかせてくれるからである。理由や動機を一言も説明することなく、兄と弟の戦いを描きつくす。『チンギス紀』のような高らかな心の交流などない。あるのは、潔くも苛烈な行いだけである。この高い密度、この凄まじい凝縮のシリーズがあるからこそ、中国小説では長く大きく、どこまでも高い調べの物語を自由に織り上げることができたのだろう。いわば、日向景一郎シリーズ全五作は、北方謙三の華々しい中国小説の原動力だったのである。同時に、これほど濃密で分厚い、惚れ惚れするほどの行動と、胸に響く箴言にみちた時代小説も珍しいだろう。北方文学のみならず国産エンターテインメントの中でも鋭く屹立する現代の古典といっていいのではないか。北方謙三ファンのみならず多くの読者に手にとってほしい傑作シリーズだ。