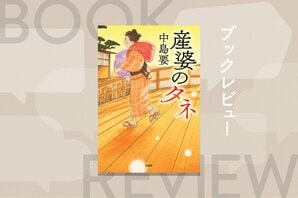四
「おっかさん、あたしはもう二度と自害をしようとしませんから、お産の立ち会いだけは勘弁して」
天王町の坂田屋へ戻るなり、お亀久は母に頭を下げた。
あれよあれよと話が進んでしまったが、万が一にも赤ん坊や母親の死に目になんて会いたくない。両手を合わせて頼んでも、母は勘弁してくれなかった。
「おタネ様がついていて、めったなことがあるもんか。お稲さんだって難産になりそうな人は避けるだろう」
そんなことを言われても、母の信じる神様はすっかり耄碌していたではないか。お亀久が眠れぬ夜を過ごした翌朝、万紀の紀次がやってきた。
「おい、昨日はどこへ行っていた」
顔を見るなり問い質されて、お亀久の眉間が思わず狭くなる。昨日、自分の留守中に紀次が来たことは奉公人から聞いていたが、今日も来るとは思わなかった。
「別にどこでもいいでしょう。あんたこそ何の用よ」
「何だ、その言い草は。俺は命の恩人だぞ」
恩着せがましい言葉を吐かれ、お亀久の頭に血が上る。
誰も助けてほしいなんて言っちゃいないわ。あたしのことが目障りなら、放っておけばよかったでしょう。
とっさに言い返そうとして、すんでのところで思いとどまる。
もしもあのまま死んでいたら、両親がどれほど悲しんだかわからない。跡取りの兄にも「親に心配をかけるな」と叱られた。
──おまえのつらい気持ちもわかるが、大事な娘に突然身投げをされてみろ。さしもの坂田屋壮一もしばらくは使い物にならないだろう。いまそんなことになれば、江戸の札差はおしまいだぞ。
横暴な幕府に一矢報いるべく、札差は一致団結して動いている。痛手の少なかった坂田屋は何かと頼りにされていて、父は寝る間もないほど忙しいとか。
──長らく札差の娘として何不自由ない暮らしをさせてもらったんだ。少しは店のことも考えろ。
兄の険しい表情を思い出し、お亀久はゆっくり息を吐く。
考えてみれば、紀次だって兄を失ったばかりなのだ。自分の身投げを止めたのはそのせいだろうと思い直し、問われたことに答えてやった。
「昨日はおっかさんと一緒に産婆さんのところへ行ってきたの」
その瞬間、紀次は目を剥いた。
「おい、まさか兄貴の子か」
「えっ」
「だから、おめぇは神田川に身を投げて、兄貴のところへ行こうとしたのか。それで腹の子は無事なのか」
血相を変えた相手はとんだ勘違いをしているようだ。お亀久は「馬鹿なことを言わないで」と真っ赤になった。
「あたしと紀一郎さんは清い仲よ。下世話な勘繰りをしないでちょうだい」
「だけど、おばさんと産婆のところに行ったって」
「おっかさんはあたしに命の尊さを教えようとしただけよ。あたしが身籠ったわけじゃないわ」
どうしてこんなことをいちいち言わなければならないのか。恥ずかしさをこらえて睨みつければ、紀次はホッとしたように座り直した。
「そ、そうだよな。兄貴が亀なんかに手を出すもんか」
仮にも義姉になるはずだった自分に向かって、「亀なんか」とは失礼な。お亀久は口を尖らせた。
この人のこういうところが嫌いなのよ。幼いころならいざ知らず、いつまでも亀、亀って人を馬鹿にして。
それからいくらもしないうちに紀次は帰ったけれど、翌日も翌々日も顔を出して、お亀久を閉口させた。
紀次さんも万紀の跡継ぎになったんだし、やることは山ほどあるはずでしょう。一体どういうつもりなの。
紀一郎捜しはいまも続いているけれど、誰もが内心あきらめている。万が一、紀一郎が生きていても、万紀を継ぐことはない。紀次は跡取りとしてもっと真面目に働くべきだと苦々しく思っていると、産婆のお稲に呼び出された。
「お常さんは四人目だからね。前の三人も安産だったし、御新造さんもお嬢さんも大船に乗った気でいておくれ」
以前のしかめっ面とは打って変わり、お稲は得意げに胸を張る。傍らに控えるお常の腹はいまにもはち切れそうなほど膨らんでいた。
「他にも臨月の人はいるけれど、お常さんはここで産むから都合がいいんだ」
お産は本来妊婦の家で行うが、子だくさんの貧乏人は家で産めないこともある。お常は上二人もおタネ様の家で産んだそうだ。
「ここなら御新造さんたちがお産に立ち会っても、近所に住む人たちに変な目で見られずにすむからさ」
「お稲さん、お気遣いありがとうございます。お常さんも無理なお願いを受けてくださって、助かりました」
「十両ももらえるなら、お産を見せるくらい屁でもないさ。ところで、その金はいつもらえますかね」
母の言葉をさえぎってお常が尋ねる。あからさまな求めに苦笑して、母は懐に手を入れた。
「ご心配なら、いますぐ払いましょうか」
「ええ、そうしてくださいな。何事も万が一ってことがありますから、お稲さんに預かっといてもらいます。お稲さん、あたしにもしものことがあれば、この金はうちの宿六に渡しとくれ」
お常はお産で命を落とし、礼金を踏み倒されることを恐れたようだ。母からもらった十両をそのままお稲に差し出した。
「これでようやく安心して赤ん坊が産めるってもんですよ。御新造さん、失礼なことを言ってすみませんね」
三人も産んでいる母親ですら、万が一のことを考えるのか。お亀久はますます不安になったが、母はまるで動じない。
「いいえ、こちらこそ。不躾な頼みということは重々承知しています」
頭を下げる母に続き、お亀久も黙って頭を下げる。お常は「礼を言うのはこっちです」と笑っていた。
お常の亭主は棒手振りの魚屋で、棄捐令が出てから稼ぎが極端に細ったという。しかも十日前に酔って転び、いまは商売を休んでいるとか。
「てめぇの女房が臨月なのに、肝心なときに稼げなくなるなんてねぇ。本当に役立たずなんだから」
子供は八つの長女を頭に五つと三つの息子がいて、いまは長女が下二人の面倒を見ているらしい。
「亭主はそんな具合だし、あたしも産後しばらくは稼げない。御新造さんの十両がなかったら、上の娘を奉公に出すか、生まれたばかりの赤ん坊を手放す羽目になるところでした」
両手を合わせて感謝されたが、お亀久はそれどころではなかった。お常の亭主が棒手振りの魚屋と知り、自分をかばって殺された加吉を思い出してしまう。
父に聞いた話だと、加吉の女房には子がなかった。お亀久の幸せを願ってくれたという女房のためにも、お常には元気な赤ん坊を産んでほしかった。
それから五日後の十月二十五日の夕方、とうとうお常が産気づいた。
知らせを受けた母とお亀久は駕籠で八丁堀に駆け付けた。お亀久は乗りたくなかったが、母が許してくれなかった。
お常のお産の無事を祈りながら母と産屋に踏み込めば、そこにはケロリとした顔のお常とお稲がいた。
「慌てさせたみたいで、すみませんね。お産は産気づいてからが長いんだよ」
お稲の説明に安堵しつつも、お亀久は拍子抜けしてしまう。母は薄々わかっていたのか、すぐに「握り飯をこさえる」と言い出した。
「腹が減っては元気な子なんて産めません。ほら、お亀久も手伝いなさい」
日頃料理をしなくとも、握り飯くらいはできる。少々いびつな握り飯を皿に並べ、さぁ食べようというところで、母がお稲に問いかけた。
「あの、おタネ様はどちらですか」
「いざというときに備えて、二階で寝ています」
あっけらかんと返されて、お亀久の顎が落ちかける。いくら年寄りとはいえ、産気づいた妊婦を放ったらかして産婆が寝ているとは思わなかった。
母もさすがに驚いて、「そろそろ起こしませんか」と言う。だが、お稲は「平気ですって」と手を振った。
「おタネ様は危なくなったら、ちゃんとお出ましくださるから。もっとも、今日は出番がないと思いますよ」
それでも母は不安なのか、心配そうに上を見る。すると、今度はお常が「大丈夫だよ」と請け合った。
「うちの二番目と三番目の子は、お稲さんがひとりで取り上げてくれたんだ。おタネ様はへその緒を切っただけなのさ」
だから心配ないと言われて、母はようやく引き下がった。
その後、陣痛の間隔が徐々に短くなり、夜も更けて町木戸が閉まった辺りでいよいよお産は佳境に入った。
産屋の畳には汚れ除けの油紙が敷かれている。お常は重ねた布団にぼろ布をかぶせて寄りかかり、梁からつるした力綱を必死に握りしめていた。
十月も末になって夜は芯から冷えるのに、赤らんだお常の額から汗が流れる。お稲は白のタスキに鉢巻き姿で、お常の開いた股の間に陣取っていた。
「お常さん、うまいよ。もうひと息だ」
お稲の励ましに応えるように、うめき声が大きくなる。
詳しいことはわからないが、お産は順調なようである。それをうれしく思いつつ、お亀久はたちこめる血の臭いに口を押さえた。
この調子だとおタネ様の出る幕はなさそうね。お常さんもつらそうだし、早く生まれてくれないかしら。
痛みに耐えるお常の顔はすさまじさを増していく。たまらず目をそらしたら、母に頭を叩かれた。
「ほら、しっかり見なきゃ駄目じゃないか。女はみなああやって、我が子を産み落とすんだから」
いくら頭を叩かれても、人が苦しむ姿なんてまともに見ていられない。お亀久は薄目を開けながら安産を祈ることしかできなかった。
しかし、赤ん坊は生まれないまま九ツ(午前零時頃)を過ぎ、血の臭いが濃くなっていく。母がたまらず両手を合わせた。
「四人目だから安心だと思ったけれど、その分年を取るものね。きっと、いきむ力が足りないんだわ」
不吉な見立てにお亀久の背筋が凍り付く。お稲も母と同じことを思ったのだろう。お常の会陰にさらしを当て、叱るように声を荒らげた。
「お常さん、もっとしっかりいきんどくれ。力を抜くのはまだ早いよ」
いままで「うまい」とほめていたのに、お稲も余裕がなくなってきたようだ。思わず母の顔を見れば、顔色が悪くなっていた。
「お亀久、急いでおタネ様を連れておいで」
「は、はいっ」
そうだ、こういうときこそ名ばかりでも産婆の神様の出番だろう。お亀久が立ち上がりかけたとき、勢いよく襖が開いておタネ様が現れた。
「おや、ちょうどいいところへ来たようだ。お稲、代わるよ。お常さん、あたしの声が聞こえるかい」
特に慌てた様子も見せず、おタネ様はしわの寄った手でお常の汗を拭ってやる。お常はうっすら目を開けた。
「おタネ様、腹の子は……」
「心配しなくとも大丈夫だ。赤ん坊はちゃんと下りてきている。次の波が来たら、ありったけの力でいきむんだよ」
たっぷり寝たせいなのか、おタネ様の声は力強い。しかも、年甲斐もなく真っ赤なタスキをかけていた。
「ちょいと血が多く流れたけれど、心配することはないからね。赤は血の色、命の色だ。お常さん、大丈夫だよ」
産婆の神様に「大丈夫だ」と繰り返されて、お常は力綱を握り直す。続いて顔をしかめた瞬間、おタネ様が大音声を張り上げた。
「ほら、いまだっ」
「あ、ああぁううぁっ」
おタネ様のタスキに負けないくらい、お常は真っ赤な顔で最後の力を振り絞る。膝を曲げて大きく開いた足の間から、ようやく赤ん坊の頭が出てきた。
「よし、うまいよ。お常さん、もうひと踏ん張りだ」
ほどなく血にまみれた全身が現れて、おタネ様が笑顔で取り上げる。夜の静寂に響き渡る近所迷惑な産声をお亀久は目の覚める思いで聞いた。
おっかさんが言った通りだわ。おタネ様は不幸の影を追い払い、赤ん坊を助けてくれた。
ああ、ありがたいと思ったところで緊張の糸がプツリと切れて、お亀久は気を失った。
次に目を覚ましたとき、お産はすべて終わっていた。
「おやまぁ、ようやく気付いたかい。なかなか目を覚ましてくれないから、こっちは気を揉んだじゃないか」
眉を下げた母の言葉にお亀久は慌てて身を起こす。じきに暁七ツ(午前四時頃)の鐘が鳴ると言われて、何度も目を瞬く。
「ふん、いきなりひっくり返られて、驚いたのはこっちだよ。脇で眺めていただけなのに、よくも呑気に寝ていられたね」
お産は無事に終わったはずなのに、不機嫌なお稲に睨まれる。お亀久が「すみません」と小さくなれば、後ろから母が割って入った。
「あんたが気を失っている間に、後産も終わった。もう血を見る恐れはないよ」
その言葉に気を取り直し、お亀久はお常の隣に目を向ける。そこには生まれたばかりの赤ん坊が眠っていた。聞けば女の子だそうで、大仕事を終えたお常はいままでになく柔らかな笑みを浮かべていた。
「よかったら、抱いてやっとくれ。お嬢さんのおかげで、手放さずにすんだ子だからね」
「でも……」
生まれてすぐの赤ん坊なんて、お亀久は抱いたことがない。怖くて手を出せずにいたら、母が代わって抱き上げた。
「ああ、思い出すねぇ。あんたも生まれてすぐはこんなふうだった。ほら、右手で尻を抱え、左手で赤ん坊の頭を支えるんだよ」
目を細める母の教えに従い、おっかなびっくり赤ん坊を抱く。この世に誕生したばかりの小さな命は不安になるほど頼りなく、驚くほど熱を帯びていた。
この赤ん坊が十五年後には自分と同じような娘になるなんて。お亀久は信じられない気分で真っ赤な顔をのぞき込んだ。
ああ、何てかわいいんだろう。
お常さんが命がけで、四人も子を産むはずだわ。
小さな顔はしわくちゃながら、ちゃんと目も鼻も口もある。産着からはみ出た足で歩きだすのは、ずっと先の話だろう。
いまはどんなものよりか弱くても、底知れない力を秘めている。人は誰しもここから始まるのだと思ったら、胸に熱いものがこみ上げた。
お亀久にとって、赤い血は死を招くものだった。
しかし、この子は母親の血に染まって生まれてきた。
赤は血の色、命の色。自分の身体にもまっ赤な血が流れている。その血がないと生きられないのに、闇雲に恐れてどうするのか。お亀久が赤ん坊を腕に抱いてそんな反省をしていると、おタネ様から声がかかった。
「へぇ、初めてにしては赤ん坊を抱くのがうまいじゃないか」
産婆の神様にほめられて、お亀久はすっかりうれしくなる。
思えばこの六年間、他人にほめられた覚えはほとんどない。調子に乗って低い鼻を高くすると、さらに予期せぬことを言われた。
「あんたは案外、産婆に向いているかもしれないよ。試しにうちで産婆見習いをしてみるかい」
まさか、産婆の神様にそんなことを言われるとは。無言で唾を呑み込むと、横から母が口を出す。
「急に何をおっしゃいます。うちの娘を産婆にする気はありません」
「おタネ様、その子は血が苦手でひっくり返ったじゃないですか。それに見習いなら、おゆきがいるでしょう」
お稲も慌てて反対するが、寝ている赤ん坊がそばにいるので、どちらも小声しか出せない。おタネ様は二人の文句を聞き流し、お亀久に向かって話を続けた。
「嫌なら無理にとは言わないけどね。一人前の産婆になれば、女ひとりでも一生生きていけるよ」
「えっ」
「それに産婆は女相手の仕事だから、男の出る幕はない」
ニヤリと笑って付け加えられ、目の前が開けた気分になる。こっちの事情をすべて承知で、おタネ様は誘いをかけてくれたのだ。
たとえ両親に反対されても、ここは神様のお告げを信じよう。ことわざも「案ずるより産むが易し」というではないか。
「あ、あたしやりますっ。産婆見習いをやらせてください」
うっかり大きな声を出せば、腕の中の赤ん坊が泣き出した。
(第一話・了)
続きは、書籍でお楽しみください