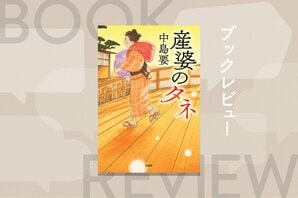その一 産婆の神様
一
負けず嫌いな江戸っ子は、何でも「一番」が大好きだ。
日本一の富士山は絶大なる人気を誇り、三十里(約一二〇キロ)先のはるかな頂を眺めては、誰もが決まって目を細める。時には「どこから見える富士が一番か」で喧嘩口論になるほどだ。
寛政元年(一七八九)九月六日は、朝から絵に描いたような秋晴れだった。
空は青く澄み渡り、はるかかなたまでくっきりと見渡せる。武家屋敷が建ち並ぶ駿河台や買い物客で混み合う駿河町のあたりなら、青空を背に雪化粧をした富士の山がよく見えるに違いない。
そんなすがすがしい外とは打って変わり、浅草天王町の札差、坂田屋の母屋の一室では重苦しい空気が立ち込めていた。
「お亀久ちゃん、いい加減にしなさいよ。あんたがここでいくら泣いたって、紀一郎さんが生き返るわけじゃないんだから」
ちっとも返事をしない幼馴染み焦れたのか、浅草瓦町の札差、相模屋の跡取り娘のお八重がまだ青い備後畳を手で叩く。二人きりの部屋の中、坂田屋の娘のお亀久は赤い目をこすって顔を上げた。
「お八重ちゃん、縁起でもないことを言わないで。紀一郎さんは行方が知れないだけで、死んだと決まったわけじゃないわ」
「でも、山崩れに遭ったのは五月半ばのことでしょう。今年の六月は閏月だったから、四月も前のことなのよ。もしも紀一郎さんが生きているなら、とっくに見つかっているはずじゃないの」
容赦のない正論にお亀久は今度こそ言い返すことができなかった。
深川佐賀町の材木問屋、万紀の長男紀一郎は、お亀久の幼馴染みにして許婚だ。この春に縁談がまとまって、来年早々にも祝言を挙げることになっていた。
しかし、紀一郎は紀州の山主に己の縁談を知らせに行き、運悪く山崩れに巻き込まれた。以来夜となく昼となく捜しているのに、いまだ行方はわからない。
お八重ちゃんだって祝言を控えているくせに、よくそんな冷たいことが言えるわね。あんたも許婚がいなくなれば、あたしの気持ちがわかるわよ。
そんなお亀久の心の声も知らず、お八重は聞き分けのない幼子を諭すように語りかけてきた。
「あくまで紀一郎さんが生きていると信じるのなら、いっそ紀州まで捜しに行きなさいよ。万紀でもあきらめきれなくて、いまも捜し続けているんでしょう。ここでくすぶっているよりも、己の目で確かめればいいんだわ」
いきなり無理難題を突きつけられて、お亀久はますます泣けてきた。
紀一郎は富士の山よりさらに遠い紀州の山中に消えたのだ。家から一歩も出ない箱入り娘がはるばる捜しに行けるものか。
無言で首を横に振れば、お八重はつまらなそうに鼻を鳴らした。
「あら、そう。子供のころのお亀久ちゃんなら、あたしが言い出す前に自ら捜しに行ったでしょうに」
ため息混じりに告げられて、お亀久は内心ドキリとした。
確かに、昔の自分なら手をこまねいてはいなかった。たとえ親に反対されても、紀州に乗り込んでいただろう。
「紀一郎さんが万紀の跡取りの座を捨てて、あんたと一緒になると知ったときは顎が外れるほど驚いたわ。それでも、長らく男を怖がっていた幼馴染みが縁談を決めたんだもの。あたしも祝福していたのよ」
「…………」
「こんなことになったのは気の毒だと思うけど……あんただってもう十六よ。いつまでも親に甘えて、閉じこもっているわけにはいかないでしょう」
お亀久は何も言えないまま、力なくうなだれた。
いまでこそ「何もできない弱虫」に成り下がってしまったが、幼いころの自分は男勝りのお転婆だった。器量よしで勝気なお八重とは何かと張り合っていたものだ。
ところが、六年前にかどわかしに遭い──すべてが一変してしまった。
当時(天明三年)は前年からの天候不順で米価が高騰、さらに七月の浅間山噴火が追い打ちをかけた。大量の灰が江戸にまで降り注ぎ、あらゆる物が値上がりする中、お亀久は食い詰め浪人に攫われたのだ。
不幸中の幸いは、その場を通りかかった棒手振りの魚屋、加吉が十手持ちの手下だったことだろう。かどわかしに気付くなり、商売道具の天秤棒ですかさず浪人に殴りかかった。
その隙にお亀久は浪人の手から逃れられたが、代わりに加吉が返り討ちに遭ってしまう。それを見たお亀久が喉も裂けよと悲鳴を上げ、近所の人々が駆けつけたので浪人はひとり逃げ去った。その後、町方の追手がかかって下手人はお縄になったものの、目の前で起こった惨劇は幼心に焼き付いた。
斬られた加吉の断末魔の声と、一面に飛び散った真っ赤な血しぶき。
涙ながらに娘の無事を喜ぶ両親と坂田屋に帰ってからも、お亀久は悪夢にうなされて飛び起きることを繰り返した。そして、知らない男と血を恐れ、家から出られなくなったのである。
幸い裕福な親のおかげで、家にいながら読み書き習い事は続けられた。
しかし、十六になった現在でも着飾って芝居見物に行くどころか、血を思わせる赤い紅すら付けられない。十二で初潮を迎えたときなど悲鳴を上げて倒れてしまい、赤飯で祝うどころではなかった。
両親はそんな娘を憐れみながらも、去年の夏あたりからしきりと縁談を匂わせ始めた。
ただでさえ、「人前に出ない坂田屋の娘」は悪い意味で有名である。早めに手を打たないと、嫁き遅れると危ぶんだに違いない。
そんな親心はわかっていても、見ず知らずの男と夫婦になるのは耐えがたい。お亀久はさんざん悩んだ末に一計を案じた。
材木問屋万紀の主人佐紀蔵と、父の坂田屋壮一は長年の狂歌仲間である。
互いの子供も幼いころから行き来があり、五つ上の紀一郎は兄の壮助とも仲がよく、家に閉じこもるようになってからも折節見舞いに来てくれた。男が怖いお亀久も紀一郎だけは普通に話すことができた。
紀一郎なら夫婦になってもやっていける気がするが、あいにく万紀の跡取りだ。材木問屋は奉公人はもちろん、出入りするのも男ばかりである。男が怖い自分に万紀の内儀は務まらない──と、さもつらそうに訴えれば、両親はもうしばらく縁談を待ってくれると考えた。
ところが、こちらの予想に反し、その話をした半月後に「紀一郎をおまえの婿にする」と父に告げられた。
──紀一郎は気性がやさしすぎて、材木問屋の主人に向かない。次男の紀次のほうが向いていると、佐紀蔵さんも以前から思っていたそうだ。
親の思惑はどうであれ、突然跡取りの座を追われた紀一郎が納得するはずがない。そんなお亀久の懸念は当の本人に吹き飛ばされた。
──俺は腕っぷしの強い男たちを顎で使うような柄じゃない。婿と言っても、坂田屋のおじさんのたっての頼みだからね。この縁談は渡りに船だよ。
ケロリとした顔で言い放たれて、お亀久は腰が抜けるほど驚いた。縁談除けの方便がこんなことになるなんて、これこそ瓢箪から駒だろう。
男女の情などないけれど、紀一郎なら信用できる。勢いトントン拍子で縁談は進み、それを知った世間は大騒ぎした。
──万紀の跡取りが婿入りとはどういうこった。坂田屋には跡取り息子がいるじゃねぇか。
──坂田屋の娘は病弱で、荒くれ野郎が出入りする材木問屋の内儀なんて務まらねぇってことらしい。万紀は次男が跡を継ぎ、坂田屋は娘のために分家を立てることにしたそうだぜ。
──だとしても、万紀はよく長男を手放す気になったもんだ。
──きっと、若い二人が手に手を取って「一緒になれなかったら、大川に飛び込む」とでも言ったんだろう。
──つまり万紀の身代と引き換えにできるほど、坂田屋の娘は美人ってことか。一遍拝んでみてぇもんだな。
憶測混じりの噂が飛び交い、一番迷惑を被ったのは紀一郎に違いない。会う人ごとに人前に出ない許婚の容姿や婿入りのいきさつを尋ねられ、江戸から逃げ出す羽目になったのだから。
あたしとの縁談がなかったら、紀一郎さんだって梅雨の最中に紀州に行ったりしなかった。知らない男と一緒になりたくない一心で、おとっつぁんに余計なことを言わなければよかったわ。
お亀久が無言でうなだれていると、お八重は目を吊り上げた。
「ちょっと、人の話をちゃんと聞いてるの? あたしはあんたのためを思って、耳に痛いことを言っているのよ。このままぼんやりしていてごらんなさい。あんたに甘いおじさんはともかく、兄さんの代には居場所なんてなくなるから」
きれいな顔を歪めて説教され、お亀久はため息を呑み込んだ。
思わず「余計なお世話だ」と言い返したくなったけれど、お八重が自分を案じているのは確かだろう。かつては仲のいい女友達も両手に余るほどいたはずなのに、いまでも訪ねてくるのはお八重だけだ。
「あんたは世間の噂ほど、器量よしじゃない。若いうちに次の相手を探さないと、間違いなく売れ残るわよ。ああ、その前に一度お祓いをしときなさいな。あんたは運が悪いから」
お八重は言いたいことを言って気がすんだのか、ほどなくすっきりした表情で立ち去った。
自分が美人でないことくらい、他人に言われるまでもない。お亀久は顔をしかめて立ち上がり、部屋の隅にある鏡台を覗き込む。
外に出ないので肌の色こそ白いものの、丸い目は小さく、鼻も低い。おまけに父親譲りの猪首のせいで、高価な着物で着飾ったって後ろ姿さえ絵にならない。口と性格が悪い万紀の次男の紀次なんて、「おめぇなんかきくじゃねぇ。首をすくめた亀じゃねぇか」と会うたびに自分を馬鹿にした。
嫁になんて行く気もないのに、いやいや見合いをした相手にがっかりされるなんて真っ平よ。気心の知れた紀一郎さんだから夫婦になってもいいと思ったのに。
お亀久は鏡に映る己に向かって、わざと歯を剥いた。
子供のころは、大人になればきれいになれると信じていた。紀次に「亀だ」と馬鹿にされても、「そう言うあんたはきじじゃないの。桃太郎の供をして、早く鬼ヶ島に行っといで」と言い返していたものだ。
だが、お八重の言い分も残念ながら一理ある。
兄は不幸続きの妹にやさしいけれど、嫁を迎えれば言うことだって変わるだろう。世間知らずの自分でもそれくらいは見当が付く。
嫁かず後家の小姑なんて、嫂にとっては目障りだもの。もしも家に居づらくなったら、いっそ尼寺に行こうかしら。俗世と縁を切ってしまえば、男とかかわらなくてすむものね。
出家後は加吉と紀一郎の菩提を弔い、静かに生きていけばいい。お亀久はそう思い付き、次の瞬間手を打った。いっそ、いますぐ尼になれば、さまざまな煩わしさから逃れられる。
尼寺に入れば、世間の噂も遠ざかる。場所柄亡骸は目にしても、血を見ることは少ないだろう。
出来の悪い妹がいなくなれば、兄の縁談も進むはずだ。お亀久はすっかりその気になり、さっそく父に思いを伝えた。
「おとっつぁん、あたしは紀一郎さん以外の人と一緒になる気はありません。尼になって紀一郎さんと加吉さんの冥福を祈りたいと思います」
ところが、最後まで言う前に「馬鹿を言うな」と怒鳴られた。
「おまえが出家して誰が喜ぶ。死んだ加吉さんに申し訳ないと思うなら、人並みに所帯を持って幸せになれ。加吉さんのおかみさんもそれを望んでいたんだぞ」
かつて父は死んだ加吉の女房に手をついて、「自分にできることなら何でもする」と詫びたそうだ。
「ご亭主の命と引き換えに娘を助けてもらったんだ。千両出せと言われても喜んで払うつもりだった。だが、おかみさんは『亭主の墓代として五両もあれば十分だ』と言ったんだよ」
そのささやかすぎる願いを父は受け入れられなかった。こっちにも札差の主人としての体裁がある。それっぽっちですませるわけにはいかないと粘ったが、相手が承知しなかったとか。
「どうしても気がすまないのなら、坂田屋のお嬢さんには亭主の分まで幸せになってもらいたい。うちは子供がいないから、それが一番の供養になると言われてね。死んだ加吉さんに誓って、必ず娘を幸せにすると約束した。だから、佐紀蔵さんに無理を言って、紀一郎の婿入りをまとめたのに……」
苦渋に満ちた父の顔にお亀久は胸が痛くなる。父が自分に甘かったのは、そういう事情があったからか。
とはいえ、こんな自分が嫁に行っても幸せになれるとは思えない。お亀久が頭を抱えているうちに、さらなる不幸が坂田屋に襲いかかった。
九月十六日、幕府は困窮する旗本御家人を救うために棄捐令を出したのである。
『産婆のタネ』(「その一 産婆の神様」)は全4回で公開予定