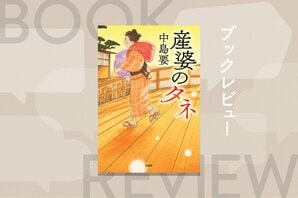三
翌十月一日はあいにくの曇り空だった。
母は嫌がるお亀久と女中を伴い、自身が生まれ育った八丁堀へ足を向けた。
江戸の町方役人が「八丁堀の旦那」と呼ばれるように、この界隈は町方役人の組屋敷が多い半面、町人も数多く住んでいる。母の実家は幸町の荒物問屋金久で、お亀久もかどわかしに遭うまではよく遊びに行っていた。
「あんたやあたしを取り上げた産婆さんが本八丁堀二丁目に住んでいるんだよ。おタネ様は『産婆の神様』と言われるほどの腕利きなんだから」
道々語り続ける母は、昨日と打って変わって機嫌がいい。娘を連れて外出するのが六年ぶりだからだろう。
「お産はいつ始まるかわからないから、家の近くの産婆さんのほうがいいんだけどね。あたしはどうしてもおタネ様にお願いしたくて、蔵前まで来てもらったのさ」
産気づいてすぐに駆け付けてもらうには、近所の産婆のほうが安心だ。
しかし、母は嫁ぐ前から「自分の子は産婆の神様に取り上げてもらう」と決めていたという。
「お産は女の命がけだ。未熟な産婆に頼んで我が子を死なせるようなことになれば、悔やんでも悔やみきれないもの」
そんなふうに言われると、勝手に死のうとしたことが申し訳なくなってしまう。それでも、昨日はそれしかないと思ったのだ。
おっかさんには悪いけど、あたしは生きることに疲れてしまった。その産婆の神様が無茶な頼みを断ってくれるといいけれど。
母には言えない思いを胸に、お亀久は母の後に続く。
大道芸人が張り合って口上を言う西両国の広小路から、大店の建ち並ぶ日本橋北の界隈を抜けて江戸橋を渡る。それほど長くもない楓川には五つも橋が架かっていて、川岸には土蔵と材木問屋が軒を連ねる。勢い、腕っぷしの強そうな男たちが数多くいて、お亀久はそういう男とすれ違うたび、息を殺して身を硬くした。
坂田屋のある蔵前から八丁堀まではかなりある。駕籠を使えば通りすがりに男を見なくてすむのだが、見知らぬ男の担ぐ駕籠に乗るのはもっと嫌だった。
怯えなくとも大丈夫。これだけ人通りが多ければ、滅多なことはできないわ。
心の中で唱えながらも、お亀久の歩みは徐々に速くなっていく。母も娘の様子がおかしいことに気付いたのだろう。女中を急かして弾正橋を渡り、本八丁堀一丁目を通り過ぎて二丁目の木戸をくぐった。
その近くの路地の突き当たりにこぢんまりした二階家があり、「取上げ婆 タネ」と書かれた軒燈が下がっている。母は迷わずその戸を叩いた。
「ごめんください。坂田屋の富久でございます。お稲さんはおいでですか」
母が軒燈とは異なる名を口にすると、小太りの中年女が現れた。
「おやまぁ、ようこそお越しくださいました。坂田屋の御新造さん、本当にお久しぶりですねぇ。そちらはお嬢さんですか」
お稲は細い目をさらに細くして、母からお亀久へと目を移す。
ここは自ら名乗るべきだとわかっていたが、お亀久はもう何年も知らない人と口をきいたことがない。なかなか声を出せずにいると、母が代わって答えてくれた。
「ええ、おタネ様に取り上げてもらった娘の亀久でございます。ずいぶん大きくなったでしょう」
「本当にねぇ。それで、どうしてお嬢さんをここに連れてきたんです。ひょっとしておめでたですか」
ニコニコしながら尋ねられ、お亀久はこっそり顔をしかめる。まだ嫁いでもいないのに、子ができたりするものか。
一方、母は残念そうにため息をつく。
「いいえ、そうじゃないんです。話せば長くなりますが、今日はおタネ様にお願いがありまして……」
「他ならぬ御新造さんの頼みだもの。まずはお上がりくださいまし」
母は「一刻(約二時間)してから迎えにおいで」と女中に命じ、娘と共に家に上がる。お稲は二人に茶を出すと、「おタネ様を呼んできます」と部屋を出ていったきり、なかなか戻ってこなかった。
二階家とはいえ、たかが町人の住む裏店である。広大な武家屋敷でもあるまいに、一体何をしているのか。お亀久がイライラし始めたとき、お稲はようやく小柄な老婆を連れてきた。
「おタネ様、ご無沙汰をしております。金久の娘で、蔵前の坂田屋に嫁いだ富久でございます。今日はお願いがございまして、娘ともども押しかけてまいりました」
深々と頭を下げる母を見て、お亀久も慌てて頭を下げる。
ひと呼吸おいて頭を上げると、お稲の隣で年寄りが大口を開けてあくびしていた。髪や着物の派手な乱れ具合からして、恐らく寝起きなのだろう。
この梅干しのタネみたいなおばあさんが産婆の神様? あたしには耄碌した年寄りにしか見えないわよ。
頭は白髪さえ薄くなり、地肌が透けてしまっている。袖口からのぞく手首は枯れ枝のようで、転んだらポキリと折れそうだ。お亀久が信じられない思いで見つめていると、母は昔語りを始めた。
「あたしがおタネ様に取り上げてもらいましたのは、寛延四年(一七五一)辛未のことでございます。あの年も今年と同じく閏年で、八代様のご葬儀が寛永寺で行われた閏六月に金久で生まれました」
いきなり四十年近く前のことを言われても、向こうは長年大勢の赤ん坊を取り上げてきたはずだ。どうせ忘れていると思っていたら、年寄りはカッと目を見開く。
「ああ、金久さんのところのお嬢さんかい。あんたは産気づいてから半日足らずで生まれてきて、親孝行な娘だったよ。するってぇと、後ろにいるのがあんたの産んだ娘かい」
「はい、安永三年(一七七四)甲午に取り上げてもらった亀久でございます」
「もちろん、覚えているよ。その子は二人目だってのに、なかなか腹から出てこなくてさ。お富久さんの腹の中はよほど居心地がよかったのか、それともこの世に出てきたくなかったのか」
まるで乾物を水で戻したように、老婆の目が生気を帯びる。母は我が意を得たりとうなずいた。
「ええ、そうなんでございます。生まれるときにさんざん苦労をかけた上に、いまもとんだ親泣かせでございまして。この子ときたら罰当たりにも身投げをしようとしたんです」
それは聞き捨てならないと、お稲に細い目で睨まれる。母は肩身の狭い娘をよそに、これまでのことを洗いざらい打ち明けた。
「かどわかしに遭ったこの子を不憫に思って甘やかし、命を粗末にするような親不孝にしてしまいました。この世には産声を上げられない子や、生きたくても生きられない子が山ほどいるのに」
「御新造さんのご心痛はお察ししますよ。それで、おタネ様にお願いというのは何でしょう」
お稲は大きくうなずきつつも、少々心配そうに問い返す。母はよくぞ聞いてくれたとばかりに膝を進めた。
「この子の性根を叩き直すため、なるたけ早くお産に立ち会わせてもらえませんか。母親が命がけで赤ん坊を産む姿を見れば、この子の目も覚めるはずです」
「でも、この子はまだ十四だろう。お産を見せるのは早いんじゃないのかい」
「おタネ様、お亀久はもう十六ですよ」
心配そうなおタネ様に母がすかさず言い返す。おタネ様は首を傾げた。
「だって、安永三年の生まれだろう。安永十年が天明元年(一七八一)で、今年は天明……何年だい」
指を折りながら尋ねる相手に、お亀久はまたもや不安になる。
赤ん坊の生まれた年は覚えていても、今年が何年かわからないとは。知らず眉をひそめると、横からお稲が耳打ちした。
「今年は天明九年ですけど、一月に寛政元年と改まりました」
「ああ、そういや、そうだったね。何やかやと元号が変わるせいで、ややこしくっていけないよ」
年寄りの文句をみなまで聞かず、お稲は母に話しかける。
「御新造さんの事情はわかりましたが、果たして目論見通りにいきますかどうか。ご存じの通り、お産は必ずうまくいくとは限りません」
どれほど経過が順調でも、無事に生まれないこともある。産声を上げない赤ん坊を目にしたら、お亀久がますます世を儚むとお稲は案じているようだ。
「ですが、おタネ様は産婆の神様です。めったなことは起きないでしょう」
「産婆の神様と呼ばれていても、本物の神様じゃありませんよ。それに股を広げていきむ姿を赤の他人の生娘に見せるのはねぇ。御新造さんだって、あのときの姿を他人に見せたくないでしょう」
母の言葉をさえぎるお稲におタネ様は何も言わない。いまはお稲がお産を取り仕切っているようだ。
母の信じる産婆の神様はとっくに名ばかりではないか。お亀久はお稲に駄目押しのつもりで申し出た。
「あの、あたしは血が苦手で……」
「だったら、なおさらやめておきな。赤ん坊を産み落とすときはもちろんのこと、後産だって結構な血を見ることになる。お産の最中に取り乱して、邪魔をされたら迷惑だ」
まったくもってその通りだが、母はあきらめが悪かった。断る気満々のお稲の前で深々と頭を下げる。
「無理なお願いをしていることは重々承知しています。それでも、この子に憑りついた死神を追い払ってやりたいんです」
「……だとしても、見ず知らずの他人にお産を見せたいって物好きがいるとは思えませんがねぇ」
「そうよ、おっかさん。そんな女がいるもんですか」
いつもツイていないお亀久だが、今日はめずらしくツイていた。ひそかにほくそ笑んだとき、「でしたら」と母が言葉を継ぐ。
「お産に立ち会わせてくれた方に十両払います。おタネ様とお稲さんにも五両ずつ払いましょう。それでも駄目ですか」
法外な金額を耳にして、お稲が目を丸くする。母はすかさず畳みかけた。
「無事に子供が生まれても、子育てはお金がかかります。特に乳飲み子の間は何かと物入りですからね」
お産を見せるだけで十両も手に入るなら、承知する貧乏人はいるはずだ──母の言葉におタネ様も「そりゃそうだ」と相槌を打つ。お稲は観念したようにうなずいた。
「……そういうことなら、臨月の人に声をかけてみましょうか」
「そんなっ」
お亀久は異を唱えかけ、母に睨まれて口ごもる。結局、お産に立ち会うことが決まってしまった。
『産婆のタネ』(「その一 産婆の神様」)は全4回で公開予定