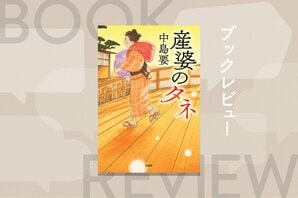二
天領からの年貢米は浅草御蔵に納められ、所領を持たない旗本御家人に家禄として支給される。札差はその米を旗本御家人に代わって受け取り、客の求めに応じて換金する商売だ。
徳川幕府が続く限り、直参の家禄は必ず支給される。
しかし、太平の世が続くにつれて物の値は上がっていくけれど、家禄はまったく上がらない。日々の費えは足りなくなり、旗本御家人は先々支給される家禄を担保に札差から金を借りる。その借金は代を重ねるごとに積み上がり、濡れ手で粟の札差は町人の分際で豪遊する。幕府はそれが目に余り、ふくれあがった借金を踏み倒すことにしたようだ。
降って湧いた人災に江戸中の札差は大騒ぎした。
坂田屋とて例外ではなかったものの、いち早く落ち着きを取り戻した。商売に明るかった田沼意次様が失脚し、「質素倹約」が好きな松平定信様が老中首座になられてから、「何らかの締め付けがあるはずだ」とひそかに覚悟していたという。
「うちはもともと返済の滞っている旗本との付き合いを断っていたからな。そのせいで性質の悪い連中の恨みを買ったが……」
父は後半口ごもり、娘からそっと目をそらす。
たとえ外に出なくとも、噂は勝手に聞こえてくる。お亀久が浪人に攫われたのは、父を恨んだ旗本が陰で糸を引いていたとか。
だが、何の証拠もない上に、下手人はすでにお仕置きを受けている。父は娘に何も言わないけれど、忸怩たる思いがあるのだろう。
「何はともあれ、おまえはいままで通り家にいろ。決して外に出るんじゃないぞ」
言われなくとも出る気はないと、お亀久は素直にうなずいた。
噂ではこの棄捐令で、百万両を超える旗本御家人の借金が帳消しにされたとか。
江戸の札差は百九人。頭数で割れば、ひとりおおよそ九千両を超える損をしたことになる。
うちは大丈夫なようだけど、他の札差はどうなんだろう。相模屋のお八重ちゃんはもうじき祝言を挙げるのに、大丈夫なのかしら。
札差は大体派手好きだが、中でもお八重の父、相模屋伝衛門の気前のよさは有名だ。跡取り娘の祝言には人一倍贅を凝らしたに違いない。ひそかに危ぶんでいたある日、女中たちのやり取りがお亀久の耳に入ってきた。
「あたしたちは坂田屋に奉公していてよかったよねぇ。他の札差は軒並み奉公人に暇を出したっていうじゃないか」
「ああ、平門町の伊勢屋なんて、六人いた女中が三人になったってさ。そのせいで仕事は倍になったのに、膳のお菜はお新香だけだって。御新造様に何とかしてくれと頼んだら、『嫌なら出ていけ』と言われたらしいよ」
「でも、伊勢屋はまだましさ。瓦町の相模屋なんて、女中はすべて暇を出されたってよ」
襖越しの話に息を呑み、お亀久は耳をそばだてる。お嬢さんの盗み聞きに気付かないまま、女中たちは噂話を続けた。
「あそこはうちのお嬢さんと同い年の跡取り娘がいただろう。祝言が近いって聞いたけど、女中をやめさせちまって平気なのかい」
「だから、祝言どころじゃないんだよ。相模屋は娘の花嫁衣装の代金が払えなくて、縁談そのものがなくなったんだって」
「えっ、そうなの」
お亀久が心で叫んだ台詞を女中のひとりが口にする。すると、訳知りらしい女中の声がした。
「もうじき潰れる店に婿入りしたって、何のうまみもないじゃないか。破談になって当然だよ」
「そりゃ、そうだけど」
「金の切れ目が縁の切れ目ってね。せめて祝言を挙げたあとに棄捐令が出ていたら、何とかなったかもしれないのに」
憐れむような言葉が聞こえたところで、母が女中を呼んだようだ。「はい、ただいま」の返事に続き、バタバタと足音が遠ざかる。お亀久は閉じられた襖のそばで、呆然と立ち尽くしていた。
花嫁衣装の代金すら払えなくて、破談になってしまったなんて……お八重ちゃんはどれほど傷ついているかしら。
跡取り娘にして器量よしのお八重は、まさしく「蝶よ花よ」と育てられたお嬢さんだ。多少わがままなところはあったけれど、情に篤く、面倒見がいい。婿となる本両替商の三男とも仲むつまじく、相手は美人の許婚に惚れ込んでいたはずだ。
お八重は家から出なくなった自分を案じ、わざわざ足を運んでくれた。今度は自分が相模屋に行き、幼馴染みを励ますべきだろう。頭ではそう思いながら、お亀久はその場を動けなかった。痛手の少なかった坂田屋の娘に慰められても、嫌みにしか聞こえまい。
どうして、お八重ちゃんがこんな目に……。札差は定法通りに商いをしていただけなのに、お上のなさることは無茶苦茶よ。
だが、どれほど理不尽なお触れでも、商人は逆らえない。お亀久は幼馴染みの胸中を思い、無力な自分に憤る。
紀一郎が行方知れずになってから、まだ半年も経っていない。どうして自分の周りで次々と不幸が起こるのか。お亀久はやり場のない怒りを持てあまし、お八重と最後に会った日のことを思い起こした。
あのときは説教がましいことを言われて、「あんたも許婚がいなくなれば、あたしの気持ちがわかるわよ」なんて恨みに思ったりしたけれど、真実、破談になってほしかったわけじゃないわ。
心の中で言い訳したとき、別れ際のお八重の言葉がよみがえった。口の悪い幼馴染みは「その前に一度お祓いをしときなさいな。あんたは運が悪いから」とお亀久に告げていたのである。
ああ、そうだ。
きっと、自分が不幸を招いてしまうのだ。
魚屋の加吉は自分をかばって斬り殺され、紀一郎は自分の許婚になったせいで、紀州の山崩れに巻き込まれた。理不尽過ぎる棄捐令が出されたのも、自分が札差の娘だからに違いない。
あたしが六年前に死んでいたら、紀一郎さんは無事だったはず。お上だって棄捐令を出さなかったんじゃないかしら。
他人が聞いたら、「馬鹿馬鹿しい」と一笑に付しただろう。だが、お亀久はそうとしか思えなかった。
これ以上自分の周りを不幸にしながら、無為に生きているのはつらすぎる。一日も早くあの世に逝き、更なる不幸を止めなくては。
しかし、「尼になりたい」と父に言ったせいで、近ごろは家の中でもひとりにさせてもらえない。隠れて首を吊ろうとしても、梁にしごきをかけたところで誰かに見つかってしまうだろう。
毒があればいいのだが、あいにく手に入らない。血を見るのは怖いから、刃物はなるたけ使いたくない。お亀久はさんざん悩んだ末に「川に身を投げよう」と決心した。
あたしが部屋にいなくとも、家の中しか捜さないはず。柳橋はすぐそこだし、目をつぶって神田川に飛び込めばいいわ。
自分のするべきことが決まり、お亀久は固く両手を握った。
加吉の最期を目にしたときから、ずっと「血」と「男」を避けてきた。だが、自ら死ぬと決めてしまえば、怖いものなど何もない。そして、九月晦日の暮れ六ツ(午後六時頃)前、夕餉の支度をする女中たちの目を盗み、裏口からそっと抜け出した。
ひとりで外を歩くのは、実に六年ぶりである。お亀久は吹きつける風の冷たさに短い首をすくませた。
日没間近の空は夕闇に染まり、わずかな日の名残が川面を赤く染めている。晦日の夜空に月は出ないが、これから屋形船を出す客がいるのだろう。頬かむりをした船頭が船の提灯に灯を入れていた。
昔はさんざん歩いた家の近所でありながら、今日はすべてが目新しい。お亀久は瞬きをするのも忘れ、じっくりと周囲を見渡した。
軒を連ねる料理屋はこれから忙しくなるのだろう。どの店も入口に女中と下足番が立ち、客を待ち構えている。粋な芸者は座敷に向かうところなのか、三味線持ちを従えて気取った様子で歩いていた。
反対に仕事を終えた半纏着の職人や人足は、くたびれた恰好で先を急ぐ。行き先は居酒屋か、女房や子の待つ自分の家か。いつもは男がそばに寄るだけで震えてしまうお亀久だが、覚悟を決めたからだろう。恐怖を感じることもなく、今生の見納めを目に焼き付けた。
よく「死んだ気になれば何でもできる」って言うけど本当ね。こんなことなら、もっと早く決心すればよかったわ。
柳橋は神田川と大川が交わるところに架かっている。
お亀久は日が暮れ切る前にたどり着き、橋の中ほどで立ち止まった。そのまま欄干に手をかければ、通りすがる人たちに怪訝そうな目を向けられる。それでも、わざわざ立ち止まって声をかけてくる人はいなかった。
すでに真っ暗な川面には、遠くの船の灯りだけがきらめいている。
そして、これから川へ飛び込むのだと改めて思った刹那、お亀久の頭が一気に冷えた。暦は明日から十月になる。神田川の水は刺すように冷たいだろう。
でも、苦しむのはほんの一瞬で、その後は楽になれるのよ。おとっつぁん、おっかさん、先立つ不孝をお許しください。
怯む心と身体を叱咤しても、手足は勝手に震えてしまう。できるだけすぐに死ねますようにと、心の中で念仏を唱え始めたときだった。
「おい、どうしてこんなところにいる」
男の声に振り向けば、死んだはずの紀一郎が暗がりに立っていた。お亀久は欄干から手を放し、よろめくように近づいたが、
「何だ、その間抜け面は。言っとくが、俺は兄貴じゃねぇぞ」
ここにいるのは弟で、口の悪い紀次だ――お亀久は相手の憎まれ口で我に返り、「言われなくとも」と言い返す。二つ違いの兄弟は見た目だけならよく似ており、どちらも端整な二枚目だった。
しかし、おっとりとやさしい兄と違い、弟は喧嘩っ早くて口が悪い。身体も弟のほうが大きくて、町娘には「男らしい」と人気があった。
長らく音沙汰のなかった幼馴染みとこんなところで会うなんて。お亀久が後ずさろうとする前に、素早く手首を掴まれた。
「出不精の亀がようやく出てきたと思ったら、よりによって身投げかよ。まったく、おめぇはろくなことをしやがらねぇ」
うんざりしたような相手の言葉がひび割れた心に突き刺さる。紀次にはひどいことを言われ続けてきたけれど、今日ほどこたえたことはなかった。
「……言われなくてもわかってるわ。あたしがいると不幸を呼ぶ。だから、死のうとしたんじゃないの」
お亀久は胸の内を吐き出して、その手を振り払おうとした。
しかし、男の力にはかなわない。引きずるように坂田屋へ連れ帰られ、両親の前に突き出されてしまう。事の次第を知った両親は青くなり、紀次に繰り返し礼を言った。
「紀次さんが通りかかってくれて、本当に助かった」
「ええ、おまえさんがいなかったら、どうなっていたことか」
「おじさんもおばさんも頭を上げてくださいよ。それより、こいつから目を離さないようにしてくだせぇ」
紀次は横目でお亀久を睨み、ふんぞり返って言い放つ。両親は深くうなずいた。
「ああ、言われるまでもない」
「紀次さんは娘の命の恩人だもの。改めてお礼をさせてちょうだい」
手を合わせんばかりの両親に見送られ、紀次は帰っていく。その後、父はどうしても外せない札差仲間の寄合へと出かけていき、お亀久は母と二人になった。
「六年ぶりに家を抜け出したと思ったら、よりによって身投げだなんて……おまえはどこまで親に心配をかければ気がすむの」
母の声が震えているのは、涙をこらえているからか。お亀久は両手で膝頭を掴み、上目遣いに母を見た。
「だって、あたしのせいでみなが不幸に……」
「心得違いもいい加減にしなさい。何でそんなことを言い出すんだか」
さも頭が痛いと言いたげに、母はこめかみに手を当てる。相手の言いたいことは承知の上で、お亀久は首を左右に振った。
「魚屋のおじさんはあたしをかばって死んだのよ。それに紀一郎さんだって」
棄捐令はともかく、加吉と紀一郎の不幸は自分にかかわったせいだろう。あくまで我が身を責める娘に母は声を荒らげる。
「あんたが望んで攫われたわけでも、紀州の山崩れを起こしたわけでもないだろう。あんたが自害をしたら、命を捨てて助けてくれた加吉さんは死に損じゃないか。そもそもあんたは難産で、あたしだって死にかけたんだよ」
初めて聞く最後の言葉にお亀久は思わず息を呑む。
「じゃあ、あたしのせいでおっかさんまで……」
やはり自分が生まれたのは間違いだった――お亀久がそう言いかけたとき、母に平手で頬を打たれた。
「実の母親の前で、よくもそんな言葉が吐けたもんだね。おまえを『亀久』と名付けたのは、万年生きる亀にあやかり、長生きしてほしいからじゃないか」
「…………」
「母親がどれほどの痛みに耐えて我が子を産むか。こうなりゃ、赤ん坊が生まれるところをその目でしかと見るがいい」
顔を真っ赤にして怒られて、お亀久は逆に青ざめた。赤ん坊が生まれるところとは、お産に立ち会えということだろう。
詳しいことは知らないものの、お産は命がけだと聞く。これ以上、人の生死にかかわるなんて真っ平御免だ。
「おっかさん、勘弁して」
「いまさら血が怖いなんて泣き言は聞かないよ。それこそ死ぬつもりなら、何だってできるだろう」
こっちを睨む母の目には、うっすら涙が滲んでいる。
自分の浅はかな振る舞いがどれほど母を傷つけたか。嫌でも思い知らされて、お亀久は嫌だと言えなくなった。
『産婆のタネ』(「その一 産婆の神様」)は全4回で公開予定