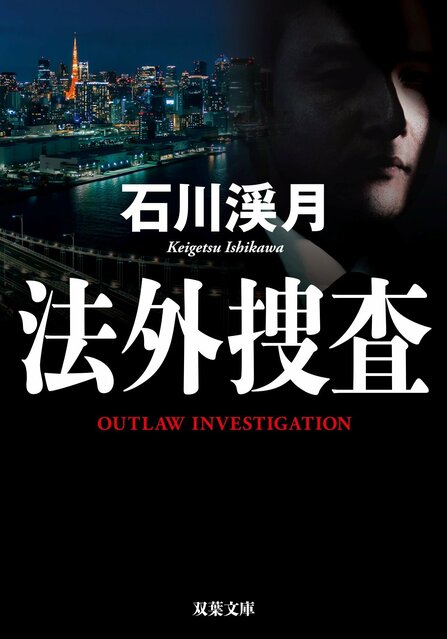3
来栖修は、ロシア大使館の裏にあるビルの前で腕時計に目をやった。秀和の事務所から歩いて十五分ほどの場所だ。ビルの地下にあるバーで男と会う約束になっている。指定された午後八時まで、あと五分。入るのにはちょうどいい時間だ。
新宿駅東口駅前広場の爆発事件から二日がたった。死者三人、重軽傷者四十人という被害が出た。新聞もテレビもこの事件で持ち切りだ。いまだに犯人の特定には至っていない。犯行声明も出ていない。
階段を下りると重い木製のドアがある。店名は書かれていない。店の外にカメラが設置してあるのだろう。扉が内側に開き黒服の男が丁寧に頭を下げて、来栖を店に招き入れた。
店内には、会話をじゃましない程度に抑えた、ピアノの音が流れている。壁もテーブルも黒を基調にした落ち着いた雰囲気だ。
「こちらでしばらくお待ちください」
黒服に言われ、ボックス席に着いた。
おそらく別の誰かと話をしていて、終わるまで待っていろということだ。来栖とは会わせたくない相手なのだろう。
来栖を呼び出した男の名は、佐々倉剛志。警察庁時代の先輩であり、現在は刑事局刑事企画課長のポストにいる。四十八歳で階級は警視長だ。かつてこのポストから総括審議官、刑事局長などを経て警察庁長官に上り詰めた者もいる。今のところキャリア官僚として、順調に歩んでいると言っていいだろう。
秀和を立ち上げて、来栖を代表に据えたのが佐々倉だった。彼個人の力で、そんなことができるわけはない。背後にどんな動きがあったのか、来栖は知らない。佐々倉が口にしないことは、あえて訊かない。
佐々倉との付き合いは来栖が東京大学に入った直後からだった。将来、警察庁に入りたいという希望を持っていた来栖は、大学の先輩の紹介で佐々倉に会った。当時の佐々倉は二十九歳で、すでに警視だった。近く、ある県警の捜査二課長として出ることが決まっていると聞かされた。まだ二十代なのに、全く別の世界の人間に見えた。
短い時間だったが、佐々倉は警察官僚としてのやりがい、将来あるべき警察の姿について熱く語ってくれた。来栖はこの濃密な時間を経験して、進路を警察庁一本に絞った。
ところが二年後、両親が飲酒運転のトラックに撥ねられ他界した。近い親戚もなく途方に暮れていると、突然、佐々倉が訪ねてきて、両親の仏前に線香をあげてくれた。
佐々倉に、これからどうするのかと訊かれた。アルバイトをしながら大学に通うと言うと、そんな時間があったら勉強しろ。これは俺からの奨学金だ。警察庁で待っているぞ。そう言ってまとまった金を渡された。
親が残したわずかな貯金と保険金、それに佐々倉から受け取ったもので、最低限のアルバイトで大学生活を送ることができた。そして卒業後、希望通り警察庁に奉職が決まった。
入庁後、同じ部署に配属されることはなかったが、常に連絡を取り合っていた。
来栖が本庁勤務の間は、定期的に会って話をした。佐々倉は、日本の警察組織の優秀さは世界に誇れるものであり、その能力を無駄なく効率的に活かすのが警察官僚の仕事だと繰り返した。
今はそれが十分に活かされているとは言い難い。組織の改革と人事評価の在り方、部署を越えた情報共有のシステムを作ることが必要だ。全ては国民の安全と安心を守ることにつながる。それが佐々倉の考える理想の警察像だった。
一方で佐々倉は、決して理想だけを口にする男ではなかった。理想を実現するためには、警察庁の中で地位を上げていかなければならない。今はたとえ必要な時に口を閉ざすことがあっても、現実の出世争いに勝ち残らなければいけない。
来栖自身、理想とは違う警察組織の姿も、嫌と言うほど目にしていた。否応なしに放り込まれる出世争いがその一つだ。同期の中での足の引っ張り合い、政権への阿り。時には現場への不当な介入まで起きてくる。
佐々倉は、その全てを乗り越えて地位を手にすることで、理想を実現させると言った。実際に佐々倉に蹴落とされ、出世レースから外れていった官僚の姿も見ていた。
来栖が、警察庁を辞めざるを得なくなった時に、声をかけられた。自分が信じる警察改革を実現するために、力を貸してほしい。佐々倉の目は真剣だった。
来栖も十年以上、警察庁に身を置いていた。佐々倉の言葉を額面通りに信じるほど甘くはなかった。同時に、この男なら何かをやってくれるという期待があった。行動を共にすることで、自分の信じる道を実現できるかもしれない。今も、その思いは持っている。
「お待たせしました。ご案内いたします」
黒服が声をかけてきた。
店の奥の個室に案内された。この部屋も黒を基調にした落ち着いた雰囲気だ。四人掛けのボックス席が二つ。部屋にいるのは佐々倉一人だった。テーブルに飲み物は置いていない。
「待たせてすまなかったな。座ってくれ」
佐々倉が厳しい表情で言った。
来栖が腰を下ろすのと同時にノックの音がした。佐々倉が返事をすると、ドアが開き黒服が入ってきた。二人の前に氷が入った水のグラスを置き、黙って頭を下げて出て行った。
「新宿駅東口の爆発事件が面倒なことになっている」
黒服が出たのを確認して、佐々倉が言った。
事件が起きてすぐ、新宿署に刑事部と公安部合同の特別捜査本部が置かれ、同時に警視総監を長とする総合警備本部も設置された。
捜査本部には、捜査一課を中心に鑑識や科捜研。そして公安部からは、公安と外事の精鋭が入っていると聞いている。組織犯罪対策部や各所轄からも大量に捜査員が動員されているはずだ。おそらく二百人は超える規模になっているだろう。
「警視庁は事件名をJR新宿駅東口駅前広場爆発事件としているが、当然テロを視野に入れている」
佐々倉が、いったん手元のグラスに目をやり、すぐに来栖に視線を戻した。
「公安はいつものように、情報を抱え込み、捜査本部にすら上げない。それを許しているのは、警備局長の海藤だ」
警視庁をはじめ、全国の公安警察官は、警察庁警備局の指揮下にある。そのトップが海藤重明だ。
「さらにこれだ」
佐々倉が上着の内ポケットから、新聞のコピーを取り出した。大手全国紙の今日の夕刊の一面だ。来栖もすでに目にしていた。
『捜査方針巡り対立』
今回の事件の捜査を巡り、刑事部が公安部に対して、これまで集めたテロ関係の捜査資料を、全て出すように求めたのが発端だとしている。公安側は、必要と認められるものは出すが、全てを見せるわけにはいかないと答え、対立が続き、捜査に支障をきたしかねない状況に陥っているとしている。
「これは幹部会議の席で、無理筋とわかりながら刑事部長が発したものだ。やり取りを知っている人間は極めて限られる」
「刑事部のリークではないのですか」
「どちらもそこまで馬鹿じゃない。今の段階で警察が世間から信頼を失い、批判を浴びることになったら、刑事も公安も関係ない。幹部が総入れ替えだ」
佐々倉が、深刻なのはここからだ、と言って来栖を見つめた。
「このリークがきっかけで、警察庁、警視庁とも幹部の間に疑心暗鬼が広がっている。誰が誰の足を引っ張ろうとしているのかわからないということだ。刑事局も警備局も、信用できる人間だけによる情報の囲い込みが一層激しくなった。はっきり言って、組織が十分に機能していない。それが現状だ」
「それを何とかするのが警察官僚の――」
「現実的な話をしたい」
佐々倉が来栖の言葉を遮って続けた。
「今回の爆発事件について秀和で調べてほしい」
思いもしない言葉だった。いくら情報の囲い込みが激しくなっていると言っても、警察が総力を挙げている捜査以上のことが、秀和にできるとは思えない。
「事件を解決してくれと言っているのではない。あらゆる面から情報を集めてほしい」
来栖は、テーブルの上のグラスを見つめながら考えた。
佐々倉は、刑事局のトップである警察庁刑事局の横光達也局長の子飼いだ。横光刑事局長と海藤警備局長は同期入庁で、警察庁長官レースの先頭を走り、しのぎを削っている。
今回の捜査の主導権を握り、手柄を立てることで、長官レースで頭ひとつ抜け出すことができるのだろう。うまくすれば、相手に致命的なダメージを負わせることもできるはずだ。主導権を握るのに必要なのは一にも二にも情報だ。
「秀和が集めた情報は、事件の解決のために使われるのですか。それとも長官レースの道具にですか」
来栖の問いかけに、佐々倉は小さく首を振った。
「この事件が解決しなければ、警察は国民から見放される。それでも情報の囲い込みは行われている。それが現実だ」
そこまで言って、佐々倉は、ふっと身体の力を抜いて、穏やかな笑みを見せた。
「君が言いたいことはわかる。確かに私は横光刑事局長に、警察庁長官になってほしいと考えている。理想を実現するためには、組織の中で上に行くことが必要だ。そして、これだけ大きな事件だから、警察改革のきっかけにできる。私はそう信じている」
横光刑事局長と海藤警備局長の長官レースは、事件解決までいったん棚上げ、とはならないのが現実だ。それでも、やる価値のある仕事だ。事件解決に力を発揮することで、秀和がこれから一定の影響力を持つこともできる。
「ひとつ確認したいことがあります」
仕事を引き受けるにしても、ただの使い走りになるわけにはいかない。
「捜査本部に上がった捜査情報はもちろんですが、佐々倉さんが掴んだ情報についても、全て教えていただけますか」
「当然だ」
佐々倉は、躊躇うことなく答えた。
「ただ残念だが、今のところ実行犯や背景について、具体的な情報は上がっていない」
捜査については、佐々倉の言葉を信用するしかない。来栖には、もうひとつ、気になっていることがあった。
「今回の事件の背景に、警察も実態を掴んでいない強大な組織の存在がある。その組織が動き出した。疑心暗鬼の原因はそこにある。そうはお考えになりませんか」
事件の一報を聞いた時から感じていたことだった。
来栖の問いかけに、佐々倉はわずかに首を捻った。
「都市伝説に捉われるとは、君らしくないな。事件が解決すれば全てがわかる。私は君を信頼している。力になってほしい」
佐々倉の口から、存在を否定する言葉は出てこなかった。代わりに出てきたのは、都市伝説という言葉だ。今はこれで十分だ。
「わかりました。やらせていただきます」
佐々倉の目を見たまま頷いた。
「期待している」
佐々倉が落ち着いた声で言って、腕時計に目をやった。
事件解決のめどが立たない中で、佐々倉に、時間の余裕などないはずだ。別の人間と会う約束があるのだろう。
「これで失礼します」
来栖は立ち上がった。
「すべてが解決したら、ゆっくりやろう」
佐々倉が笑みを浮かべて言った。
黙って頭を下げて部屋を出た。黒服がドアまで先導した。
階段を上がりビルの外に出ると、夜の喧騒に身体を包まれた。
思いもかけない展開になった。秀和が、この事件の解決に力を発揮する機会を与えられた。背景に触れた時、佐々倉は都市伝説だと一蹴した。それは来栖が考えている組織の存在を意識しているからに他ならない。
存在を確認した者はいないが、警察関係者だけでなく政財界のトップに立つ人間なら、誰もがその気配だけは感じる組織。誰が名付けたのか、警察関係者の間ではスサノウと呼ばれている。日本神話の破壊の神。そして新しい国を造る先駆けとなった神。誰もが都市伝説と言って、正面から見ることを避けている。
その見えない組織が動き出した。事件の一報を聞いた時から、そう感じていた。いつかこの日が来る。警察庁にいた頃から持ち続けてきた感触だ。
立ち止まり、深呼吸をした。昨日までとは明らかに違う風が来栖の頬をなでた。秋の気配を感じる風だった。
このつづきは、書籍にてお楽しみください