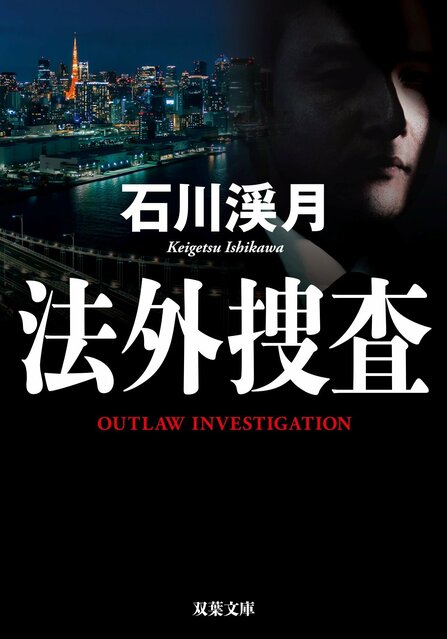2
間もなく十月の声を聞こうというのに、真夏を思わせる日差しが降り注いでいる。街を歩いている若者も夏の装いだ。
滝沢は、六本木の街を秀和の事務所に向かって歩いている。
昨夜は自宅に帰ったのが午前三時を回っていた。今日は少し身体を休めるつもりだったが、朝方、来栖から呼び出しがあった。
六本木交差点を背にして、外苑東通りを飯倉方面に五分ほど歩き、左に曲がった。その先に秀和が入っているマンションがある。
オートロックの玄関を開き、エレベーターで最上階の八階まで上がった。廊下に面して三つの扉がある。一番奥が秀和の事務所だ。
鍵を開けて中に入る。短い廊下を通って、すりガラスの入ったドアを開けた。広いリビングがそのまま事務室になっている。
「おはようございます。お疲れのところ申し訳ありません」
窓際のデスクから来栖が声をかけてきた。この季節でも濃紺のスーツに白いワイシャツ、そしてネクタイをきっちりと締めている。実直な銀行員を思わせる風貌だが、元は警察庁の官僚だ。辞めた経緯は知らない。滝沢と同じ年の三十六歳だが、警察庁を辞めた時の階級は、滝沢の警部補より三つ上の警視正だった。お互い警察に残っていたとしても、こうして挨拶を交わすことなどなかっただろう。
秀和を設立した経緯については口にしないが、警察庁時代の上司と、それにつながる政治家あたりが出資している、と滝沢は踏んでいる。
「滝さん、おはよう」
フロアの奥から声がかかった。応接ソファに座った翔太が、コーヒーカップを手に笑顔を見せていた。
向かいには冴香が座っている。滝沢の顔を見て、小声で、おはよう、と言った。すぐに視線を逸らし、セミロングの髪を軽くかき上げた。今日もライダースジャケットだが、昨日の活躍など想像もできない静かな佇まいだ。
その隣に座っているのは、秀和副所長の肩書を持つ沼田信三だ。五十歳を少し過ぎているが、無駄な肉はなく、いつも背筋を伸ばしている。現場に出ることはめったになく、仕事を遂行する上での作戦参謀といった立場だ。これで秀和のメンバーが全員そろった。
滝沢は、コーヒーメーカーから紙コップにコーヒーを注ぎ、翔太の隣に腰を下ろした。コーヒーは、毎朝、来栖が淹れる。彼なりのこだわりがあるようだが、豆を替えたと言われても、滝沢には、わからない。旨いことは確かで、全員が毎日飲んでいる。
来栖は自席で電話をかけだした。
ソファーの脇にあるテレビでは、政治家の討論番組をやっている。衆議院の解散総選挙が近いと噂されるなかで、最近はこうした番組が増えている。画面に大久保隆司議員がアップになった。熱弁をふるっているようだ。娘の行動は思うようにならなくても、国の舵取りは語れるということだ。
「昨日は、ご苦労だったな」
沼田が声をかけてきた。かつて警視庁公安部の外事一課にいたと聞いている。公安時代に身に付いた習性なのか、表情から感情を読み取ることはできない。ロマンスグレーの穏やかな中年紳士に見えるが、時折り見せる視線の鋭さは、公安時代の姿を彷彿させる。
「お待たせしました」
来栖が歩み寄ってきた。
「昨日の件でいくつか確認させていただきたいことがあります」
来栖は、隣のデスクから椅子を引き寄せ、滝沢たちを左右に見る位置に座った。
「ちょっと待って」
冴香が声を上げた。
「なんでしょうか」
来栖が穏やかな顔を冴香に向けた。
「もし昨日、五分早くあいつらの仲間が駆け付けていたら、あたしたちは、今頃どこかに埋められてる。政治家や金持ちの裏を探るような仕事とは違う」
来栖は、黙って冴香の話を聞いている。
「冷静に考えて昨日は運が良すぎたわ。本来ならあの状況で店に入るべきじゃなかった」
冴香の言う通りだった。いくら相手の人数がわかったからといって、あそこで突っ込むのは無謀だった。
「俺の判断ミスだったかもしれないな」
滝沢は、冴香に向かって言った。あの場での判断は滝沢に任されていた。
「そんなことを言っているんじゃない。やめた方がいいと思ったら、あたしもその場でそう言うわ」
「冴香さん。結論を」
来栖が落ち着いた声で促した。
「あの手の連中を相手にするときは、こちらもそれなりの武装は必要よ」
「銃を用意すればいいですか」
「できるの」
「この国で銃を持って歩くのはリスクが大きすぎます。それでも皆さんが――」
来栖が言葉を切り、テレビに視線を向けた。
全員の目がテレビに向いた。画面はまだ討論会をやっているが、ニュース速報を知らせる音が鳴っている。画面の上に文字が現れた。
『JR新宿駅で爆発 複数のけが人 警視庁』
画面の文字が消え、新しい文字が現れた。
『JR新宿駅東口駅前広場で爆発 けが人多数 警視庁』
誰も口を開かずテレビを見つめている。
しばらくすると画面が、スタジオのアナウンサーに切り替わった。特設ニュースが始まった。翔太がリモコンでボリュームを上げる。
アナウンサーは短い原稿を繰り返し読んでいる。爆発があったのが午前十一時頃だということだが、速報のテロップで流れた以上の情報はない。
画面がヘリコプターによる上空からの中継映像に換わった。すでに救急車や消防車、警察車両が周辺に集まっている。ブルーシートの上に何人かが横たわり、救急隊員の処置を受けている。重傷者用のテントも張られている。
周辺は人で埋まっている。土曜日の昼前の新宿だ。どれだけ多くの人が、この辺りにいるのか想像もつかない。駅の東口と広場に直接つながっている通路は封鎖されているようだが、他から外に出た乗客や買い物客が集まってきている。
中継の画面に新たな文字が出た。
『三人心肺停止 少なくとも数十人が重軽傷』
同じ内容をアナウンサーが繰り返している。
「信じられんな」
沼田がつぶやくように言った。
「どういうこと」
翔太が沼田に顔を向けた。
「建物の中ならガス爆発といった事故が考えられる。だが広場で爆発というのは……」
沼田はそこで言葉を切った。
「爆弾テロ」
来栖が画面を見ながら言った。普段は見せることのない険しい表情だ。
「今の日本でテロを起こすグループなんているの?」
冴香が沼田に顔を向けて訊いた。元公安警察官の沼田の専門分野だ。
「難しい質問だな」
沼田が腕を組んで目を逸らし、わずかの間考え込んだ。
「一般的にテロというのは、政治や宗教、それに特定のイデオロギーに基づいた目的のために、政府や社会に対して恐怖を植え付ける行為とされている。だが時代と共にその形態も複雑になっている」
沼田がひと呼吸おいて続けた。
「自由主義の経済社会では、必ず格差とそれによる不満が生まれる。そして不満と被害者意識が広がり、それらを共有するグループができる。ネット社会では、顔も知らない人間が仲間になることは簡単だ。そしてそれが国家体制や社会の制度を壊す目的で行動を起こせば、警察はテロと位置付ける」
沼田がいったん言葉を切ってみんなの顔を見回した。
「二〇〇八年に起きた秋葉原の無差別殺傷事件を覚えているか。男がトラックで歩行者天国に突っ込み歩行者を撥ね、その後、車を乗り捨てて、刃物で周囲の人を殺傷した事件だ。七人が亡くなっている」
滝沢は黙って頷いた。刑事になる前だったが、警察官になってこれほど衝撃的な事件はなかった。
「それと同じ構図の事件がロンドンであった。二〇一七年に起きたロンドンテロ事件だ。犯人は、テムズ川に架かる橋でワゴン車を暴走させ、歩行者を次々に撥ねた。車から降りた犯人たちは、近くのマーケットで食事中の客を刃物で襲った。死者は八人、負傷者は五十人近くに及んだ。犯人はその場で警察官に射殺された。その後、ISが犯行声明を出した。ヨーロッパで相次いだテロ事件の一つだ」
沼田が小さく首を振って続けた。
「車で無差別に通行人を撥ね、その後、近くにいた人を殺傷する。犯行の形は同じだが、秋葉原の事件は、社会に鬱屈した感情を持った個人による無差別殺傷事件とされている。だがこの男に同じような感情を持つ仲間がいて、他でも事件を起こして国家や社会を崩壊させてやろうという意図があったらどうだ。これはテロ事件になる」
「無差別殺人とテロは紙一重か。そういう意味で言ったら、今の時代、いつ日本でテロが起きてもおかしくない、ということになるね」
翔太がコーヒーカップに手を伸ばして言った。
「ネットで知り合って犯罪を犯す連中は年々増えている。ネットと言っても裏の世界だ。そこでつながった連中を見つけるのは難しい。警察がやらなければいけないことは、山ほどあるよ」
翔太は、秀和の調査員の顔の他に、ホワイトハッカーの顔を持っている。コンピューターやネットワークに関して、高度な知識と技術を持つ仲間たちと活動している。企業や公的団体からの依頼を受けて、ウイルス対策やハッキング防止の指導をしているということだ。以前、ハンドルネームをkoban、交番にしていると笑って話していたことがあった。
翔太は制服警察官の時に、警察庁のデータがハッキングされていることを掴み、悩んだ末に上司に報告した。そのおかげで大事には至らなかったが、翔太自身も警察庁のデータにアクセスしていたことを咎められ、戒告の懲戒処分になったと聞いている。
「翔太の言う通りだ。警視庁のサイバー犯罪対策課が中心になるのだろうが、公安も独自にサイバー対策チームを作った。即戦力の人材を求めていたと聞いたが、翔太は、そこには誘われなかったのか」
沼田が言うと、翔太は顔をしかめた。
「非公式に打診はあったよ。でも公安のやるサイバー対策は、捜査対象を裸にするために、どんなシステムにも侵入できる技術が求められるんだ。言ってみれば、令状なしで家宅捜索するみたいなものでしょ。僕には向かない」
「それで警察を辞めたの?」
冴香が少し驚いたような目で翔太を見た。
それには答えず、翔太はコーヒーを口にした。
今回の爆発がテロであれ、社会への歪んだ感情が起こした個人の犯罪であれ、警察が威信にかけて解決しなければいけない事案であることは間違いない。
そして警察としてもう一つ重要なのは、無差別殺人であれば刑事部が、テロと認定されれば公安部が捜査の主導権を握るということだ。一般市民にとっては、どちらでも構わないところだが、警察ではこれが重要な問題になってくる。
ふと気付くと、来栖が険しい表情のまま、テレビの画面の見つめている。
「所長、どうかしましたか」
その言葉で我に返ったように、来栖がいつもの冷静な表情に戻った。
「秀和の仕事は、しばらくはなさそうですね。皆さん待機ということでお願いします」
来栖が落ち着いた声で言って、自分のデスクに戻っていった。
『新しい情報です。警視庁は、現場付近にいた三人の死亡が確認されたと発表しました』
アナウンサーの声で、みんなの視線がテレビに移った。
『さらに、少なくとも三十人以上がけがをして、手当てを受けているということです』
なんの罪もない市民が理不尽に命を奪われた。警察にとってまさに存在意義を問われる事件だ。すぐに特別捜査本部が設けられ、あらゆる部署から人が集められるはずだ。
滝沢は、テレビ画面に映る現場の映像を見ながら、捜査はどこから手を付けるべきか、自分なら何ができるか考えた。
すぐに首を振って、頭の中の考えを追い払った。今の滝沢にできることは何もない。元刑事。元が付けば何もできない。理不尽な犯罪に対する憤りを黙って噛みしめるしかない。
窓の外に目をやった。日差しは来た時よりも強くなっている。捜査で外を回る捜査員たちの苦労を思った。それでも彼らには正義がある。
都会の明るい空がやけに虚しく見えた。