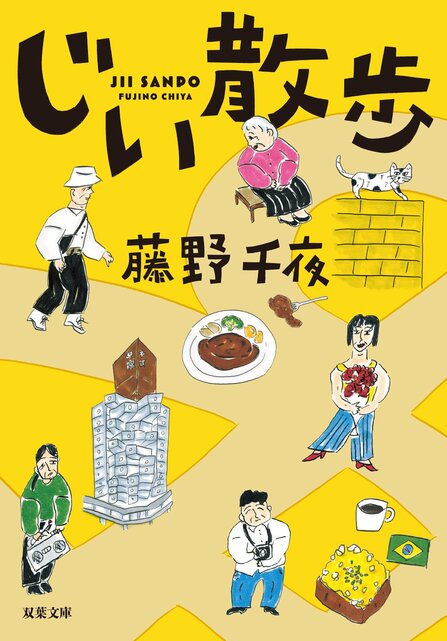3
「新平さんは、どういうつもりで英子と会ってるの?」
玄関先でいきなり訊かれ、新平は首筋にじんわり汗をかいた。英子と付き合いはじめてすぐ、東京で彼女の面倒を見ていたお姉さん、ひい姉ちゃんが帰郷して、新平の家を訪ねて来たのだった。
昭和十七年だった。
ひい姉ちゃんは英子より十歳以上年上で、姉というより、母親がわりだった。純粋に心配で訪ねて来たのか、それとも本心を探ってほしいと英子に頼まれたのか。いずれにしろ問われたことの重さを真剣に考え、考え、考えて新平は真っ直ぐ顔を上げた。
「七年待ってください。七年経ったら結婚します」
「七年?」
大工の棟梁をしている父親のもと、あと七年みっちり修業を積めば、一人前になれると計算したのだった。一人前になれば、所帯だってもてる。
その計算も説明すると、ひい姉ちゃんは了解してくれた。
椎名町の自宅から池袋まで、もうすぐ八十九歳の新平の足でも、だいたい二十五分くらいだった。
もっとも新平はかくしゃくとして、七十代、七十九歳くらいに見えるけれども。実際、よく体を鍛えているぶん、まだその頃の脚力は維持しているのだろう。
昔は川だったタイル敷きの遊歩道を、ぶらりぶらりと行く。細い道幅に植え込みがたっぷりあって、植木がくねくね道のコースを作っている。
真っ直ぐ行ってあちらへくねり。また真っ直ぐ行って、今度はこちらへくねり。両脇の建物は、一軒家よりマンションが多くなった。昔なじみの銭湯も、いつの間にかビルの一階に、こぢんまり収まっている。ちょうど園庭の手すりが見える幼稚園は、お休みかと思うくらい静かだった。
校舎に蔦のからまる立教大学へとつづく通りを曲がる。
ふと思い立って路地を折れ、江戸川乱歩邸の前まで歩いた。
平井姓の表札がかかった門柱と、ゆるくカーブを描く、玄関までのしゃれたアプローチ。ガラスタイルで囲われた、広々とした玄関口と、薄茶色いタイル貼りの洋館に目を細める。
ちょうど観覧日だったので、砂利道に敷かれた丸い飛び石を踏み、新平は庭のほうへ進んだ。洋館の裏手へ回ると、何度か訪れた庭から、書庫になった二階建ての土蔵、天井の高い洋館の応接間を硝子越しに見ることができる。乱歩は戦前から、昭和四十年に亡くなるまで、ここで暮らしたそうだから、だいたいその頃の様子だろうか。マントルピースのある応接間の、窓枠の白とソファの青が美しい。
いい目の保養になったと乱歩邸を出ると、アートや文学、ちょっとだけエロスもある古書店、夏目書房にも立ち寄る。
さらに向こうの文庫専門書店、文庫ボックスで、いい本がないかと物色。小説の文庫を一冊買って、カバーをかけてもらった。
馴染みにしている喫茶店に寄ったのは、もう午後一時だった。
壁に大きくブラジルの国旗がかかった店内に、席が空いているのを確かめ、奥の注文カウンターへ進む。アルバイトの若い女性に、コーヒーと玉子トーストを注文した。白いブラウスにセンターで分けた長い黒髪、どこか儚な笑顔が魅力的な女性だった。お名前は? と前に新平が問うと、恥ずかしそうに下を向いて首を横に振った。九十歳近いおじいさんにナンパされておかしかったのか、いつもより大きく笑っていた。名前はまだ知らない。
一品が二百円ちょっと、二品でも小銭で済む会計をその場でしていると、すぐにマスターが横からコーヒーを運んできた。豆のことを訊ねると、早口でなんでも教えてくれる陽気なマスターだった。彫りの深い顔立ちをして、青白ストライプのシャツを着ている。店の奥が焙煎室になっていて、そこで挽いた豆を店内で販売もしている。
砂糖とミルクをたっぷり入れたコーヒーを、新平は自分の決めた席に運び、すっと一口飲む。豆を煎って粉を挽き、お湯を注いで濾したものを飲もうだなんて、一体誰が言い出したのだろう。
うまい。
産地別、ブレンド別のコーヒー豆が入った透明な筒型キャニスターが、奥と手前、店を二つに分けるようにずらりと並んでいた。あちらとこちらで不揃いな椅子やテーブルは、どれも年代物で、よく使い込まれている。カウンターの向こう、オーブントースターに分厚いパンがセットされるのが見えた。
新平が注文した玉子トーストを、いよいよ焼きはじめるのかもしれない。
七年経ったら結婚します。
その約束に怒ったのは新平の母だった。あんな気取った娘、うちにはいらない。前から気に入らなかったけど、お姉さんを寄越して、あんたを脅すなんて、もう許せない、と。
怒りは完全に英子に向けられていた。
「脅されたわけじゃない」
「いや、脅された」
「俺のほうが待ってもらう話だよ」
「やめなさい。あんな娘。いますぐおやめ!」
「やめるもんか!」
新平は昔から意地っ張りだった。一度自分がこう、と決めれば、それを貫き通す。たとえ窮屈でも、大変でも。理不尽にやめろと言われると、なお反発した。
ただその性格は、もとより母から受け継いだものだった。その喧嘩めいたやり取りをして以降、母は余計に意固地になった。新平の嫁に英子はふさわしくない、絶対に結婚させない、と、ことあるごとに言いつづけた。どうせあっちだって、七年も待っていないだろうがね、とも。
結婚する、と決めた意地っ張りと、させない、と決めた意地っ張りとの闘いは、ほどなく新平が工場に徴用されたことで一旦やむことになった。
大工の修業を休んで、鍛錬工場で働かなくてはいけない。溶鉱炉を赤く燃やし、鉄鋼を鍛錬する工場だ。新平は、そこで二年半働いた。やっと離れることになったのは、「赤紙」と呼ばれる召集令状が届いたからだった。
出征の朝、駅には新平を見送りに四人の若い女性があらわれた。
うち三人は鍛錬工場の女工さんで、一人は手作りのタバコ入れを、もう一人はお弁当を作ってきてくれた。そしてもう一人、細面の可愛らしい娘が、千人針を縫ったさらしと、武運長久、と血文字で記してある日の丸を差し出した。
「これは、どうした?」
「小指を」
切って、その血で書いたのだという。まだ傷跡も生々しい右手の指を立てた若い女工に、そう、ありがとう、と新平は礼を言った。
そしてホームには、もちろん英子もいた。目に涙をいっぱいためて、小さな針箱をくれた。なんてきれいな目をした人かとあらためて思ったけれど、未練になりそうでそのことは言わなかった。
連隊のある赤羽までは、新平の父親と、五つ離れた弟の定吉が一緒に来てくれた。途中、土浦を過ぎたあたりで列車が空襲に遭って急停止した。霞ヶ浦の飛行場を攻撃に来た敵機かもしれない。車両の床にしゃがみこんだ定吉が、座席に隠れるような低い体勢で、なむあみだぶつ、なむあみだぶつ、と何度も唱えた。新平はそのまま真っ直ぐ背を伸ばして、席に座っていた。
赤羽では、爆弾をかかえて戦車の下に走り込む訓練をした。
爆弾、というより、火薬の詰まった木箱だった。重さが十キロ以上あり、導火線を引くと爆発する。荒川土手で、その木箱を抱えて走り、実際に爆発もさせた。
死にたいとはまったく思わなかったが、死ぬ覚悟はできていた。言われたことならやるけれど、自分からお国のためになにかをするといった意識はなかった。むしろ嫌なこったと思っていた。でも、これはこれで、もうそういう運命なんだと新平は悟った。
訓練を終えると、隊は熊本へ向けて出発した。
敵の戦車が上陸したら、爆弾を抱えて、その下に走り込んで導火線を引く。引かなくても踏みつぶされて爆発できるのかもしれない。
山中に潜んでその機会を待ち、どれほど経っただろう。やがて新平を含めた三人が、食糧を調達するよう命じられた。雑嚢を背負い、おそるおそる峠を越して行くと、戦争はもう終わっていた。里の民間人に新聞を見せてもらって知った。
八月の十七日だった。
慌てて隊に戻ったときには、そちらも解散済みだった。炭焼小屋に隠れていた三百人ほどは、まるで夢のあとのようにすっかり消えていた。待っている者はおろか、書き置き一つなかった。
新平は唇をとがらせ、ふん、と一回鼻を鳴らした。
ふんどしを五本持って入隊したが、すぐに荷物から替えが全部消えてしまった。残りはつけている一本だけになった。軍隊なんてそんなところだ。どろぼうだらけだと新平はずっと思っていた。
雑嚢の中に、靴下に入れた生米を持っていたから、取り残された三人でそれを分け、かじりながら帰った。途中の農家でかまどを借り、ようやく煎った米を食べることができた。そうして辿り着いたのは鹿児島本線の駅だった。
切符を買うお金なんてなかったから、着払いで、と無理を言って乗せてもらった。すでに客車は満杯で、外に掴まるしかない列車だった。あるいは石炭車に乗って、ずり落ちないように気をつけるか。
一体どれほどその列車に掴まっていたのか、やがて博多駅で降ろされ、駅前の広場で野宿をした。一緒にいた二人とは、いつの間にかはぐれていた。
つぎの日もまた客車には入れず、外に掴まったまま、水がじゃぶじゃぶとしたたる関門トンネルを通った。広島で乗り換え、そのまま寝ずに大阪から名古屋へ。いよいよ限界、と客車の手すりに体をロープでくくりつけて眠った。中にいた小父さんが、兵隊さん、どこから? とおにぎりをくれた。
東京駅についたのは八月二十三日だった。
そこから郷里へ帰り、ススだらけ、シラミだらけの服と、体を釜で煮てもらった。
風呂に入ったというより、煮てもらったという心境だった。幸い懐かしい町の風景に、戦火の被害はほとんど見られなかった。