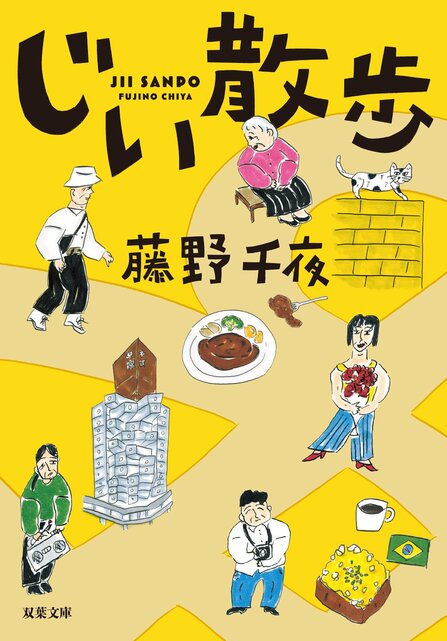1
深夜、おかしな物音がして目を覚ますと、横の布団に正座をして、妻の英子が泣いていた。
十一月で八十八になる老妻だった。もちろんそれを言うなら新平のほうは十月で八十九になる、もっと立派な老夫だったけれども。
どうした、と訊くと鼻をすすり、なんでもない、と妻は言った。コンセントに挿した平たい常夜灯のオレンジにぼんやり照らされる中、両手で顔を覆って、二、三度首を振り、また短く鼻をすする。
「なんだ? 大丈夫か?」
さっきより目を大きく開け、首を傾け、はっきり訊くと、
「うん。大丈夫」
と、ようやく新平のほうを見て言い、英子は丸い体をころんと横たえた。掛け布団の作っていた空洞に、うまく足から潜り込むと、布団の端を掴んで、さっと顎の上まで引き上げる。なんだかそういう珍しい動物がいるみたいに。
おやすみ。新平が声を掛けると、おやすみなさい、と言った。
朝九時にはもう、けろっとなにごともなかったような顔をして、お手洗いに立ち、顔を洗い、着替えをしていたから、新平はなにも訊かなかった。
自分の布団を畳み、マットレスの上で、いつもの体操をするのに忙しい。お尻をつき、両足をVの字に広げ、上体を倒す。右足に二回、左足に二回、正面に二回。これを五セット。
できるだけ膝を曲げず真っ直ぐに、と昔のテレビ体操なんかでは教わった気がするけれど、何年か前に参加した区の健康講座では、無理をしないで、膝は曲げてください、と若くて屈強なインストラクターさんが言った。高齢者向けの講座だったからかもしれない。
上体を起こし、頭のうしろに両手を当て、体を左右にひねる運動も同じ。決して無理はせずに、と言われている。まず左に二回ひねったら、次は右に二回。左右は必ず、同じ回数だけひねるように。これも五セット。
健康講座で教わったストレッチ体操をベースに、自分なりに手直しして、病気予防や、これまでの病歴に合わせた対症療法的な運動もつぎつぎ付け足していくと、いつのまにか一通り終えるのに、毎朝四十分から四十五分ほどかかるようになった。
肩を回したり、腕を上げたり、下ろしたり。あぐらをかいて足首を回し、アキレス腱を伸ばし、手首をぶらぶら、ぶーらぶら。べろを出して、ぐるん、ぐるんと回す表情筋の訓練は、お昼の情報番組を見ていて真似することにした。
「ママもやったら。体操」
たびたび妻のことも誘ったけれど、
「いいえ、どうぞおひとりで」
運動嫌いの英子はしれっと答え、すぐにキッチンやお手洗いに立ってしまう。ただの一度も、真似さえしてみようとしなかった。
「そんな長いの、よく覚えてられるわね」
英子は半ば呆れ、半ば感心したように言ったけれど、新平にすれば日課だったし、いくら長くなっても、自分で付け足し、自分で考えた体操だ。覚えられて当然だった。
新平と英子は同じ町の出身で、小さい頃から顔見知りだった。
新平のすぐ下の妹、さとえの小学校の同級生だったのだ。家も近い。どちらの家族も兄弟姉妹が多く、夏に揃って川遊びをしたこともあった。
彼女が十一歳のとき、両親がつづけて亡くなり、先に家を出て東京の郵便局で働いていた姉、ひい姉ちゃんのもとから女学校に通わせてもらうことになった。以来、長い休みに戻った姿を見かけることはあったけれど、新平が「おう」と声をかけると、途端に走り去ってしまう。どうしたのかと不思議に思いながら、父親の仕事、大工を手伝い始めたばかりの新平に、古い顔見知りを懐かしむ時間はそれほどなかった。
二人がつぎにはっきり顔を合わせたのは、彼女が女学校での勉強を終え、郷里に戻って郵便局で働きはじめてからだった。長兄が継いだ、農業を営む英子の実家の改築を、新平の父親が引き受けたのだ。新平もその手伝いで毎日家に通えば、親しさは蘇り、愛しさは増し、英子のほうだってもう、声をかけられて逃げ出す年齢でもなかった。
好意を告げたのはどちらが先だったか。
成長した新平は長身でがっしりと体格がよく、一本気で頼りがいのある青年になった。一方、目抜き通りの郵便局で働く英子は、すぐに小首を傾げ、ぽかんととぼけた顔をし、と、いくらか上品ぶった振る舞いは目についたけれど、やはり東京帰りの美しい娘で、高嶺の花、と大勢からもてはやされた。
すぐに両想いになった二人は、北関東ののどかな山間の町で、交際をはじめた。
新平が十七歳に、英子が十六歳になる年だった。
2
ヨーグルトにきなこ、すりごま、干しぶどうを入れたものをカフェオレボウルにたっぷり一杯。
それから梅干しを一粒。米ぬかを煎ったものをスプーン一杯。はちみつスプーン二杯。
朝十時、新平はこの順番で食べ終えると手を合わせ、ごちそうさま、と言った。
お父さんって、健康おたくよね。
今はよそに住む、孔雀のように華やかな色を好む次男にそうからかわれるけれど、これも新平が独自に考えた、朝食のメニューだった。
毎朝この食事をする。
おかげで体調はよかった。
「それだけじゃお腹すくでしょ。鳥じゃないんだから」
朝から餅入りのうどんを食べる英子に、それぞれの食品の効能を話して聞かせるのは何度目だろう。
べつに一日中、三食それを食べろという話でもない。むしろ一日一回、朝食で必要な栄養素を摂れば、あとの食事をのびのび楽しむことができる。新平が長い生活の末、辿り着いた健康の理屈だった。
でもこの理屈は、三食のびのび、好きなものをげっぷが出るまで楽しむ英子に通用するはずもなかった。
老眼鏡をかけ、新聞を読み始めると、「お父さん」と英子が言った。
「なに」
「今日、雄三が話があるって」
「話って?」
「さあ、なにかしら」
「金だろ?」
三男からの急な相談は、金の無心に決まっている。他には考えられなかった。「もう駄目だろ、あれは」
「そう言わずに、話だけでも聞いてあげたら」
「話?」
新聞から顔を上げて、ほんの少し顎を引くと、新平は廊下のほうを見た。「だってまだ寝てるんだろ、どうせ」
「なんか、今日は仕事お休みだとかで」
一人暮らしをしていた三男が、戻って来てもう半年になる。
「問題外だな」
「お父さん、このあといますか」
「今日? 家に?」
「ええ」
「いや、出かけるよ」
新平が金の無心を断り続けているから、三男は甘い英子にこっそり仲立ちを頼んだのだろう。今までも、そのやり方でどうにか思いを遂げてきた。そのくせ人の都合に合わせられるよう、ひとまず早起きしておこうという気さえないのが腹立たしい。「それにもう金なんかないって。なんも。すっからかん。ゲルピン。全部あいつに貸した、おまえに頼まれて」
「またあ」
「またあ、じゃないよ。おまえが考えるより十倍は貸してる」
「いくらよ」
金額を教えると、嘘でしょ、と英子は目を丸くした。
「なんで甘いかね、あいつに」
新平は首を振った。金の無心は外で暮らしていたときからつづいていて、当時は雄三から電話があると、「間違いなく本人からの電話のぶん、オレオレ詐欺よりタチが悪い」と英子と話していた。
英子自身も、五万、十万と少額ずつながら、へそくりをずいぶん引っ張られたはずなのに、四十八歳、独身の三男が一人暮らしをやめて、家に戻ったのを喜んでいる。
「庭に水やり終わったら、散歩に出かけるからな」
朝十一時、わざわざそんな宣言までして、ゆっくりエビネと胡蝶蘭の手入れをし、居間に上がっても三男の姿はなかった。
予定通りに散歩の支度をして、お手洗いを済ませ、居間を覗く。
「ほら、足腰が弱るよ」
体操は嫌でも、せめて散歩に同行するようにと丸い体の妻を誘うと、ちょうどBSの韓国ドラマを見ながら昆布茶を味わっている最中だったようで、湯呑みをほんの少し下げ、ぺろっと舌を出し、首を横に振った。
「行かない?」
「行かない」
今度は笑いながら答えて、また湯呑みに口をつけた。自分の運動不足は、ちゃんと承知しているようだった。
「そう……。孝史は? おまえもたまには外出たら?」
同じテーブルに長男の孝史もいたので誘うと、
「行かない」
こちらはぷいと、横を向くように言った。小さな顎に、針金のような長い黒い毛が二、三本見える。生活態度について、少し前に新平が意見をしたから、それをまだ怒っているのだろう。
幼い時分から体が弱く、神経質で、対人恐怖の気があり、ほとんど不登校で高校を中退したあとは、ずっと定職に就かないまま家にいる。もう五十二歳だった。
「なにかいる?」
「お饅頭」
新平の短い質問に、英子が素早く答えた。散歩のお土産のことだった。
新平はうなずくと、玉のれんをじゃらじゃらと鳴らして廊下へ出た。それから思い直して、顔だけ覗かせると、
「散歩のあとは事務所にいっから、用があるなら、そっちに来いって雄三に言っといて。ただし、金は絶対貸さないから」
そう居間に声をかけた。
玄関脇の階段に、田舎の知り合いから買ったうどんだの、送ってもらった醤油だの、大量すぎて減らないどんこだの、調味料や食品類の入った箱がいくつも置いてある。おかげで階段の通れる幅は、いつだって半分しかない。なんど注意しても直らないから、ずっとこのままだろう。
スタンド式の帽子掛けから、お気に入りの白いハンチングを取ってかぶる。毎年恒例、兄弟会のバス旅行で、男兄弟が全員ハンチング姿なのは、新平がさらっとかぶってあらわれたこの帽子に、みんな憧れたからだ。
あんちゃん、それいいな、どこで買った、ちょっと貸して、あんちゃん、いくらすんの。新平は明石家、男五人女四人きょうだいの長男だった。
本来、地元に残って家業を継ぐはずだったのに、二十代前半で英子と駆け落ちした。
郷里ではずっとそう言われていた。