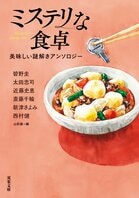ウェブサイトを見てみるといいですよ。
そう言われて、瑛子は帰ってすぐに、カフェ・ルーズで検索をした。
あまりに近くだからこそ、インターネットで検索してみるなんて思いもつかなかった。
カフェ・ルーズのサイトはすぐに見つかった。飛び込んでくるのは「店舗はただいま休業中です」という一文。だが、その下に、「オンラインショップはこちら」と書かれている。
オンラインショップをクリックすると、「世界の焼き菓子詰め合わせ」というものが売られている。四個入りから十二個入りまで。だが、全部売り切れだ。ページの上部には「販売開始は日曜日の夜十時です」とある。
今日は月曜日だから、つまりは二十四時間経たないうちに、売り切れてしまうということだ。どうやらかなりの人気らしい。
もう一度、トップページに戻り、ニュースを見ると、こんな一文が見つかった。
「キッチンカーはじめました」
まぶしいくらいのいいお天気だった。
こんな天気の日に、外に出かけるのも何ヶ月ぶりかわからない。長い間、すっかり気持ちも沈んでしまっていた。
外に出て歩くだけで、こんなに気持ちが晴れるなんて、すっかり忘れていた。
公園では、レジャーシートを敷いた家族連れや、フリスビーを楽しむ若者、犬を散歩させる人たちなどが、思い思いに休日を楽しんでいた。誰も急いでいないことが、とても心地よい。
オフィス街では、誰もが脇目も振らずに歩いている。
目指すキッチンカーは、駐車場の一画にあった。三人ほど並んでいるから、待つ間、台の上に置かれているメニューを手に取る。
コーヒー、カフェラテ、紅茶などに続くのは、ミントソーダ、ざくろソーダ、ハーブレモネードなどの、見覚えのあるメニューだ。香港式レモンティーもある。
食事の方はパニーニやベトナムサンドイッチがメインだが、三角形のパッケージに入ったフライドポテトなども売られている。歩きながら食べるのに便利そうだ。
キッチンカーでは、知らない女性が働いていた。少し、拍子抜けするが、彼女が後ろに向かって注文する声が聞こえた。
「店長、バインミーひとつ」
「はーい」
笑顔で振り返ったのは、間違いなく円だった。伸ばした髪にふわふわのパーマをかけている。
瑛子の番が回ってくる。接客してくれたのは、もうひとりの店員だった。二十代くらいの女性で、顔立ちは日本人と同じ東アジア系だが、ことばのイントネーションから、日本語が第一言語でないことはわかった。
「なにになさいますか?」
「じゃあ、ハーブレモネードとフライドポテトお願いします」
「フライドポテトはソースが選べます。トリュフ塩かケチャップかマスタードマヨネーズ、もしくはサムライソースです」
「サムライソース?」
はじめて聞く名前のソースだ。
「唐辛子の入ったピリ辛のマヨネーズです」
「へえ……おいしそう。じゃあサムライソースで」
ふいに円が振り返った。彼女の目が丸くなる。
瑛子と円は、近くのベンチで話すことにした。
「店はいいの?」
「大丈夫です。もともとひとりでも回せるようにしてあるんです。でもひとりだとトイレにも行けないから。友達に手伝ってもらっているんです」
たしかにそうだ。カフェ・ルーズならば店内にお手洗いがあるから、接客の合間に行くことができるが、キッチンカーだとそういうわけにはいかない。
揚げたてのフライドポテトには、オレンジ色のマヨネーズがかかっていた。これがサムライソースなのだろうか。フライドポテトにつけて食べてみる。
辛すぎない唐辛子の風味とマヨネーズのコクが、フライドポテトの甘さを引き立てる。
「いかがですか?」
はじめてのものを食べるとき、円はいつも緊張した顔で、瑛子を見守る。この顔で見られるのもひさしぶりのことだ。
「うん、おいしい。でも、背徳の味だね。フライドポテトにマヨネーズなんて……」
「ええ、でもオランダではすごく人気あるんですよ。このソース」
「日本ではほとんど知られてないのに……」
だが、サムライソースなんて、日本発祥みたいだ。
「オランダの人に、『日本にはサムライソースがない』と言ったらびっくりされました」
アルムドゥドラーはすっかり瑛子にとって懐かしい味になっている。意外にフライドポテトとも合う。
「今、どこに住んでいるの?」
そう尋ねると、円は驚いた顔になった。
「ヒョンジュさんと、偶然会って、シェアハウスを出たって聞いたから……」
「そうなんです。他の留学生が、このコロナ禍で住むところがなくなったって聞いたから、その人と交代することにしたんです」
じゃあ、今は? と尋ねようとして、瑛子は円に恋人がいたことを思い出した。もしかしたら、一緒に住んでいるのかもしれない。
「今は、店に住んでます」
「え?」
思いもかけないことを言われて、フライドポテトを持った手が止まった。
「店って、カフェ・ルーズ?」
「そうです。他に店なんて持ってないですよ。あそこ、大部分は店ですけど、奥にシャワー室と、一部屋あるんです。そこに簡易ベッドを置いて寝泊まりしてます。台所は店のを使えばいいし……」
「そうだったの……」
「兄と揉めてたから、住居は別のところにしたかっただけで、揉め事が片付いたらもう店に住んでもいいかなと思って……まあ節約にもなるし」
「じゃあ、オンラインショップのお菓子も店で焼いてるの?」
「そうです。早起きして店で焼いてます」
「早起き?」
円は軽く肩をすくめた。
「実は、前、緊急事態宣言のとき、夜に焼いていたら、こっそり夜に営業していると勘違いされて、苦情の電話がかかってきたんです。それからも、なんだか店の中を覗こうとする人とかもいたり、営業しているかどうか電話で問いただされたりして、ちょっと嫌になってしまったんです」
そのことばを聞いて、はっとする。緊急事態宣言による影響は、ただ、売り上げが減り、営業できなかったというだけではない。そんなふうに、働く人の気持ちまでへし折ってしまう。
「正直、ちょっと転職しようかなと思ったこともあります。でも、オンラインでお菓子を売って、キッチンカーで販売もやってたら、少しこの仕事が好きな気持ちを思いだした気がします」
瑛子はおそるおそる尋ねた。
「もうあの店では営業しないの?」
円は、肩胛骨を広げるように、両手をぐぐっと伸ばした。
「どうしようかなと思ってたんですけど、やっぱり、あそこがわたしの原点かなあ、とも感じるんですよね。キッチンカーも好きなんですけど」
どこにでも行ける。その自由さは、円にふさわしいような気もするけど、一方で、瑛子はあのカフェ・ルーズが懐かしくて仕方ないのだ。
「もうそろそろ開けてもいいかなあ」
決めるのは円だけど、待っていることくらいは伝えたい。瑛子は言った。
「そろそろ、カフェ・ルーズのカルボナーラやカレーが食べたいなあ」
ツップフクーヘンや、パンデピス、セラドゥーラ、苺のスープ、懐かしいものはたくさんある。
まだ気軽に旅には行けない。だからこそ、カフェ・ルーズを待っている人たちはたくさんいる気がする。
円は、両脚を伸ばした。そして笑う。
「カフェ・ルーズ、そろそろ再始動しますか」
この続きは、書籍にてお楽しみください