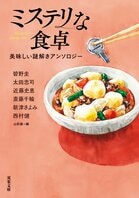家に帰って、作り置きの常備菜で夕食を済ませて、その後、デカフェの紅茶を淹れた。デザートとして、さきほど買ったシュークリームを取り出す。
テーブルの上に広げられた仕事の資料を隅に寄せ、そこに紅茶のカップと皿にのせたシュークリームを置いた。
コンビニスイーツだと、立ったままかぶりつくことだってあるが、こうやってきちんとテーブルで食べた方がおいしい。もちろん、理屈ではわかっていても、そうするのがしんどいときもあるが、今日はちゃんと自分をいたわりたかった。
シュークリームを一口かじる。
最初、甘くない、と思った。乳脂肪の豊かな味がして、その後シューの香ばしい香り、それからやっと砂糖の甘さを感じた。
チーズクリームの文字を見たときは、もっと濃厚なものを想像したが、驚くほど軽い。なにより甘さがかなり控えめなのだ。それでも物足りなくないのは、牛乳のおいしさがはっきり感じられるからだ。
クリームチーズと生クリームの中間くらいの爽やかさだろうか。癖がないので、子供だって嫌いではないだろうが、お酒にも合いそうな気がする。
これはおいしい。オーソドックスな品揃えだと思ったが、他のメニューも一工夫あるのかもしれない。
今度は違うものにも挑戦してみたい。
ふいに、円の作るお菓子のことを思い出した。彼女の作るお菓子もこうだった。
甘いものも、それほど甘くないものもあるけど、どちらにも驚きと、寄り添ってくれるような優しさがあった。そのふたつは相反するものだと思っていたが、そうではないのだと知った。
円が探してくるのは、日本ではそこまで知られていなくても、その土地で長年愛されているお菓子だ。はじめて食べる驚きと、それでも長年愛されてきたレシピの持つ揺るぎなさが優しさとして感じられるのだろう。
このシュークリームはきっとまた食べたくなる。
その数日後だった。駅のホームを歩いているとぽんと肩を叩かれた。
「瑛子さん、おひさしぶり」
振り返ると、ヒョンジュがいた。葛井円のルームメイトで、カフェ・ルーズで何度か会ったことがある。
「あ、おひさしぶり。会えてよかった」
彼女は韓国からの留学生で、大学を卒業して院に進んだという話は聞いた。
色白の頬がつややかで、元気そうなことにほっとする。
いつからだろう。旧知の人と会ったとき、その人が元気そうだというだけのことに、安心するようになったのは。
しばらくぶりのメールさえ、怖くなってしまったのは。全部パンデミックのせいだ。
「瑛子さんも元気そうですね」
「うん、わたしはね。葛井さんも元気ですか?」
そう尋ねると、ヒョンジュは驚いた顔になった。
「円さんは、もうあのシェアハウスを出ました。今は別の子が入ってます」
「えっ? 引っ越し? どこに?」
ヒョンジュは首を振った。
「家がどこかは……郵便物はお店に転送してもらってるみたいです」
だが、その店も閉まったままだ。
「いつ頃?」
「うーん……去年の終わりです」
ならば十ヶ月くらいは経っていることになる。
「あ、でも、ラウラが夏頃に電話で話したって言ってました。元気そうだったって」
それはほっとする情報だが、どこにいるのかがわからないことには変わりはない。
「わたし、メールアドレス知ってますから、瑛子さんが心配してたって伝えておきますよ」
そこまでしてもらうのも妙な気がする。
「なにかのついでがあったときで、大丈夫です。元気ならそれでいいし」
円に過剰に気を遣わせるのも悪い気がする。
電車がきたので、乗るヒョンジュと別れて、改札を出る。円はどこにいるのだろう。
なるべく、良い方に考えることにする。
旅の好きな円だから、どこか遠くに行ってしまっていても不思議はない。
北海道とか沖縄なら、隔離期間はないし、もしくは隔離期間があっても行ける国はある。
勤め人でもなく、子供がいるわけでもない。店を開けないのなら、彼女は自由だ。
旅先で、どこかでキッチンを借り、その土地に伝わるレシピを試作してみたり、もしくはよその土地のお菓子を、別の土地で売ったりしているのかもしれない。
カフェ・ルーズのコンセプトは、「旅に出られるカフェ」だと、最初に訪れたときに聞いた。
お客さんが、遠い土地の飲み物やスイーツを楽しんで、旅に出た気分になれるカフェだということだが、カフェそのものが旅に出てしまうことも、できるかもしれない。
もちろん、これは、瑛子が過剰に心配してしまわないための妄想だ。
本当はそんなに楽で素敵なはずはないことくらいわかっている。
だが、心配したって瑛子にできることはなにもないのだ。カフェ・ルーズが再開したら、また足繁く通おうと思うだけだ。
帰り道、遠回りして、カフェ・ルーズの前を通ったが、明かりはついていなかった。
翌日、瑛子は会社帰りにトルタに立ち寄った。あのチーズクリームのシュークリームがまた食べたかったのだ。
店内の客は年配の女性がひとりだけだった。ケーキを包んでもらうのを待っているようだ。
時間が遅かったせいだろう。ショーケースにはあまりケーキは残っていなかったが、チーズクリームのシュークリームはまだ少しだけ残っていた。
「ああ、よかった」
思わず声が出た。
「チーズのシュークリームひとつください」
そう言うと、店員が箱を女性客に渡しながら答えた。
「はい、少々お待ちください」
ケーキ箱を受け取った女性客が、瑛子を見て微笑む。
「そのシュークリーム、甘さが控えめでとてもおいしいわよね」
「ええ、そうですね」
「最近、年を取ったせいか、あまり甘いのが駄目になってしまったのよ。前、同じ通りにあったヴォワヤージュさんで買ったチョコレートケーキは甘すぎて無理だったし、やっぱり日本らしいケーキがいちばんね。シュークリームとか」
まあ、シュークリームも完全に日本発祥ではないと思うが、たしかに日本ならではのケーキというものがあって、それがおいしいのもわかる。特に年齢を重ねてくると、新しいものよりもそういうものの方が受け入れやすくなるのかもしれない。
そういえば、円が言っていた。
「なぜか、シュークリームってフランス発祥なのに、あんまりフランスでは食べられてないんですよ。エクレアはどこでも売られているのに」
「えっ、そうなの?」
それは瑛子にとっては、意外な情報だった。
「バームクーヘンだって、日本ではみんな知ってるけど、ドイツでは地方のお菓子で知らない人も多いんですよね」
それは聞いたことがある。
「だから、生まれた場所で根付かなくても、遠くに行って根付くお菓子みたいなのもあるのかも」
人だってそうなのかもしれない、と、そのときに考えたのを覚えている。
女性客は支払いを済ませて出て行った。トルタの店内には、客は瑛子ひとりになる。
三十代ほどの女性の店員はふふっと笑った。
「実は、そのシュークリーム、昔ながらの日本のケーキとはちょっと違うんですよね」
「あ、わたし、このクリーム、はじめて食べました」
濃厚なのに、軽い。甘さも控えめだ。
「コフピームって言うんです。エストニアの国民食だという話です。コフピームと言っても知られてないし、イメージも湧かないから、チーズクリームという名前にしているんですけど」
なんだか、円が言いそうなことだ、と思った。
エストニアという、あまり聞いたことのない国の名前も、円ならよく知っていそうだ。
「エストニア……って、たしかIT大国ですよね」
「そうです。ロシアの近く、バルト三国の」
想像するだけで寒そうだ。なんとなく、こってりと甘いお菓子が作られていそうな気がするが、そこで作られているのが、こんな爽やかで甘さ控えめのクリームだということに驚きを感じる。
「チーズなんですか?」
「カッテージチーズとか、リコッタチーズとか、そういう種類のチーズです。発酵はさせずに、酢を使って固めるんです」
だから、癖がないのだ。
瑛子は思い切って聞いてみた。
「あの……駅の向こう側にある、カフェ・ルーズってご存じですか。今は閉店しているんですけど、いろんな国のお菓子を出していて……」
店員は少し驚いた顔になった。
「もちろんです。だって、このクリームは葛井さんに教えてもらったんです」