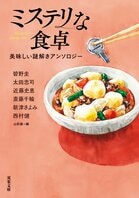少しずつ、出社する頻度は増えている。だが、瑛子の会社は、どうしても出社しなければならないとき以外は、テレワークを推進する方向で行くらしい。社長が自然の多い長野に引っ越して、田舎暮らしを満喫しているという話だった。
ミーティングは時間を合わせてオンラインで行えばいい。取引先に直接行く機会はあるが、直行直帰すればいい。そうなると、オフィスには週に二度行けば充分だ。三度も行けば、「今週は出社が多いな」という気持ちになっていて、五日も出勤していた日々のことが、遥か遠い昔のようだ。
いいことばかりではない。光熱費がかかるようになっても、会社はそれを負担してくれるわけではない。今年の夏の冷房代には、目が飛び出そうになってしまった。家でだと、だらだら仕事をしてしまい、プライベートの時間が減ったような気はするし、残業代も出ない。
だが、それにしたって、満員電車での通勤がないと、身体は圧倒的に楽である。もちろん、それも瑛子が一人暮らしだからだ。
同僚の久保田亜沙実は、テレワークが推奨されるようになっても、ほぼ毎日出勤している。
「夫もテレワークになってしまって、家にいるし、子供だって、ひとりでできることでも、わたしが家にいるとわたしにやってもらえると思って仕事にならない。通勤時間を考えても圧倒的に会社の方が捗る。前ほど電車も混んでないしね」
彼女の子供はふたりとも小学生だ。彼女も最初の全国一斉休校のときは、ずっとテレワークを続けていた。その時期、オンラインでミーティングをしても、あきらかに疲れた顔をしていた。
今はその頃よりは、ずっと元気そうだ。
「不思議だよね。わたしが家にいないと、夫も子供の面倒をみるし、子供だってやれることは自分でやる。なのに、わたしがいると、みんなわたしのところに回ってきてしまう。まあ甘えてるんだろうけどさ」
「頼れる優しいお母さんだからですよ」
瑛子がそう言うと、亜沙実はふっと鼻で笑った。
「まあね。それと都合のいいお母さんは同じ意味だよね」
彼女の夫は、家で働きながら、ちょくちょく家事をやり、亜沙実は、出勤して仕事に集中し、定時に帰ってその後は自分の分担の家事を高速で片付ける。それがいちばん上手く回るらしい。
その日、瑛子はひさしぶりに出社した。同じく、ずっとテレワークをしている後輩の塩崎恵里香とも珍しく出勤日が合い、数週間ぶりに直接顔を合わせた。
「奈良さん、リアルではおひさしぶり! お元気でしたか?」
その言い回しに笑ってしまう。たしかにオンラインでは、昨日ミーティングをしたところだ。
「奈良さん、今日はお弁当ですか?」
「ううん、コンビニでなんか買ってこようかなと思ってる」
「わたしも、今日はなにも持ってなくて、ひさしぶりに外にランチに行こうかなと思ってるんですよね。黙食だったら、大丈夫だと思うから、奈良さん、一緒に行きませんか」
そういえば、人と食事をするのも何ヶ月ぶりだかわからない。今の感染状況ならば許されるだろう。
「うん、行こう」
念のため、亜沙実にも声をかけたが、彼女はお弁当を持ってきたらしい。
ランチの時間も、今は自由に決められる。前は、十二時から一時と決められていたのが、今となっては馬鹿馬鹿しい。瑛子と恵里香は、一時を過ぎてから、席を立って、オフィスを出た。
ひさしぶりに、会社のまわりを歩いてみると、すっかり風景が変わってしまっていることに気づく。よく昼食を取っていたうどん屋も、喫茶店も閉店してしまっていた。
無理もない。テレワークが推奨されれば、当然、オフィス街で昼食を食べたり、帰りに一杯飲んだりする人は減る。身体が楽だと、テレワークを歓迎していた瑛子も、飲食業界の厳しさを思うと、胸が痛む。
もちろん、感染を防ぐためには、前のような生活はできない。でも、誰が悪いわけでもないのだから、もう少しなんとかできなかったのだろうか。そう思い続けてしまう。
ようやく、営業しているパスタの店を見つけて、中に入る。カルボナーラを注文して、その後、少し後悔した。
円の作るカルボナーラが好きだった。どこで食べても円のものと比べてしまうから、よっぽどおいしいお店でなければ、不満を感じてしまう。
運ばれてきたのは、生クリームを使っていない、パルミジャーノの味が強く感じられるカルボナーラだった。
「よかった。ここのカルボナーラおいしい」
食べ終えてから、そう言う。
「おいしくないカルボナーラもあるんですか?」
恵里香にそう聞かれて、瑛子は少し笑った。瑛子も前は、どこで食べてもおいしいものだと思っていた。
「好きな店のカルボナーラがあって、いつもそこのと比べてしまうから……つい、ね」
「へえ、食べてみたいです。そこのカルボナーラ」
恵里香の返事に、胸が痛んだ。
「それが……ずっと休業したままなんだよね」
「ああ、仕方ないですよね」
恵里香はなにげなく言った。仕方ないということばに胸がちりちりとした。彼女を責めるつもりはないし、瑛子だって同じようなことを何度も口に出した。
だが、それで生活している人たちにとっては、仕方ないなんて片付けられてはたまったものではないだろう。
自分たちが少しずつ、鈍感になってきている気がした。
仕事の帰り、ドラッグストアに寄りたくて、駅の反対方面に出た。
前に、ヴォワヤージュというカフェがあった通りを、歩く。ヴォワヤージュはあれからすぐにフィンランド風のコーヒーショップに装いを変えて、営業していたが、去年、店を閉めた。それからずっと、テナント募集の紙が貼ってあるところをみると、あのオーナーも撤退したのだろう。
いくつもカフェを経営していても苦しいのか、それとも余裕があるからさっさと撤退して、営業形態を変えられるのかはわからない。
ただ、どこも無傷ではいられない。
買い物を済ませて、帰宅しようとしたとき、ふと一軒のケーキ屋が目に入った。店名はトルタ。少しレトロで可愛い雰囲気だ。
テーブルはふたつあるが、テイクアウトが中心なのだろう。近くだが、これまで買ったことがなかった。
駅のこちら側にくるときは、たいてい買い物が目的なので、荷物が多くなる。なかなかケーキを買っていこうという気になれない。
今も、エコバッグは買ったもので重いが、少しでも営業している店を応援したい気持ちになっている。
瑛子はドアを押して、店の中に入った。
「いらっしゃいませ」
店の奥に工房があり、ケーキを作っている女性が見える。パティシエールがひとり、販売がひとりという少人数でやっているようだ。
瑛子はケースの中を覗いた。モンブラン、ショートケーキ、レモンタルト、プリンにシュークリーム、スフレチーズケーキ。
奇をてらったところのない、街のケーキ屋さんだ。コロナ禍になってからは、ケーキを食べる回数も減っているし、その前はデパ地下や話題の店で買うことが多かったから、かえって新鮮に感じる。
他にお客さんもいないので、念入りにケースを見る。よく見れば、シュークリームが二種類ある。ひとつは定番のカスタードクリーム。もうひとつはチーズクリームと書かれていた。
チーズ味のシュークリームなんて珍しいから食べてみたい。
瑛子の視線に気づいたのだろう。三十代ほどの店員の女性が言う。
「それは、先月からの新製品です。評判いいんですよ」
じゃあ決まりだ。プリンは賞味期限が明日までだと言うから、チーズクリームのシュークリームと、プリンをひとつずつ買う。
箱に入れてもらっていると、ドアが開いて、家族連れが入ってきた。続いて、年配の夫婦。繁盛している様子を見ると、ほっとする。味も期待できそうだ。
箱を渡すとき、店員の女性はマスク越しでもわかる笑顔で言った。
「またいらしてくださいね」
少しだけささくれていた気持ちが、軽くなった気がした。