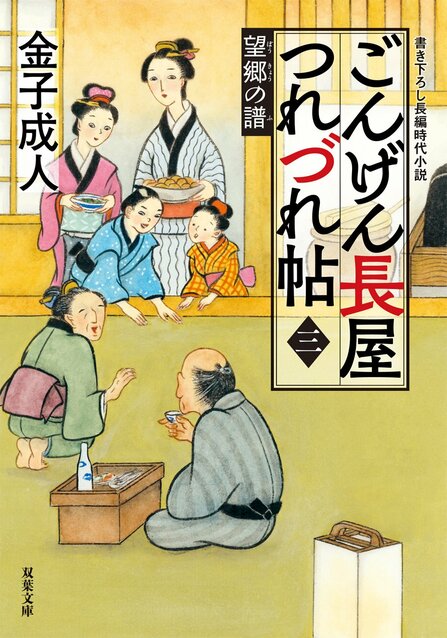五
二月二十五日から三月二日にかけて、例年、江戸の諸方で雛市が立つ。
月が替わったこの日、質舗『岩木屋』では、店を開けて早々に、雛飾り一式を借りたいという損料貸しの客が立て続けに三組ほどやってきた。
雛飾りの品物を大八車に載せて運ぶ車曳きの弥太郎と、配達の段取りを決めたところで、お勝は『岩木屋』を後にして、『ごんげん長屋』に戻ってきていた。そのことは、昨日のうちに、吉之助の了解を取りつけていた。
『ごんげん長屋』の路地に、暖かみのある日が射している。
ほどなく、五つ半(午前九時頃)という刻限である。
彦次郎夫婦の家の中は、障子紙を通した日の光に満ちていて、結構明るい。
壁際に置かれた白木の祭壇には、線香立てと蝋燭立てがあり、その奥に白布に包まれた骨箱がある。
お勝と彦次郎は祭壇の前に膝を揃え、土間の框にはお富とお啓が腰掛けていた。
およしは、倅の梅太郎と対面を果たした日の翌日、静かに息を引き取った。
それから四日が経っている。
およしの死は、すぐに巣鴨の鍛冶屋に知らせて、梅太郎を呼び寄せた。
その翌日には、栄五郎が師匠を務めている手跡指南所のある瑞松院で弔いを済ませ、火葬して骨になったおよしは、『ごんげん長屋』に戻ってきていたのである。
路地から下駄の音が近づいてくると、土間に立ったお富が戸を開けた。
「あ、伝兵衛さん」
お富は、入り込んできた大家の伝兵衛の名を呟いた。
「お迎えは、五つ半ということだったね」
伝兵衛が誰にともなく言うと、
「えぇ」
彦次郎が殊勝に頭を下げた。
伝兵衛は土間を上がり、およしの遺骨に手を合わせた。
この日、常陸国の府中に帰る梅太郎が、遺骨と彦次郎を迎えに『ごんげん長屋』に来ることになっていた。
だが、早朝から仕事に出たり用事があったりして見送りの叶わない者たちが、およしの祭壇に手を合わせてから出掛けていったことに、隣家で朝餉の支度をしていたお勝は気づいていた。
「梅太郎です」
その声に、土間にいたお富が戸を開けた。
「おはようございます」
旅支度を整えた梅太郎が、中の一同に挨拶して土間に入ると、
「皆さんには、おっ母さんのために手厚い弔いをしていただき、本当にありがとうございました」
深々と腰を折った。
「さぁ、およしさんも旅支度だ」
あえて明るい声を張り上げたお啓が土間を上がると、骨箱の傍に置いてあった風呂敷を広げた。すると、お富は祭壇の骨箱を両手で持ち上げ、お啓が広げた風呂敷の上に置く。
お富は、風呂敷で骨箱を包むと、一か所だけ短く結び、もう一か所は首から掛けられるように長めに結わえた。
「彦次郎さん、支度はまだでしたか」
梅太郎が訝るように口にすると、
「あ、ほんとだ」
声を発したお富も、お啓も、普段着姿の彦次郎に眼を遣った。
「彦次郎さん、着替えの用意はあるんですか」
お勝が気遣うと、
「梅太郎さん、府中には、およしだけを連れていってくれませんかねぇ」
彦次郎は膝を揃えると、梅太郎に向かって頭を下げた。
「けど」
梅太郎は、戸惑ったようにお勝たちを見回す。
「わたしのことはいいんだ。あんたが物心ついたときには、傍にいなかったおっ母さんじゃないか。これからは、離れ離れになっていたおっ母さんの傍には、あんたが一緒にいてやる番だよ」
彦次郎の声が沁みたのか、梅太郎はそっと唇を噛んで顔を伏せた。
すると、彦次郎は祭壇の下に置いてあった小さな壺を出して、板張りに置いた。
「昨夜、およしの骨をひとかけら貰って、この中に入れたから、わたしはここで、毎朝拝むことにするよ」
彦次郎の言葉を聞いたお勝たちは、両掌に収まるくらいの釉薬の掛かった壺に眼を凝らした。
「さぁて」
ゆっくりと腰を上げた彦次郎は、骨箱を持って立つと、長めに結わえた風呂敷の結び目を、土間に立つ梅太郎の首に掛けた。
「梅太郎さん、頼みますよ」
彦次郎の声に、梅太郎は大きく頷く。
「何も国に帰りたくないわけじゃないんだが、どうも、気恥ずかしいというのかねぇ。それに、こんなわたしに、ずっとここにいろと言ってくれるお人もいるもんだからね」
彦次郎は笑みを見せた。
「それじゃ」
骨箱を胸に抱いた梅太郎は、会釈をすると路地へと出た。
続いて彦次郎が出て、その後にお勝たちも続いた。
「彦次郎さん、気が変わったらいつでも帰ってきてください」
「あぁ」
彦次郎は、梅太郎をしっかりと見て、頷いた。
「およし、梅太郎さんに抱かれて府中に帰れるんだぜ。よかったなぁ」
骨箱にそう語りかけた彦次郎が、風呂敷包みの上から軽く撫でた。
「それでは皆さん、お世話になりました」
住人たちに一礼すると、梅太郎は木戸の方へと歩き出した。
お勝たちは、去っていく梅太郎の背中に向かって両手を合わせた。
その日の日暮れ時である。
いつもは賑やかな夕餉だが、およしの遺骨が梅太郎の胸に抱かれて行ったことを話すと、子供たちはさすがにしんみりとしてしまった。
だが、彦次郎が残ることになったのは、子供たちには朗報だったようだ。
いつの間にか路地には夜の帳が下りていた。
夕餉の片付けを終えて、お勝が茶を淹れようとしていたとき、
「こんばんは」
聞き覚えのある男の声がした。
「あ、お隣の治兵衛さんだ」
お妙がそう言った通り、お琴が戸を開けると、戸口には隣に住む足袋屋の番頭の治兵衛が畏まっていた。
「何か」
お琴が何気なく問いかけると、
「お勝さんに、折り入ってお話が」
治兵衛は身を硬くして、声を掠れさせた。
「どうぞ」
お勝が声を掛けると、治兵衛はおもむろに土間に足を踏み入れ、
「表通りの『春月堂』の菓子ですが、お子たちとどうぞ」
框に菓子箱を置いた。
「うわ」
幸助が歓喜の声を上げた途端、
「今は食べないよ」
お琴が窘めた。
「それで、お話というのは」
お勝がそう切り出すと、
「ここしばらく、長屋で起きたことの数々、ま、彦次郎さん夫婦のこともそうですが、住人に対してのお勝さんの気配り目配りには大いに胸を打たれた次第です。そういうお人ならば、さぞかし心穏やかに過ごせるのではと思い、ぜひとも、わたしと夫婦になっていただけないかと、こうして」
治兵衛は、少し白髪の交じり始めた頭を下げた。
「しかし、それは、困りましたねぇ」
お勝は、苦笑いを浮かべると、
「この年になって花嫁になるなんて、思いもしないことでして」
そう口にして、子供たちの反応を見た。
「それは、やめた方がいいと思います」
お琴が、治兵衛に向かって真顔でそう口を開いた。
「え」
声にならない声を出して、治兵衛は眼を丸くした。
「治兵衛さんは、ここの住人になって日も浅いからそんなことを口になさいますけど、きっと後悔することになります」
お琴の言うことに、幸助とお妙が大きく頷いた。
「気に入らないことがあると、恐ろしい雷が落ちます」
そう打ち明けたのは幸助である。
「そのたびに、きっと、しまったと思うに違いないのです。そうなっても、わたしたちにはもう、手の施しようがないのです」
そう付け加えたお妙は、せつなげなため息をついた。
「それでもよければ、この雷を、いえ、母をどうぞお連れください」
丁寧な口を利いて、お琴は頭を下げた。
「あ、そりゃそうですよ。ここへ来て日が浅いということもありますし、もう一度、よくよく考えてからのことにします。では、おやすみなさい」
腰を折ると、治兵衛は慌ただしく路地へと出ていった。
「お前たち、よくも」
お勝は、ごくごく小さな声で子供たちを睨む。
「嫁入りしたかったの?」
お妙は、小さな声で尋ねた。
お勝は、ぶるぶると首を横に振った。
顔を見合わせた四人は体を揺すり、声を殺して笑った。
『ごんげん長屋』の井戸端は、洗顔や朝餉の支度に忙しい住人たちで混み合っている。
雛祭りの昨日は、一日中薄雲に覆われていたが、今日は朝から青空が広がっていた。
梅太郎がおよしの遺骨を郷里に連れていってから、三日が経っていた。
お勝とお富は米を研ぎ、お啓と栄五郎は青菜の根の泥を濯ぐ。
青物売りのお六は、いつものように暗いうちに出ていったようだ。
町小使の藤七は、髭を剃ったばかりの顔を洗っている。
「南無阿弥陀仏」
路地の方から、彦次郎の唱える念仏が聞こえてきた。
「なんだか、昨日より、声が軽くなったようだね」
お富の声に、井戸端の一同が耳を澄ました。
「あれだよ、長年背負ってきたものを肩から下ろして、彦次郎さん、ほっとしているのかもしれないねぇ」
長屋で一番年かさの藤七の言葉が、お勝の胸にしみじみと沁み渡った。
彦次郎の念仏の届く朝の井戸端に、ふわりと白いものが舞った。
どこからか流されてきた、たった一片の桜の花だった。