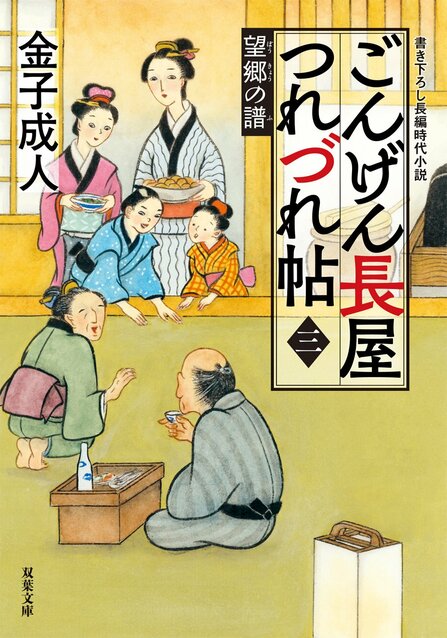二
『岩木屋』は、店を開けた五つ(午前八時頃)過ぎから大わらわとなった。
お勝と手代の慶三だけでは間に合わず、蔵番の茂平や修繕係の要助の手も借りた。
質草を預け入れる客や請け出す客で混み合うのは、いつも午前中のことではあったが、今日は珍しく一時に集中してしまった。
その騒ぎが続いたのも一刻(約二時間)ばかりで、ほんの少し前に、店から客の姿は消えた。
帳場に着いたお勝が帳面を広げ、慶三が板張りに置いたふたつの火鉢に炭を足し終わったとき、出入り口の腰高障子が開いて、
「ごめんよ」
彦次郎が土間に入り込んだ。
「彦次郎さん、遠慮なく上がってくださいよ」
そう促したお勝が帳場から腰を上げると、
「さささ」
慶三が手を伸ばして、火鉢の傍を指し示す。
「彦次郎さん、これが手代の慶三さんです」
「番頭さんから、お名は伺っておりました。今日はひとつよろしくお願いします」
彦次郎に頭を下げると、「わたしはお茶でも」とお勝に断って、慶三は帳場の奥へと入っていく。
「『岩木屋』の旦那さんが挨拶をしたいと言っておいでだったんだけど、妹の娘さんに縁談が持ち上がったとかで、ついさっき、おかみさんと二人して神田の方に出掛けられたばっかりなんですよ」
お勝がそう言うと、
「なぁに。お気遣いは無用だよ」
彦次郎は笑って片手を左右に打ち振った。
そこへ、お盆を手に戻ってきた慶三が、ふたつの湯呑を彦次郎とお勝の前に置いた。
「ま、おひとつ」
お勝が促すと、彦次郎は湯呑を手にした。
湯気の立つ茶を、ふた口ばかり口にしたところで、上野東叡山の方から鐘の音が届いた。
最初に三つ撞かれる捨て鐘は、一打目は長く響かせるが、二打三打はぼんぼんと、続けざまにふたつ、短く撞くことになっている。
上野東叡山からの鐘も、三つの捨て鐘の後に打たれ始めた。
四つ(午前十時頃)を知らせる時の鐘である。
時の鐘が打ち終わってしばらくすると、入り口の戸が外から荒々しく開けられた。
昨日と同じ装りをした浪人が、布の刀袋を小脇に抱えて土間に足を踏み入れ、大股で板張りの框の前に来て仁王立ちするなり、
「刀の目利きは来ているのか」
尊大な口を利いた。
「こちらに」
お勝が彦次郎を指し示すと、浪人は、胡散臭そうな眼差しを向けた。
「見てもらうが、少なくとも二十両の値がつかなければ、預け入れることはせぬぞ」
浪人はそう言うと、布の袋から出した朱塗りの鞘の一振りを板張りに置き、自分は框に腰を掛けてふんぞり返る。
「では、拝見させていただきます」
彦次郎は、置かれた刀の前に膝を進めると、一礼して刀を手にし、刀身をゆっくりと引き抜く。
彦次郎のその動きを、お勝と慶三はもちろん、浪人までもが息を詰めて見ていた。
刀の柄を持った彦次郎は、刃先を横向きにして刀身を眼の前に立てると、刃文に眼を凝らす。
柄を回して、反対側の刃文も見る。
すぐに刃先を上に向けて、片眼で刀の反りを見た。
それが済むと、柄の目貫、目釘を外して柄を外し、茎を剥き出しにした。
右手で茎を持った彦次郎は、刀身の平地を左の掌に載せると、目釘穴の近くに刻まれた判然としない銘に、顔を近づける。
「これは、新刀ですな」
彦次郎が、ぽつりと呟いた。すると、
「いや、たしか、鎌倉期か室町期のはずだと」
浪人が口ごもった。
「銘の刻みもおざなりですが、山城国、重平東次という銘はなんとか読み取れます。ですが、山城国で名のある刀工といえば、室町期では、長谷部国信でしょうなぁ」
穏やかな声でそう言うと、刀身を刀袋の上に横にして置いた。
「その長谷部某だと、刀の値はどのくらいに」
慶三が恐る恐る問いかけると、
「ものにもよりますが、五十両から二百両で売り買いされると聞いたことがあります」
彦次郎の返事に、慶三は息を呑んで刀に顔を近づけ、眼を吊り上げた浪人は板張りに這い上がるような動きを見せた。
「山城国にはもう一人、伊賀守金道という刀工もいるんだが、この刀はそんなものには及びもつかない代物ですな」
彦次郎はそう断じると、剥き出しになっていた茎に目釘と目貫を通して柄に納め、再度、刀身に眼を遣った。
「この刀には、刀身の平地と鎬地の境目にある鎬筋に勢いというものがなく、節目がぼんやりとして曖昧ですな。多分、名もない山鍛冶が打ったものだと思いますが」
そう言いながら、彦次郎は刀身を朱塗りの鞘に納めた。
「これだと、いくらぐらいで買える代物ですか」
慶三が小声で尋ねると、
「そうですなぁ、一両の半分以下で買えると思いますがね」
「もう頼まんっ」
彦次郎が口にした値に業を煮やしたのか、浪人は顔を真っ赤にして朱塗りの刀と刀袋を引っ掴み、乱暴に開け放った戸から、大股で表へと飛び出していった。
すぐに土間に下りた慶三は、
「あの浪人は、あの刀が金になるまで、他の質屋に持っていくんでしょうねぇ」
表に顔を突き出してそう言うと、戸を閉めた。
「彦次郎さん、これは些少ですが、旦那さんから預かっておりましたので」
お勝が、一朱を包んだ紙を彦次郎の膝元に置く。
「お勝さん、これはいけませんよ。こんなことをされるのなら、わたしは目利きを断っていましたよ」
笑みを浮かべた彦次郎の声は、穏やかである。
「わかりました。引っ込めさせていただきます」
彦次郎の気性を知っているお勝は、すぐに紙包みを取って、自分の袂に落とした。
「それじゃわたしは」
彦次郎が土間に下りると、見送ろうと、お勝も履物に足を通す。
そのとき、外から戸が開けられ、お琴が恐る恐る土間に入ってきた。
「何ごとだい」
お勝が問いかけた。
「長屋に彦次郎おじさんを訪ねて人が来たけど、およしおばさんは出掛けてたから、ここに連れてきたのよ」
お琴はそう言うと、表に顔を突き出して、「どうぞ」と呼びかけた。
「ごめんください」
入ってきたのは、手甲脚絆姿の丸顔の男である。
「彦次郎はわたしだが」
「わたしは、常陸国の者で、恭太といいます」
年の頃は三十くらいの丸顔の男は、誠実そうな物言いをした。
「ほほう。常陸ねぇ」
彦次郎の顔が微かに綻んだ。
「それじゃわたしは」
お勝に声を掛けると、お琴は下駄の音をさせて表へと出ていった。
「どこか、外に出ようか」
彦次郎の誘いに、恭太と名乗った男は頷いたが、
「彦次郎さん、お客もいないことだし、なんならここでも構いませんよ」
お勝がそう言うと、
「それじゃ、お言葉に甘えることにして、隅の方で」
彦次郎は、恭太を土間の奥に誘い、板張りの框に腰を掛けた。
「お勝さんたちは、こっちには構わず仕事をなすってくださいよ」
「えぇ」
お勝は彦次郎に返事をして帳場に着き、慶三は火鉢の傍に腰を下ろし、質草に結びつける紙縒りを縒り始めた。
「常陸から、わざわざ訪ねてきたってわけじゃあるまいね」
彦次郎の穏やかな声がした後、
「へぇ。この二、三年、知り合いを訪ねて、年に一、二度は江戸に来ております」
恭太の返答する声が、帳面を繰るお勝の耳に届き、
「実は半年前に江戸に来たとき、浅草の道具屋で気になる短刀を見つけましたので買い求めておりました」
話を続けた恭太が、懐から出した白木の鞘の短刀を、彦次郎の前に置く動きがお勝の眼にも留まった。
「何が気になったかと言いますと、多くは茎に入れる銘が、この短刀には棟に刻まれていて、山形の印の下に〈彦〉の一文字が刻んでありました」
恭太のその言葉に、彦次郎の顔がにわかに強張ったように感じられた。
短刀を買い求めた道具屋に、どこのなんという刀工が作ったものかと尋ねると、
「かなり以前、中之郷の鍛冶師、松蔵さんのところから出た一品だ」
と、そう教えてくれたのだと、恭太は話を続けた。
半年前と今回、江戸に出てきた恭太は、中之郷の鍛冶師、松蔵にゆかりの人を訪ね歩いたり、江戸の刃物屋などを回ったりして、〈山形に彦〉の刻印を記す刀工を捜し回ったところ、今は研ぎ屋になっている彦次郎という人が、中之郷の鍛冶場にいた時分に打った短刀だろうという推測を、二、三の刀剣屋の口から聞いたのだという。
「それで、中之郷の松蔵さんの鍛冶場に行ってこの短刀を見せたら、根津権現社近くに住まう彦次郎さんが打ったものに違いないと聞きましたので、こうして訪ねてまいったようなわけで」
恭太は、逸る気持ちを懸命に抑えた様子で、静かにそう語った。
「あんたは、いったい」
彦次郎の顔はさっきよりも強張り、口から出た声は、痰が絡んだように掠れた。
「わたしは、刀鍛冶、久市の倅でございます」
その声を聞いた途端、彦次郎が弾かれたように立ち上がり、
「その刻印は、わたしのもんじゃありませんよ」
掠れ声を発すると、転がるようにして表へと飛び出す。
「あの」
お勝は恭太と名乗った男に声を掛けたが、聞こえなかったのか、蹌踉とした足取りで表へと出ていった。
暮れ六つ(午後六時頃)の鐘が鳴ってから、ほんの少し過ぎた頃おいである。
『ごんげん長屋』の井戸端は、久しぶりに混み合っていた。
夕餉を摂り終えたお勝は、お琴と一緒に鍋釜、茶碗などを洗い、お富とお啓も洗った茶碗などを笊に並べている。
辺りはすっかり暗くなっていたが、二月も下旬ともなれば寒さも和らぎ、これからは水仕事も大分楽な時節となるのだ。
「ただいま戻りました」
木戸を潜ってきたのは、紐のついた小さな紙包みを提げた沢木栄五郎である。
「お帰りなさい」
井戸にいた女たちが一斉に声を掛け、
「沢木先生は、これから夕餉ですか」
以前、栄五郎の手跡指南所に通っていたお琴が、元師匠を気遣った。
「今朝炊いた飯と、表で買い求めた煮物でね」
提げていた紙包みを持ち上げて見せた。
そのとき、大家の伝兵衛の家の方からやってきた彦次郎が、急ぎ無言で井戸端を通り過ぎた。
その直後、バタバタと足音を立てて現れた伝兵衛が、
「彦次郎さん、ここを出るって、どういうことですか」
そう問いかけながら、彦次郎を追って路地へと駆け込んだ。
「なんだって」
素っ頓狂な声を上げたお富が、洗い物を放り出して彦次郎の家の方へ駆けていった。
「お琴、後を頼むよ」
お勝はそう言うと、前掛けで手を拭きつつ、お富に続いて彦次郎の家の戸口に駆けつける。
「なんですか彦次郎さん。わけも言わずに、どうしてここを出るなんて」
土間に立った伝兵衛がおろおろと声を掛けた。
だが、板張りに置いた行李に荷を入れる彦次郎も、茶箪笥の茶器などを紙に包むおよしも、口を開かない。
「彦次郎さん、『ごんげん長屋』を出るっていうことですか」
土間に足を踏み入れたお勝が問いかけると、
「さっき、そう言いに来たんだよ」
呟いた伝兵衛が、ため息をついた。
「彦次郎さん」
戸口に立った栄五郎が声を掛けると、横に立ったお啓は、
「およしさん、どうしたのさ」
と、唇を噛む。
「彦次郎さん、わけも言わずにここを出ていくなんて、あんまりじゃありませんか。水臭いですよ」
お勝が静かに声を掛けた。
「何も、ここが嫌だというわけじゃないんですよ。その辺はわかってもらいたい」
彦次郎が行李に着物を詰めながら頭を下げると、傍で荷作りをしていたおよしも、亭主に倣って頭を下げた。
「でも、だって、急にこんな。『ごんげん長屋』に二十年もいて、こんな出ていき方はないじゃないかぁ」
十年以上も『ごんげん長屋』に住んでいるお啓の声は、今にも泣き出しそうになっている。
「わかってる。わかってるんだが、どうか、勘弁してもらいたいんだ」
彦次郎は、両手を膝に置くと、深々と頭を下げた。
すると、およしも彦次郎の横に並び、両手を板張りに伸ばそうとして、そのまま、ばたりと音を立てて、板張りに突っ伏した。
「およしさん」
土間を上がったお勝が、抱き起こそうとした手を止め、およしの額に載せた。
「ひどい熱だよ」
お勝が呟くと、
「わたしが医者を」
紙包みを伝兵衛に預けた栄五郎が、木戸の方へと駆けていった。
土間から板張りに跳び上がったお啓は、立て掛けられていた枕屏風をどかして、薄縁を敷いて寝床を作る。
すると、お富がお勝の向かい側に片膝を立てて構えたのを見て、
「一、二の三で持ち上げるよ」
お勝が言うと、お富は大きく頷いた。
「一、二の三」
声を合わせたお勝とお富がおよしを抱えて薄縁に寝かせると、すかさずお啓が掻巻を掛けた。
女たちが動いている間、彦次郎は板張りに座ったまま動けず、伝兵衛も茫然と土間に立ち尽くしていた。
「医者が来る前に、湯を沸かしておいたほうがいいね」
お富がそう言うと、
「ともかく、井戸端を片付けてから家々で湯を沸かすことにしようじゃないか」
お勝の意見に頷いたお富とお啓は、急ぎ路地へと飛び出していく。
「彦次郎さん、心配しなくていいですよ。後は、わたしらにまかせておけばいいんだから」
そう言って土間の下駄に足を通したお勝は、
「医者に診てもらえば、およしさん、きっとよくなりますよ」
そう声を掛けたが、およしの枕元に座り込んだ彦次郎から返事はなく、身じろぎひとつなかった。