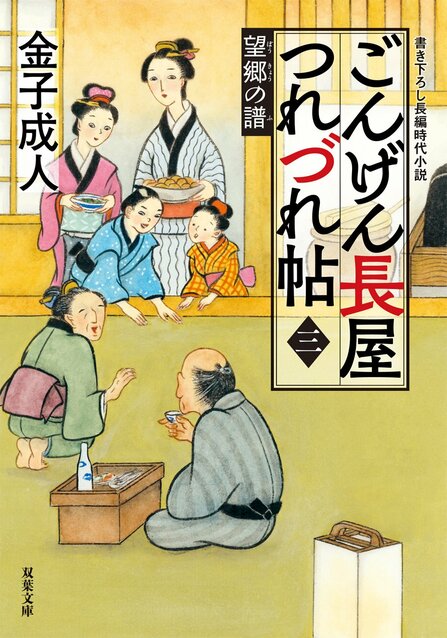三
『ごんげん長屋』は静けさに包まれている。
小さな行灯の明かりの傍で、お勝と彦次郎が火鉢を間に向かい合っていた。
手伝いや見舞いに駆けつけていたお富やお啓、それにお六は、ほんの少し前に彦次郎の家から引き揚げていった。
栄五郎が連れてきた医者の診立てによれば、およしの熱は風邪が引き起こしたものだという。
医者が置いていった薬が効いたのか、およしは半刻以上も眠り続けていた。
およしが倒れてから一刻ほどが経った、五つ半(午後九時頃)という頃おいである。
火鉢に掛けられた鉄瓶から、湯気が小さく立ち上っている。
「お勝さん、もう引き揚げてくれていいよ。明日もあるだろうからね」
彦次郎に声を掛けられたお勝は、
「えぇ」
曖昧な返事をした。
明日からの彦次郎夫婦の食事の世話や看病については、昼間長屋にいるお富、お啓、それにお琴が順番に受け持つことで、さっき話は決まった。
お志麻やお六も、手空きのときは手助けをすると申し出たから、お勝は明日からも安心して仕事に行くことはできる。
「実は、彦次郎さんと差し向かいで話をしたいことがありましてね」
お勝は、一人残ったわけを静かに口にした。
「ここを出ることにした一件なら、勘弁してくれないかねぇ」
弱々しい声を出した彦次郎は、
「およしがこんなふうじゃ、治るまで身動きは取れないだろうし」
呟くような声とともに、小さく吐息を洩らした。
「急にここを出ると言い出したのは、昼間、『岩木屋』にやってきたお方と関わりがあるんじゃありませんか」
お勝は努めて穏やかな物言いをしたが、彦次郎はわずかに顔を俯けた。
「常陸国から来た、恭太とかいう──」
そこまで口にしたお勝に、彦次郎がふっと顔を上げた。
「あのお方が短刀を見せたときから、なんだか、彦次郎さんの様子が変わったように見受けられましたのでね」
お勝は、鉄瓶の湯気に遣っていた眼を彦次郎に向けた。
「常陸の府中は、およしさんの郷里だそうで」
そう口にしたお勝を、彦次郎が、何か物言いたげに見た。
「昨日、寺巡りの途中『岩木屋』に立ち寄ったとき、およしさんの口から、常陸国総社宮や西光院っていうお寺の話が出たんですよ。なんだか、懐かしそうな口ぶりでしたから」
そう打ち明けたお勝は、眠っているおよしの方に眼を向けた。
お勝につられたように、彦次郎はおよしに眼を遣ると、
「わたしとおよしは、生まれた府中から、逃げた身の上なんだよ」
そう打ち明けて、小さなため息を洩らした。
「逃げた──?」
「といっても、何もご法度を破ったわけじゃないんだ。だがね、逃げた身としては、同郷の者とはいまだに関わりたくなくてね」
火鉢に手をかざした彦次郎は、小さな苦笑いを浮かべた。
「でも、どうして、あの恭太と名乗った方が府中のお人だとわかったんですか。あの人はたしか、久市の倅だと口にしただけだったと──あ、彦次郎さんは、久市という人に心当たりがあったんですね」
お勝の問いかけに、彦次郎は深く息を吐くと、大きく頷いた。
「わたしは、十五のとき、府中の刀鍛冶、二代目義平に弟子入りしたんだ。そこに、三つ年上の兄弟子として、久市さんがいたんだよ」
彦次郎が、静かに語り始めた。
弟子入りしてから七年後、二代目義平が急死するという出来事が起きた。
そこで、三代目義平を立てなければならなくなり、久市と彦次郎の間で修業していた二代目義平の長男、万治が、鍛冶仲間や刀剣屋の主たちとの話し合いの末、三代目となったという。
三代目義平は、彦次郎よりひとつ年上であった。
その翌年、幼馴染みのおよしが、三代目の女房として、彦次郎の前に現れたのである。
「ふたつ年下のおよしとは、幼馴染みというだけで、十年以上も会っていなかったから、師匠の女房に収まったことに驚きはしたが、それだけのことだったんだ」
だが、幼馴染みだということもあって、三代目の前でも気安く言葉を交わすことはあったと、思い出したように彦次郎は口にした。
およしが、三代目の子、梅太郎を産んだ翌年のことに話は及んだ。
二十八になっていた彦次郎の打った刀が、三代目義平の刀よりも高い評価を受け、水戸家の重臣の一人に買い取られるということが起きて、府中ではちょっとした騒ぎになった。
「わたしにすりゃあ喜ばしいことだったが、三代目を継いだ義平さんとしては、きっと、苦杯を嘗めさせられた思いがあったんだよ」
その直後から、彦次郎に対する三代目の対応が変わり始めたという。
『おれは、逆立ちしても彦次郎様の腕には敵わない』
『おれが弟子になった方がいいな』
『うちに住み込みをさせて、美味くもない朝餉夕餉を食べさせなきゃならないのが申し訳ない』
などと、盛んにへりくだった物言いをするようになって、ついには、
「ご立派な彦次郎様をうちで引き留めておくのは恐れ多いことだ」
三代目はそう公言して、彦次郎を自分の鍛冶場から追い出した。
そんな彦次郎に救いの手を差し伸べたのが、一年前に独り立ちして鍛冶場を興していた、久市だった。
久市の元で刀鍛冶に没頭できたおかげで、彦次郎の刀への評価は安定して続いた。
三代目の元を追われてから二年後、およしが離縁されて義平の家を出たという話が彦次郎の元に届いたのである。
久市とともにことの真偽を調べたところ、三代目は、梅太郎を手元に置いて、およしを家から追い出したということがわかった。
そればかりか、三代目は前々から、彦次郎とおよしの不義密通を疑っていたらしいということも知った。
三代目は酒に酔うと人前も憚らず、梅太郎はまるで、彦次郎の種であるかのようなことを方々で口走っていたというのだ。
「あの時分のわたしとおよしには、そんなことは一切なかったよ。にもかかわらず、三代目からあらぬ疑いをかけられて、我が子を置いて家を出されたおよしを思うと、不憫で仕方がなかった。密通の相手と名指しされたわたしにも、責められる一端があるようにも思えてね」
そんな思いに駆られた彦次郎は、家を出されたおよしのことが気にかかり、仕事の合間に、その後の消息を調べ始めた。
だが、その足跡を辿るのに難儀したのだという。
府中で下駄屋を営む実家を訪ねたのだが、「あんな娘のことなんか知らん」と、親兄弟からは冷淡な言葉を浴びせられた。
親戚や知人を訪ねても、不義密通を犯したおよしは白い眼を向けられていることを知っただけだった。
「およしがそういう目に遭っていると知ったときは、可哀相でねぇ」
呟きを口にした彦次郎が、およしの方にそっと眼を向けた。
お勝もつられたように眼を向けると、およしは昏々と眠っていた。
「下駄屋のおよしに似た女が、小幡の旅籠で働いていたぞ」
宗太郎という幼馴染みの男がそう知らせてくれたのは、およしが三代目義平の家を出されてから三年が経った頃だったと、彦次郎が口を開いた。
宗太郎は、およしとも幼馴染みだった。
長じて府中の米問屋の手代になっていた宗太郎は、年に何度か、水戸の出店と府中を行き来しており、水戸街道にある小幡宿は行き帰りのときに通りかかる宿場であった。
およしに似た襷掛けの女は、旅籠の表通りに桶の水を撒いていたということだった。
十年以上も言葉を交わしたことはなかったものの、府中では、嫁に行ったおよしを町中で何度も見かけていたから見間違えることはないと、確信を持って宗太郎は頷いた。
婚家を出されたおよしの不遇を知っていた宗太郎は、声を掛けるのを躊躇ってしまったが、小道を奥に向かったおよしが、勝手口から旅籠の中に入ったのを確かめていたのである。
彦次郎が水戸街道の小幡宿に足を向けたのは、宗太郎の話を聞いてから十日後のことだった。
世話になっている身とすれば、久市が請け負っていた仕事をないがしろにするわけにはいかなかった。
宗太郎から聞いた話を久市に打ち明けた彦次郎は、一日の休みを貰い、小幡宿へと向かった。
府中から小幡宿までは、三里十七町(約十三・七キロメートル)だから、その日のうちに往復できる道のりであった。
朝の暗いうちに府中を出た彦次郎が小幡に着いたのは、五つ半(午前九時頃)という時分だった。
ほとんどの泊まり客を送り出した旅籠は一息ついた頃おいで、台所女中のおよしを訪ねてきた彦次郎を、勝手口から入れてくれた。
台所の外で待たされた彦次郎の前に、前掛けを締め、襷掛けをしたおよしが現れたが、眼を瞠るだけで声はなかった。
それは彦次郎も同じだったが、
「宗太郎が見かけたって言ったもんだから」
一言、そう口にすると、用意してきた府中の菓子と、百五十文ばかりを入れた袋をおよしの手に持たせ、
「また、来るから」
と、その日はそのまま府中へと立ち帰ったのだ。
「それからは、月に一度は小幡に通って、およしの様子を見て、何か要るようなものはないかと聞き、何かあれば翌月には届け、届けるものがないときは、ただ、およしの顔だけを見に行っていましたよ。そのうち、およしがわたしを待っているということがわかってね。そうなると、こう、情というのかね、そんなもんが湧き出してきたんだよ」
そう話すと、彦次郎は若い時分のことを思い出したのか、照れたように苦笑いを浮かべた。
府中から小幡宿に通い始めて二年が経つと、お互い、離れがたい思いが募って、ついに彦次郎とおよしは江戸行きを決意したのだ。
二人の決意を知って、久市は快く送り出してくれた。
その際用意してくれた道中手形には、〈常陸国府中 鍛冶師久市方雇人 彦次郎〉と記されていた。
その手形のおかげで、江戸に着いた彦次郎は、中之郷瓦町の刀鍛冶、松蔵の元で働くことができ、たまたま見物に訪れておよしが気に入った、根津権現社にほど近い『ごんげん長屋』に身を落ち着けることになったのである。
「松蔵親方の鍛冶場には、十人くらいの弟子がいたんだ。近くには武家屋敷もあるし、小梅村には百姓家もある。もっぱら刀を打ったり直したりする何人かと、鎌や鍬なんかを作る何人かに分かれて仕事をしたよ。逃げてきた身としては、ありがたかった。ただ、中之郷瓦町と源森川を挟んだ北側には、水戸様の二万坪を超えるお抱え屋敷があって、そこからの注文にも応えてたんだ。江戸へ来ても、常陸国と関わることになるとは、不思議な因果としか言いようがなかったよ」
「でも、彦次郎さん、話を聞いたかぎりじゃ、何も逃げなきゃならないわけはないじゃありませんか」
「そりゃ、そうなんだが。どこかで何か、後ろめたい思いがあったんだよ。三代目の義平さんに疑われるような羽目になったのも、わたしの落ち度のような気もしてね。そのあげくに、およしをかっ攫って飛び出したことで、もうひとつ罪作りをしたような気がしてしょうがないんだよ」
そう言うと、彦次郎は、小さく自嘲ぎみに笑みを浮かべた。
「そんなことはもう、忘れてもいいんじゃありませんかねぇ。昨日、およしさんが『岩木屋』で洩らしてましたが、国を出て二十年くらい帰ってないんじゃありませんか」
お勝が問いかけると、
「あぁ。そうなりますかねぇ」
そう呟いた彦次郎が、ふと寝ているおよしに眼を向け、
「およしを江戸に連れ出して、五十四の婆さんにさせてしまったかぁ。わたしだって、五十六の爺さんになったがね」
小さな笑みを浮かべた。
「彦次郎さん、二十年も住み慣れた『ごんげん長屋』じゃありませんか。出ていくなんて、あんまりですよ」
お勝は静かにそう投げかけた。
だが、彦次郎は黙って火鉢の縁に両手を置くと、軽く俯いてしまった。
表通りの方から、微かに拍子木の音が届いた。
町の木戸が閉まる、四つ(午後十時頃)を知らせる音である。
ほどなく九つ(正午頃)という頃おいである。
『岩木屋』の店の中は、先ほどまでの賑やかさが嘘のように静かになっている。
「ありがとう存じました」
土間に下りた慶三が、質草を請け出して帰る浪人を戸口の傍で送り出した。
お勝は帳場に着いて、帳面付けに余念がない。
「さてと」
声を発して土間を上がった慶三は、帳場近くの火鉢の傍に膝を揃えると、紙縒り作りを再開し始めた。
そこへ、奥から現れた吉之助が、提げてきた鉄瓶を火鉢の五徳に載せるとそのまま座り込み、慶三と並んで紙縒りを縒り始める。
「番頭さん、さっき慶三に聞きましたが、この前ここに立ち寄った『ごんげん長屋』のお年寄りが、寝込んだらしいね」
吉之助が、縒りながら声を掛けた。
「えぇ。そうなんですよ」
帳面を繰る手を止めて、お勝は返答した。
「加減はどうなんだい」
「ひと晩は心配しましたけど、翌日には熱も下がってほっとはしたんですけどね」
はっきりと快復したとは言いがたいおよしの容体に、お勝は言葉を濁した。
およしが熱を出してから、四日が経っていた。
熱は下がったものの、年のせいか、まだ起き上がることはできないでいる。
およしの世話と彦次郎の食事や身の回りのことは、『ごんげん長屋』の住人が交代で手助けをしていた。
「およしさんの傍に座り込んでると、お前さんまで病魔に取り憑かれるぜ」
向かいの棟で一人暮らしをしている年長の藤七の言葉に背中を押されたのか、彦次郎は昨日から、研ぎの仕事を始めた。
「彦次郎さんが刃物を砥石で研ぐ音が子守歌に聞こえるのか、目覚めていても、およしさんは安心したような顔をして、すぐ眠ってしまうんですよ」
昨夕、長屋に帰ると、微笑みを浮かべたお志麻からそんな報告を受けて、お勝はほのぼのとした思いに駆られたことが、頭をよぎった。
そのとき、勢いよく戸が開けられた。
「いらっしゃ──おや」
慶三は、入ってきたお琴を見て口ごもったが、
「こりゃ、お琴ちゃんか」
吉之助は笑みをこぼした。
「たった今、男の人が二人来て、彦次郎さんの家の外で、中に入れてくれって声を上げてるんだよ」
お琴の顔は引きつっている。
「男って」
お勝が口にすると、
「一人はこの前、わたしがここに連れてきた丸顔の人だよ」
お琴はそう答えた。
「二人の男の用件はなんなんだい」
お勝は帳場から腰を上げた。
「わからないけど、彦次郎おじさんの家の中にいたお啓さんに、おっ母さんを呼んできてって言われて来たんだよ」
お琴は訪ねてきたわけを、懸命に伝えた。