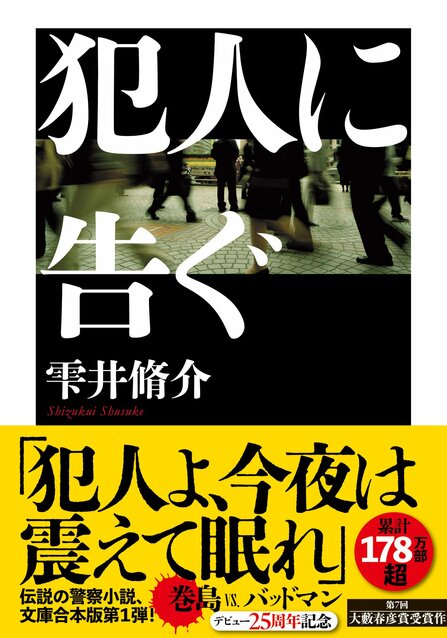豪邸とはいってもトイレにまでエアコンは利いていない。巻島はトイレットペーパーを巻き取って汗を拭った。
警察幹部二人が汗だくになって肩を組み合い、恫喝や媚を駆使して“交渉”している様はさぞ異様だろうが、巻島当人としてはある種の割り切りで対処できるものだった。いつしか、プライドも道理も軽く捨てられるのを覚えていた。昔、〔ヤングマン〕と言われた男は、手練手管で組織に尽くす男になりつつあった。
「うちの参加は特殊班だけだ」上との協議を済ませた後藤が、廊下で巻島に囁きかけてきた。「あと西東京の各署中心に人質保護に動ける人員を待機させとく。部長の新宿署入りも中止。課長も本庁に戻って成り行きを見ることになった」
主導権を譲った以上、警視庁の士気はすっかり下がってしまったらしい。
「イッパツヤの線も、目ぼしい相手は監視下に入れたが、これというような動きはないらしい。とりあえずはそっちのお手並み拝見だ」
「分かりました」
巻島は無線を対策本部につないで藤原課長に調整の結果を報告した。〈了解〉との反応しかなかったが、藤原にしろ曾根にしろ異存はあるまい。
そのあとリビングに戻って、家族に健児君の写真を見せてもらった。こんな幼い子をさらうとは許せんな……そんな感情を自分の中に喚起させて写真を返した。それが作為の感情か本当の感情かの判断は自分でもつかない。段取りの一つとして機械的にやっているとの認識がないでもない。
家族とは、それぞれの役割について簡単に打ち合わせた。桜川社長夫妻は犯人から電話がかかってきた場合に応対するため自宅に残る。一方、息子の桜川夕起也は妻と一緒に新宿に行くことを主張してきた。夫がいればそれが心の支えになって、妻の麻美も何とか身代金の受け渡しに臨めそうだという。
桜川麻美は小柄で華奢な身体つきをした女だった。眼の下にはかすかに隈ができている。二十八歳らしいが、印象的にはよくも悪くも少女っぽい面影があり、誰かが支えてやらないと重責を果たせそうにないようなか弱さが確かに見受けられる。巻島は娘のいずみを思い出した。顔つきこそ似てはいないが、雰囲気には通じるものがある。
犯人が新宿までの移動途中に接触してくる可能性も捨て切れないため、夕起也は麻美とは別行動で、巻島らとともに新宿まで行ってもらうことにした。麻美には、夫が近くにいるということで我慢してもらう。代役候補の女性捜査員がやってきたが、一見して髪型も体格も雰囲気も麻美とは隔たりがあったので、その手は巻島の判断であっさり捨てた。
新宿までの道中、麻美に付かず離れず警護する相模原南署の刑事も待機場所でスタンバイし、新宿でのオペレーションスタッフもすでに出発したとの連絡が入った。巻島も連絡係としてここに残る者以外を引き連れて、先に現場へ向かう頃合いになった。
「麻美さんの出発時間は本部からの無線で指示が来ることになっていますから。我々と夕起也さんは一足先に出ることにします」
「よ、よろしくお願いします」
麻美は青白い顔をして震える声を絞り出した。いかにも頼りないが、ここまで来たら開き直って、母は強しというところを見せてもらうしかない。
「どんと行きましょう」
巻島はそう声をかけておいた。
「とにかくな、健児の命を第一に考えてやってくれ。頼んますわ」
傲岸に見えていた桜川社長も、ソファから腰をずらして床に膝をつき、頭を下げてきた。
「お前もぼけっとしとらんと。夕起也も」
そう言って、ほかの家族にも頭を下げさせる。
巻島はただ単に頭を下げ返すにとどめておいた。
「じゃあ、行きましょう」
目の前の空気を嫌って、夕起也に声をかける。
家族が頭を下げなくとも手を抜くことはあり得ないし、逆に頭を下げられたからといって能力以上の結果が出せるわけでもない。そんな醒めたプロ意識が二十年の刑事生活の中で身に付いていた。そういう処し方が結局のところ、アベレージとして安定した結果を出すことにつながる……それは事実だった。
順次、時間をずらして外に出る。後藤は警視庁の車が待機しているらしく、さっさと巻島たちから離れていった。巻島が乗ってきた車には、助手席に本田が乗り、後部座席に巻島と夕起也が乗り込んだ。
国道十六号線を南下し、横浜町田インターから東名高速道路に乗り入れて、新宿へと急ぐ。
無言の車内には、現場に臨む緊張感がじわりと漂い始めていた。
予定のオペレーション通りで本当にうまくいくのだろうか……ふと、そんな素朴な疑問が巻島の頭に湧いた。曾根ははなからこの事件を楽勝ムードで捉えている。犯人は電話交渉でうまくやったと思っている。だから、金を受け取りにのこのこ現れたところを捕まえればいい。そう決めつけているようだ。
しかし、実際に犯人が油断しているかどうかは分からない。警察はまだ、犯人の声も聞いてはおらず、それが逆に根拠のない自信につながっているように思える。巻島も含めて、まだ誰も現実感を伴ってこの事件に当たってはいない。一抹の不安を感じるならそこだ。
ただ、曾根が打ち出したオペレーション方針は、考えられる選択の中では最善であり、堅実であるのも確かなのだ。共犯の有無にかかわらず、とりあえず現場に現れた犯人を捕捉するのは、誘拐捜査の成功例の典型でもある。いくら犯人が金に困って見境のつかない人間であろうと、幼児誘拐が卑劣な犯罪であることくらいは分かっている。逮捕された時点で彼のすべては終わり、観念するものなのだ。もし共犯が人質を監視していて、計画が失敗したときにはその命を奪おうと考えていたとしても、逮捕された人間にとっては自分の罪を重くするだけのことで、もはや迷惑以外の何物でもない。厳しく追及すれば、必ずあっという間に落ちる。
交渉の過程から考えても、今現在、子供が生存していることはまず疑いがない。身代金を受け取りに来た犯人を取り逃がすようなことさえなければ、結果は堅いはずだ。
納得してみて、何ということはない不安だと気づく。万全の腹構えを求めるいつもの癖で、無意識のうちに何か気になることはないか探してしまっている。事前点検に異状はない。
「親父の仕事関係の人間はマークしてますか?」
不意に、横に座っていた夕起也が硬い声を出した。
「親父はあの通り、ワンマンタイプだから敵も多いはずなんです。商売敵には憎まれてるだろうし、取り引き先を泣かせるようなこともやってるはずです。売り出しのときは朝から晩まで狭い路地に客が行列を作って、近隣から苦情が出たことも一度や二度じゃない。結局、ああいうやり方で金儲けに走ったツケが出て、こんなことになってるんですよ」
父親の手前、家の中では話せなかったのだろう。夕起也の口振りは本心からのものに聞こえた。
「考えられる可能性はすべて視野に入れてます」巻島は冷静に受けた。「ただ、今は身代金の受け渡しに集中する態勢を敷いてますから。まあ、お父さんもテレビに出られる有名人ですし、必ずしも交際範囲の中に犯人がいると決めつけられるケースでもないと思います。予断は禁物です」
「そもそも、テレビなんかに恥ずかしげもなく出るのが間違ってるんだ」夕起也は外の景色に視線を外して言う。「あんなのにもてはやされて、いい気になって、冗談じゃないよ。金のために、悪魔に魂を売った結果がこれだ」
抑えた声ではあるが、口調は感情的だった。
夕起也は本郷の会社に通う普通のサラリーマンだという。事情聴取をした本田から簡単に聞いたところによれば、かつては父親の店舗で働いていたこともあったらしい。跡継ぎが辞めるのだから、よほど肌に合わなかったのだろう。三十三歳という若さながら、商魂逞しい父親とは正反対の保守的な男のようだ。
とかく有事には家族間に亀裂が入りやすいものだが、それに口を挿む立場にはないと心得ている巻島は、夕起也の言葉も聞き流すにとどめておいた。