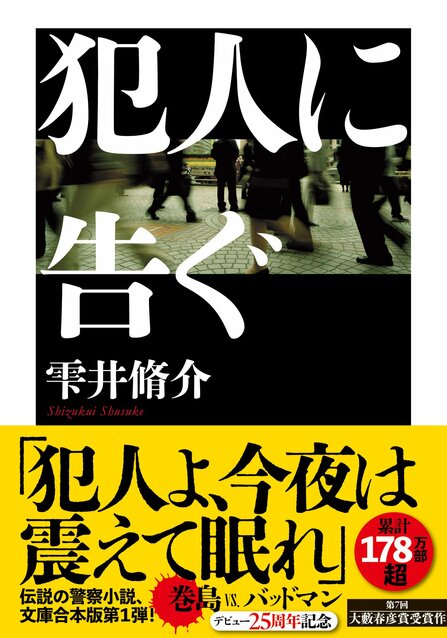刑事を続けていると、自分が追っているはずの犯人に、ふと、そこはかとない恐怖心を抱くことがある。
たいていの場合、それは相手の姿が見えないからだ。姿がないのに、足跡だけが残っている。追っても追っても姿を見つけることができない。ただ、足跡だけが増えていく。正体を暴けば何の変哲もない、ただのチンピラなのかもしれない。しかし、闇夜が人の心に化け物を見せるように、姿の見えない犯人は刑事の心の中でいつしか怪人と化していく。
ときには捜査の中でその怪人の気配を感じることもある。じっとこちらを窺っているような暗い眼差しが溶け込んだ空気……それを感じ、刑事は立ち尽くす。あたりを見回すが、やはり怪人の姿は見えない。
神奈川県警の警視、巻島史彦にとって、そんな畏怖にも似た感情を抱いた最初の相手は、数年前に出会った〔ワシ〕だった。
〔ワシ〕と出会ったその年、巻島は県警本部捜査一課の特殊犯捜査中隊、通称特殊班に戻ってきていた。前年、四十五歳にして警視に昇進し、しばらく港北署の次長として主に刑事部門の統括管理的な職務経験を積んだ上での古巣復帰。特殊犯捜査の三中隊を束ねる担当課長代理が巻島の新しいポストだった。
若い頃には強盗や殺人事件を捜査する強行犯捜査中隊の刑事を務めていたが、世の中の景気が大きく浮き沈みする中で企業恐喝事件が相次いだ時期、誘拐や脅迫を捜査対象とする特殊班の増員が図られることになり、巻島もそちらの隊に異動した。以来、階級昇進後の一時期、外の空気を吸いに出ることはあったものの、専門色の強い部署だけに、そこをホームグラウンドとする刑事生活が長く続いていた。
〔ワシ〕と出会った七月のその日、巻島は非番だった。県警本部に勤める警察官の世帯が固まっている官舎の自宅で目覚めのコーヒーを喉に流し込んだのが七時半頃だった。ちょうど十日前から娘のいずみが出産のために戻ってきていて、この朝いよいよ陣痛らしきものが始まったということで、妻の園子と市内の病院の産科に連れていく支度をしながらの慌しい一杯だった。
いずみはまだ二十一歳である上に、身体つきは華奢で、ほとんど子供のような見かけをしている。それが赤ん坊を産むというのだから、浮き足立つなというほうが無理であった。
「ゆっくりしてていいよ。まだ本番じゃないみたいだから」
とりあえず痛みの治まったいずみは、ダイニングの椅子に座って呑気に言う。
「あーあ、今日の港の花火大会、見たかったのになあ」
「そんな身体で、何、馬鹿なこと言ってんの」
園子が本気になってたしなめている。
産まれたときから心臓に疾患が見つかっていたいずみは、典型的な虚弱体質で貧血がひどく、学校の体育授業もほとんど見学して過ごすような子供だった。幾度かの手術を経て、かろうじて命がつながっていると思っていたら、東京の短大に入るときには一人暮らしをしたいと言い出し、短大を卒業するときには人並みにアメリカへ卒業旅行に行き、あげくには卒業するやいなや恋人を連れて帰ってきた。すぐにでも結婚したいと言うに至っては、あまりにも子供じみていると思ったが、お腹に小さな命ができていると聞かされては説得のしようがなかった。かつての担当医からも現在の身体であれば出産に支障はないとのお墨付きをもらったらしい。
とはいえ、何となく娘が生き急いでいるように思えて、不安は拭えない。園子もそのあたりの思いは同様で、出産予定日が近づくにつれ、いざというときに困るから早く家に戻ってきなさいと重ねて娘に声をかけていた。娘のほうは親の心配をよそに悠長に構えていて、ようやく十日前に帰ってきたところだった。それでも一人の命を身ごもっている自覚はだてでなく、中高生時分からは想像もつかない食欲でもって、なかなか血色のいい顔をしている。あとはとにかく、母子ともに健康で……というのが最高にして最低限の願いであった。
「さあ、あなた、早くしないと」
妻に急かされ、巻島が着替えをしようと寝室に入りかけたところで家の電話が鳴った。
電話は巻島が取った。
〈相模原南署管内で誘拐事案の発生です〉
特殊班の中隊長、本田明広からだった。
タイミングの悪さに、巻島は思わず舌打ちをしたくなった。しかし、〈誘拐されたのは五歳の男の子〉だと聞かされて、私情はひとまず引っ込めた。
幼児誘拐、それから人質籠城は、巻島たちが扱う中でも特別の意味を持つ事件だ。何が特別かというと、世間やマスコミの注目度である。もちろん誘拐事件の進行中は報道協定が敷かれるのが通例だが、事件が決着すれば大々的に報道される。結局のところ警察の存在意義とは世間の信用を勝ち取ってこそのもので、上層部に行くほど世間の目を気にするようになり、失敗は隠し、手柄は自慢する。幼児誘拐のような、解決の道筋をつけるのに警察力が直結する現在進行形の大事件は、一般の会社でたとえるならさしずめ社運を懸けたビッグプロジェクトである。その成否によって、現在の人事体制から捜査能力まで、警察のすべての評価が下される。威信が問われるわけだ。
〈ただですね、誘拐されたのが一昨日、金曜日の夕方頃でして、昨日までに犯人から都合七度ほどの電話がかかってきて、すでに今日の身代金受け渡しの段取りまで決まってるということなんです。二千万らしいですけど、もう用意してあるとか〉
巻島は今度こそ小さく舌打ちした。身代金交渉の段階で犯人グループのシルエットを掴み、あわよくば逆探知などで一気に間合いを詰めようとするのは誘拐捜査の定石だ。それを飛ばしての捜査となると、はなからハンディを背負うことになる。
〈町田にあるイッパツヤっていうディスカウントショップをご存じですか? テレビの小売業最前線のようなドキュメント番組にもよく出てる店でしてね。家電でも食料品でも何でも全国各地から在庫品を現金商いで買いつけてきて安く売るところです。社長自ら、札束入れたアタッシェケース持ってね、まあテレビ向きの派手な商売屋ですね。そこの社長の家ですよ。ええと、桜川とかいったかな、ちょっと詳しくはまだあれなんですが、六十過ぎの元気なオヤジで、誘拐されたのはその孫ですね〉
商売の勢いで身代金交渉も勝手に進めてしまったというわけか。現金商売だからまとまった金も手元にある。テレビにもてはやされるのも痛しかゆしだなと思いながら、一方では商売上のトラブルが絡んでいる可能性もあるかもしれないなどと考えてみる。
〈警察に頼らずに自分で解決しようと思ってたようなんですが、息子夫婦がそれに反対したらしくて、彼らが勝手に通報を〉
「なるほど。で、誰が持っていくんだ?」
〈嫁さんです。犯人がそう指定したみたいですね。それで、場所が新宿なんですよ。今日の十三時です〉
「新宿か」
巻島は顔をしかめた。もたもたしていると警視庁に主導権を握られる。
「課長にはまだだな?」
〈ええ〉
「よし分かった。あとの連絡は俺がやる。君は三、四人見繕ってその家に入ってくれ。そのほかの者は所定の機器をそろえて相模原南署に集合。九時までには俺もそこに入ることにする。そのときに詳しい報告を」
〈了解です。のちほど〉
電話を切ると、巻島はため息を添えて妻を見た。
「重要な仕事が入った」
元女性警察官の園子は、嫌味も言わない代わりに労りもしない。「じゃあタクシーね」と言って、早速タウンページを広げている。
「帰ってくる頃にはおじいちゃんね。若いおじいちゃん」
いずみにも失望の色はなかった。あくまで明るく振る舞っている。
「そうだな」
巻島も軽く応じておいた。