発売中の南綾子さんの『わたしは今すぐおばさんになりたい』は、人生迷子中の30代の響が庶務にいる“どこにでもいそうな”おばちゃんと友情を育み、一歩前進する姿を描いています。
『川のほとりに立つ者は』など数々の作品で人間の機微を巧みに描く作家・寺地はるなさんのレビューで読みどころをご紹介します。
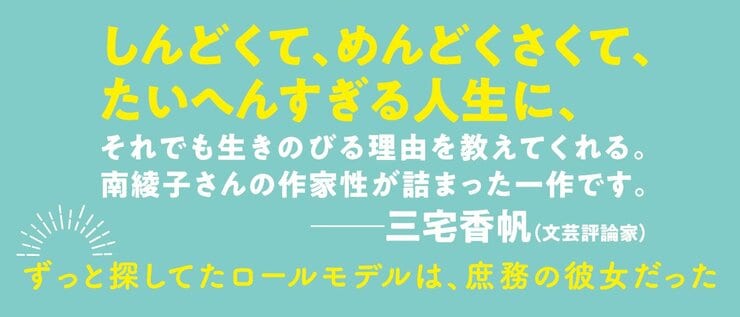
■『わたしは今すぐおばさんになりたい』南綾子 /寺地はるな [評]
「おばさん」は、年配の女性を意味する言葉である。そこになんらネガティブな意味はない。にもかかわらず、「おばさん」は蔑称とされている。
多くの人は、若さを失った女性には価値がないと思っており、だから「おばさん」と呼べば相手を傷つけられると思っているし、女性が自虐的な自称として用いることもあるし、年配のきれいな女性にはほめ言葉のつもりで「おばさんじゃない」などと言ってしまう。
本書は三十代の会社員宇佐美響が、同じ会社の年上の女性社員である桜子さんに憧れのまなざしを注ぐ場面からはじまる。「年上の女性」「憧れ」という言葉から多くの人が想像するであろう女性像とはおそらくかけ離れた、本文中にも「どこにでもいる、小太りのおばさん」と描写される桜子さんを筆頭に、いろんなおばさんが出てくる。パートナーがいる人、いない人、介護をしている人、趣味に邁進している人……とずらずら並べ立てたけれども、「こんな人」と一色でべったり塗りつぶせるような単純な人物はいない。皆、苦悩とよろこびを両脇に抱えている。
彼女たちは響を受け入れるが、有益な人生のアドバイスなどはしない。示唆しないし、導かない。むやみに包容力を発揮したりもしない。各々がただ、複雑な人生をひたむきに生きている。
おばさんたちが主人公の成長のための環境的要因ではなく、人間として描かれている。そんなのあたりまえだろ、と思われるだろうか。しかし多くの物語は「おばさん」の年齢に達した女性に「おせっかいだが親切で、未熟な主人公の世話を焼く」的な役割を強いている。もしかしたら現実においても。
その役割をさらりとかわす桜子さんは「どこにでもいる」と見せかけて、じつは稀有なキャラクターなのである。
家庭を持つか、仕事で成功するか。かつて女性たちの多くがその二択を迫られてきた。いや両方を手に入れなくては、と言う人も多い。
そうした価値観を否定することなく、でもそれとは違う幸福もあるよ、と教えてくれるこの作品に出会えたことに、大きな喜びを感じている。














