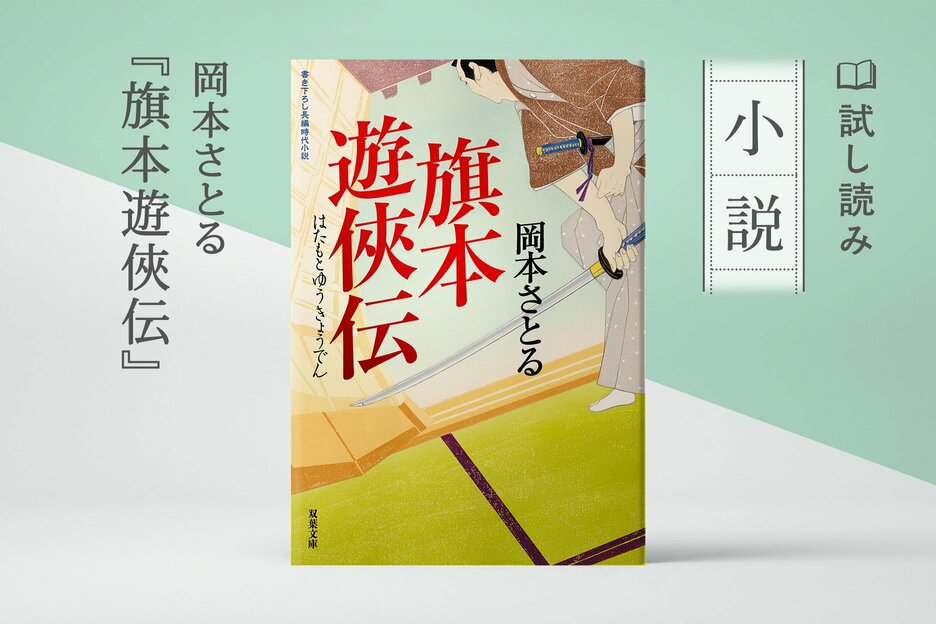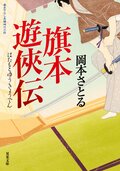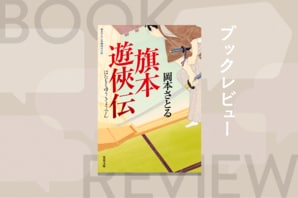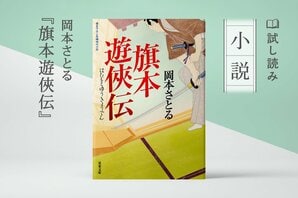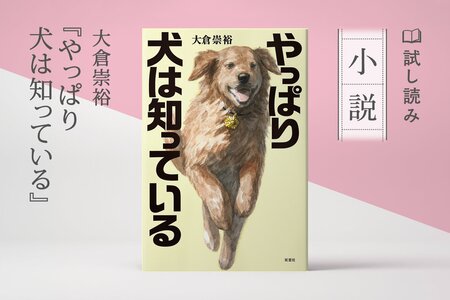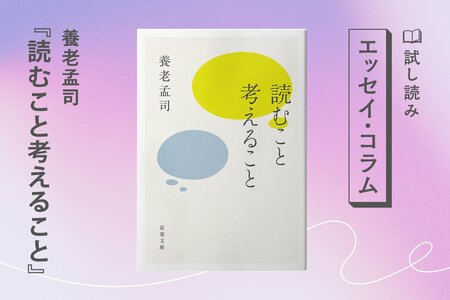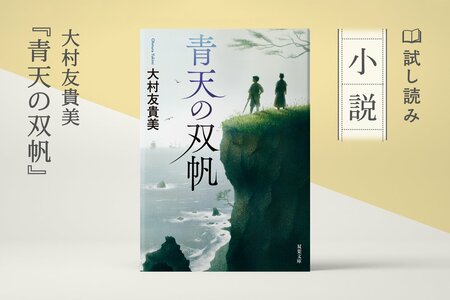四
「おい、よろしく頼むぜ……」
星影の下で、勇之助が白い歯を見せた。
そこは、すっかりと夜更けた六間堀の、宝城家屋敷裏の塀外である。
放蕩三昧の勇之助とて、そうそう屋敷を空けてはいられない。
出て行けと言われたら、いつでも出ていってやるが、そもそもこの屋敷は、亡父・主水之助から異母兄の六太夫が継いだものだ。
「部屋住の身は辛かろうが、ここはお前の家なのだ。堂々と部屋に住み続ければよいのだぞ!」
主水之助は、まだ子供であった勇之助に、よくそのように言ったものだ。
自分が死んでしまえば、妻のせいと、嫡男の六太夫は勇之助を疎んで、あれこれと意地の悪いことをするであろう。
少しでもそれに楔を打たんと思って、せいと六太夫に聞こえるような声で語り聞かせたのであった。
勇之助は、主水之助が心配するほど柔な男ではなかったが、子供心に自分が頼れるのは父親だけで、養母と異母兄から次男坊を守ってやろうという親心は、ひしひしと受け止められた。
それを思うと、
「婆ァや兄貴が何と言おうと、ここはおれの家なんだ。遠慮なく住まわせてもらうぜ」
という気持ちが湧いてくる。
大きな大名屋敷のように門限が決まっているわけでもなく、早かろうが遅かろうが、
「ただ今帰りました」
と、形ばかりの挨拶と共に、勇之助は父に言われた通り、堂々と屋敷を出入りしていた。
とはいえ、あまりにも遅い時分となれば、屋敷裏手の塀を乗り越えて、澄まし顔で己が部屋へ入るようにしている。
そんな時は、
「何だ、帰っていたのか」
と、咎められても、とっくに帰っていたような顔をして、
「いやいや、お声がけしたつもりでしたが、声が通りませなんだか。兄上も母上も、何やらお忙しそうでしたので、わざわざお訪ねするまでもないかと存じまして……。これは御無礼仕りましてござりまする」
努めて丁重に応ずるのだ。
もちろん、勇之助がこんな物言いをすると、からかっているように聞こえなくもないのだが、
「もうよい……!」
と、六太夫はすませてしまう。
彼もまた、剣術は直心影流の道場で稽古をしたのだが、三百石の旗本の長男ということで、師範は厳しい稽古も課さず、形ばかりの免状を与えた。その後も、
「まず、時には汗を流しに参られるがよろしかろう」
師範に言われて、六太夫は時折型の稽古などをしに、道場へ行ったものだが、そこで一度、勇之助が面、籠手を付けて竹刀で立合っているところを見た。
その時の勇之助の、虎の咆哮を思わせる鋭い掛け声。それと共に、縦横無尽に体を捌き、目が覚めるような技を次々に繰り出す姿をまのあたりにして、六太夫はすっかりと圧倒されてしまった。
まだ十五、六の頃の勇之助は、既に練達の士の域に達していた。
六太夫は、異母弟の上達ぶりに感心するどころか恐怖を覚えた。
勇之助が五体から発する気迫は、泰平の世に生きる武士のものではなかった。
怒りを力に変えて、いざとなれば平気で死地に赴く意思の強さを、そこに見たのであった。
以来、この困った異母弟に相対すると何やら気後れするようになってしまったのだ。
せいは、そんな弱気を詰ったが、
「母上、たとえばでござりまするぞ。勇之助が思い詰めて、母上を斬り、わたしを突き殺した後、六太夫が乱心して母を斬り、その後腹を切った……、などと言い立てたらどうなさいます」
六太夫は、親も呆れる深読みで、その小心さをさらけ出したものだ。
しかし、考えられないこともない。
旗本屋敷においては、生殺与奪の権はその当主にある。
当主が俄に乱心し、母を殺害し、腹を切ったとしても、あり得る話で、御家は取り潰されようが、異母弟の次男坊に罪は及ぶまい。
密かに母を斬り、兄に罪を被せ人知れず殺すのは容易いことではない。
しかし、勇之助の腕をもってすれば、それほど難しくもなかろう。
六太夫には現在絹という妻女はいるが、病弱で子に恵まれず、彼女が表に出ることは滅多になかった。
それだけに、六太夫は勇之助を叱り切れぬのだ。
「よし、頼む!」
勇之助は、笛五郎に手伝わせて、直助の肩に乗ると、たちまち塀の向こうに消えた。
塀の向こうは、屋敷の裏庭の一角で、大きな楠が立っている。
勇之助は、まずその大樹に飛び移り、木の陰を伝って下に下りる。
屋敷を抜け出す時は、その逆を辿ればよいのである。
長年かけて、屋敷内のそんな特徴に目をつけたわけだが、五百坪ほどの広い敷地であるとはいえ、自分に与えられた部屋と広書院、湯殿、厠以外は、勇之助は未だにほとんど足を踏み入れることはない。
部屋住の悲哀がそこにあるが、いかにこの屋敷に愛着がないか、時折自分自身気づかされて、
──いっそ、出奔してやろうか。
そんな衝動にかられたものだ。
勇之助は、息を殺して、庭から自分の部屋へまんまと入った。
我ながら巧みなものだ。
──いっそ、盗賊にでもなるか。
皮肉な笑いを浮かべて、真っ暗になった部屋に、行灯の火を入れた。
そっと抜け出し、そっと戻っても、出ていく時に行灯の火を入れておくわけにもいかない。
こうして夜になって灯を点すと、夜更けに密かに帰ったのが露見してしまうのだが、近頃は六太夫も何も言ってこなくなった。
顔を合わさねば、この穀潰しから小遣いをせびられることもないゆえ、かえって幸いだと思っているのであろうか。
すぐに寝てしまってもよいのだが、今日はその前に日誌を書いておきたかった。
彼がせっせと日誌を認めている姿は、なかなか想像がつかぬが、暴れて騒いでいるばかりでは、筆を持つ機会がなくなるゆえ、せめて日誌を認めんと考えている。
朝になって、世間が明るくなってから書けばよいのかもしれないが、
──その日に書くから日誌なのだ。
というこだわりを持っていた。
筆を手に取ると、昨日からの騒ぎを書きとめた。
こうして字にしてみると、馬鹿馬鹿しくもあり、痛快でもあり、
──おれはいったい何をしているのだろう。
と、おかしさが込みあげてきた。
すると、用人が部屋を訪ねてきて、
「申し上げます。殿がお呼びでございます」
と、告げた。
この続きは、書籍にてお楽しみください