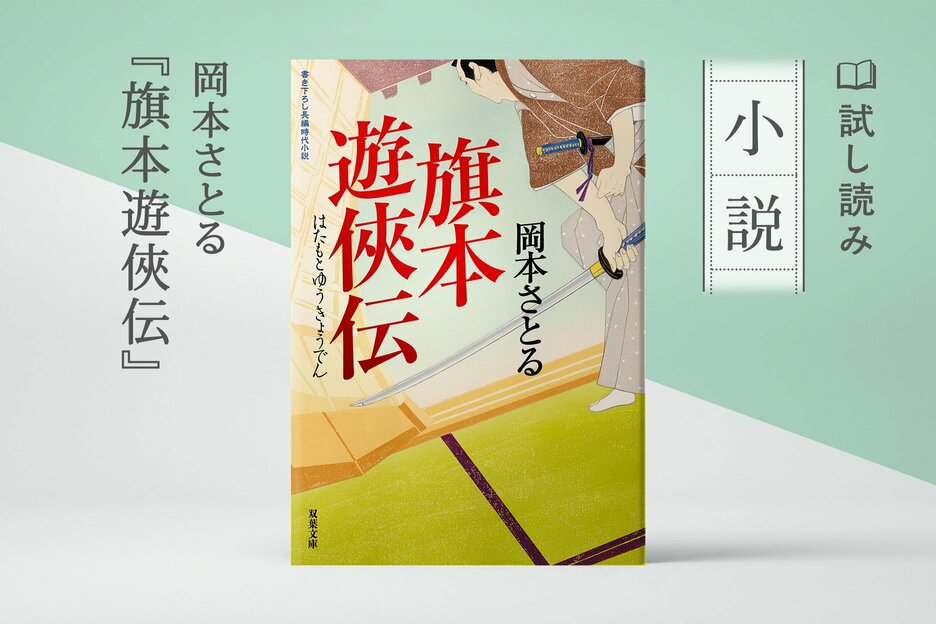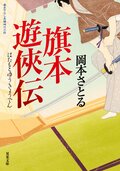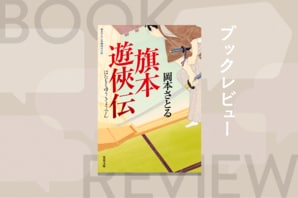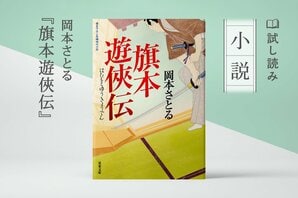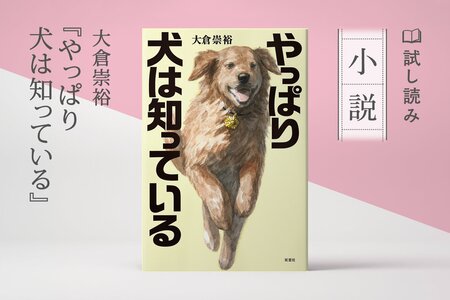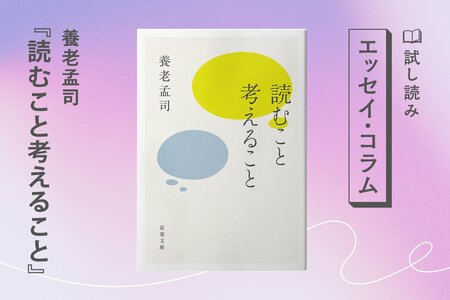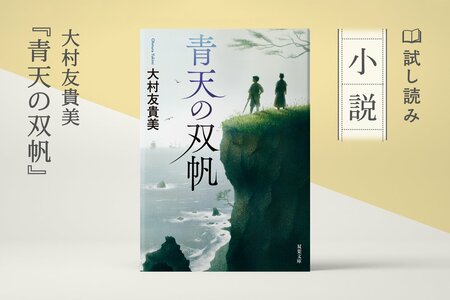二
「芳二郎の野郎、今度はきっと決着をつけてやるぜ……」
見物衆が大笑いしながら引きあげた料理屋の座敷で、ごくりごくりと水を飲みつつ、勇之助はぼやくことしきりであった。
お銀、直助、笛五郎は、新たな茶碗に次々と水を注いでやりながら、楽しそうに勇之助を眺めていた。
天根芳二郎に軽くあしらわれたからといって、それは勇之助のご愛敬であることはわかっている。
三人は、これまで何度も勇之助が大暴れしている姿を見ているが、どんな時でも弱い者は守ってやり、相手を圧倒する無双の強さを誇りつつ、どこか憎めぬおかしさを持ち合わせているこの男に惚れ込んでいるのだ。
「それで、おれに頼みごとがあると?」
酔いを醒ましつつ、勇之助は訊ねた。
「ああ、儲け話だよ」
「やっぱりそうか。お銀、そうこなくっちゃあいけねえや」
勇之助の顔が華やいだ。
「ちょうど、金に困っているところだからよう……」
うわばみの姐さんに飲み競べで負け、二両を巻き上げられた上に、料理屋に飲み代を払わねばならず、踏んだり蹴ったりの勇之助であった。
「で、何をすりゃあ好い?」
「喧嘩の仲裁さ」
「引き受けた。そんなのは、わけもねえことだ。まず話を聞こうじゃあねえか」
「それがねえ。技組と力組が果し合いをするというのだよ」
「相変わらず、いがみ合っているのか……」
技組というのは、大工、左官、瓦といった職人達の集まりで、これに対して力組というのは、車力、駕籠舁き、米搗きといった人足達の集まりである。
両者とも、遊び好きの者達が盛り場で顔を合わすうちに、
「おかしな奴らに絡まれたら、助け合おうじゃあねえか」
という話になり、結成されたのだが、こういう連中が寄り集まると、いつしか気が大きくなり、かえって喧嘩が起り易くなるというものだ。
互いを助け合い、身を守るという前提は、組同士の張り合いとなってゆき、技組と力組は、対立するようになっていた。
そのうちに些細なことから、大工と車力が喧嘩になって、それから引くに引かれぬ男の意地が重なり、遂には技組と力組の果し合いに発展したというわけだ。
両組共に十名ほどが属していて、今まで参加していなかった連中も、喧嘩の話を聞きつけて加わり、さらに人数を増しているらしい。
お銀は、時に賭場で壺振りをしたり、荒くれの溜り場には顔が利く。
すぐに喧嘩の話を耳にして、職人、人足、それぞれの親方の許を廻って、
「まあ、そりゃあ、男には男の意地ってものがありますからね。下手に引き下がれば沽券にかかわるってものですよ。親方も見て見ぬふりをしてやりたいところでしょうが、怪我でもされたら仕事がままならない。何とかしないといけませんよ。ここはひとつ、仲裁人を立てて、この喧嘩を収めてしまいましょう……」
と、持ちかけ、金を集めたのだ。
「さすがは、さいころお銀だ。大したもんだなあ」
勇之助は感心した。
「それで、幾ら集まった?」
「十両ってところさ」
「でかしたぞ。そんならおれが出張るから、半分くれるかい」
「わかったよ。そんならあたしは三両もらっておくよ」
「残りの二両は、直、笛五郎、お前らに一両ずつやるから、ちょいと手伝え」
「へへへ、こいつはありがてえ」
「何でもするぜ。でも勇さん、喧嘩は明日の朝だっていうぜ。それまでに酒は抜けているのかねえ」
笛五郎は心配したが、話すうちに、勇之助の強靱な体はきびきびと動き出し、顔付にもいつもの律々しさが戻ってきた。
「案ずるねえ。こちとら金がいるんだよ。二日酔いしたって、喧嘩の仲裁くれえどうってこたあねえよう」
「それでこそ勇さんだ」
「お銀、さっそく軍議だ。直も笛五郎も抜かるんじゃあねえぞ」
「合点承知之助!」
「酒にするかい?」
「馬鹿野郎、匂い嗅ぐのも嫌だよう」
男達が笑い合うのを見ながら、お銀はふと顔を曇らせて、
「勇さん、殿さまになっちまうのかい?」
ぽつりと言った。
「おれが、殿様に……? ははは、何の洒落だよう」
「いや、さっき、芳二郎の奴が、そんなことを言っていたからさ」
「芳二郎が?」
勇之助は、先ほどの天根芳二郎とのやり取りを思い出して、
「ああ、あれか……」
ぷっと吹き出した。
酩酊して、芳二郎に軽くあしらわれてしまった勇之助であったが、芳二郎はあの時、
「お前は貧乏旗本の殿様がお似合えだな……」
と、吐き捨てて立ち去った。
「お銀、お前はどんなことでも聞き逃さねえなあ」
「そんな話がきているのかい?」
勇之助は、旗本の次男坊だが、どこかの家の養子に迎えられたら、まだまだ殿様になることも夢ではないのだ。
「芳二郎の野郎も、なかなかの地獄耳だからな。ちょいと小耳に挟んだのかもしれねえなあ……」
勇之助はニヤリと笑った。
お銀、直助、笛五郎は、いったい何の話だと身を乗り出した。
「このところ、本家の小父さんが具合が悪いとかでよう……」
本家の小父さんというのは、菊川橋の東方に屋敷を構える、宝城家本家千五百石の当主・宝城左衛門尉豊重のことである。
勇之助にとっては、祖父同士が兄弟で、豊重は父・主水之助の従兄弟にあたる。風狂の人で、これまで無役に甘んじてきた。それゆえ勇之助は、豊重に流れる血を受け継いだのではないかと言われてきたのだが、子供の頃は、
「お前が勇之助か、なかなかおもしろい奴だと聞いているぞ」
本家へ挨拶へ行くと、いつも親しげに声をかけてくれたのを覚えている。
豊重には子がなく、五十六歳になるというのに、まだ嫡子を決めていなかった。
身体壮健で、跡取りについては、
「そのようなものは、己が体の具合が悪うなった時に決めればよいことだ」
と、今まで意に介さなかった。
無役の変わり者のこととて、支配も特に口を挟まず、緩やかに時が過ぎていた。
ところが、文政三年(一八二〇)の夏となり、俄に体調を崩して、この十月を迎えた。
暦の上では冬である。
厳しい暑さを乗り越えたが、これからやってくる寒い日々に体が堪えられるか、不安になっているらしく、
「いよいよ、養子を迎える時がきたようじゃのう」
と、遂にその言葉を口にしたらしい。
まだ六十にもなっていないのだが、病気ひとつしたことのない身が、立て続けに風邪をひいたり、腹を壊したりすると、一気に心が折れてしまって弱気になったのだそうな。
本家が養子を迎える──。
そういう噂は、どこからか広まるもので、俄に周囲が騒がしくなってきて、
「いよいよ、その日がきたようですぞ」
宝城家分家の後家・せい、即ち勇之助の母は、長男の六太夫が迎えられるものだと確信し、大いに胸をときめかせているのである。
六太夫は、これといって人より優れたものもない。
剣術も学問も人並で、才気走る器量もない。
就職の運動をしても、一向に声がかからず無役のままでいるのを見ても、その凡庸さはわかるのだが、
「わたしは、まったく付いていない……」
と、駄目な男が必ず口にする言葉を吐いてばかりいた。
本家の豊重が風狂の人で、小普請のまま特に働かずに過ごしたのが、宝城一族全体に悪影響を及ぼしたと言うのである。
本家の当主がやり手であれば、自ずと一族の者も世に出やすくなるというものだと、豊重を恨んだものだ。
だが、ひとつだけ本家の小父様がありがたいのは、今まで嫡男を儲けなかったことだ。
六太夫が養子として召し出されれば、三百石の小旗本から、一気に千五百石の大身となる。これは願ってもないことだ。
その余裕が、この先の就職にも上手く影響して、やがて召し出されるのではないかと、夢がふくらむのであった。
千五百石の旗本となれば、作事奉行、普請奉行、大坂町奉行などの要職に就くことも出来ぬではない。
本家が養子を取るとなれば、血統としては六太夫が一番相応しいはずだ。
「六太夫は、さしたる者ではないが、泰平の世にあっては、あのような男が殿様でいるのが無難なのであろうのう」
かつて豊重は彼をそう評していたと聞いていた。
豊重としては、決して六太夫を称えたわけではないはずだが、
──自分は旗本の殿様に相応しい男なのだ。
と、彼は好いように捉えていた。
実際、殿様などというものは、何ごとに対しても、
「よきにはからえ」
と、言っている方が、家中の者もやり易く、御家安泰といえるであろう。
あれこれと想いを馳せると、せいと二人で養子への期待が日々何度も口に出る。
「まあ、それで、うちの兄貴が、本家の養子に迎えられるという噂が出たんだろうよ」
勇之助は他人事のように言った。
「だがよう、勇さん、お前の兄さんが本家を継ぐとなれば、お前が分家を継ぐってことになるんじゃあねえのかい」
「直助の言う通りだ。そうなりゃあ、勇さんは三百石の御旗本のお殿様じゃあねえか」
直助と笛五郎は、神妙な顔付きとなった。
先ほど芳二郎は、それを揶揄して、貧乏旗本の殿様がお似合いだと言ったのではなかったのか。
確かに三百石では大身といえないが、同心は十石二人扶持、与力でも二百石取りなのだ。これは立派な殿様ではないか。
芳二郎はそれを僻んで言ったのに違いない。
「そうなりゃあ、勇さんは、あたし達とつるんじゃあいられないんだねえ」
寂しそうにお銀は言った。
「おきやがれ。兄貴が本家を継いだからって、あのくそ婆ァが、そんならお前が分家を継げとは言わねえよう」
勇之助は、大きく頭を振った。
「おれは、死んだ親父が、端に手を付けて生まれたんだぜ。あの婆ァはどこまでもおれが気に入らねえんだ」
それが彼の身上であった。
勇之助を産んだのは、おしんという下女で、口入屋から雇い入れた百姓の娘であった。
主水之助はおしんを気に入り、つい手を付けてしまい、おしんは子を腹に宿した。
せいは、狂わんばかりに怒り、夫を詰ったが、主水之助はおしんを実家に戻し、子を産ませた後に、次男として引き取った。
おっとりとした男であったが、武家の当主は男子を二人生すものだと、一歩も引かなかった。
おしんは勇之助を産んでほどなくして亡くなり、生母として屋敷に暮らすことはなかった。
妻妾の板挟みにならずにすんだのは、主水之助にとっては幸いであったかもしれないが、せいは何かというと勇之助に辛く当った。
それを不憫に思ったか、主水之助は次男坊をことあるごとに庇ったものだが、彼もまた、勇之助が十歳の折に亡くなり、若くして跡を継いだ六太夫は、父に代わってこの異母弟を庇いはしなかった。
六太夫とてまだ二十歳にもならず、気の強い母の言いなりになるのは仕方がなかったのだが、何かというと、母に反発する勇之助が疎ましかったのである。
このような境遇に置かれた勇之助が、ぐれて屋敷を出ては、深川界隈の盛り場で暴れ廻ったのも頷ける。
養母と異母兄と今さら折合いをつける気もないし、
「まず、兄貴が本家へ行きゃあ、婆ァはそれについていって、そん時改めておれを廃嫡にするのだろうよ。そもそもおれは、三百石の殿様になんぞ成りたくもねえや。芳二郎は羨ましかったんだろうがよう。継げと言われても今さら御免さ」
勇之助は、さばさばとした表情で言った。
お銀、直助、笛五郎は、それを聞いてほっとしたが、勇之助がこれまで辿ってきた日々を思うと、何とも切なくなる。
勇之助に惚れ込む三人だけに、
──これほどの男を、盛り場で腐らせていてもよいのであろうか。
そんな想いをも抱くのだ。
とはいえ、天根芳二郎が言うように、勇之助がその辺りにいる、貧乏旗本の殿様でいるのは尚嫌で、遊び人達の胸を締めつけるのだ。
「旗本遊俠伝」は全4回で連日公開予定