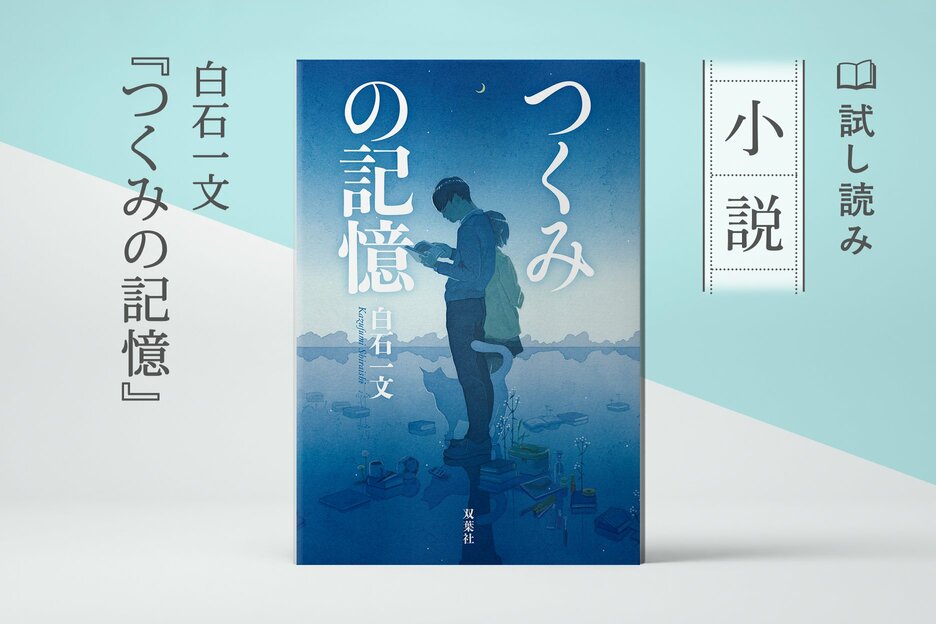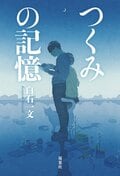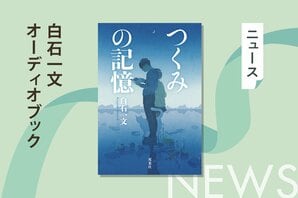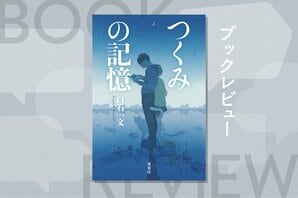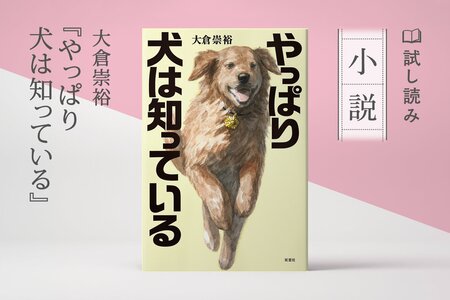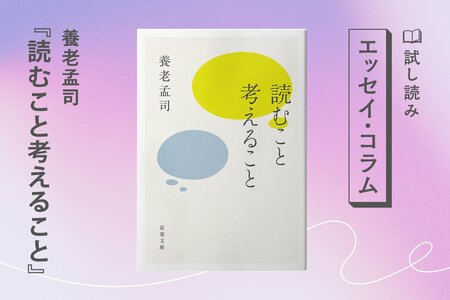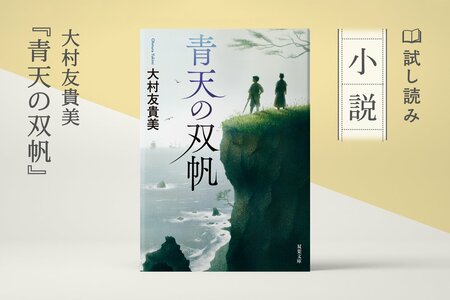4
友莉と食事をしながらも、時折、昼間会った隠善つくみの言葉や表情が脳裏によみがえってきた。愛おしいとか恋しいというのではないが、ああやって二人きりで面と向かってみれば、やはり彼女とは特別なつながりがあるような気がしてならなかった。さほど打ち解けたわけでもないし、つくみがよほどの親愛の情を示してきたわけでもない。
それでも彼女と一緒にいるとやけに気持ちが落ち着いた。げんに目の前の、幼馴染みで、付き合い出してからも十数年になる友莉と比べても、気の置けなさに遜色はない。
友莉は「清兵衛」に導入するフライヤーの話をえんえんと続けていた。
「いまのはもう十年以上も使ってるし、何とか買い替えには賛成してくれたんだけど、次もガスにしたいって言ってきかないの。身体のためにも電気にしようってお母さんも私も言ってるんだけど、なかなか首を縦に振らないのよ」
友莉の説明では、ガスよりも電気フライヤーの方が熱効率が高く、排熱も少ないのだという。「ガスだと熱効率は五割くらいで、残りの熱は全部あの狭い厨房にいっちゃうんだよ。揚げ物のときは冬だって汗だらだらなんだから」と言っていた。
友莉の父の板倉智司は二年前に心筋梗塞で一度倒れていた。友莉が、勤めていた信用金庫を退職して、長年、両親で切り盛りしてきた門前仲町の居酒屋「清兵衛」を手伝うようになったのはそのときからだ。「清兵衛」は門仲の駅を出て徒歩数分の場所にある繁盛店だった。
当時、遼平は二十九、友莉は二十六。そろそろ一緒になろうかと話していた矢先に智司が入院し、友莉もそれどころではなくなって、いつの間にか結婚の件は沙汰やみになってしまった。
遼平は、友莉が店のことをあれこれ喋るのを黙って聞きながら、お気に入りのレモンハイを飲んでいる時間が好きだった。
気立てのいい友莉は信金でも人気者で、退職するときは同僚たちからずいぶん惜しまれたらしいが、遼平の見るところ「清兵衛」で働くようになって肩の力がずいぶん抜け、自然体になった気がしていた。そういう点では、智司の発病は彼女にとってはもっけの幸いの面があったと思うし、そのことは友莉本人にも言ったことがあった。
友莉を見ながら、こいつとは長い付き合いだな、と思う。
家が隣同士で、母親たちがとびきりの仲良しだったから友莉とはきょうだい同然に育った。本当のきょうだいでもよかったが、幸か不幸か血のつながりがなかったため、男女としての仲に変化することになった。それが発展だったか後退だったかは、結局、結婚してみなければ答えは出ないと遼平は考えている。
ただ、幼い頃から彼女と夫婦になるのが当たり前だと思ってきたし、そのことに抵抗はなかった。友莉にしても気持ちは同じだったろう。
遼平が中学のときに母の満代が亡くなり、以降は、勤めに出ている父に代わって板倉の両親が弟の耕平ともども世話してくれた。おかげで、兄弟二人、多感な時期をさみしい思いもせずに通り抜けることができた。
耕平の方はいまやすっかり身を持ち崩しているが、それは母の死が原因でもないし、まして板倉の両親と折り合いが悪かったせいでもない。すべては彼自身の問題だった。
「清兵衛」から目と鼻の先にある炉端焼きの店で夕方から飲み食いし、十一時過ぎに外に出た。門仲の街を手を繋いでぶらぶら歩く。遼平の実家も友莉の家も変わらず木場にあった。首都高速9号深川線の塩浜入口の近くだが、いまは向かいに深川ギャザリアという巨大な複合施設ができていて、子供の頃には想像できなかったほどに開けている。
友莉はそこに両親と住んでいるが、遼平の家は空き家だった。
遼平が清澄に移って一人暮らしになっていた父の富士夫が、三年前の四月に上海郊外の工場へ赴任してしまったのだ。富士夫は自動車部品メーカーのエンジニアだった。
あぶない会社を渡り歩いているらしい弟の耕平はもとから実家には寄り付きもしない。
五月の夜風は生ぬるかった。酔いの回った身体には少しべたついて感じられる。永代通りへは戻らず、葛西橋通りを木場公園の方へと二人で歩いた。
今夜は公園の先にあるホテルイースト21東京に部屋を予約している。友莉が清澄に泊まることもあるが、たまにこのホテルを使うこともあった。
「この前、耕ちゃんが店に来たよ」
木場公園の南北をつなぐ木場公園大橋の下を歩いているとき、思い出したように友莉が言った。
「いつ?」
耕平とはかれこれ半年近く会っていなかった。
「一昨日の木曜日かな。看板直前に男の人と一緒に来て、すぐ帰っちゃったけど」
「何しに来たんだ?」
「分かんない。二人でビール三本空けて、エビフライ食べて、一時間くらいで出て行ったよ」
エビフライは子供の頃からの耕平の好物だった。
「何か話した?」
「別に。遼ちゃんとは会ってるのって訊いたら、全然って言ってた。よろしく伝えてくれって」
「ふーん」
呟くように言って、
「一緒にいた男って、どんなやつ?」
ふと気になって訊ねる。
「茶髪で背が高くって、めっちゃイケメンだった。歳は耕ちゃんくらいかな、たぶん」
長身で茶髪のイケメン――タケルに違いなかった。
しかし、タケルを連れて木曜日の晩になぜ耕平はわざわざ「清兵衛」に顔を出したのだろう? 看板間際といえば十二時近くだ。タケルは店を休んだのか。
彼とは連休明けに一度会っていた。
救世会病院の堀切理事長に夜中に呼び出され、その場で連絡させられたのだ。タケルは渋々、堀切理事長の住む三田のマンションにやってきた。入れ違いで遼平はさっさと退散したから、二言三言話しただけだったが。
ホテルの部屋に入ると、交代でシャワーを浴びてベッドに入った。
部屋は空調が効き過ぎて寒いくらいだったが、薄い毛布の下で素っ裸の身体を合わせているとみるまにあたたかくなってくる。遼平の股の間になめらかな友莉の太ももがすべりこんでくる。足がからまり、遼平は強い力で彼女を抱き寄せた。豊かな胸のふにゃりとした感触も心地よかった。
抱くのは半月ぶりくらいだ。前回、部屋に泊まっていったときは生理中でできなかった。
明かりを落とさずに、友莉を組み伏せる。
友莉は目を閉じて、小さな唇を半開きにしている。すでに感じ始めているようだった。
覆いかぶさり、感じやすい各部に舌を這わせ、あっあっという間欠的な喘ぎを耳にするうちに遼平はいつになく興奮してきた。
脳裏には昼間会った隠善つくみの顔が浮かんでいた。
腕立て伏せの要領で身体を浮かせて友莉の顔を見る。
くりっとした瞳と丸顔が特徴で、若い頃のキョンキョンに似ているとよく言われる。その見慣れた顔が次第に隠善つくみの顔とだぶってくる。小顔で首が長く、切れ長の目がいつもぼうっと霞んでいるつくみと友莉とでは似ても似つかないはずなのだが、それがだんだん一つに重なっていくのを不思議な心地で遼平は眺めていた。
下半身は激しく脈打ち、すでにはちきれんばかりになっていた。
右手を添えてぐいと分け入った瞬間、友莉の顔が消えていく。
終わると、友莉はすぐに静かな寝息を立てはじめた。しばらく腕枕していたが、寝返りを打って背中を向けたところで、遼平は起き上がり、ベッドから降りた。目が冴えてまったく眠くなかった。
シャツとパンツを着け、窓辺に行って、一人掛けのソファに座る。小さな窓の向こうはのっぺりとした闇で、明かりの一つも見えない。時間を確かめる。午前一時半を回ったところだった。
窓に映る自身の顔を見つめた。
それがさきほどのように隠善つくみの顔に変わっていくことはなかった。ただ、いかにも困った顔つきに、おいおいどうしたんだと声をかけたくなる。
何かがずっと頭に引っかかっている気がした。
一体、何だろう?
心の中でそう言葉にした瞬間、勢いよく幕が上がって、一つの光景が目の前にあらわれてきた。
そこは白壁の塀で囲まれた広い庭で、たくさんの木々が植えられていた。正門につづく道にはつつじやこぶし、庭の入口から東面の白壁にかけては数本の桜、北側にはさざんか、そして、庭の真ん中に一本の太いクスノキがすっくと立って四方に枝を広げていた。西の山を背にして、長い廊下と縁側を持った平屋の古い民家が建っている。
遼平はその民家の縁側に腰を下ろして中央のクスの巨木を見上げていた。
「おーい」
とクスが話しかけてくる。
空は真っ青な夏空で、遠く豊後水道の方角にはソフトクリームのような雲が浮いていた。
「りょうちゃーん」
クスが遼平を呼ぶ。
その声に向かって遼平は手を振った。強く振りたかったが力が籠もらず、肩のあたりまで腕を上げるのが精一杯だ。ひらひらと手を動かすだけで息苦しさが胸に迫ってくる。
背後では赤ん坊の泣き声が聞こえ、誰かがあやす声もうっすらと耳に届いていた。
泣いているのは生まれたばかりの耕平だった。そして、耕平をあやしているのはむろん母の満代だ。
ということは俺はまだ五歳くらいか……。
忘れていた記憶がだんだんによみがえってくる。
目を凝らすと、繁った葉々の隙間に人影が見える。白シャツ姿の小柄な男性が張り出した太い枝にちょこんと腰かけていた。ずいぶんと高いところだった。
そうだった。
目が覚めたように遼平は善弥さんのことを思い出した。
善弥さんは、よくクスノキに登って下界の景色を眺めていた。
彼は母方の実家で面倒を見ていた人だった。祖父が校長を務めた小学校の生徒で、幼児のときに鉄砲水で身寄りを失くしてからは近在の地主でもあった祖父の家に引き取られ、畑仕事などを手伝いながらずっと一緒に暮らしていた。
当時は、大人なのにまるで子供みたいな善弥さんが幼心にもちょっと不思議だった。ただ、その分、たまに帰省すると遼平たちといつも一緒に遊んでくれた。
その善弥さんには特技が二つあって、一つは動物を巧みに手なずけることで、もう一つが木登りだった。
善弥さんは祖父の家で飼っていた犬や猫の世話を一手に引き受けていた。口笛を吹いて、空を飛んでいる鳥を呼ぶことだってできた。
彼の動物好きはきっと重宝されたことだろうが、木登りの方はどうしてそんなことをするのか誰もよく分かっていなかったに違いない。遼平だっていまのいままで善弥さんがしょっちゅう木に登っていたことをすっかり忘れていたくらいなのだから。
遼平は長い縁側に座って日に当たっていた。ようやく床払いして、身体を起こせるようになったばかりだった。夏休みに入って大分にある母の実家に里帰りした。お盆の中日の夜からひどい熱が出て、二日目に往診を頼むと、診療所の先生に肺炎の疑いがあると言われた。山間の僻村とはいえ現在だったらドクターヘリでも飛ばすところだろうが、当時はのんきなものだった。毎日往診してもらっても、町の病院へ入院することはなかった。
そういうもろもろの話は、長じて母に聞かされたことで、遼平自身はほとんど記憶がない。さらに三日三晩高熱がつづき、先生もこのまま解熱しないようであれば市民病院に運びましょうと言っていたそうだ。生前の祖父母も、お盆休みで後乗りしてきた父も深刻に見える病状に気が気ではなかったという。
ところが医者がそう告げて帰った翌日、熱は嘘のように下がったのだった。
あの日――。
耕平が泣き止んでほどなく、母が、切りたてのすいかをお盆に載せて持ってきた。
それを見た善弥さんもクスノキから急いで降りてきて、一緒に縁側に座ってすいかを食べた。
「りょうちゃん、よかったなあ、元気になって」
彼はすいかを頬張りながら「これのおかげやねえ」と手にしたすいかを掲げてみせた。
その場面を遼平はいま、くっきりと脳裏に再現させていた。
たしかに数日前、熱にうかされていた遼平に、母が井戸で冷やしたすいかを持ってきて、そっとそのひとかけらを口に入れた。甘くて水っぽいすいかの汁をひと飲みしたとたん、全身にしがみついていた熱がすーっと発散されていくのを幼い遼平は感じた。その瞬間の感触もいま同時に思い出していた。
「このすいかは魔法のすいかや。どんどん食べりぃ」
善弥さんが言った。
彼は、そう言いながらぽろぽろぽろぽろ大粒の涙を流したのだった。
どうして善弥さんはあんなに泣いていたんだろう?
二十数年ぶりにあのときの光景をありありと想起して遼平は訝しく思う。
それほどに肺炎が重かったのだろうか。だから奇跡的に回復したことに、心のやさしい善弥さんは感極まって泣いてしまったのだろうか?
よく分からなかった。
小学校高学年の頃に、祖父母が相次いで亡くなり、中学で母の満代も死んで、大分の母の実家からはすっかり足が遠のいてしまった。社会人一年目のときに親戚から善弥さんが入院していると聞いた。ほどなく訃報も受け取ったが、血の繋がりのある人ではなかったし、父も遼平たちも葬儀には出向かなかった。
昼間の隠善つくみの言葉が引っかかっていたのは、彼女の木登りの話を受けて、木登り名人の善弥さんのことが意識の表面すれすれまで浮上していたからだろう。
祖父母の家は大分県の津久見市の山側にあった。東は豊後水道の豊かな海に接する風光明媚な土地だった。
つくみと津久見。
三週間以上も経って、ようやく二つの一致に遼平は思い至った。
この続きは、書籍にてお楽しみください