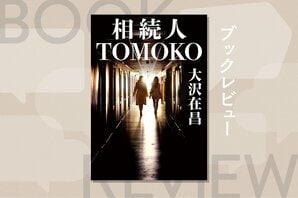ディスコで一時間ほど過ごすと、僕らは四人でそこを出た。沢辺の案内で、適度に暗く、上品で、とびきり高い、軽い食事を提供するナイトレストランへと向かった。彼女らは酒の飲み方も、軽いジョークの返し方も心得ていて、我々の知らないクラスメイトやクラブの先輩の話などで場をしらけさせることもなかった。わずかだけ背のびをして、それが僕や沢辺の目には「可愛い」と映ることも計算しているのだった。そして背のびをした分、興奮させられることを望んでいた。
それはゲームだった。沢辺も僕も、ゲームのルールは知りつくしていた。だから、二人の娘をメルセデスに乗せ、中央高速へと走らせた。
暗いうちにホテルにチェックインし、それぞれ暗黙の了解でできあがったカップルは、部屋の窓辺から、明けてゆく湖を眺めた。
僕と律子は、部屋のビールを飲みながら、黒から紺に、紺からブルーに、色を変えてゆく、空と湖の境い目を見つめていた。隣の部屋にいる、沢辺と裕美が何を飲んでいるか、あるいは飲んでいないかわからなかった。
魔法のようなものだった。演技でも自己演出でもなく、夜明けのその時間、二人は互いを愛しいと思っていた。
話しあい、飲み、抱きあった。
会話には、わずかばかりの虚栄心が溶けこんでいたが、嘘つき呼ばわりされるほど大げさなものではなかった。そして、虚栄心をとりさった残りには、真実があった。ほんの数時間前に知りあったばかりにもかかわらず、我々は、自分を隠さず、素直な気持を表現しあった。ただそれは、両方から一度に見えるものについてだけだった。互いの知らない、短い時間では理解しようのない問題については、会話はさりげなく巧妙にそらされた。
二本のビールが空になり、それが溜まっていた酔いと疲れを表面に押し出した。
湖面が正視できぬほど明るくなると、僕はブラインドをおろし、シャワールームに入った。
浴びている最中に、長い髪をクリップでまとめた律子が飛びこんできた。小麦色の肌にくっきりと残された白い水着の跡に、僕は嫉妬とみじめさを感じた。一度も海へ出かけなかった夏は初めてだったのだ。
僕は自分の肉体を醜いと感じ、それを気どられぬよう律子の体を抱きよせた。輝きのあるグリーンレッドのシャドウをひいた目が、期待に瞠かれていた。化粧も巧みで、それ以上に、きれいな娘だった。そのきれいさは、六本木では十人に一人を数えることができ、他の街では百人に一人になる。「合格点」の娘なのだ。一流のモデルにはなれないかもしれないが、そこらの二流タレントよりは、はるかにましだった。二人はジミーに感謝すべきだ、と僕は思った。相手に対し、失望せずにすむ魔法をかけてくれた。
シャワーの下で、二人はじゃれあい、抱きあった。濡れた体でバスルームを出ると、人工的な夜の部屋で、ゆっくりと楽しみの最高点へと向かった。
時間も規律も禁忌も、すべてない、その場だけ、その時間だけの幸福だった。
わずらわしい排卵日や避妊具についても気を使う必要はなかった。律子は自分が安全な女であることを、既に会話の中で表明していたのだ。
納得し、満足がいくまで互いを貪りあった。それは一転して、獰猛な行為だった。撫で、噛み、さすり、つかみ、唇を使い、吸い、ついばんだ。
爪をたて、喘ぎ、叫び、泣いた。
その時間が瞬く間に過ぎると、静かで優しい、静止が訪れた。
「素敵よ。愛してる」
律子は、うつぶせになった僕の肩に唇を押しつけて囁いた。それについてとやかくいうのは野暮だった。さらさらとした髪が肌に心地よく、気持が柔らぐ香りを彼女は放っていた。
そうして僕らは眠りに落ちた。
目が覚めると太陽は、西に低く移動していた。再び四人になり、遅い朝食を摂った。四人とも少し照れ臭く、そして疲れているようだった。
食事を終えると、僕らはホテルを出発した。彼女たちは、食事の最中から、時間を気にし、電話を捜していた。
暗くなる前に、六本木に帰りつき、そこで別れた。それだけだった。
「楽しかったわ」
二人は口々にいい、車を降りていった。
「またね」
とはいったが、電話番号も住所も、本名すら知らなかった。毎晩のように、あのディスコに現われているわけではないし、何といっても「良家の子女」という仮面は、彼女らの体からはがしようのないものなのだ。
「またな」
僕らはにこやかに手を振った。
二人きりになると、僕も沢辺も口をきく元気があまりなかった。沢辺は行きたいところがある、といい、僕は無言で頷いてメルセデスを降りた。
律子と裕美とは、おそらく二度と会わないだろう。だから「またな」といった。沢辺とは、これから幾度でも、一生でも、顔を合わせる。
だから別れの言葉は口にしなかった。軽く手を振っただけだ。
四谷の部屋は、二カ月つづいた忙しさのためほとんど掃除されておらず、ひどく散らかり無残なありさまだった。
ちらばった洋服やレコード、本を押しのけ、ソファに腰をおろすと、僕は何をなすべきか考えた。おかしいほどに何も浮かばなかった。
ヨーロッパに留学した恋人・悠紀は、留学期間を半年から一年にのばすという手紙をよこしていた。ありきたりのピアノ教師になる筈の女の子に、予想もしなかった機会が訪れたのだ。
僕は暗くなってゆく部屋で、その手紙をこれで何度目か読み返した。文章は、彼女の口調そのもので、文字を追うだけで、悠紀が語りかけてくるような気がした。そして、同じように、何度目か、彼女がつかんだ希望を祝福し、喜び、彼女の不在を寂しがり、それがこれ以上長びかぬことを願った。
午後八時を過ぎると再び空腹になり、僕は表に出た。ハンバーガーとビールを買いこみ、開いていたレコード屋と本屋で、それぞれ買い物をした。レコードは、ジュリー・ロンドンと松任谷由実で、前から欲しいと思っていたものだった。考古学の本は、ベッドサイドやビールの肴にもってこいの眠気を提供してくれる。
貸しビデオ屋は閉まっていた。明日の昼、まとめて映画のビデオを借りよう、と僕は思った。休暇は、あと五日残っていたが、何かをしようという気持はなかった。そういう自分をわずかに情なく思った。
都会の孤独は、都会に家族がいない者にしかわからない。窓辺の、お気に入りのチェアにかけ、ビールのプルトップを引いて呟いた。
ジュリー・ロンドンは暗すぎ、松任谷由実は、魔法が解けた今、あまりに寂しかった。
それでも松任谷由実をかけた。自己憐憫が甘かった。その甘い気持を楽しめるだけ、歳をとってきていることは、とうの昔にわかっていた。
窓の下方では、タイヤが音をたて、クラクションが鳴り、人々がざわめき、笑いと、ときおり叫びも聞こえた。その人たちをうらやましいとは思わなかったが、自分の方をすぐれているとも感じなかった。
真夜中に達する前に、僕は酔っていた。缶ビールたったふた缶でだ。レコードは、一枚の両面と二枚目のA面を聴いただけだった。僕はベッドに入った。
最後の曲は『ファッシネイション、魅惑のワルツ』だった。
2
四回目の『イージーライダー』のオープニングシーンを見ているとき、ドアがノックされた。ステッペンウルフのサウンドには熱気があった。この時代のロックは皆そうだ。
音がバラつき、場合によっては不協和音すら感じる。“雑”と表現すればいいのだろうか。だが、その熱気は、今のヘヴィメタルに比べれば、はるかにアツく、僕をのせてくれる。
録音技術の向上が原因なのだろうか。今のロックは僕にはクール過ぎる。サウンドのクライマックスに向けて、血がたぎらないのだ。十五年前には、確かにたぎった血が。
そう思いながらドアに歩み寄った。訪問販売員か集金人、そんな頭があった。朝からずっとテレビとデッキの前にすわりつづけていて、人と話す気分ではなかった。
三度目のノックが、錠を外す音で止んだ。
ドアを開けた。
ざっくりしたVネックのトレーナーにジーンズをはいた女が軽く息を弾ませて立っていた。かすかにハッカの匂いがした。
意志の強そうな顎と切れ長の瞳を、兄と共有している。髪は短くカットされていて、ことさら長くのばしウェーブをかけなくとも、自分が充分に女であることを知っていると宣言していた。事実その通りだった。
彼女は、これまでに僕が知りあった女性の中では群をぬいて魅力的な娘だ。会うのはこれが二度目、一度目は四年前の大晦日だった。
「――久しぶりだね」
僕はいった。まず驚き、それから狼狽した。僕はこの二日間、ヒゲを剃らず、髪もとかしていなかった。着ているものといえば、くたびれたコットンパンツに洗いざらしたトレーナーだ。
「あの……久しぶりです」
何かをいいかけ、織田羊子は、ぱっと微笑んだ。
「お邪魔じゃありませんでしたか? こんな突然で」
「『イージーライダー』特別試写会をやっている。観客の入りが悪くて、ピーター・フォンダがぶつぶついっているところさ」
「え?」
僕は苦笑した。四年前二十だった彼女が『イージーライダー』を知らなくても無理はない。
「映画の話さ、ビデオを見ていたんだ」
「まあ」
「どうしたの?」
いってから、彼女がただ通りがかったからといって、僕のアパートに立ち寄る身分ではないことを思い出した。四年前、彼女の書いたCMソングをめぐって殺人事件がおきた。直接は、彼女に関係のない殺人だった。シンガーソングライターとしての彼女は、その後ちゃくちゃくと人気を上昇させ、その翌年に出したデビューアルバム以来、六枚のLPをリリースしている。最新アルバムは、発売二週間でトップ20に入った。
「とりあえず、どうぞ」
僕は彼女を招じ入れた。沢辺は、自分のアキレスの踵が、突然、友人の部屋をひとりで訪ねたと聞いたらどんな顔をするだろうか。
腹ちがいとはいえ、この才能豊かな妹を彼は無闇に可愛がっている。といって、羊子は決してお嬢さんタイプではない。高校時代は暴走族にいたこともあると聞いていた。
「ひどくちらかっているよ。君の兄貴の部屋とは大ちがいだ」
彼女がソファにすわると、僕はいいわけがましくいった。
「あれは、お兄ちゃんが片づけているんじゃないわ。お兄ちゃんにこき使われている女の人たちよ」
四年間のブランクをまったく感じさせない話し方だった。決してなれなれしいというわけではない。彼女は、ごく自然に相手の内懐にとびこんでしまえる才能を持っていた。同じ才能を持つ兄貴は、それを専ら異性相手に活用しているが。
「何を飲む? コーヒー、紅茶、麦茶?」
最後のを聞いて、羊子は笑い出した。
「冷たい、麦茶?」
「そう。一度も海に行けなかったので、夏が終わったことが実感できないんだ」
「わかる、その気持。じゃあ私も麦茶」
麦茶だけではない。ビールも生がまだ数ダース残っている。とりあえずそれは寝かせておくことにして、グラスに麦茶を注いだ。洗い物だけは、数年前のボーナスで買った自動食器洗い機が果たしてくれる。
自分は飲みかけのコーヒーカップを手にして、向かいにかけた。彼女がその間に、素早く、部屋の様子を観察していた。
「あら」
レコードケースに手をのばした。
彼女の最新アルバムが端をのぞかせている。
大きな笑顔を僕に向けた。
「ありがとう」
「『キュート』って歌がB面のラストにあるだろ。すごく好きなんだ」
大切なものはキュートなあなた、歳をとるだけ、心がキュートになるあなたが好きよ。夜更けに、幾度も歌ってくれた。
「恥ずかしいけど、とても嬉しい」
「ただのファンさ。兄貴の方とは腐れ縁だけど」
羊子の笑みが消えた。瞳が考え深げに、麦茶のグラスを見つめた。
「どうしたの、何か心配事でも?」
「お兄ちゃん」
「沢辺がどうかしたのかい」
「何か聞いてません?」
「おとといの夕方まで一緒だったけど?」
「何時頃ですか?」
「五時過ぎ、六時までには別れてた。六本木で」
「何かいってました?」
「どこか寄っていくところがあるって」
「そう、か……」
「行方不明なのかい?」
羊子は、ちょっと唇を尖らせて肩をすくめた。肩をすくめる仕草は兄貴にそっくりだった。
この続きは、書籍にてお楽しみください