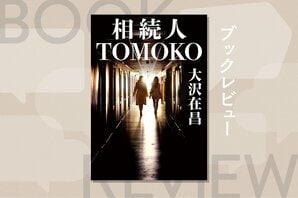「やれやれ、だな」
沢辺が呟いた。美紀子を家に送り届け、母親に簡単な注意を与えた僕が戻ってきたときだった。
「いつも、ああかい」
「何回か、その目で見たろう」
僕は助手席にすべりこむと、サイドウインドウを全開にした。美紀子がつけていた化粧品の強い香りが車内に残っている。
「ああ。だがな」
ステアリングホイールに手をかけたまま、首を振った。
「何か御不満かい。何だったら、青少年の犯罪を未然に防止した功績で感謝状でも交付するよう、警視総監にかけあうが」
「ろくなもんじゃねえ」
沢辺は顔をしかめた。
「だったらさっさと車を出せよ。僕らがここで思案したって何も変わりはないんだ」
沢辺は頷いた。だが、どこか心にひっかかっているような素振りだった。
「俺あ、それほど世間知らずじゃねえ。五番、センター」
そういって、沢辺はキューを突き出した。
バックスピンのかかった白い手球は五番に当たると、いい位置まで後退した。五番球は、ストン、とセンターポケットに落ち、虚ろな音をたてて転がっていった。
「人はそれぞれだ、ということもわかってる。だ、け、ど、な」
突いた。手球に押された六番がツークッションしてサイドポケットに落ちる。
「あれは、いってみりゃ、家庭の恥部だぜ。覗く方も覗かれる方も、いい気分のものじゃない」
タップの先にチョークをこすりつけた。左手の小指、薬指、中指がぴんと張ったきれいなブリッジを作る。そこにキュー先を通した。
「たまには刺激的なこともある」
僕はやんわりといった。
沢辺は手球から視線を上げた。
「その結果、何回、死にかけた?」
「二回」
「ほかに骨折や、歯を失くしたのは数えきれないだろう」
「刺激さ。単なる刺激」
「馬鹿だよ、それじゃ。七番サイド」
しくじった。七番はコーナーの角にあたり、その場で独楽のように回転した。沢辺は舌打ちした。コーデュロイパンツの前にかけた小さなエプロンで手をぬぐう。
終夜営業のビリヤード場『R』はひどく混んでいた。どこかに居たいのだ。アパートでも自宅でもない。どこかに居たいから、若者たちはやってくる。さして美人ではない女を連れ、突き方を教えてやるプレイボーイ気取りもいる。厚め薄めもろくにわからず、ただ交代で突きあうからっ下手もいる。ひと目見て、地方から出てきたとわかる二人連れの若者が、気どってくわえ煙草をしている――だがこれは従業員の注意ですぐにやめさせられた。
広い店内の隅のソファでは、古ぼけたオーバーを着こんだ老人がうずくまるように眠っている。いつもいて、酒臭く、陽に焼け、よごれた身なりをしている。右手の指が何本か欠け、たまに突いていると、かつてはひどくうまかったことがわかる。今は駄目だ。握力が落ち、震える指先で撞点が一定しない。
有線がオールディズを流している。マービン・ゲイ、ダイアナ・ロス、エスター・フィリップス。マービン・ゲイは実の父に射殺されるとも知らず、ダイアナ・ロスは、シュープリームスを率いて、ごついカツラを被っていた。
モータウンの熱気が、ここでは、汗と煙草と小さな喚声の中で拡散する。
「俺はお人好しなんだよ」
僕が手球でこすっただけで、ポケットへと消えた七番を見ながら沢辺はいった。
「そうさ。ターザンはいつだってお人好しだ。ジャングルで生き抜く術を心得ている。いざ格闘となれば、猛獣の息の根を止めるまで戦うことはやめない。なのに、どうしてかお人好しなのさ」
僕は突きつづけた。最後の九番をワンクッションでセンターポケットに落とす。センターは倍得点、これで僕の勝ちだ。白球が、反対側のセンターポケットすれすれではね返り、静かにテーブル中央で動きを止めた。
「お前にいわれるようじゃ終わりだな」
沢辺がいい捨ててかがみこんだ。九つのボールをすくい、ラックする。
僕は手球を拾い、セットした。
ブレイク。重い球を打った。散ったボールのひとつがサイドポケットに落ちる。二番――得点にはならない。
「お気の毒」
沢辺がいった。一番は、手球から見ると、ふたつのボールの背後に隠れている。クッションを使っても、当てるだけに終わりそうだ。修行不足、ということか。
沢辺がマッセを決め、一番をサイドに落とした。つづいて三番を反対側のサイドに。僕は得点を書いていった。
「お前が人助けしようと思ってやってるわけじゃないことは、わかってる。といって金だけなら、他にも道がある」
四番をセンターへ、うまく使って九番も落とした。拾い上げた九番をリセットする。おいしい得点だ。負ける、この勝負は沢辺のものだ。どのみち、大差はつかない。十四時間ぶっ通しでやって。二ゲームか、三ゲームの開きだった。
「好きなんだ。あってる」
「名探偵の才能か」
五番、六番と七番をたてつづけに決める。
「君もその気になれば、僕につづく名探偵になれる」
「嫌だね――見ろ、おかしなこというからしくじっちまった」
八番と九番が団子になった。手球の位置は悪くない。
「殺しなら殺しばっかり、ヤクならヤクばっかり、というのならわかる。だが、毎度、あんなセコくてやりきれんホームドラマを見せられるのは御免だよ」
「なるほど」
僕はタップにチョークを塗って頷いた。
「だけど失踪人てのは、大抵、家庭の事情が絡んでる。殺人や麻薬がひっかかってくるのは、わずかな可能性さ」
思いきって突いた。ふたつの球がサイドにはたきこまれる。勢いで手球までがつきあった。欲張ったのが失敗の原因だ。
「ホームドラマが嫌なら、やれんというわけか」
「好きなわけじゃない。見ても、見ないんだ。見てるふりをしてね」
「すれたな」
なにげないひと言が胸に刺さった。そうだ。確かにすれた。だがすれなければ、僕はどうなったのだ。
かつてそんな男に会った。一匹狼のもめごと処理屋。ホテル住まいで、事件のないときは、日がなバーでとぐろを巻いている。カウンターの端にすわり、隣のストゥールには、いつもバーバリーのコートを置く。人を寄せつけないためだ。そこで両切りの煙草を吸い、ウォッカを仇のように飲みつづけていた。
彼は一度、僕の命を救った。
失踪した少年を連れ帰ることで、自分の宝物を奪われたと思いこんだ女性が僕を撃った。彼女の心は、均衡を失い、奈落の方へすべりこんでいた。背中に弾丸を食らった僕は、救うものもないまま、一昼夜を彼女と過ごした。
激痛、出血、そしてとどめの一発が放たれようとしたとき、彼が僕を救った。今でもそのときのことを思うと、小さな笑窪が残る背中がむずむずする。
死にたくないと思い、願った。
それまで沢辺が予言していた。いつか、駆けおちした男女をひき離した罪で、狭いアパートの台所で刺されて、血まみれになり命を落とす――笑っていた。
あの事件の後、沢辺はいわなくなった。
今は僕がいっている。次は君の番だ。ふられた女が腹いせに、君を殺る――。
「どうした、飽きたのか」
沢辺が訊ねた。
「かもしれない。酒が飲みたくなった」
沢辺はにやりと笑った。
「トシなんだよ」
エプロンを外し、テーブルに投げた。ゴロワーズをテーブルからつかみあげ、火をつける。
「畜生」
さして感情のこもっていない言葉を、煙と共に吐き出した。
僕は沢辺を見た。ゆらりと巨体を動かして肩をすくめた。目は、グリーンのラシャをはったテーブルに向けられている。
「天に向かって唾するだな。自分でいって腹がたつ」
「帰るか?」
「帰る? 冗談じゃない。コウが帰りたいなら帰れ。俺は嫌だ。夜はまだ始まったばかりだぜ」
確かにそうだ。午前一時を回ったばかりだ。
「これからが佳境なんだ」
「いいさ。何をやらかす」
「久し振りにナンパといくか。こんな日がお誂えかもしれん。上玉はとっくに釣られたあとだろうが」
「とにかく、何かをしよう」
僕はいった。
「自分の体が休みに順応していないんだ。何か悪さをして、そいつを教えこまなきゃならない」
それも歳のせいなのだろう。口にしたくはないが、そう思った。切り換えが面倒になってきた。仕事で捜す若者と、自分が遊びの対象にするものは別だ、と割り切れなくなってきている。早い話、初対面でベッドに入る女の子の年齢が気になって仕方がない。
六本木に戻った。
会員制のディスコに入る。二人とも会員ではない。だが沢辺は顔をきかせられる。金でメンバーを買うほど、イモじゃない――そういった。
すたったと思っていた。そうでもなかった。結構、いける線が多い。季節感のない服装と、国籍の不明な客層がいり乱れている。
実際、最近の六本木は外国人が増えた。それもドル安、円高でぴいぴいしているマリーンの類ではない。ビジネスマンか、大使館員か、金の張る服装をして、クレジットとキャッシュの双方で財布をふくらましている手合いだ。兵隊に比べれば、はるかに洗練された雰囲気と日本語のボキャブラリィを持っている。
「いけ線は全部、奴らにナンパされているな」
ステージに近いブースに陣どると、僕は沢辺に囁いた。
「あぶれているのは、水商売とプロだけだ」
店では殺している自分の若さを、確認したい銀座ふうが数人、そして化粧と服装のタイプではっきり売春婦とわかる女たちが、隅の席を占領している。
「まあ、見てろ」
沢辺はいうと、指を鳴らした。
「ジミー、ジミー!」
スティクスに合わせて、フロアで踊っていた白人が振り返った。ほっそりとしていて、白い麻のシャツにぴったりとした皮のパンツをはいている。金髪のサイドを刈り上げ、中央の部分を長く額に垂らしていた。
うっすらとアイシャドウを塗った瞳が輝いた。
「サ・ワーベ!」
十八、九か。端整なマスクをしている。
白人の少年はフロアを駆け降りてきた。小猫のように沢辺の膝にじゃれつく。
「サ・ワーベ、寂しかったよ。久しぶりだもん、ボク、何回か電話した。サ・ワーベ、いなかった」
「わかった、わかった。おい、こら離れろよ」
沢辺は少年の体を離した。パコランパンの香りが漂った。
「こいつは、俺の友達でコウだ。佐久間公」
ジミーは微笑して細い腕をのばした。僕の頬をすっと撫で上げる。〝女子大生〟が見たら地団駄を踏むほど、色っぽい流し目をくれた。
「よろしく、ミスターコウ。グッドフィーリングだよ」
「お前は、ジミーの眼鏡にかなったんだ」
沢辺のバルキーのセーターに金髪をこすりつけるジミーを見おろしながら、沢辺はおかしそうにいった。
「ジミー、俺たちは今、ここに来たばかりで、誰とも待ちあわせていないんだ。わかるだろ」
「オーケイ」
ぴょんと、少年は立ち上がった。
「グッガールね、ジョシダイセーオアモデル、どっちがいい?」
「どっちでもいい。楽しい子なら」
「マカセナサイ!」
ジミーは薄い胸をはった。フロアの踊りの列にとびこんでいく。その後を追うように、グリーンのレーザーが走った。
「奴は、コールボーイなのさ。男にでも女にでも売る。値は一晩二十万かな。副業がモデルだ。あと二年稼いだらパリに行ってヘアカットの勉強をするそうだ」
「君が最近、そちらにも御発展とは知らなかった」
僕はわざとらしく尻をもじもじさせていった。
「勘弁しろよ、そんなのじゃねえ。ちょいとわけありで手なずけてあるんだ」
五分と待たないうちに、ジミーが踊りの列をかき分けて現われた。両手を、二人の女の子の腰に回している。
一人はニットのミニのワンピース、もうひとりが濃いオレンジのブラウスに茶のスカートをはいている。どちらも背が高い。パンプスの踵を差しひいても百六十二、三はある。
「サ・ワーベ、友だち連れてきたよ」
ジミーが片目をつぶって見せた。
ミニを指し、
「彼女がリッキー」
ブラウスとスカートを、
「ユウ」
と紹介する。
正確には、律子と裕美だった。二人は、同じ女子大の二年だといった。
「サ・ワーベ。最高のプレイボーイ、ナイスイブニング、ナイスモーニングね」
「嫌だ、ジミーったら」
律子が手慣れた感じでかえした。沢辺がニヤッと笑う。
「サ・ワーベ、リッチだけどジェントルマンだよ。楽しむといい」
「ありがとう、ジミー」
先に礼をいったのは娘たちの方だった。これには沢辺も僕も苦笑した。どうやら、どっちが釣り上げられたかわからないようだ。
緒戦でジャブの応酬がつづいた。どうやらふたりとも、シンデレラタイムを気にする必要はないようだった。そこそこ遊びなれ、頭も回る。高校時代からレッスンを積んできているのだ。
今ではこういうタイプの女の子があたり前になった。異性とのつきあいを親に知られ、問い詰められるのは〝ドジでダサい〟ことになる。うまく親の視線をかわして、進学か、社会に出てさえしまえば「不良」だの「非行」という言葉からは縁遠くなる。
彼女らは、下らない男にひっかかって売春を強要されるほど愚かでもなく、危険と知って麻薬に手を出すほど大胆でもない。そんな真似をしなくとも、人生にはいくらでも楽しむ要素があることを知っているのだ。
そういった意味では、賢い女子大生なのである。
「追跡者の血統 〈新装版〉 失踪人調査人・佐久間公 4」は全4回で連日公開予定