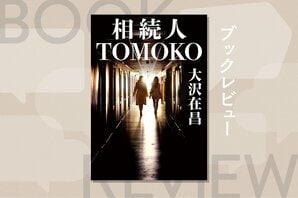沢辺を見送ると、僕は階段を昇った。ビルは明るい新築で、一階にはウインドウだけに灯りを点したブティックが、三階から上には酒場が入っている。
喫茶室に入ると、入口に近いボックスにかけ、アイスコーヒーを頼んだ。もはやアイスコーヒーは季節の飲み物ではない。
二人は、奥のボックスに並んで、入口の方を見るようにしてすわっていた。灯りのもとでは、彼女の若さがますますはっきりする。
十六という実際の年齢より、むしろ若く見えるほどだ。
男の方は、顔色は悪いが背が高く、なかなかの男前だ。甘い顔つきで、アイドルタレントに似ているが、どこか暗い狡猾な翳がある。
喫茶室の中央に、箱型の電話ボックスがある。男は、不釣り合いに豪華な腕時計を覗いて立ちあがった。
女の子を残し、電話ボックスに入った。
硬貨を落とし、ダイヤルを回す。レジの横におかれた、喫茶室の着信用の電話が鳴った。受話器を取ったウエイターが叫んだ。
「山田さん、いらっしゃいますか? 山田さん――」
僕の斜め向かいにすわっていた四十がらみのスーツの男が立ち上がった。眼鏡をかけありきたりのサラリーマンといったいでたちだ。テーブルの上のコーヒーカップには手をつけた様子はない。
男はわずかに緊張した様子で、レジの電話を取った。耳を傾ける。
男の目が奥のボックスの、少女の方角に注がれた。
ありふれた、素人臭い手口だ。カウチンセーターの若者が、組織には属さず、小遣い稼ぎにやっていることがわかる。
店の外側で、特徴のあるフォンが短く二度なった。スタンバイしたという合図だ。
僕は煙草をくわえ、微笑した。メルセデス500SELに乗った調査員。
カウチンセーターがボックスを出た。そのまま、わき目もふらず店を出てゆく。
レジの電話を置いた男が、奥のボックスに歩みよった。女の子にふた言み言話しかけると、自分の分と併せて二枚の伝票を手にした。
僕は素早く立ち上がった。男より先に、料金を払い、表に出る。
沢辺がメルセデスを降りて立っていた。芋洗坂の下の方に目を向けている。
僕はその方角を目で追った。カウチンセーターの姿はない。六本木交差点の方角に向かったようだ。ゲームセンターかどこかで時間を潰す気なのだろう。
「どっちに行った?」
訊いてみた。
「え?」
沢辺が訊き返す。珍しいことだった。仕事でなくとも、目のやり場を心得ている男なのだ。
「カウチンセーターの奴さ」
「すまない、気がつかなかった。ちょいと知りあいに似たのがいたんでな」
僕が出てきたビルを、顎で指した。
「なんだ、どこのホステスだ?」
「女じゃねえ、男さ」
話していると、少女とスーツの男が階段を降りてきた。
僕は彼らに向き直った。
「下居美紀子さん?」
少女が立ちどまり、スーツの男が驚いたように僕を見た。
肯定はしなかった。化粧の濃い、しかもそれゆえでなく表情の乏しい顔を僕に向けた。
「下居美紀子さんでしょ」
少女は黙って頷いた。
「君、何の用だ?」
迷っていたらしいスーツの男が、居丈高にいった。僕は彼に向き直った。
明るい紺のスーツに、オレンジと青のタイ、決して金持ちには見えない。“普通”の男だ。
「彼女の年齢を御存知ですか?」
眼鏡の奥に狼狽の色が走った。
「未成年者との――」
「待ってくれ、人ちがいじゃないのか?」
「人ちがい?」
僕はゆっくりいって、男の顔を見つめた。
「何なんだ。これはいったい……」
男は気弱く呟いた。
「僕は法律事務所の失踪人調査士で、彼女は家出中の高校生です。あなたは、それを御存知の上で、彼女と――」
「ちょ、ちょっと待ってくれ。私は関係ない、関係ないよ」
男はいって後退りした。
「関係ないからね」
くるりと背を向けて、足早に歩き出す。少女はうつむいたまま、何もいわなかった。
「いいのか?」
沢辺が低い声で訊ねた。
「放っておこう」
僕はいって少女を見た。
「御両親に頼まれて、君を捜していたんだ」
「嘘」
下居美紀子が小さくいった。
「嘘をいっても仕方がない、ほら」
僕はガードレールに腰かけ、ブルゾンの内側から出した身分証を見せた。マネキンの着るファーコートを照らす灯りが、文字を浮かびあがらせた。
美紀子は無言でそれを見つめた。
「いつまでも、こんなことをしているわけにはいかないだろう。ガタガタになっちゃうぜ」
美紀子は答えなかった。
「一度、帰ってみたら。心配はしてるけど、があがあはいわないさ」
「死んじまえばいいのに」
「前からそう思ってた?」
唇をかんだ。年齢にはあわない、濃いピンクだった。厚塗りのファンデーションが粉を吹いたようになっている。
ケニー・ロギンスのサウンドが大きく聞こえた。窓を全開にして、カーステレオを鳴らす阿呆が芋洗坂を降りてきたのだ。
「ミキ! ミキじゃねえか。何やってんだよ。そんなところでよ」
背中から声がかかり、振り向いた。黒塗りのRSターボの運転席から、カウチンセーターの若者が腕と首をのぞかせていた。どうやら交差点にでかけたのは、車を取りにいくためだったようだ。
「どうしたんだよ!?」
何もいわない美紀子に男は畳みかけた。後ろについたタクシーがクラクションを鳴らし、男は振り返って怒鳴った。
「うるせえな、このタコ! ちょっと待ってろよ」
沢辺が苦笑を含んだ目で僕を見た。
「どうする? あいつにつきあってまた客を取らされるのかい?」
「何だよ、お前ら」
僕と沢辺を警官ではない、と見てとったのだろう。
タクシーがクラクションを鳴らした。
「わかったよ、待ってろよ」
RSターボを乱暴に二重駐車して、若者は降りたった。ガードレールを大きくまたぐ。
「お手並み拝見だな」
沢辺はにやつきながら囁いた。
若者は精一杯つっぱっていた。僕と美紀子との間に割りこみ、胸をそらした。
「どうしたんだ、ミキ。何かされたのか……」
若者は、美紀子が黙っていると、僕に向き直った。
「ナンパもよう、相手見てしてくれよ。なあ、おい」
「ナンパじゃない」
僕はいった。
「何だよ、じゃあ」
若者の口調が低くなった。
「管理売春罪って知ってるか?」
顔色が変わった。身を翻して、ガードレールを飛びこえようとした。僕は、カウチンセーターのその背をつかまえた。アスファルトの上にひきずり倒す。
通行人が数人、驚いて立ち止まった。
「何すんだよ」
素早く、顎に膝蹴りをくらわせた。一発で止め、襟首をつかんでひきずり起こした。
「俺は何もしちゃいねえよ」
「騒ぐな! 本物の警官が来るぞ」
髪をつかんで囁いた。
「なんだって」
「こっちは、法律事務所の調査員だ。彼女の親に頼まれて、捜していたんだよ」
「じゃ――」
「このままポリボックスに行くか。マエがあるんだろ」
「何いってやがんだよ、俺は関係ねえ。ただの友だちだよ」
「笑わせるな」
「本当だ、なあミキ」
これを待っていたのだ。美紀子は張り手をくらったように顔を上げた。黙って男を見つめる。
「な、そうだよな、ミキよ」
今度は懇願するような口調になっていた。
「……うん」
「それ、見ろよ」
男は勝ち誇ったようにいって、僕の腕をふりほどいた。
「そうか、ただの友だちなら、彼女を家に連れ帰っても構わないな」
僕は男の目を見つめて静かにいった。
「そりゃ、ミキの……ミキが決めることだよ」
男は口ごもった。
「彼女は高校生なんだよ」
男は黙っていた。僕は彼女の肩をぽんと叩いた。
「よし行こう」
沢辺が無言でメルセデスのドアを開いた。それを見て、男が目を丸くした。
「あんたら、法律事務所の人間って――」
「そうだ。それが、お前に何か関係あるのか」
僕は男にいった。男は首を振った。おびえた表情になっていた。
美紀子は無言でリアシートに乗りこんだ。僕が隣にすべりこむ。
沢辺が運転席にすわって、ルームミラーから僕を見た。
「西品川だ」
軽く頷くとイグニションキィを回した。
振り返った。カウチンセーターの若い男の姿はなかった。RSターボも置き去りだった。六本木の雑踏の中に姿を消したのだ。
渋滞をくぐりぬけ、六本木を出ると、僕は腕時計をのぞいた。午後十一時を過ぎていた。街は、これから混み始める。
下居美紀子が低い声で泣き出した。
「追跡者の血統 〈新装版〉 失踪人調査人・佐久間公 4」は全4回で連日公開予定