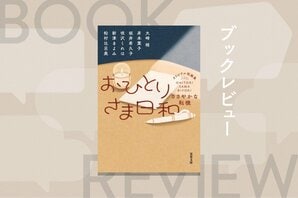「あの犬の写真、ほんとうなの?」
庭や室内でのアンジェの様子を母にLINEしたところ、既読になってすぐ電話がかかってきた。
「母さんも知らなかった?」
「ぜんぜん、まったく。レンタル番犬って仕組みも初めて聞いたわ」
「おれもだよ。犬がいるから留守番役が必要だったらしい」
「伯父さん、番犬が必要なほど弱ってるわけじゃないわよね? でなければ近所で凶悪事件が多発しているとか」
「ちがうよ。むしろ生き生きとして元気になっていた」
母親はひとしきり、「なんなのかしらねえ」「信じられないわ」と言ったあと、「伯父さんが元気ならいいわ」と納得する。
「母さんも見に行ってくれば。家の中も犬に合わせてリフォームしてて、すごく変わっていたよ」
「行きたい気持ちは山々だけど、時間が取れないのよ。伯父さんの入院にも付き添った方がいいんだけど、それを言いかけたらタクシーを使うから大丈夫と言われたの。申し訳ないけど甘えることにしたわ」
母親は看護師の資格を持っていて、今は友人の立ち上げた学童保育の施設で働いている。発達障害のある子どもを受け入れているので人手が常に足りないらしい。いつも忙しくしている。
伯父の入院日は訪問の翌週だった。アパートの冷蔵庫を整理して、着替えを選んでリュックに詰めて、ささやかな準備を進めた。当日は九時までに来てほしいと言われ、それくらいの時間に到着すると、アンジェが散歩から帰ったところだった。
マキタのスタッフが足を洗って室内に入れる。今日は年配の男性ひとりだ。玄関先で伯父と話を始める。今日からですね、手術よりもアンジェが気になって、しっかりお世話いたします、そんなやりとりが聞こえた。
男性はトレーニングウェアに身を包み颯爽としているが、六十は超えていそうだ。マキタの社員なのか、非正規か。散歩だけのアルバイトか。ついそんなことまで考えてしまう。里志に気付き、「おはようございます」と快活に声をかけてくれる。里志も笑顔を返した。
その後、アンジェに朝のフードを食べさせると、伯父は愛犬とのしばしの別れを長々と惜しんだ。到着したタクシーのクラクションでようやく腰を上げる。里志とアンジェは道路まで降りて見送った。
玄関ドアを閉めてもアンジェの態度は変わらず、大人しくリビングに移動してくれた。暴君に変身することはなく里志が促すとケージに収まる。
アンジェの一日はだいたい七時頃起床して、八時から九時までの間に散歩。九時から朝ご飯を食べて、その後はフリータイム。十七時から十八時まで散歩、十九時から夕飯、二十二時頃に就寝だそうだ。週一の割合で、トレーニングデイが設けられているので運動不足の心配はないと言われた。
要するに散歩から散歩までの日中は何もしていない。することと言えば昼寝くらい。室内犬の飼い方を検索してみたところ、だいたいがそんなものらしい。散歩してご飯を食べて寝る。気楽な身の上だ。
羨ましいと思いながら、いつの間にかソファーに寝そべってうとうとしていた。アンジェを見るとケージの中でじっとしている。寝ているらしい。自分も犬と変わらない。そう思うと同時に身体が起きる。
眠気覚ましに伸びをしているとアンジェの首が持ち上がった。少しくらい相手をしてやろうか。何事にもコミュニケーションは必要だろう。ケージの扉を開けて外に出るよう促したがそっぽを向かれた。カーテンや窓を開けて庭で遊ぼうと誘っても無視する。
「おい。気を遣ってやってるんだぞ。おまえも付き合えよ」
語気を強めてみたものの、なんの変化もない。灰色の毛並みは静かに上下するだけだ。
夕方の散歩にやってきたのは女性のスタッフで、顔を合わせたのは二度目だった。何かお困りごとはと問われ、アンジェの話をすると笑われた。庭への誘いだけでなく、玩具をちらつかせたり、ボールを転がしたりしても無反応を貫かれ、ケージの扉を開けたまま二階に上がるといつの間にかアンジェはリビングに出てきた。気がついて階下に降りていくと、あからさまに避ける。吹き出しがあったら入る文字は「かまうな」だったにちがいない。
「たしかにアンジェは喜怒哀楽はあまり出さず、どちらかというと沈着冷静ですね。でも、柔軟性は備わっているのでちゃんと臨機応変に動けます。だから甥御さんの留守番でも大丈夫と、こちらも了解したんですよ」
里志は思わず聞き返した。
「甥だとまずかったんですか。ふつうは同居家族がいるから、その人たちに任せるということですか」
「いいえ、二、三週間の不在でしたら、訓練センターで預かることも可能なので」
初耳だった。電話では、どうしても留守番役が必要というニュアンスで伯父は話していた。
「預けることができたんですか。ならそうすればいいのに。なんでわざわざおれを呼んだのか」
「すみません。変な言い方をしてしまったのかもしれません。入院の間もアンジェには変わらず家にいてほしいというのが波多野さんの希望でした。でもひとり暮らしですし、ときどき誰かが来てくれるだけではやはり犬がかわいそうです。そう思っていたところ、甥御さんが泊まり込んでくださると。波多野さん、とっても喜んでらっしゃいました」
訓練センターではなく家にいてほしい。伯父ならばたしかに言いそうだ。なにしろ猫かわいがり(犬かわいがり?)をしてるので。
「伯父さん、子どもみたいだな」
「私たちからすると大変喜ばしいです。それだけ愛情も愛着も持ってくださっている、ってことでしょう?」
楽しげに白い歯をのぞかせる彼女は伯父と同じタイプの人間らしい。犬好きの犬派、犬かわいがり。
散歩や夜の食事が終わればもうすることはない。検索によれば飼い主とのふれあいタイムが就寝前にあるようだがアンジェは望まないだろう。だったら早くケージに入ってくれればいいものを、夕食後はそわそわと落ち着かない。
廊下を行ったり来たりして、玄関のたたきに降りてドアを開けるようせがむ。里志が首を横に振るとドアに前足をかけてガリガリ爪を立てる。叱りつけると何度か吠えて渋々リビングに戻る。カーテンの隙間からじっと外を見つめ、和室に入ってふんふん鼻を鳴らす。
さすがに気付かずにいられない。
「おまえ、伯父さんを待っているのか」
つぶらな瞳が「そうだ」と訴える。
「入院なんてわからないもんな」
どう言っていいのかわからず歩み寄って傍らに膝を突く。アンジェは逃げずにじっとしている。その身体に里志は手のひらをあてがった。温かな体温を感じる。心臓の拍動も伝わる。
「伯父さん、しばらく帰らないんだ。ちょっと長いよ。二、三週間らしい。でも大丈夫。悪くなっている膝を治すための入院だ。元気になって戻ってくるよ。それまでいい子でおれと待っていよう」
腕を伸ばしそっとハグした。アンジェは嫌がらずにいてくれる。それどころか鼻を鳴らしてうなだれた。初めて見る弱気な姿だ。帰ってこない伯父を思い、不安でもあり、寂しくもあるのだろう。
なんだよおまえ、可愛いじゃないか。
いかつい容姿をしているのに健気でまっすぐ。
しばらく撫でたりトントンしたあと、スマホを持ってきて掛け布団に鼻面を押し当てるアンジェを撮影した。伯父のLINEに送る。明日の手術の励みになるにちがいない。すぐに既読になり、興奮した言葉やスタンプが返ってきた。
「だよね、これは効くよね」
ギャップ萌えというやつか。夢中になる気持ちが少しだけわかった。
この続きは、書籍にてお楽しみください