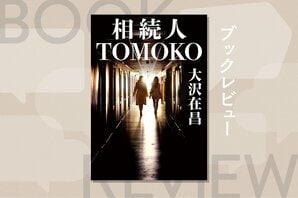わかっているのは名前と年齢だけだった。“伊丹愛子──二十八歳”写真も無く、旧住所もわからない。名前と年齢、全く手がかりにはならない。偽名という大袈裟なものじゃなくて、遊びには遊びの名を使う連中が多いのだ。
十一年前、“伊丹愛子”という名で遊んでいた“元少女”。半年間だけ、童貞で、煙草も酒も覚えたての、十五のガキとつきあったズベ公。
──“ゴールデン・ゲイト”って店知ってるか?
斎藤はそう訊ねたものだ。
──昔、本牧にあった店さ。今は“レッド・スケルトン”て店に変わっちまってる。
──ディスコかい?
──そうよ。嫌いかい、ああいうの。
──チーク・タイムにスタイリスティックスがかからなくなってからは行かないな。
僕がそういうと斎藤はあの笑みを見せた。
──マービン・ゲイはどうだい。
──ダイアナ・ロス抜きなら、何とかってところだな。
──もっと、もっと昔の頃さ、俺が“ゴールデン・ゲイト”に通っていたのは。
むかし、昔、大昔のことに違いない。今をときめく暴走族“クール・ライダース”のアタマが鼻たれ小僧の頃の話だ。
ボトル一本程度で見合う仕事だった。見つからぬ方に僕がボトルを一本賭けてもいい。ボトル一本程度の成功報酬なら見つからなくとも失望は少なくてすむ。
──何で会いたいか知りたくないか。
──無性に、ただ会いたいのだろう。
──違うのさ。こいつを見せたいのさ。昔、約束したんだ。真っ赤なアメ車でドライブに連れていってやるって……。
そういって斎藤は笑った。自分を笑ったに違いない。彼にしか、彼を笑うことはできない。曲がりなりにも彼は約束のものを手に入れているのだ。彼がその約束を果たす気になったとしても、誰も彼を笑うことはできない。
“レッド・スケルトン”は元町から車を約十分走らせたところにあった。横浜のディスコにありがちな、周囲を変哲のない商店街でかこまれた店構えで、そこだけイルミネーションが輝き、何台もの車が縦列駐車をしている。僕は自分の車をフェアレディZとマッハワンの間に駐めた。
午前二時半。斎藤と別れた後、すぐに車を飛ばしてやってきたのだ。連休を控えたディスコが馬鹿込みでそんな中で二十八の「おばさん」が見つかるわけがないことも知っていた。ただ、店の雰囲気を知っておきたかったのだ。ディスコの入場料をいくら高くとったとしても“サムタイム”のニューボトルの値段を上回ることはあるまい。そう勝手に決めて、僕は入ってみることにしたのだ。
理由はもうひとつあった。
──信田って野郎があの頃、“ゴールデン・ゲイト”にいたよ。マネージャーか何かだった。愛子はあそこの常連らしく、信田とは親しかったようだ。そうだ、愛子があそこで金を払うのを俺は見たことがなかったっけ……。
ディスコの店員は流れ者が多い。ただ、マネージャー・クラスになると、簡単には店を移らないものだ。たとえ経営者が変わっても、そこに居残る場合もある。
十一年も前の話だ。考えようによっては、馬鹿げた手がかりだった。だが手がかりらしいのはそれだけだ。さっきも述べたように本人の名前と年など当てにならない場合が多いのだ。
僕が勤める法律事務所の仕事はほとんどが、依頼人は失踪者の肉親である。従って、失踪者の写真や肉体的特徴は確実にこちらの手に入る。失踪時から、あまり時間の経過も無い。つまりそれだけやり易いわけだ。今回の場合はそうでないだけに唯一の期待は、その、ミスター信田の記憶だったのだ。
黒っぽいアクリル樹脂の扉を押すと、そこがクロークとキャッシャーだった。髪が長くて若い男と、これも若い女が、奥に坐っていた。上半身は店名を染め抜いたトレーナーだ。多分下はジーパンだろう。
“サンタ・エスメラルダ”のボーカルに負けずに若い男が怒鳴った。
「……ぜんえん」
「え?」
「三千円です。お一人ですか」
「そう」金を払うと、クロークの女が番号札をよこした。あずけるものは何もないのだ。
「いや、いらない」
僕は番号札を返していった。『朝日の当たる家』はもと歌の方が好きだ。「アニマルズ」──解散している。
「信田さんいらっしゃる」
「え?……」
女の子は訊き返した。鼻も目も丸くて、開けた口もまん丸だった。
「の・ぶ・た・さん」
そういいながら、野豚に聞こえはしまいかと思った。無論、彼女が知らなければ、である。
「店長ですか」
即座に彼女は返事をした。十一年間は、信田氏にも出世のチャンスを与えたわけだ。
「他にいないのだろ、信田さんは」
「ええ……」
つまらなさそうに女の子は頷いた。
「今、ちょっと出てますが、もうじき戻ります」
腕時計をのぞいていった。
「三時には帰るといって出ましたから……」
「有難う」
そういって席につき、踊っている連中を見ながら水割りを飲むことにした。
三時になり、四時になっても店長、信田氏は現われなかった。クロークの女の子は僕にすまながったが仕方がない。どこに行ったのかはわかりません、ええ、電話があったもので。店長が戻らなくても店の方は一向に構わないようだった。四時半になると、DJは喋りつかれたのか、スロー・バラードしかかけなくなった。ステージに立つのは仕上げをお互いで焦っている、にわかカップルだけになり、ボックスは酔っぱらいと、仕上がったカップルと、誰とも仕上がらなかった連中で埋まった。
僕は立ち上がり、カウンターに坐ってさっきから熱いマナザシをくれていたお姐ちゃんに手を振った。
信田氏は現われず、二十八歳ぐらいの年増女も客には居らず、DJは切ったマイクの向こうでアクビをしている。今夜は空振りだった。
クロークの娘にちょいと頷いてドアを押すと、店の外に出た。
駐車された車の数は減り、今や、僕の車は白のマーキュリーの隣にへばりついている有様だった。マーキュリーは室内灯を点けたままである。まさか、ホテルまで待てないカップルがいるわけでもあるまい。そう思って中をのぞいた。男が一人助手席でのびている。僕はもっと顔をよせて、のぞきこんだ。スリーピースのジャケットがはだけ、ネームを読むことができる。ネームは漢字で「信田」と書かれていた。
信田氏は飲みすぎて酔いつぶれているわけじゃなかった。ベッドまで待てなかったのは、胸に穴があいていたからだ。ヴェストの左胸に黒い焦げで縁どられた穴が三つあった。
信田氏からはもう何も訊き出せない。僕は店の入口に戻ると一一〇番をした。
この続きは、書籍にてお楽しみください