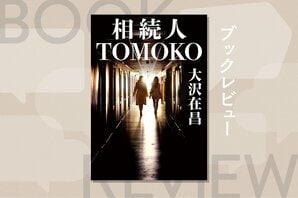爆音が轟き、排気管が震える。何十ものヘッドライトが放つ光芒が目を貫き、頭の芯をしびれさせる。
寒い。じっと立っていられない。ランチコートの前で腕を組み、足踏みをする。
何人いるのだろう。いや何台か。バイクが二十台はいる。車が十五、六台。一台をのぞく、そのすべてが僕の方に車首を向けている。佐久間公オン・ステージというわけだ。たった一台がその前に横腹を見せてとまっている。トランザム──真っ赤なトランザムだ。
ブーツにスリムのジーンズ、スウェードのハーフ・コートを着た奴が車体に背中をあずけ僕を見ている。ハンサムじゃないがいい男だ。ひきしまった浅黒い顔に髭がよく似合う。
スポーツ選手──バンタム級のボクサーのような体つき。ただし、顔はちがう。ボクサーにしてはどこも壊れていない。
僕の背後にとまっていたうちの一台がライトをアップにしたお陰で、左耳から頬にかけて白っぽい傷跡があるのがわかった。目が一瞬まぶしそうに細められ、神経質そうな口元がゆがんだ。今のは、間違いです、というようにライトがすぐ消えるや、その顔の陰に再び目も傷跡も沈んだ。
やんでいた風が再び、強烈に僕の耳をひっぱった。痛いなんてものじゃない。言葉を吐こうと口を開くと、ガサガサに乾いた唇から煙草をもぎとっていった。海から来て、海に帰る風だ。オホーツクの寒気団の尖兵かもしれない。生臭く、海の風だと、すぐ知れる。
埠頭まで五百メートルと離れていない。海面も船も見えないが僕にはわかる。煙草がアスファルトに叩きつけられ、火の粉をぱあっと散らすと転がっていった。飛んだ火の粉が、男のブーツまで辿りつけずに、風の中で消えた。
「海の風だ、冷たいよ」
トランザムから背中を起こしていった。その瞬間、わめいていた幾つものエンジンが唸るのをやめた。ガソリンを節約することにしたようだ。
「だったら早く話をしようか。タレントじゃないけど、体が元手なんだ」
僕はいい返した。キザにこようというなら、受けて立とう。お互いのボキャブラリィが尽きたとき、勝負が決まる。
「捜して欲しいんだ」
口髭のお兄ちゃんはいった。彼のことを、僕をとり囲む連中は、アタマという。最近は「支部長」なんて言い方はすたったようだ。
「女かい」
いった途端、クシャミが出た。僕の負けだ。ハードボイルド・ガイとはまさに君のことさ。
「女だ。年は二十八」アタマはいって、“ニヤリ”と笑って見せた。得意の笑みに違いない。年下をビビらすのと、女を転がすには、うってつけの笑いだ。前者は人けの無い駐車場、後者はディスコのチークタイムがよく似合う。
「恋人かい、姉さんかい」
二十八より彼が若いことは確かだ。答えなかった。半歩踏み出すと僕の顔をじっと見つめた。真剣な顔付きだ。怒ってるのだか、悲しんでいるのだか、わからないような表情だ。
「ついてきてくれ」
そういい捨てて、トランザムに乗りこんだ。僕は黙って後退りすると、自分の車の屋根に手をかけて中をのぞきこんだ。オイルの匂いがした。あのガキが車内にふんぞりかえっている。ジーンのジャケットの下はアロハという季節を間違えたような格好だ。ハンドルに手をかけ、軽蔑しきったような顔付きをしている。僕の車はエンジンも車高もいじくっていない、普通の国産だ。それが彼には面白くないらしい。僕がドアを開けると何もいわずに車を降りた。
トランザムは大きくターンして、埠頭の方に走り出した。
「ブレーキが甘いぜ。気をつけな」
エンジンをかけると、アロハのガキがいった。
「浜町のエッソに勤めてるんだ。来たらサービスで直してやるぜ」
僕は彼の顔を見た。ガキといったって僕と十も離れちゃいない。なのに、少しも寒そうな顔をしていなかった。
「そのうち頼むよ」
いって、車を出した。十離れていなくても、若さの持ち合わせは大分違うようだ。
尾灯だけを点けて止まっているトランザムの左側に車を寄せた。ウインドゥを下げると隣あった位置で話ができる。ヒーターを最強にして体をのばした。
「悪かったな」
トランザムに乗った。アタマがいった。
「何が」
「おかしな呼び出し方をした。ケンカにでもなったらマズイと思ったが、あんたが大人なんでよかった」
「明日から休みなんだ。暴走族のお兄ちゃんについてきてくれって、いきなりいわれたときには驚いたけどね。別にこういうやり方で呼び出されるのが好きなわけじゃない」
「あんたのこと」
いいかけて、細くて黒い煙草をくわえた。ジッポの炎が傷跡を浮かび上がらせる。効果満点だ。
「六本木の“サムタイム”のバーテンに聞いたんだ。人捜しの名人だって」
「名人なんかじゃない。仕事なんだ」
「知ってる。法律事務所で働いてるんだろう」
「そう」
ジッポのフタが音を立てて閉じた。
「あんたを連れてきたカズはG・Sにつとめてる。だから、タイヤやオイルの交換をやらせたら人の倍の早さでやるよ。手際が良くて、見てると惚れぼれするぐらいだ。それが仕事だからな。うまいんだ……。あんた、人間に詳しいんだろ」
「人間に?」
「カズが車に強いのはそれが仕事だからさ」
僕は答えなかった。
早川法律事務所は巨大な法律事務機構である。擁している弁護士は〝社長〟の早川弁護士を含めると十数人に達する。機構の中には調査課が二つあり、下請け興信所を必要としない。一課は証拠収集、二課は、失踪人調査をその業務としている。僕がそこで、失踪人調査を専門にやっていることは確かだ。
それも若者の失踪人を中心に。
「あんたのつとめてる法律事務所を通すのが筋なんだろうけど、俺は苦手なのさ。ああいう、お巡りや、弁護士みてえのが」
風が唸りを立てて、ウインドゥを直撃した。貨物船の舷側で波頭が白く光った。陰鬱で灯りのもとで見たら、もっと寒々とした眺めだったろう。
「俺、斎藤っていうんだ」
アタマはいった。
「さっきの女の話をしてみないか、斎藤さん」
僕はいった。
「血はつながっちゃいないよ、別に。寝たことを別にしたらな」
「恋人かい?」
「まあ……な。昔、十五のときに抱いたんだ。あっちは十七よ。俺はよ、オクテだったのさ」
そのひと言が気に入った。彼が子分達の前で見せるニヒルな態度より、よほど好感が持てる。といって、その持ち前の表情の暗さがツッパリの演技だけじゃないことも確かだ。
「で、今は」
「どこにいるのかも、何をしているのかもわからねえ、何年も会ってないんだ。ただ、無性に会いたいんだ」
斎藤はウインドゥを指で弾いていった。
そっといった。彼の気持ちを傷つけたくはなかったからだ。
「向こうは会いたがらないかもしれないよ」
彼は黙って弾き続けた。乾いてこもった音が続く。コツン、コツン、コツン。
「ああ」
しばらく無言だった。やがて、彼がいった。
「じゃこうしよう。あんたが見つけて、もし、もしだよ、俺が会っちゃマズいような状態、例えば結婚して、ガキや父ちゃんとマトモにやっている──っていうようなのだったら、あんたが見つけられなかったことにしてくれないか」
「……」
「どうだい?」
「まだ、引き受けるとはいってないよ。アルバイトをしたことはないんだ」
「金かい? なら幾ら……」
僕は彼の言葉をさえぎった。
「待った。金はいらないよ。といって貸しだの、借りだのというのもいやだ。こうしよう。僕は向こう三日間、休みなんだ。その間、別に予定があったわけじゃないから、その女性を捜してみよう。それで見つからなかったら、この話はそれまでだ。見つかったら……“サムタイム”のボトルが切れかかってる。斎藤さん。あんたが行ったときに、僕の名前で入れといてくれないか」
斎藤は奇妙な目つきで僕を見た。本当のハードボイルド・ガイはあんな目つきをしないものだ。
「わかった。あんたの条件で行こう。何たって捜してくれるのはあんただからな」
彼にも僕の考えていることがわかったようだった。
彼の理想がライアン・オニールだとしても今夜の彼が“ザ・ドライバー”になることはないのだ。
「感傷の街角 〈新装版〉失踪人調査人・佐久間公 2」は全3回で連日公開予定