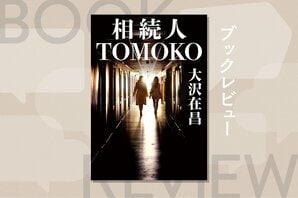九番ボールはセンターポケットの真ん前、ちょい右あたりで止まった。白球に軽く右ひねりをくれて突き出せば良い。
「貰ったよ。センター……」そういって突いた。九番はストンと落ちていった。ブルーのラシャを張ったテーブルに残されたのは白球だけだ。九つのボールはすべて、ポケットに消えた。ボーイのスミさんが口惜しそうにエプロンを投げつけると、ふわりと広がって、テーブルにかかった。
「またか、これで八本の敗けだ」
黒のスラックスから抜いた財布を手に叩きつけて、彼はいった。
八千円──休みの前日に、軽く玉突きを遊んで得る小づかいにしちゃ悪くない。
「ごち!」
キューをラックに戻していった。
「まったくもう、来なくていいよ、あんたは……。家出娘のケツでも追っかけてなよ」
「明日は休みなのさ、土、日、月曜が祭日だから三連休」
エプロンを外してカウンターに置くといった。終夜営業の玉突屋“R”もだから混んでいる。テーブルは満パイだ。騒がしくて、活気がある。本当はもっと寂しい玉突屋が好きなのだが。
「幾ら……」
「八百円!」
おしぼりをドンと置いてスミさんはいった。手にブラシを持っている。“R”が終わる午前五時までにはあと三組の客があのテーブルを使うだろう。
まだ、午前零時だ。エレベーターが開いて、ジーンズの上下にブーツといった格好のお兄さん方が降りてきてもそういう客の一組だと思った。だが違った。サングラスをしたまま玉突きをやる奴はあまりいない。
「佐久間公ってのは……」
僕の耳にそいつらの一人が息を吹きかけていった。三人のうちの一人だ。振りかえると、“スタッフ・オブ・クール・ライダーズ”という横文字の縫いとりが目に入ってきた。
ライダーといってもサーフィンのじゃない。
「僕だ」
声をかけた奴は無言で後の二人と顔を見あわせた。可愛がってくれるつもりなのか。こっちは暴走族をいじった覚えは無い。
「いっしょに来てくれますか」
言葉づかいがていねいになった。といってサングラスを外すわけでもない。五、六年前、日本に来たときマイルス・デイビスがかけていたようなグラスと、レイバンのミラーが二つ。二十を超えてもいないのに、サングラスをこんなにきめることができるようになるまでいったいどんな努力をしたのだろう。
「どこへ」
「来てくれればわかりますよ」
「歩きかい?」
「いや、自動車で……」
スミさんは少し緊張した顔付きをしていた。
「公……」と声をかけてくる。
「何でもないよ。また来るから」
そういって、三人とエレベーターに乗りこんだ。声をかけてきた奴のジーパンからオイルの匂いがした。ガソリン・スタンドの息子かもしれない。
「感傷の街角 〈新装版〉失踪人調査人・佐久間公 2」は全3回で連日公開予定