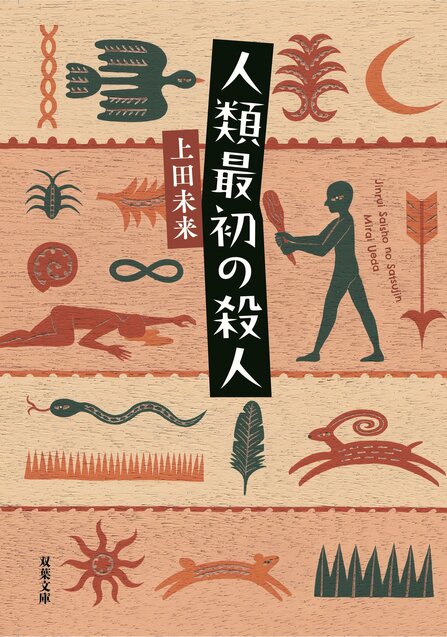数時間後、ルランは子供たちの叫び声で目を覚まします。洞窟のなかで目を覚ました彼の目前には不思議な光景が広がっていました。子供たちが棍棒を持ち、「マーラー!」と叫んでは、それを振りおろし、「ハンハン!」と叫びながらでんぐり返しをしています。そしてその繰り返し……。
ルランには子供たちが何をしているのかさっぱりわかりませんでしたが、それを誰かに尋ねることはできません。
ルランが目を覚ましたことに気づくと、子供たちはルランを洞窟の外へと連れだしました。そこでルランに何かをねだります。が、ねだられたところでルランは何も手にしていませんから、何もあげることはできません。それでも子供たちはしきりにルランに何かを求めています。
そのうちひとりの子供が、さきほどまでおこなっていたことをしました。それはマーラーがハンハンを殺害する場面です。どうやらそれをもう一度ルランにやってみせてほしいといっているようです。
気が進まないながらも、ルランはそれをやってみせました。
子供たちはアゥーと歓声をあげました。それからまたルランの真似をします。
子供たちは、すっかりルランの動きに魅せられていたのです。そのドラマティックな所作、反復がつくりだすリズム、感情のほとばしる叫び声──しかもその感情は、「怒り」でもなく「愛情」でもなく「恐怖」でもなく、彼らがいままでに体感したことがないものでした。
これが人類最初の演劇だったということをルランが知る由もありません。
子供たちは無邪気にルランにせがみ続けます。
ルランはこんな意味のないことをしたくはありませんでしたが、無邪気な子供たちにせがまれ続けては従うよりほかありません。だるそうにそれをやってみせます。そのだるさ加減がまた子供たちを喜ばせるのでしょう。子供たちはさらに歓声をあげ、器用にルランがやったのとまったく同じ動きをしてみせます。だるそうな雰囲気もそのままに。
そのうち子供たちは動きにアレンジを加えるようになりました。棍棒を二回振るってみたり、でんぐり返しではなく宙返りをしてみたり、横に回転してみたり……。
子供たちはそれに飽きる様子を見せません。そこに女たちが加わり、さらに狩りから戻ってきた男たちも参加しました。ひとりの子供はルランが持ち帰った頭蓋骨をリズミカルに棍棒で叩いています。
その騒ぎは夜半まで続きました。皆でさまざまな名前を叫んでは棍棒を振るい、また誰かの名前を叫んではでんぐり返しをします。何がおかしいのか、皆はそれをするたびに大喜びしています。
ルランは岩場を背に、複雑な思いでその様子を眺めていました。
人々のその異様な興奮は五日続きました。食事や就寝を除いては皆、それを嬉々として繰り返しています。
ときおり、ルランを引っ張りだしてはお手本をするように頼みます。ルランは仕方なく、それを見せてやります。やるたびにおざなりになっていくのですが、それがまた皆の目には新鮮に映るのでしょう。皆もルランのおざなり具合を真似て、歓声をあげます。
ルランの心はいまにも破裂しそうなほどに乱れていました。誰もルランの気持ちをわかってくれないばかりか、ルランが必死に演じた行為を笑いながら真似しているのです。
寝ているあいだでさえ、ルランは夢のなかで同じ光景を見ていました。頭のなかで子供たちが頭蓋骨を叩く音が鳴りやみません。
五日目の夜、ルランはついに洞窟を出ていきました。次の日もあれを見せられるのかと思うとたまらなかったのです。
月相は晦になっていました。その頼りなげな細い線を見あげてルランは嘆息しました。ひどく疎外感を抱き、何もする気が起きません。
あてもなく、消えかかる月に向かって歩いていきます。
明け方近くまで歩いていると、あたりに甘い匂いが漂ってきました。ずいぶん遠くまで来たようです。いままで来たことのない場所です。
目を凝らすと、前方の森に赤い点がいくつか見えました。
シュシュです。
前に見つけた森とは別の森です。放心状態のまま、その森へ入っていきました。
シュシュの実をひとつ採り、じっと見つめますと、またため息が出ます。
そのときです。うしろから「ルラン!」と懐かしい声が聞こえました。
振り返ると、そこに異様な人間が立っていました。鳥の羽根を全身につけた男です。その男は羽毛が無数につけられた毛皮を着ているのです。頭には、古代ギリシアで勝者に与えられる月桂樹の冠のように、鳥の羽根を繋いだ輪を被っています。
ルランはあまりの驚きに声を出すこともできませんでした。
よく見ると、その男はハンハンでした。全身に鳥の羽根をつけていますが、この毛深く丸い顔は間違いありません。
「ハンハン?」思わずルランは問いました。
「ルラン!」とハンハンが答えます。
ハンハンの口許はシュシュの実で真っ赤に染まっていました。さきほどまでシュシュを食べていたのでしょうか。ハンハンのうしろを見ると、葉が積まれ、踏み固められた場所があります。
ハンハンは嬉しそうにルランの腕を掴むと、葉の敷き詰められた場所へと引っ張りました。そこには大量にシュシュの実が積まれ、ほかにも動物の肉が置かれていました。幾日かここで生活した跡があります。その向こうには、赤い実の森が延々と続いています。ここはシュシュの一大生育地になっているようです。
ハンハンは何度も飛びあがり、仲間に会えた喜びを表現しています。
ルランは呆然として動きまわるハンハンを見つめました。
ハンハンは生きていました。ということは、ルランが先日森のなかで発見した遺体は、ハンハンとは別の人物のものだったことになります。マーラーはハンハンを殺してはいなかったのです。
当時は行き倒れたり、野生動物に殺されたりして命を落とす人間は少なからずいました。葬儀の概念のない時代です。荒野で死んでしまった者は野ざらしになります。あの遺体もそのひとりだったのでしょう。ルランの群れとはまったく関係のない個体だったのです。
ハンハンが、羽毛をつけた毛皮を広げて得意げな顔をしました。その羽毛は防寒のためにつけたのでしょうか。見事なほどにびっしり毛皮にとりつけられています。ハンハンは両手を広げ、鳥のように羽ばたかせました。羽毛の大きさからすると、かなり大きな鳥だったようです。
じつは、この鳥こそが、マーラーが持ち帰ってきた肉の正体でした。現在ではすでに絶滅してしまった種ですが、大型で、大量の羽毛を持つ鳥です。ハンハンがこの羽毛を気に入り、シュシュの森から離れることを嫌がったため、マーラーは仕方なく肉を捌いて持ち帰ることになったのでした。ハンハンは一枚残らず羽毛を欲し、マーラーはその肉をバラバラにせざるを得なかったのです。
一通りの狩りを覚えて独り立ちの時期が近くなっていたハンハンは、この羽毛さえあれば洞窟に戻らなくても寒さがしのげると考えたのかもしれません。地球はまだ氷河時代でしたから、人間が洞窟の外で暮らすには何かしら工夫をしなければなりませんでした。
ハンハンが鳥の真似をするように両手を羽ばたかせました。ルランに何か伝えたいようですが、身振りだけでは伝わりません。
しばらく頭のなかで言葉を探したあと、ハンハンは叫びました。
「ハンハン、ポー、マーラー、ポー、ハンハン、ポー!」
ルランは愕然としてその言葉を聞きました。
「ポー」には「獲る」と「殺す」のふたつの意味があります。ハンハンは、この鳥は自分とマーラーが獲ったものだと伝えたかったようですが、ルランの耳にはまったく別の響きとして聞こえました。
それは、ルランが必死に仲間に訴えた、あの叫びと同じだったのです。
人類の諍いのほとんどはコミュニケーションの齟齬によって生じるものです。当時の人類にまだ「侮蔑」の概念はありません。人類はそこまで自分の意思を表現する力を持ってはいませんでした。当然ハンハンにもその意図はなかったはずです。が、ルランの胸の裡に湧きあがったものは、まぎれもなく、侮蔑された者の胸に宿る、あの、薄暗い色の感情でした。
ルランは、ハンハンが自分のしてきた一連の行動を揶揄していると感じたのです。
論理的に考えれば、ルランが仲間に必死に訴えていたとき、ハンハンはその場にいなかったのですから、ルランの行動を知っているはずがありません。が、ハンハンの紡いだ言葉がルランの訴えていた言葉とまったく同じだったという偶然が、ルランの思考を完全に論理の埒外へとはじき出してしまったのです。
目の前では、鳥の羽根をつけたハンハンが大げさに両手を羽ばたかせ、シュシュで真っ赤に染まった歯を剥き出しにし、満面の笑みで「ハンハン、ポー!」と叫び続けています。
ハンハンが笑っているのは仲間に会えたという純粋な喜びからでしたが、ルランの知性を持った目には、その笑顔は自分に対しての嘲りに映りました。
この鳥を仕留めたことがよほど嬉しいのか、ハンハンの叫びはやみません。両手を羽ばたかせ、さきほどの言葉を繰り返します。
「ハンハン、ポー!」
自分の態度によって相手に引き起こされると予期した感情と、実際に相手の心に浮かぶ感情が異なることは多々あるものです。それを埋めるのが言葉であり、相手への理解です。どちらも彼らには未発達の領域でした。
ルランが反応を示さないことで、自分の気持ちが通じないと思ったのか、かえってハンハンの叫び声は大きくなっていきます。
「ハンハン、ポー!」
ルランの胸の裡に、ふつふつと黒い感情が膨らんでいきました。
疎外感からくるストレス、誰にも自分の考えを明確に伝えられないもどかしさ、どこにも居場所のない息苦しさ──これらもろもろの感情に囚われ、ルランはまるで現代人のように、精神的にも肉体的にも限界まで張り詰めた状態にありました。
あたかも彼の心は、晦の月相のごとく細くしなった弓にピンと張られた弦のようだったのです。
「ハンハン、ポー!」と、すぐそばで叫ばれたとき、ルランは棍棒を振りおろしていました。
棍棒はハンハンの頭を直撃しました。
突然の攻撃によってよろめいたハンハンは、「ポー……」と呟くと驚いたような表情を凍りつかせて二、三歩さがり、そのままうしろに倒れました。ルランはその上に乗り、何度も何度もその頭を正面から棍棒で叩きつけました。やがてハンハンは動かなくなりました。
棍棒が血で真っ赤に染まり、顔や身体に返り血をたっぷり浴びてルランは立ちあがりました。しげしげとその遺体を見つめたあと、細く消えかかる月に向かって叫びました。
「マーラー、ポー、ハンハン、ポー、ルラン、ポー、ルラン、ポー……」
こうして“バードマン”は殺されたのです。これが人類最初の殺人になりました。
ルランには罪悪感があったのかもしれません。彼は“バードマン”ことハンハンを撲殺したあと、羽毛だらけの毛皮を着せたまま近くで見つけた洞窟の奥にハンハンを寝かせました。それから遺体が動物に襲われないように、その上を土と石で覆いました。最後にハンハンが大好きだったシュシュの実をそこに供えました。
その化石が二十万年のときを経て、イギリスの古人類学者によって発見されることになったのです。
「言葉なき世界に人は非情かな」
いつの世も自分の意思を正確に相手に伝えるのは難しいようでございます。
このへんでこのお話は終わりにしたいと思います。
〈ジングル、八秒〉
お話は、国立歴史科学博物館、犯罪史研究グループ長の鵜飼半次郎さんでした。
人間って怖いですね。
次回は来週月曜日午後十一時からの放送になります。
ナビゲーターは漆原遥子でした。
それではまた次回の放送でお会いしましょう。
この続きは、書籍にてお楽しみください