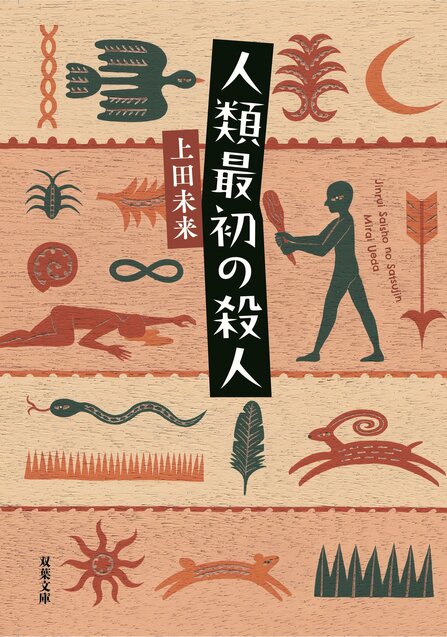皆はまったく気にする様子がありませんでしたが、ルランはどうしても気になりました。マーラーが持ち帰った鳥の肉に羽毛がまったくついていなかったことも気になります。
皆に二度の食事という幸福をもたらしたマーラーは、いつのまにか洞窟の奥で女たちといちゃついています。ルランは面白くない気持ちでそれを眺めていました。
当時、ホモ・サピエンスのあいだにはわずかながらに社会性が育っていましたから、群れへの貢献もその序列に影響を与えていました。マーラーはルランに次ぐ序列ナンバー3の地位にいます。ルランはマーラーに脅威を抱いたのです。
ルランは立ちあがると、マーラーに近づいていきました。そばまで行き、
「ハンハン!」
と怒鳴りました。
マーラーはルランに顔を向け、
「ハンハン?」
と聞き返しました。
当時人類はすでに言葉を発することができたのですが、まだ複雑な文法は持ってはいませんでした。あるのはいくつかの名詞と動詞だけ。それだけでコミュニケーションをとっていたのです。そのころはまだ誰も複雑なことを考えてはいませんでしたから、それでじゅうぶんなのでした。
マーラーはしばらくして、ようやくルランが尋ねているのは、ハンハンの居場所のことだと気がつきました。マーラーは、なんでもないといったように、
「シュシュ」
と呟きました。
それから空中の何かを手にとる振りをして、それを口元まで運ぶ仕草をしてみせます。
シュシュというのは、ある赤い実のことです。現在ではすでに見られなくなった植物ですが、ハンハンがその実を食べたということをその動作は意味しているのだとルランは解釈しました。ルランはハンハンがその実が好きなことを知っています。
しかし、そのことがハンハンが帰ってこない理由にはなりません。それでもマーラーは、それでじゅうぶん説明し尽くしたと思ったのか、ふたたび女といちゃつき始めました。
納得のいかないルランでしたが、それ以上追及する言葉の術を持ち合わせてはいませんので、ハンハンは「シュシュ」の実を探しているうちにはぐれてしまったのだろうとマーラーの言葉を補って考えました。この時代にしては、ルランは頭がよい男でした。
空にまんまるな月が昇りました。皆はすっかり寝入っています。そのなかでルランだけは寝つけずに考えごとをしていました。
はぐれてしまったとはいえ、あのハンハンがこの洞窟に帰ってこないのは妙だ、動物にでも襲われたのだろうか、はたまた群れに戻るのをやめて別の群れに加わったのだろうか、などと考えていたのです。
そんなことを朝方まで考えていると、お腹が空いてきました。マーラーに嫉妬するあまり、マーラーの獲ってきた肉をほとんど食べなかったことがよくなかったのでしょう。そういえば、あの鳥はどんな鳥だったのだろうとルランは思いました。
以前にもルランは鳥の肉を食べたことがあるのですが、夕方に少しだけ食べた肉は、どうも鳥の味ではないような気がしてきました。そもそも一羽の鳥にしては量が多すぎます。それに、なぜマーラーがその肉を捌いて持ち帰ったのかということも気になります。
その瞬間、ルランの頭のなかで何かが光りました。輝くそれは脳内を一瞬稲妻のように駆け抜けただけでしたが、ルランは得もいわれぬ興奮を味わいました。もやもやしていたものが突如として明晰な形を持って現れ、点となっていたものが線で繋がったのです。
──そうだ。マーラーは何も獲れなかったものだから、ハンハンを殺して、その肉を持ち帰ったんだ。
思考は言葉によって紡がれます。お話ししたようにこの時代にはまだ文法がありませんから、このようにはっきりとした文の形でルランの頭のなかに浮かんだわけではありません。しかし、ルランの頭のなかのイメージを統合すると内容はおおよそこのようなものでした。
これは人類最初の論理的な思考でしたが、もちろんルランがそんなことを知る由もありません。
ともかく、この天啓のような閃きにより、ルランの頭のなかで、ハンハンの失踪とあの妙な味の肉が結びついたのです。
モラルという概念のない当時であってさえ、カニバリズム──いわゆる人肉食は嫌忌されることでした。ましてや仲間を殺すなど許されることではありません。これは皆に周知しなければならぬことです。しかし、そこには問題がありました。
かの谷崎潤一郎氏は『文章讀本』のなかで、こう述べておられます。
〈人間が心に思うことを他人に伝え、知らしめるのには、いろいろな方法があります。たとえば悲しみを訴えるのには、悲しい顔つきをしても伝えられる。物が食いたい時は手真似で食う様子をしてみせても分かる。その外、泣くとか、呻るとか、叫ぶとか、睨むとか、嘆息するとか、殴るとかいう手段もありまして、急な、激しい感情を一息に伝えるのには、そういう原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやや細かい思想を明瞭に伝えようとすれば、言語によるより外はありません。言語がないとどんなに不自由かということは、日本語の通じない外国へ旅行してみると分かります〉
そうなのであります。
ルランは伝えるべき事柄を抱えてしまったのですが、その「細かい思想」を明瞭に伝える術を持っていなかったのです。
そのため、朝、さっそく群れのリーダーであるガルーダに自分の考えを伝えようと試みたルランでしたが、やはりそれはうまくいきませんでした。
ルランは、ただ、
「ハンハン、ポー、マーラー、ポー、ハンハン、ポー……」
と繰り返すばかりでガルーダにはまったく通じません。
「ポー」は「殺す・獲る」を意味する言葉です。ルランはマーラーがハンハンを殺したと訴えていたのですが、まったく伝わらなかったのです。
ルランの発する言葉のなかには、図らずものちに発生する英語や中国語のように主語、動詞、目的語の語順に相当するものがありました。必要は発明の母と申します。言葉とはこのように発達していったのでありましょうか。さりとて、聞くほうがその法則を知らなければ意味が伝わるはずもありません。
ガルーダは、ルランのいわんとすることを理解しなかったばかりか、その表情には、もはや「ハンハン」という言葉が意味するものを忘れている感さえありました。
当時の人間からすると、いなくなった者の存在を忘れることは無理からぬことでした。ハンハンはこの群れで生まれ育ったのですから、いずれはこの群れを出ていく運命です。それが早く起こっただけ。皆はそのように考えていたのです。いなくなった人間のことを覚えておく道理はありません。記録のない世界、どうせ忘れるのなら、早いにこしたことはないというわけです。
とりわけリーダーのガルーダは、記憶力に乏しく、頭のなかには食べることと女を抱くことのふたつしかない男です。まさしく原始人を代表するような男でした。
が、諦めきれないのはルランです。彼にはなぜかしら物事を記憶する力があり、一度考えついたことを頭のなかから消し去ることができなかったのです。
ルランは、ガルーダを説得するのを諦め、マーラー本人を問い詰めました。といってそれは、ガルーダにしたようにただ言葉を並べて繰り返すだけでしたから、やはりマーラーの反応もガルーダと同じようなものでした。マーラーは首を傾げ、不思議そうな顔をしてルランを見つめるばかりです。
ルランは、目の前にはっきり見えているのに、それに手を触れることのできないもどかしさを覚えました。
どうやってみても自分のいいたいことが伝えられないのです。
それからというもの、そのことばかり考えてしまいます。思うように狩りもできません。さらにはあの日以来、皆から慕われるようになったマーラーの態度も鼻につきます。
マーラーの序列はルランのすぐ下です。当時の男性にとって序列はひどく重要なものでした。
まあ、それはいまでも変わりはございませんが。