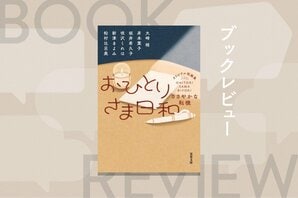がっかりという感情はわかなかった。それよりも、初めましてこんにちはと挨拶したくなる。あなたがうちに来てくれるのと問いかけたくなる。毎日恐い思いをしているのよ、助けてちょうだいと言いたくなる。だって、犬そのものが恐そうだもの。
そして思う。私を守ると約束してくれるのならば、払っていいのかもしれない。毎月の十万円。年に百二十万円。だって、私の老い先は短いの。それくらい使ったって罰は当たらない。
「名前はなんていうんですか」
「リクヴェルです。通称リク。どちらでも」
「いいお名前ね」
スタッフ、というよりトレーナーと言うのだろう。見るからに体育会系とおぼしき精悍な顔立ちの男性が声をかけると、犬は照子から二メートルほど離れた場所に腰を下ろした。お座りの形になる。
照子の傍らにいた武内が犬に歩み寄り、手を伸ばしてその背を優しく撫でた。
「リクヴェル、こちらは副島照子さん。君の新しいご主人になるかもしれない人だよ。もしも決まったら、くれぐれもよろしく」
新しい? 聞きとがめて照子は武内に話しかけた。
「この犬はこれまでにもどちらかに貸し出され、ご主人がいたんですか?」
「はい。その方はほんの二ヶ月前に高齢者向けの施設に入居されました。もともとそういうご契約内容でした。ですがリクヴェルをたいそう気に入ってくださって、あと半年、あと半年と延ばされて。いっそ施設に連れて行きたいとも言われたのですが、この犬を必要としている人がきっといるだろうからと、最後は気持ちよく手放してくださいました」
「まあ、そんなことが」
「リクヴェルはとても賢い犬なので、自分の役割をちゃんと心得ています。新しいご主人が決まったら、その人を守るために全力を尽くします。もっともふだんは室内でごろごろしているだけですが」
「そうなの?」
犬のリードを持つトレーナーが苦笑いを浮かべ、武内がさらに言う。
「警戒心が強く、いざとなったらとても勇敢で物怖じしない犬なのですが、何事もないときはマイペースでくつろいでいると思います。吠えたり騒いだりはないので、居候がいるくらいに思っていただければちょうどよいかと」
「うちでもくつろいでくれるのかしら。私もくつろいでいいのかしら」
「もちろんです。見かけによらず人なつこくて構われたがり屋なので、話しかけたり撫でたりすると喜びますよ」
「この犬が?」
照子の反応がおかしかったらしく、武内もトレーナーも小さく吹き出す。
「見かけよりずっと可愛いやつです。ご主人が大好きで、役に立とうと張り切ってます。ときどき褒めてやってください。おだてに弱いタイプです」
にわかには信じられない話だ。でも神妙な面持ちで照子を見つめる犬に硬質な威圧感はない。純粋に見ず知らずの人を眺めている。たった今、引き合わされた人が主になるのかならないのか、その選択をゆだね、平然としていられる。そういう強さは人間ならば意外と難しい。ごちゃごちゃとよけいなことを考えてしまうから。もしかしたら一緒に暮らす上で重要な要素かもしれない。
瞬時に危険を察知する護衛官でありつつ、ふだんはおだてに弱い居候というのも親しみが持てる。人間くさい。この場合は犬くさいか。笑いたくなって気持ちが軽くなる。
「もしもお願いするとしたら、ここから先はどうなりますか」
「トライアル期間が始まります。三段階ありまして、この施設でリクヴェルと少しずつ親睦を深めてもらいます。問題なく進めば、次は副島さんのお宅でお試し滞在。だんだん時間を長くしていって、大丈夫そうならば本格的な同居に移ります」
よどみのない説明に、犬の貸し出しがサービスとして確立されていることを実感した。武内の話からすると最初の貸し出しから数えて八年目になるそうだ。これといったトラブルはなく、今までどの利用者からも好評を得ていると言う。現在は十四匹が都内西部で職務を全うしている。
番犬の話を聞きに行く前に、照子は子どもたちに電話をした。犬の件は伏せ、友だちの家に不審者が現れたことを話し、昨今の物騒なニュースがよりいっそう身近になったと訴えた。
娘の裕美子は真剣に耳を傾け、とても心配してくれたが、すぐに二世帯住宅を建てる話に変わる。今住んでいる狛江の家を売って、裕美子のいる松戸に新しい家を建てようと数年前から言われている。裕美子の一人娘も一緒に住むことにして、もうすぐ生まれる赤ちゃんも加えると四世代同居だと楽しげにしゃべる。
けれど照子は乗り気になれなかった。合意したとして、実際住むのは何年先になるだろう。早くても二年、三年はかかるのでは。八十四歳の自分は九十歳近くなっている。元気でいられる保証はない。
愛着のある今の家を手放すのにも抵抗がある。長年馴染んできた狛江からも離れがたい。娘たちとの同居は心強いが、そこを自分の家と思えるだろうか。
心配されたことにありがとうと言い、他には曖昧な返事をして受話器を置いた。
そのあと貴宏に電話をかけた。前々から高齢者施設への入居を勧められている。自分たちの住んでいる長野で気に入った施設を見つけてほしいけれど、狛江から離れたくないのならばそちらで探すのも致し方ないと。今回もその話になって急かされると思いきや、やけに優しく長野においでよと言われた。子どもたちが外に出たので今は夫婦ふたり暮らし。気兼ねはいらないとのことだ。
でも、二階の二間は子どもたちの部屋で、外に出たと言っても荷物は未だ置きっぱなし。下はリビングダイニングの他、和室がひとつきりだ。そこを貴宏夫婦が使っている。照子はどこにいればいいのだろう。和室を譲られても落ち着けない気がする。
丁重にお礼を言って電話を切る。娘も息子も年老いた母の身を案じてくれている。自分たちにできる精一杯のことを考えてくれている。ありがたくて嬉しい。それはほんとうなのだけれども、どちらも狛江の家に住むつもりはないようだ。ここにいる限り、照子は家族と暮らせない。
もうひとりの息子、名作「男はつらいよ」の“フーテンの寅”を地で行く長男・光昭にはメールを送った。数日後に届いた返事には、六十歳になったと書いてあり、そのさい催されたとおぼしき誕生パーティの写真が添えられていた。ホールケーキを掲げた赤いシャツのおっさんが大笑いしている写真だ。
こんなのに比べたら、よっぽど犬の方が頼りになる。
この続きは、書籍にてお楽しみください