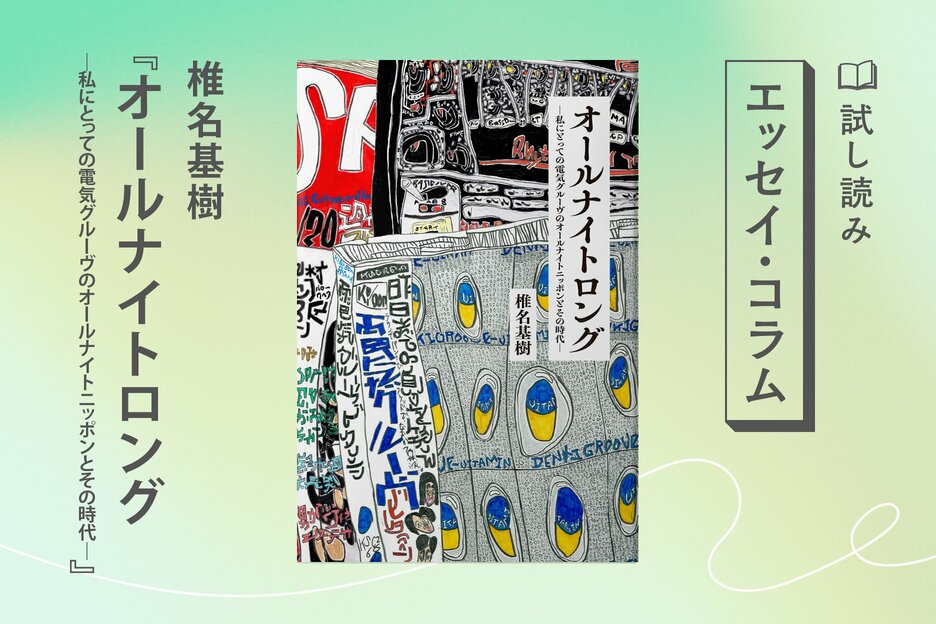ラジオという「荒々しいメディア」
ジョージ・ルーカスによる1973年の映画「アメリカン・グラフィティ」には、謎のラジオ番組「ウルフマン・ジャック・ショウ」が登場する。劇中のアメリカのある街に住む若者は、皆この番組を聴いている。この青春群像劇の登場人物は、「ウルフマン・ジャック・ショウ」によって、ゆるやかにつながっている。
この「ウルフマン・ジャック・ショウ」は、ウルフマンを名乗る男が、メキシコから発信した、実在した海賊ラジオ放送がモデルになっているという。この放送局は過大な出力を誇り、アメリカ全土にリスナーがいたという。
ラジオ放送は、電波を発信した時点で、完結しているような気がする。イタズラが完了していると感じるのだ。
インターネットメディアは、ただ発信するだけでは虚しすぎるから、どうしてもフォロワー数や、閲覧数を追い求めてしまう。しかし、電波によって発信することは、メッセージ付きの風船を空に飛ばすようなロマンを私は感じてしまう。
話は逸れてしまうが、日本でも「ウルフマン・ジャック・ショウ」のような、ラジオの海賊放送が摘発される事件があったそうで、その顛末が、あんまりおかしいので、少し触れておこう。
1978年に八王子に住む大学生の2人組が、自宅アパートから、海賊放送を始めた。放送は、同じアパートに住む学生や近隣の住人にも聴かれ、リクエストハガキが届くなど思わぬ反響を生んだ。
熱が入った2人は、秋葉原で部品を買い集め、高出力送信機を自作して、「FM西東京」を自称し、週平均3回、午後11時から午前2時までの本格的な定期放送を開始した。
八王子郵便局に「八王子放送研究会」の名義で私書箱を開設し、リクエストハガキを受け付けた。摘発によって活動が終了するまでの約1年間の間に、600通ほどのハガキが届き、バレンタインデーには、チョコレートまで送られてきたそうだ。
ラジオ番組の制作に携わった者は皆、その楽しさを語るのではないだろうか。リスナーとの絶妙な距離感。レスポンスの良さ。それは生放送ならなおさらだ。思いついたアイディアをすぐに番組で実践できるスピード感。マイク1本でスタジオの外に飛び出していける機動力。ラジオには融通無碍な楽しさがある。そして、その魅力の源は、電波による音声放送であることのような気がするのだ。
ニッポン放送の局内に明るい活気が溢れていたので、加藤さんに「今、ラジオ調子いいんですか」と尋ねると「いいみたいだよ」と、加藤さんらしい、そっけない答えが帰ってきた。
30年前に私が仕事をしていた頃は、ニッポン放送はラジオ界の絶対的な君主だったけれど、ある時期から長くその座を奪われていた。それが最近になって、ようやく聴取率トップの座を取り戻したらしい。ラジオの仕事からは遠ざかっていたけれど、隅っことは言え、同じ放送業界に身を置かせてもらいながらも、私はそのことを知らなかった。
ラジオ局でも、テレビ局でも、放送局の数字に対する反応は、滑稽なほど過敏だ。そこには電波放送のロマンなんて甘ったれた考えは入り込む余地はない。
地上波の放送局の数は限られているので、他局との比較からどうしても逃れることはできないだろう。民放の聴取率トップの座を取り返したならば、ニッポン放送の局内に明るさが溢れているのも、非常にうなずける。
明るい雰囲気の要因は、それだけではないらしい。ラジオというメディア自体が復権しているという。ライバルと目されたインターネットの登場が、逆にラジオの良さを見直すきっかけになったのかもしれない。
インターネットの登場で、マニアックなものや個人的なコンテンツに、注目が集まるようになったように感じる。インターネットの動画配信番組は、画があるラジオとでもいうべき内容も多い。
テレビのバラエティー番組で、チームプレイが徹底されるようになった今、お笑いタレントにとってラジオ番組は、個性を発揮できる貴重な場になっているのではないだろうか。
また、出演タレントにとって、少人数のスタッフと濃く長く付き合うことになるラジオ番組は、そこに行けば、あたたかく迎えてくれる仲間がいるホームにもなる。出演者が、番組に愛着を持てるということは、タレントが猛スピードで消費されていく時代の中で、とても貴重で重要になっていくような気がする。
エンターテイメントメディアが、これだけ多くなった現在において、昔に比べて聴取者数自体は少なくなったかもしれないけれど、様々な意味でラジオ番組は、存在感を増しているようだ。
一通り新しいニッポン放送の局内見学を済ませた後、会議室で、送られてきたメールを読んで、大まかに面白そうなものを選んでいると、ニッポン放送で働く人たちが、次々と会議室を訪れて、「加藤さん、今日キュー振るんだって?」と、久々にディレクションをする加藤さんを冷やかしにやって来た。
男の人も、女の人も、ニヤニヤしながら嬉しそうだ。それに対して、加藤さんは「うるせーよ」なんて、30年前と変わらない、荒っぽい放送業界口調で言い返していて、なんだか微笑ましい。
「加藤さん、今どんな仕事してるんですか?」と私が尋ねると、ぶっきらぼうに「カネ勘定ばっかやらされてるよ」と加藤さんは言った。久しぶりに味わう、ニッポン放送の男っぽいノリが楽しい。
メールを仕分けし終えて、しばらく加藤さんと談笑していると、加藤さんの携帯電話に、電気グルーヴの2人がニッポン放送入りしたという連絡が来た。加藤さんと2人で、玄関まで迎えに行く。
満面の笑みで、電気グルーヴの2人はやってきた。挨拶もそこそこに、加藤さんの見た目の変わらなさをいじっている。実際、加藤さんは、驚くほど変わっていない。体型も変わらないし、髪の毛も黒々と多い。
「坊ちゃん刈りのまんまじゃん」なんて、石野さんがいじっている。体の小さな加藤さんを、2人で取り囲んで、子犬でも撫で回すようにいじっている。特に石野さんは、久しぶりの加藤さんとの再会が本当に嬉しい様子である。
石野さんには、昔から少し歳の離れた男の先輩に甘えたいという「中年愛」とでも呼ぶべき欲求があるように感じる。
加藤さんに対する態度と同様に、オールナイトニッポンに、ケラリーノ・サンドロヴィッチがゲスト出演した回の、石野さんのテンションも非常に高かった。はしゃいでいるようにも感じる。ケラは、石野さんの才能を最初に見出し、世に送り出してくれた年上の恩人だ。そして、ラジオでの話しぶりから、彼は非常に包容力があり兄貴肌の人間だと感じる。
石野さんには、好意を抱く人に久しぶりに再会した時などに、興奮と、おそらくは照れくささのあまり、その人に向かって悪態をつき、罵詈雑言を吐くという、非常にへそまがりな困った習性がある。
ケラリーノ・サンドロヴィッチの結婚式の際、石野さんが彼に向かって、悪口を言いまくり、本気でキレられたことは、ちょっとした伝説だ。それはケラを、慕うあまりのことで、嬉しさで犬が吠えるようなものだと思われる。
石野さんの中年愛と言えば、高校時代にもこんなことがあった。石野さんが高校3年生の時、彼は当時交流があった静岡のヒッピー家族と共に暮らすと、突然言い張って、布団を背負って家出をしようとした。ヒッピー家族の父である「よっちん」を、彼は非常に慕っていたのだ。
困った石野さんの母親は、瀧さんに家出を止めてくれるように頼み、その説得により、石野さんは実家住まいに踏みとどまった。
この家出騒ぎの時は、まだナゴムレコードから、作品リリースの声がかかる前だったと思う。その時の石野さんは、東京に行ってバンド活動を続けると、はっきりと決意していなかったのだろう。
あの頃、石野さんは、自分の進路について模索していたのだと思う。きっと彼は、高校生の当時から、一般社会に対して違和感を感じていた。だから、社会に背を向けて暮らしていた、よっちんの生き方に共感して、自由に生きられる可能性を見出したのかもしれない。
ところで、石野さんが憧れたその家族であるが、彼らの暮らしぶりは、とてもアナーキーだった。まず第一に、彼らが住んでいた家は非常に変わっていた。多分、社会が混乱していた時代に、不法占拠で建てられた建物だったのではないだろうか。
静岡市に流れる安倍川という巨大河川の土手のてっぺんに、住居の入り口があって、そこから入ると、部屋がひとつだけあり、そこで家族は「種屋」という名の喫茶店を経営していた。店内の隅の床に穴が開いていて、土手の傾斜に沿ってはしごが立て掛けてあった。
はしごを降りていくと、土間の部屋があった。土間には、西洋式の大きなバスタブが設置されていて、その横が(多分)手作りの小上がりになっていて、そこが家族の居間兼寝室だった。壁には、ジョアン・ミロを模した絵が、よっちんによって、直接描かれていた。
石野さんは、その種屋で「人生」とは別のバンドのライブを定期的に行っていたので、私も含め、「人生」のメンバーは、よくその店に溜まっていた。
ヒッピーの夫婦は、よく息子の子守りを、高校生の私たちに任せて店を留守にした。その息子が、「人生」のナゴムレコードからのデビューミニアルバム「9 tunes for mirai」のタイトルの由来になった、当時3歳児の未来くんだ。
喫茶店の飲食物を勝手に飲み食いすることを許されていたので、私たちは長時間にわたり店に居座った。夜になって、未来がぐずり出すと、石野さんは膝枕をしてあげて、背中をトントンと叩いて寝かしつけた。
石野さんは、もちろん高校生の頃から今と同じような毒々しい人だったので、そうした行為を見て私は内心驚いていた。彼は子供が好きだった。
その未来であるが、私たちが高校を卒業して静岡を離れてから、長い間彼と会う事はなかった。しかしある時、石野さんがDJをしている京都のパーティーに、未来はひょっこり顔を出した。彼は20歳になっていた。それは、3歳児だった子供の、文字通り未来の姿だった。
それをきっかけに、彼は上京してきて、それ以来、私たちとの交流は続いている。未来は一度、電気グルーヴのライブの前座を務めた。
「未来、現る」のニュースに、私は心底驚いたが、また同時にその再会は、必然であるとも感じられた。若い時の、特別なある時期ある場所で出会った人間同士は、運命の一部分が共有されてしまうような感覚が、私にはある。
特に高校生以降、自分の生き方を決定する時期に出会った人間とは、不思議な縁で結ばれることが多いのではないだろうか。私にとって、高校時代に知り合って「人生」の活動を共にした人たち、そしてその活動によって知り合った人たちも、もちろんそうだ。
ニッポン放送で見習い放送作家をやっていた数年間に知り合った中にも、加藤さんをはじめ、強い結びつきを感じる人たちが多い。高校時代の「人生」の周辺も、あの当時のニッポン放送も、私にとって非常に熱を帯びた場所だった。
ニッポン放送時代、電気グルーヴの盟友に浅草キッドがいる。その玉袋筋太郎と私は、「KAMINOGE」という雑誌でインタビューページをやらせてもらっていて、その連載はもう15年余り続いている。
玉さんとは、ニッポン放送時代、タレントと放送作家という関係においても、プライベートにおいても、ほとんど話す機会がなかったと思う。しかし、連載のために再会した最初から、同じ価値観を共有しているような気持ちを持つことができた。それは私の一方的な認識であるけれど、連載が15年間も続いていることがその証明だと、勝手に考えている。
玉さんとの関係も、30年前のあの時期にニッポン放送が発していた磁力の影響で、運命づけられたことのように思える。
復活電気グルーヴのオールナイトニッポンは、電気グルーヴと加藤さんの信頼関係があれば、やる前からうまくいくことが決まっていたのだ。私があれこれ緊張したって、何の意味もないことだったと、加藤さんを取り囲んで、はしゃぐ彼らを見て思った。
1時間ほど瀧さんを中心に、メールに目を通して、採用するものを決定して、いよいよ本番に臨むことになった。
この続きは、書籍にてお楽しみください