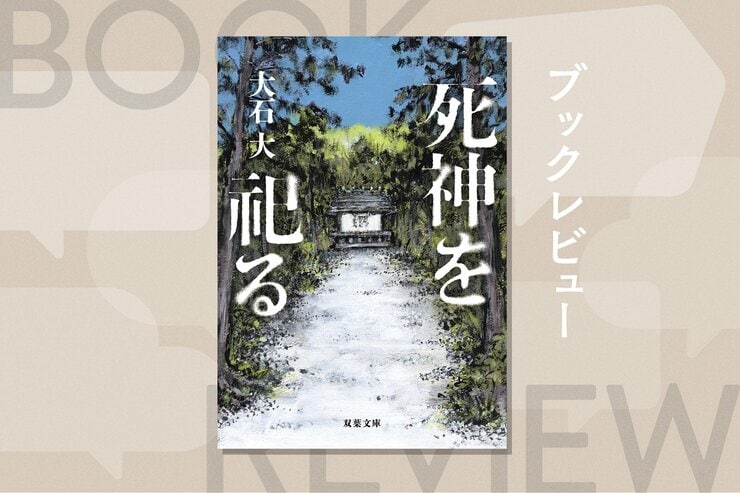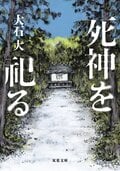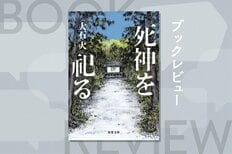一ヶ月間欠かさず、お菓子を供えてお参りすると、30日目の夜、この世のものとは思えない快楽のなかで死を迎えることができる神社があるという。それを体験した男の日記がネットで拡散し、その神社は話題に。死を願う人たちが集まり、街は活気を取り戻すが……。
そんな「死神によって蘇った町」を舞台にした連作小説集を、デビュー前から著者と親交のあった作家・友井羊が特別解説。友井さんが語る本作の魅力とは⁉
■『死神を祀る』大石大 /友井羊 [評]
30日間、甘いものを供えながらその神社に参拝すると、幸福な死を迎えられる──。
本作『死神を祀る』は、他に類を見ない独創的な小説だ。不思議な力を持った神社を巡って、どんな恐ろしい出来事や衝撃の展開が起こるのか、設定を知った読者は強く興味を惹かれたことだろう。この作品は、その期待に充分に応えてくれるはずだ。
ただ私は、この作品が奇抜さだけの物語でないことを強く主張したい。本作では多くの死が登場するが、それ以上に描かれていることがある。それは死を通して浮き彫りになる、懸命に生き抜く人々の美しさだ。
まずは作者について紹介しよう。大石大は2019年、『シャガクに訊け!』(光文社)で第22回ボイルドエッグズ新人賞を受賞し、同作で小説家としてデビューした。個性的な登場人物たちが社会学を題材に様々な謎と対峙するこの作品は、豊富な知識や一筋縄ではいかない展開が楽しめる良質なエンタメ作品だ。
2作目『恋の謎解きはヒット曲にのせて』(双葉文庫)は、失恋に隠された真実を、各年代のヒット曲に絡めて綴った王道の連作ミステリで、こちらも作者のストーリーテラーとしての高い実力が存分に発揮されている。
本作『死神を祀る』は、ライトな読み口のミステリが続いた後に発表された3作目だ。あらすじを知った私は、当時とても驚いた覚えがある。作品の方向性が変わったためなのだが、私の知っている大石大の作風に戻ったことが最大の理由だった。
実は解説を担当する友井羊は、大石大とは互いに小説家デビューする以前からの友人だ。何者でもない小説家志望者だった2人が、解説という形で関わり合うことに深い感慨を覚える。
それはさておき、私はデビューが決まる前の大石大の作品を読んだことがある。詳しい内容は割愛するが、独創的な設定と読み口という点で『死神を祀る』に近い雰囲気を持っていた。
そして私は、大石大の作品が放つ独特の感性が好きだった。正直にいうと、自分にはない発想力を羨ましいとさえ思っていた。そのため第一作と第二作で発揮した高い小説技法を用いた上で、あの個性的なイマジネーションが楽しめることが嬉しかった。そして今作は想像を遥かに超えて素晴らしい作品に仕上がっていた。
本作の舞台は、東北にある過疎が進む寂れた田舎町だ。産業も観光資源もないため、街からは活気が失われている。似たような自治体は日本全国に無数に存在するのだろう。秋田出身である大石大も、同様の景色は目の当たりにしているはずだ。そのため停滞した空気感には強いリアリティが感じられる。
そんな地方都市にある奇妙な神社を巡り、物語は進む。
実はあらすじを読んで、不安に思ったことがあった。発想には心惹かれるが、人の死が軽く扱われているのではないかと危惧したのだ。だが懸念は完全に杞憂だった。
大石大は絶妙なバランスで死を描いていった。殊更に残酷さを強調するわけでもなく、恐ろしい怪異として誇張することもしない。神社の力は現象であって、人智を超越した死がただそこに存在している。そのため周囲の人々は自然と、神社による死があるという前提で物事を考えるようになる。
俯瞰するような眼差しで淡々と語り、どことなく文章にユーモアさえ感じる。最も近いのはテレビドラマ『世にも奇妙な物語』かもしれない。本来は異常なものをあるがままに描くことで、読者に違和感を覚えさせないのだ。
この描写の仕方は誰にでもできるというわけではない。もちろん読者を不思議な世界にいざなうために、いくつもの技法を用いている。だがそれ以上に、作者の文体の為せる業だと私は考えている。
奇妙な存在をさらっと描ける独自の文章は、大石大の魅力の一つだ。それは学校を舞台にした不可思議な短編集『校庭の迷える大人たち』(光文社)でも発揮されている。『死神を祀る』の語り口に魅力を感じたら、この作品も手に取ってみると良いだろう。
次に大石大作品の特長として、設定を徹底的に考え抜く点が挙げられる。この神社があったら何が起こるのかを、あらゆる可能性を多角的に検討し尽くした上で物語を書いているのだ。すでに本作を読んだ読者は、この神社の設定からこんな話まで思いつくのかと、各話ごとに新鮮な気持ちになったはずだ。
まず私は、第1話の「私の神様」に驚かされた。演劇部を舞台に少女たちの悩みが描かれる青春物なのだが、メインであるはずの神社の扱い方が秀逸なのだ。
ありふれた日常描写が、異物によって緊張感で満たされる。それが読者にだけ理解できるという点が心憎い。キャッチーな設定を前面に出さなくても話を面白くできるのだと、作者にしてやられた気持ちになった。さらに第1話で心の準備をしたからこそ、読者は第2話でスムーズに神社の存在を受け入れることができる。こうした細やかなテクニックも作者は実に巧みなのだ。
第2話の老夫婦は、この設定から期待する王道の物語だろう。認知症に苦しむ姿は胸に迫るし、30日間通うという設定のおかげで、夫婦のすれ違いや葛藤が丁寧に描かれていく。夫婦の心の交流に、きっと多くの人が涙するはずだ。正統派の物語も味わい深く描けるのは小説家としての力量の表れだろう。
この時点で読者は、以降も神社がもたらす死が描かれると想像するはずだ。実際に私もそうだった。だが大石大は一筋縄にはいかない。
第3話「ゆがんだ顔」から、作者が得意とするミステリ色が一気に強くなる。神社の力によって幸福な死を迎える直前に、1人の男が自殺をしたのだ。
男はなぜわざわざ苦しむ死を選んだのか? 刑事が真相に迫る物語とその真相を読み終えた瞬間、私はあることに気づいた。
この作品は死を描くと同時に、死に直面した人々の生き様を描く物語なのだ。
有名映画をオマージュした第4話「テルミ&ルイ」では、追い詰められた女性2人が登場する。神社の真実に迫る第5話「封印された民話」、第6話「死者でよみがえる街」と続くにつれて、物語は参拝客から家族、街の人々、そして社会全体へと波及していく。
物語のスケールが広がるにつれて、当初は予想もしていなかったような発想の飛躍が読者を待ち受ける。未読の方はぜひ楽しみにしていてほしい。
だが作者は読者を置いてけぼりにするようなことはしない。東日本大震災や原発、安楽死や姥捨山を思わせる描写など普遍的な題材を巧みに織り交ぜることで、物語に入り込めるようにする配慮も欠かさない。
余談だが、川越を舞台にした連作短編集『いいえ私は幻の女』(祥伝社)でも、記憶を消せるカフェという設定を、あらゆる角度から考え抜いた上で多彩な物語を生み出している。そのため「この手があったか!」という驚きを何度も体験できる作品に仕上がっている。
幸福な死をもたらす神社という異常な存在に出会ったとき、人は変わることを余儀なくされる。己の人生と向き合わざるを得なくなるのだ。そして登場人物たちは過去の失敗や自分自身の弱さに直面することになる。
大石大の作品に登場する人たちは弱点や欠点が多い。人によっては受け入れがたいと思うくらいの過去を持つこともあるし、作中で大きな間違いを犯すことも珍しくない。
しかし大石大は、作中で失敗した人たちを頭ごなしに否定しない。そして根拠なく肯定することもしない。各人の事情に真摯に目を向け、全てを受け止めた上で、悩み抜いた先に新たな一歩を踏み出させる。
第3話の刑事は弱さに悩んでいるが、それゆえに救える人がいる。第4話では欠落のある女性たちが互いを理解しようとする。第6話に登場するケーキ屋の夫婦は、善悪や愛憎を全て抱え込んだ上で、何とか生活を続けようともがいていく。
登場人物たちの決断に触れた読者は、きっと応援したくなるだろう。だが作者はその決意に対しても、「本当にそれでいい?」と問いかけるのを忘れない。だからこそ作品はより深い余韻を残すことになる。
昨今の風潮として、極端な意見が支持されがちだ。価値観が多様化するなかで、誰かに断定してもらうのは楽なのだろう。だがその結果、多くの分断が生まれている。
作者は善と悪、成功と失敗、正と負、そして生と死など相反する事柄について、どちらにも偏ることがないように常に考え続けていると感じる。その姿勢が作品全体に表れているように思えるのだ。
神社が与える死は、幸福に満ちている。だが本作ではそれと同じくらい、人々が生きる姿も美しく描かれている。その両方を等価値に描けることが大石大の持ち味なのだと私は思う。その独自の眼差しをもって今後どのような物語を生み出すのか、1人のファンとして楽しみでならない。