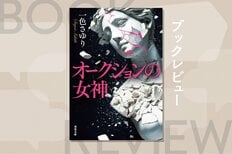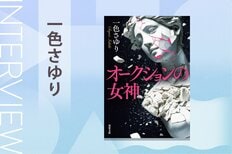人類の生んだ崇高な美を巡り、大金が動く──巨大な欲望、エゴがせめぎ合い、火花を散らす、アートオークションの世界。力を入れたオークションに「中止しなければ会場を爆破」との犯行予告が届いた。いざ、当日……予想もしない展開のなか、関係者の企み、思惑が炸裂する!!
先が気になって仕方ないページターナー作品であり、若者の成長物語でもあり、お仕事小説の側面も持つ、楽しみ方も豊富な小説。著者の一色さゆりさんに、本作に込めた思い、読みどころをうかがった。
現実の「サラリーマン・コレクター」は、素敵で常識的な方ばかり(笑)
──オークションをテーマにした小説は新鮮でした。まずは題材にオークションを選んだ理由をお教えいただけますか。
一色さゆり(以下=一色):私は以前、画廊で働いた経験があるのですが、そのときに社長のお使いで、日本のオークションハウスで入札をしたことがありました。オークショナーに向かって一人でパドルを掲げたりしたんです。そのときの心臓がバクバクと破裂しそうな感じや、ひりつくような周囲の緊張感は、いまだに鮮明に記憶しています。今回は、そういった自分の実体験を大切にしました。もちろん、オークションに関する本や記事もたくさん手に取りましたが、私自身のリアルな経験がこの本のリアリティを支えてくれていると思います。画廊時代は、社長のかばん持ちをしながら、海外のオークションハウスにもあちこち足を運んでいました。
──本書ではグランドホテル形式を取って、ひとつのオークションに絡んだ様々な人間模様を描いています。この小説の形式には初挑戦でしょうか。
一色:恩田陸さんの『ドミノ』や、辻村深月さんの『本日は大安なり』が好きで、さまざまな人のストーリーが最後に重なり合うという構造には、以前から挑戦したいと思っていました。そこで、今回「オークションの話を書いてはどうか?」と担当編集者の方と打ち合わせをしたときに、ぴったりだと思いました。オークションハウスでは数時間のあいだに沢山の作品が競売にかけられ、さまざまな人々の思惑が交差するからです。人の心理を描写するのには苦労しましたが、書いていてとても楽しかったです。
──第一章「ウォーホルの死」では、物質的には恵まれている資産家令嬢が、自分は家族から愛されていないと感じる空虚な心理が描かれます。この設定とウォーホル、およびその作品が見事に結びついていくわけですが、構想時、まずはどちらが先に題材としてあったのでしょうか。
一色:ウォーホルのほうが先にありました。アートとお金の話をするなら、ウォーホルは欠かせない存在だと思っていたからです。でもウォーホルは、Tシャツやポスターで超有名なアーティストでありながら、じつは自分の外見にコンプレックスがあったり、「死」をテーマにしたシリアスな作品を発表していたり、意外と知られていない面が多い。だから今回は、そんな知られざる側面をうまく物語とシンクロするように、資産家令嬢というキャラクター設定を考えました。
──第二章「ポロックの妻」では、実際のポロック夫妻が、冷えた関係の夫婦に投影されます。夢を見て家庭を顧みない男と、現実的な妻。共感を覚える読者が多そうですね。
一色:ポロックの人生はドラマチックで、映画にもなっています。妻だったクラズナーは同じ画家だったので、ポロックのせいでキャリアを阻まれたり、一人の画家ではなく「ポロックの妻」としか見られなかったり、夫婦の関係は複雑でした。クラズナーに愛想を尽かされたポロックはアルコールにいっそう依存して、あげく不倫相手と自動車事故を起こして他界します。一見、クラズナーは被害者のように思えますが、じつはポロックの死後、遺された作品を売却するなど遺産を受けとり、自分の画家としてのキャリアも成功させました。では、ポロックが死んで清々したのかというと、複雑だったと思います。夫を許せなかっただろうし、悲しかったでしょう。というか、クラズナーの本当の感情は誰にもわかりません。それと同じで、どちらが悪でどちらが善とか、そういった単純な図に落としこめないのが夫婦であり、リアルな人間関係だと思います。そんな夫婦の不可解さに、共感していただけると嬉しいです。
──作中には会社勤めをしながらアート収集で名を馳せる「サラリーマン・コレクター」も登場します。実際にこのような人はいるのでしょうか?
一色:海外だと、郵便局員と図書館司書だったアメリカのコレクター夫婦が有名で、『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』という映画にもなっています。日本にも、大勢いらっしゃいます。ただし現実の方々は、私の小説に出てくるよりも、もっともっと素敵で常識的な「サラリーマン・コレクター」の方ばかりだということは断っておきたいです(笑)。
(後編へつづく)