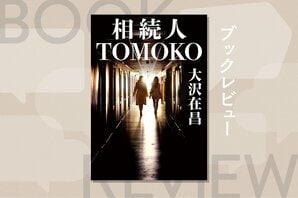朝
悪夢が現実になった。
だが、これは僕の描いていた悪夢なんかではなかったはずだ。沢辺が僕にくれたことだ。
「いつか狭いアパートの台所で刺され、血まみれになって命を落とすぜ」
よくいっていた。
僕は今、キッチンの床に横向きに倒れている。浅く、小刻みな呼吸をくり返して。
大きく息を吸うことはできない。背中の裏に麻痺したような重みがある。正確には右の脇腹の、もう少し背骨よりだ。
目の前にきちんと揃えたスリッパがある。ふかふかとした毛のついた、可愛い猫の絵がついたスリッパだ。その向こうに六畳間。
大きなダブルベッドとドレッサー、スタンドが一本。あとは何もない。
いや、ダブルベッドにひとりの人間が腰かけている。爪先が見えている。脚には何の表情もない。
その脚が膝を組んだ。
僕の脚は少しねじれている。倒れるときは、その六畳間とは反対の方角を向いていたからだ。苦痛はなかった。下半身は何の感じも、ない。
煙草の匂いがする。ふんわりと広がった煙が、台所まで届き、香りが僕の鼻にまで辿りついたのだ。
背中を動かそうとした。はっとするほどの痛みが全身に走った。声も出ない。
不思議だ。背中には何の感覚もないのに、血が流れているのがわかる。それも大量の血が。
まず上半身を起こさなければならない。そして向かいあう。ベッドの人物に。
話しかけるべきか。
命乞いをするべきか。
沢辺の予言はひとつだけちがっていた。僕を傷つけたのは包丁なんかじゃない。ちっぽけな、オモチャのようなピストルだ。
ピストルが二度、乾いた破裂音をたてるのを僕は聞いていた。そして、その音を聞いた者は他にひとりしかいないはずだ。僕を撃った人物だ。
ここには誰も来ない。銃声を聞きつけた隣人も、その隣人が一一〇番で呼んだ警官も、誰も来ない。
古ぼけ、ありふれたアパートなのだ。そして朝の十時だというのに、この部屋の他には誰もいないのを僕は知っている。出かけていないのではない。そもそも、誰も住んではいないのだ。そして、そう仕向けたのは僕を撃った人物だ。
僕達は二人きりだ。拳銃はまだ撃った人間の手に握られている。右手に銃を持ち、のんびりと煙草を吸っているのだ。
怪我は幾度もした。
歯を折られ、腕を折られ、肩の骨を折った。ライフルの台尻で殴られ、爆弾を投げつけられ、手刀でへし折られた。
だが、今ほど死に近づいてはいない。なぜなら、それらはいつも一瞬の出来事だったからだ。気がつけばすべてが終わっていた。
僕に殺意を持った人間は、その場を立ち去るか、殺意を捨てていた。
今はちがう。僕を撃った人間はそこにいて、僕が死にかけるのを見ている。喜んでもいない、恐れてもいない。ただ見ているのだ。
恐ろしかった。死にかけている自分を感じていて、逃げることは疎か、叫ぶことも涙を流すこともできない。あるのは麻痺、それだけだ。頭だけが目まぐるしい速さで動いている。あまり速いので何に考えを絞ればよいのかわからない。
沢辺、悠紀、早川法律事務所の調査二課長、今まで会った依頼人、捜し出した失踪人、調査の途中で関わった人々。男、女、老人、若者、子供。
それからひとりの男に行きついた。
岡江、僕にいった。警告した。
**
依頼人は小島という名の小柄な男だった。流行の紺の六つボタンブレザーにグレイのスラックス、それだけが流行の規格に外れた幅広のタイ。黒のタッセルシューズは磨きぬかれて厭らしいほど光っていた。
これだけのいでたちに茶のアタッシェケースを抱えてやって来た。それでも彼はどこか小狡げで貧相に見えた。頭が薄く禿げかけていて、それを隠すためか襟あしを長くのばしている。左手の小指に赤い石をあしらった指輪をはめ、マイルドラークに金のカルチェで火をつけるような、そんな貧相な男だった。
彼が早川法律事務所の応接室のテーブルにのせた名刺には、
「ハマ・プロダクション、芸能部企画室長」
と記されていた。その名刺は、宝くじにも似た夢を抱く若者には魔法のような効果を与えるにちがいない。僕や調査二課長に同じような反応を期待したとは思えないが、彼はことさら大事そうに名刺を置いた。名刺の角とテーブルのへりがぴったりと合うようにのせたのだ。
喋り方は、元来せっかちな人間が鷹揚に見せようと努力しているような、そんな聞きづらさを感じさせた。そのせいか口中に唾液がたまり、湿った発音になる。
「うちの若くて有望な新人タレントを捜していただきたく、参上しました」
言葉の使い方までが嫌味だった。
「漂泊の街角 〈新装版〉失踪人調査人・佐久間公 3」は全3回で連日公開予定