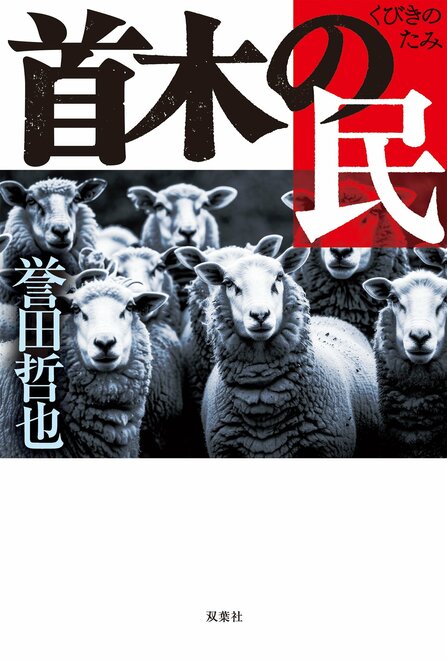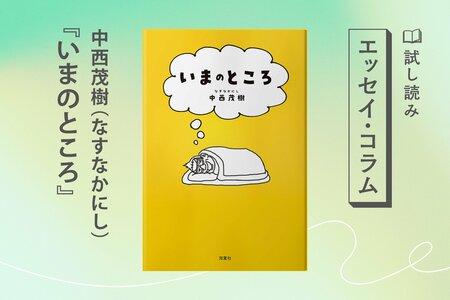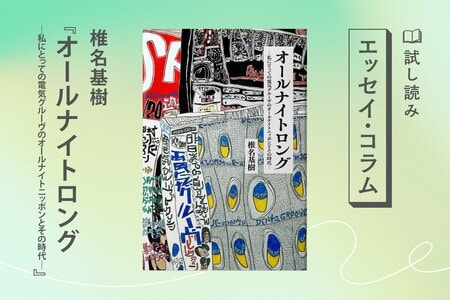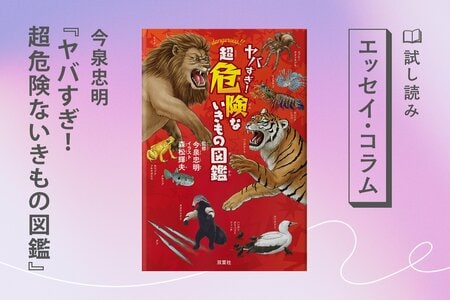元財務省官僚の大学の客員教授が窃盗と公務執行妨害の容疑で逮捕されたが、「公務員を信用していない」と言い、取調べは進まなかった。前代未聞! 取調室が教室に?
なんだ、それは。
「はい?」
「もう一度申し上げた方がよろしいですか。私は、ありとあらゆる公務員を信用しておりません」
意味は分かる。だが、今それを口にする理由が分からない。
「なぜ、ですか」
「むろん、その理由を説明することは可能ですが、かなり長い話になると思います。その話が終わる頃には、佐久間担当係長も私があらゆる公務員を信用しない理由を理解されることと思いますが、その時点で佐久間担当係長は果たして覚えておられるでしょうか。私が、ありとあらゆる公務員を信用しないと発言した、この状況を」
待て。全然分からない。
「え、ですから、なぜ、公務員を信用しないのか、その理由を、お尋ねしているのですが」
「その理由を説明することはむろん可能ですが、私が、ありとあらゆる公務員を信用しないと発言した、まさに今の、この状況を覚えているでしょうか、とお尋ねしているのです。別の言い方をすれば、私が今さっき、ありとあらゆる公務員を信用しないと発言したのには、それなりの理由があるということです」
分かった、ような気がするが、果たして、これで合っているだろうか。
「久和さんが、今、公務員を信用しないと言った、理由ですか」
「そうです。今のこの、状況が重要なのです。文脈と言い替えてもいい。『畑仕事を終えたので足を洗う』というのと、『この逮捕を機会に泥棒稼業から足を洗う』というのとでは、『足を洗う』という言葉の意味が変わってしまいます。それと同じで、私が公務員を信用しない理由を今ここで説明するより、私が公務員を信用しないから、だからなんなのか、ということを、先に申し上げておいた方がよいのではないかということです」
もういい。それでいい。
「ええ、ではお伺いします。なぜ、そのような事を今、仰ったのですか」
「私は、今回逮捕された件に関して、一切の供述をいたしません。しかしそれは、自己に不利益になるから供述しないのではありません。あらゆる公務員を信用しないから、むろん警察官も公務員ですので、警察官も信用しない。信用できない。だから、供述をしないということです。お分かりになりましたか」
分かった、と思う。
「自己に不利益だから供述しない、のではなく、警察官が信用できないから、供述しないと」
「仰る通りです」
「でも、公務員を信用しない理由は、お話しいただけるんですよね」
久和が目を、ほんの一ミリくらい、大きくした。
「……ええ。理由をお話しすることは、吝かではありません」
今のやり取りで、一つ分かったことがある。
久和は決して、平気で嘘をつく人間ではない、ということだ。今後、ひょっとしたら嘘をつく場面もあるのかもしれないが、基本的にはそれを良しとしない性格、とでもいおうか。
公務員を信用しない理由は説明可能、と自身で発言した以上、自分にはその説明責任が生ずる、と考える人間のようだ。
この取調べ、案外簡単に終わるかもしれない。
「では、改めてお願いします。公務員を信用しなくなった、その理由をお聞かせください」
久和が、小さく二度頷く。
「分かりました。ご説明しましょう。長くなりますが、本当に構わないんですね」
全く構わない、ことはない。実質、今日一日の取調べだけで検察官送致に持っていかなければならないのだから、できれば無駄話には付き合いたくない。しかし、一切の供述はしないと宣言されてしまった以上、それがどんな内容の話であろうと、自発的にしてくれるのであれば、聞かないよりは聞いておいた方がいい。
「構いません。お話しください」
すると、久和はまた長めの息を吐き出し、深く頷いた。
「……分かりました。ではまず」
もうこの時点で、取調べが取調べではなくなっているのを感じる。久和先生から、大変貴重な講義を受けているような気がしてきている。
「佐久間担当係長は」
「すみません。私からも一つ、よろしいですか」
よほど佐久間の制止が意外だったのか、久和はさも不快そうに眉をひそめた。
「……なんでしょう」
「丁寧にお話しいただくのは大変ありがたいのですが、毎回毎回、『佐久間担当係長』とお呼びいただかなくてけっこうです。名前でも、なんなら担当だけでもいいんで。そこは短めにお願いします」
なんで取調官が被疑者にお願いばかりしなきゃならないんだ、と思わなくもないが、まあいい。最終的に「私がやりました」と頭を下げさせることができれば、取調官としてはそれでいい。
久和も、無駄に話を長くするつもりはないらしい。
「分かりました。では『佐久間さん』ということで」
「はい、恐れ入ります」
「佐久間さんにとって、お金とはなんですか」
いきなりクイズか。
「お金、というのは……貨幣とか、紙幣とか、そういうことですか」
「それもそうですが、それだけですか」
「あと、最近だと、デジタル通貨とか」
「デジタル通貨とは、なんのことを指して仰っていますか」
「なんのこと……ああ、正式には『暗号通貨』って言うんでしたっけ」
「では、佐久間さんが考える『お金』というのは、貨幣と紙幣と暗号通貨ということでよろしいですか」
改めてそう言われると、自信はない。
「何か、漏れてますかね」
「いろいろ漏れています。でもそれは、あと回しにしましょう。もっと根本的な、佐久間さんにとっての『お金』ではなく、そもそもお金とはなんなのか、というお話からいたしましょう」
まただ。取調べが「講義」に変容していくのをひしひしと感じるが、ここはしばし辛抱か。
いま久和の目は、真っ直ぐ佐久間に向いている。
「これはお金の、つまり通貨の歴史をお話しするのではなく、あくまでも概念を共有するためのたとえ話とご理解ください」
「はい、たとえ話」
「言うまでもありませんが、人はその昔、物々交換をしていました。仮にこの世界には我々三人しかいなくて、私は米を、佐久間さんは肉を、横澤さんは芋を生産しているものとします。各々は創意工夫をし、より良い物を、より多く生産しようとします。しかし、いずれも食べ物なので、食べきれないほど作っても仕方がない。あるいは、同じ物ばかり食べていたら飽きてしまう。そこで、我々は物々交換を始めます。私の米と佐久間さんの肉、私の米と横澤さんの芋、佐久間さんの肉と横澤さんの芋を、最初は各々の感覚で、米ひと升と芋三本とか、互いが納得できる割合で交換します」
なんだか、お伽噺でも聞いているような気分だ。
しかし、話している久和の表情は至って真面目だ。
「ところが、実際の世界にはもっと多くの人がいるし、物も多く溢れています。三人だけの世界だったとしても、横澤さんは葉物野菜も作り始めるかもしれないし、佐久間さんだって、複数種類の獣の肉を扱うようになるかもしれない。すると、何と何を、どれくらいの数量で交換するのかという交渉が、加速度的に複雑になっていく。私の米と横澤さんの芋は交換可能だったのに、私の米と横澤さんの白菜は、何対何で交換したらいいのか、それを別途交渉しなければならなくなる。交渉の末、納得がいかなかったら交換そのものが成立しなくなってしまう。これを解消するために生まれたツールが、お金ということです。つまりは通貨です」
分かる。さすがにこれくらいは理解できる。若干馬鹿にされている気もしないではないが、理解できたこと自体は素直に嬉しい。
がしかし、困る。
これは、どう考えても取調べではない。
この続きは、書籍にてお楽しみください