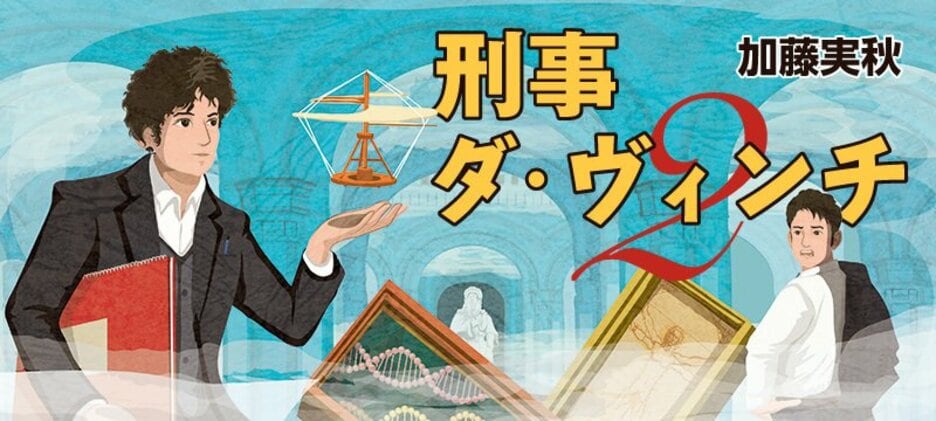7
翌日。時生と南雲は夜勤だった。警視庁の警察官は四交替制で、日勤にあたる第一当番、夜勤にあたる第二当番、夜勤明けの非番、休日を繰り返している。夜勤の日は午後三時半出勤だが、時生は午前十時に一旦署に行き、外出した。
最寄り駅から電車に乗り、中野坂上にある綾部美桜の自宅に向かった。地下鉄を降りて伊東真佑に教わった住所を頼りに、左右に住宅が並ぶ一方通行の狭い通りを進む。目当てのアパートは軽鉄筋の二階建てで、建物の外には鉄製の階段が取り付けられている。敷地の脇から覗くと、二階の端にある美桜の部屋のベランダでは、アジア系の外国人の女性が洗濯物を干していた。と、通りの先から南雲が歩いて来た。ここで落ち合い、聞き込みをする予定だ。
「お疲れ。このアパートの何部屋かは、いわゆる民泊に貸し出してるんだって。美桜が住んでたのもその一つで、先月末にチェックアウト済み」
「よくわかりましたね。民泊の運営会社に訊いたんですか?」
「うん。美桜の知人だって言ったら怪しまれたけど、運営会社の社長は年配の女性で、僕のスケッチブックに興味を示したんだ。だから『似顔絵をプレゼントします』って言って、三割増しで美人に描いてあげたら大喜びで話を聞かせてくれたよ。でも、『孫の似顔絵も描いて送って』って頼まれちゃったけどね」
朗らかに語り、南雲は片手で表紙が深紅のスケッチブックを持ち上げ、もう片方の手に握った青い鉛筆で通りの後ろを指した。「ははあ」と時生が返すと、こう続けた。
「美桜は部屋を四カ月借りて、家賃は現金で前払いだって。綾部美桜名義で借りたそうだけど、運営会社は身分証などの提示は求めなかったらしいよ」
「わかりました」
似顔絵を描きながら聞き出したのか。適当なようでいて、やる時はやるんだよな。時生がつい感心すると、
「てな訳で、ここには手がかりはない。行こう」
と促し、南雲は通りを駅の方に歩きだした。
大通り沿いに並ぶコンビニやファストフードショップ、クリーニング店などで美桜の写真を見せ、話を聞いた。しかし返事は、「見たことがない」「覚えていない」だった。
「美桜は詐欺目的で婚活アプリに登録し、アパートまで借りたんでしょう。用意周到で警戒心も強そうだし、この辺りの店は利用していないかも。アプリの運営会社に問い合わせれば身元が割れるかもしれないけど、非公式な捜査だしなあ」
通りを歩きながら、時生は言った。隣で南雲が応える。
「白石さんが言ってた通り、こっちがやることをやれば、伊東さんも諦めが付くでしょ……あの店に入ろうよ。喉が渇いちゃった」
そう告げて、通りの先のドラッグストアに向かう。真夏日で、歩いていると首筋が日焼けしていくのがわかった。
南雲に続き、時生もドラッグストアに入った。広い店内には棚が並び、薬や化粧品、生活雑貨が陳列されている。その中に「特価! お一人様一点限り 208円」のポップが付いた五箱パックのティッシュペーパーを見つけ時生が心を動かされていると、南雲がやって来た。
「新製品のジュースがあったよ。小暮くんも飲むよね? 僕はレモン味で、小暮くんはケール味ね。後で一口ちょうだい」
目を輝かせて告げ、手にした二本のペットボトルを見せる。時生は、
「飲みますけど、ジュースよりお茶の方が。しかもケール味って」
と返したが、南雲はいそいそと奥のレジに向かった。仕方なく、時生も続く。
「いらっしゃいませ」
レジの中で店員が会釈をした。べっ甲風のフレームのメガネをかけた中年男で、スタンドカラーの白衣風のユニフォームを着ている。ペットボトルをカウンターに置き、南雲は店員の男に微笑みかけた。
「どうも。暑いですね」
「本当にねえ。今年も猛暑らしいですよ」
大袈裟に眉根を寄せ、レジのリーダーでペットボトルのバーコードをスキャンしながら男が応える。代金を支払ってペットボトルを受け取ると、南雲は言った。
「人捜しをしてるんだけど、この女性を知ってます?」
ジャケットのポケットからスマホを出し、男の前に差し出す。そこには美桜の写真が表示されている。写真を見た男は、思わずといった様子で「ああ。この人」と頷いた。しかし時生が「ご存じですか?」と身を乗り出すと、警戒した様子で問い返した。
「あなたたち、何なんですか?」
すると南雲は男に笑顔を向けたまま、肘で時生の腕を突いた。仕方なく、時生は一旦署に行った時に持って来た警察手帳をポケットから出す。それを見た男は、納得したように答えた。
「このところお見かけしませんけど、お得意様ですよ。週に一、二回来店して、たくさんお買い上げいただきました」
「どんなものを買いましたか?」
「詳しくは覚えていませんけど、とにかく一度にドカッと──うちのメンバーズカードを作って下さったので、調べればわかると思います」
「お願いします」
時生は促し、男はカウンターの中のタブレット端末を手にした。間もなく、男は「多分、この方ですよ」とタブレット端末の画面を見せた。
そこには表があり、上に会員番号と名前、下に来店日と時間、購入した商品、代金などが表示されていた。確かに三カ月前から週に一、二回のペースで来店し、毎回一万円近く買い物をしている。登録された名前が「田中あかり」となっているのに気づき、時生も美桜の写真を見せて問うた。
「この女性で間違いないですね?」
男が「ええ」と頷いたので、会員データをプリントアウトしてもらい、礼を言ってドラッグストアを出た。
その後、ドラッグストアに絞って聞き込みを続けた。結果、美桜は中野坂上駅近辺の他のドラッグストアでも週に一、二回来店し、一万円近く買い物をしていた。
「他の店でもメンバーズカードを作ってるけど、名前は『佐藤真澄』に『佐々木ちひろ』『鈴木利恵』。田中あかりと綾部美桜を含め、偽名でしょうね」
脱いだスーツのジャケットを膝に載せ、時生はため息をついた。聞き込みを終え、駅近くの広場のベンチで一休みしている。返事がないので隣を見ると、南雲は手にした紙を眺めていた。他のドラッグストアでもプリントアウトしてもらった、美桜の会員データだ。
「僕にわかるのはシャンプーぐらいですけど、美桜はどの店でも化粧品を買い込んでいるようですね。その割に伊東さんは『美桜はナチュラルメイクだった』と話してたし、写真もそんな感じですよね」
そう続け時生は首を傾げたが、南雲は顔を上げて言った。
「署に行こう」
美桜の会員データをスケッチブックに挟み、立ち上がって歩きだす。慌てて、時生も続いた。
8
楠町西署に着いたのは、午後一時前だった。駐車場で待っていると、すぐに剛田力哉がやって来た。制服姿の若い女性署員も一緒だ。南雲は二人に「やあ」と手を振り、時生は頭を下げた。
「呼び出してごめんね」
「いえ。夜勤明けで帰るところだったので」
にこやかに剛田が返し、女性署員も、
「私も今日はこれから昼休みなので、大丈夫です」
と応え、手にした小さなトートバッグを持ち上げて見せた。瀬名花蓮といい、刑事課で事務を担当している巡査だ。
「で、持って来た?」
南雲が訊き、剛田は「ええ」と返し、ポケットからキーを出して傍らの白いセダンに向けた。電子音がしてドアが解錠され、南雲と剛田、瀬名が後部座席に乗り込み、時生も周囲を確認してから運転席に乗った。
広場から中野坂上駅に行き電車を待つ間に、南雲は誰かに電話をかけた。話の内容から、時生は電話の相手が剛田で、四十分後に刑事課の車のキー持参で、瀬名も連れて駐車場に来てと頼んでいるとわかった。電話を切った南雲にどういうことかと訊ねたが、「すぐにわかるよ」としか答えてくれなかった。
「これを見て。ある女性がドラッグストアで買ったものなんだけど、解説して欲しいんだ」
南雲は告げ、スケッチブックから美桜の会員データを出して隣の二人に渡した。それを聞き、時生は南雲の意図が読めた。趣味は美容だという剛田は化粧品や美容法に詳しく、瀬名も以前、メイク雑誌と化粧品のパンフレットを持っているのを見たことがある。
会員データに目を通しながら、剛田が言った。
「コスメを爆買いしてますね。この人、かなりのフリークですよ」
「しかも研究熱心。新製品や話題のアイテムは網羅してます。ドラッグストアで買える、プチプラだけど優秀なアイテムばっかりです」
感心したように、瀬名もコメントする。「ふうん」と呟き、南雲は問うた。
「買ったコスメで、どんなメイクができるの? 具体的に教えて……小暮くんはメモ」
訳がわからないまま時生は「はい」と返し、ポケットから手帳とペンを取り出した。
「そうですね……わかりやすいのは、アイテープ。接着剤付きの透明で細長いテープで、まぶたに貼るとくっきりした二重まぶたがつくれます」
会員データの一箇所を指し、剛田が答えた。運転席からそれを見る時生の頭に美桜の顔写真が浮かび、そう言えば一重または奥二重の厚ぼったいまぶただったなと思い出した。
「こっちのお店では、バーガンディーのアイライナーとライトブラウンとダークブラウンのアイシャドウを買ってます。目頭と目尻の脇にアイライナーで細く線を引いて、ライトブラウンのアイシャドウを上まぶた全体、ダークブラウンを上まぶたの黒目の上あたりに塗ると、切れ長でぱっちりした印象の目になるんですよ」
瀬名も言い、指先をまぶたの上で動かして見せる。
「なるほど。バーガンディーは目の粘膜と馴染みのいい色だから、自然に見えるね」
南雲が返し、瀬名は「そうそう」と首を縦に振る。一方時生は、化粧品メーカーだろうと思っていたバーガンディーが、色の名前らしいと気づく。と、瀬名が声を上げた。
「あっ。星花堂の涙袋ライナーを買ってる。これ、便利なんですよね」
「涙袋っていうのは、下まぶたの下の膨らみのことです。星花堂のアイライナーで影を付けると、ぷっくりしてキュートな涙袋がつくれるんです」
すかさず、剛田が解説する。その間に瀬名は膝に載せたトートバッグからメイクポーチを取り出し、細長いスティックを掴んで「私も使ってます」とかざした。スティックの先端に付けられた透明のキャップ越しに、細い筆のようなものが見える。それを眺めながら、時生は訊ねた。
「涙袋って、ぷっくりしてるとキュートなの?」
すると瀬名と剛田は声を揃え、「もちろんです!」と即答した。
その後も剛田たちの解説は続き、会員データにあったハイライトとノーズシャドウ、細めのフェイスブラシを使うと鼻を高く、小鼻を小さく見せられること、リッププランパーとリップコンシーラーを使うと、艶やかでふっくらした唇をつくれること、さらにリフトアップテープを顎の脇や耳の後ろに貼ると、小顔に見せたり、シワとたるみを隠したりする効果があることがわかった。それに対して時生は驚いたり感心したりしながら手帳にメモし、南雲はふんふんと頷いていた。
三十分ほどで話を聞き終え、南雲は「お礼にランチを奢るよ」と瀬名とともに署の五階にある食堂に向かい、時生は警視庁の独身寮に帰るという剛田を見送るため、署の門まで歩いた。
「ありがとう。助かったよ。事情があって、詳しいことは話せないんだけど」
「大丈夫です。訊かれたから答えただけなので」
あっさりと、剛田は返した。少し戸惑ってから、時生は訊ねた。
「本当に美容が好きなんだね。ちなみに、剛田くんもメイクをするの?」
「もちろん……でも、勤務中はノーメイクですよ。スキンケアと日焼け止めだけ」
「ははあ」
時生が間の抜けた相づちを打つと、剛田は、
「また役に立てそうなことがあれば言って下さい。小暮さんと南雲さんには、お世話になりましたから」
と言い、「お疲れ様です」と会釈して門から出て行った。少し前、時生たちは剛田に頼まれ、あるユーチューバーの女性を巡る事件を捜査した。
見た目や言うことは今どきの若い子なんだけど、義理堅くて熱いところもあるんだよな。そう思いながら時生は「お疲れ」と返し、細身のスーツに包まれた剛田の背中を見送った。
9
同じ日の午後九時。時生と南雲は、楠町西署二階の刑事課にいた。部屋の手前に置かれた打ち合わせ用のテーブルに、本庁科学捜査研究所の野中琴音と向かい合って着いている。
「山口直江の事件ですが、特別捜査本部はヘビやトカゲ、虫の入手ルートからリプロマーダーに辿り着けないかと考えたようです。でも販売店やブリーダーを洗っても、これといった手がかりは得られていないとか」
硬い表情で、野中は報告した。たっぷりとしたつくりのベージュのパンツスーツに、どこかのバンドのグッズと思しき、モヒカン頭の男がマイクを手に大きく口を開けたイラストの描かれたTシャツを合わせている。
僕と南雲さんの予想通りだなと思いつつ、時生は「そう」と返した。隣の南雲は左手に青い鉛筆を握り、テーブルに載せたスケッチブックに何か描いている。広い部屋にいるのは当番の時生たちと野中だけで、天井の照明も奥半分は消されている。野中は今夜、リプロマーダーと相対した唯一の人物である時生に改めて話を聞くという口実でここに来た。
「で、琴音ちゃんのプロファイリングは?」
スケッチブックに目を落として手を動かしながら、南雲は問うた。日本の警察官は右手で拳銃を持つように義務づけられているため、彼のような左利きは珍しい。野中が答える。
「犯罪のカテゴリーとしては、劇場型。舞台は東京の街で、主役は犯人、被害者が脇役で警察は敵役、それをマスコミや市民が見物するという構造が典型的です。山口もこれまでの四人同様いわゆる悪人なので、ネットなどでは『現代の仕置き人が帰って来た』『ダークヒーロー再降臨』などと騒ぐ動きもみられます」
南雲は手を止めずにふんふんと頷き、野中は続けた。
「いわゆるシリアルキラーに分類され、犯人像としては秩序型。高い知能とコミュニケーション能力を持ち、裕福で社会的地位も高い。三十代から五十代の男性で、共犯者がいる可能性もあります。シリアルキラーには四つのタイプがあると言われていて、リプロマーダーはこのうちの快楽主義者と考えられますが、悪人をターゲットにしているところは、自分は社会の悪を正していると自己を正当化する使命、すなわちミッション系の傾向もあり、さらなる分析が必要です」
「マニュアル通りだね。美しくない」
話を聞き終えるなりきっぱりと、南雲は告げた。唖然とした野中だったがすぐに息をつき、「南雲さんの『美しくない』、十二年ぶりに聞いたわ」と呟いた。フォローのつもりで、時生も口を開いた。
「リプロマーダーが犯行を再開したなら、新たな被害者が出ないようにしないと。また悪人を狙うんだろうから目星をつけて警護しながら張り込み、リプロマーダーを待ち伏せするんだ」
「もちろんそれは捜査本部も考えてるけど、いわゆる悪人が東京だけでもどれだけいると思う? 育児放棄、保険金殺人、パワハラ、婦女暴行と、被害者が関わった犯罪はばらけているから、いま私と同僚のプロファイラーがリプロマーダーは次にどんな犯罪を選びそうか、それに該当する絵画はあるかをリサーチしているところよ」
タメ口になり、野中が返す。すると南雲は一旦手を止めて「ますます美しくない」と呟き、また手を動かし始めた。時生は訊ねた。
「どういう意味ですか?」
「リプロマーダーはアートを愛し、造詣も深い人物だよ。根拠は、選んだ絵画の再現度の高さ。それに有名無名を問わず、人間の死をモチーフにした優れた絵画を選んでいるところも。思うに、リプロマーダーは罪に絵画を当てはめるんじゃなく、再現しようと決めた絵画にふさわしい罪、悪人を選んでいるね」
自信に満ち、かつリプロマーダーを称賛するようなその口調に、野中は呆れ顔になる。一方時生は胸が騒ぎ、隣に身を乗り出して語りかけた。
「それ、十二年前にも言っていましたよね。でも特別捜査本部では取り合ってもらえず、南雲さんは独断で絵画をピックアップし、僕が悪人を選んだ。でも、悪人の家に駆け付けると彼は殺された後で、そこにいたリプロマーダーらしき人物は逃げた。南雲さんが応援を呼んでいる間に僕はそいつを追いかけたけど、襲われて取り逃がしてしまった」
知らず早口になり野中の視線を感じたが、構わず南雲の横顔を覗いた。すると南雲は再び手を止め、こう応えた。
「ああ、そうだったね。エドゥアール・マネの『自殺』。四人目の被害者だ」
口調も表情も呑気で、他人事のようだ。苛立ちを覚えた時生だが、絶好のチャンスと斬り込んだ。
「ええ。被害者は救えなかったけど、僕らの読みは当たっていたんです。なら、次の犯行は? 南雲さんがリプロマーダーだとしたら、どんな絵を再現したいですか?」
極力さりげなく、とくに「南雲さんがリプロマーダーだとしたら」と言う時には気をつけたつもりだ。と、南雲が時生を見た。胸がどきりと鳴って時生が緊張した直後、南雲は、
「いい質問だね」
と言い、にっこりと笑った。「どこが?」と野中は突っ込んだが、時生はその笑顔の屈託のなさに強い疑惑を覚えた。笑顔のまま、南雲は続けた。
「でも、教えない。事件の捜査や推理ってすごくクリエイティブで、創作活動に近いと思うんだよね。だとすると、僕は創作の過程は公にしない主義で」
とたんに落胆し、時生は返した。
「またそれですか。説明してもらわなくても、何度も聞いて覚えてますよ」
「琴音ちゃんは初めてでしょ」
「十二年ぶりだけど、初めてじゃありませんよ……ていうか、さっきから何を描いてるんですか?」
そう問いかけ、野中は首を突き出して南雲のスケッチブックを覗いた。つられて時生も覗くと、女の顔らしきものが描かれている。スケッチブックを持ち上げて向かいに見せ、南雲は問い返した。
「美人でしょ?」
「ええ。誰ですか? まさか、南雲さんの彼女?」
野中はさらに首を突き出し、南雲は「さあ」と笑う。うんざりして、時生は言った。
「昼間話してたやつでしょ? 民泊を運営してる会社の社長に頼まれた、孫の似顔絵」
「民泊? 何それ」と野中が騒いだので、時生は「話の続きなんだけど」と軌道修正した。
野中が真顔に戻り、南雲もスケッチブックを下ろす。
南雲さんは「でも、教えない」とはぐらかしたけど、僕が「リプロマーダーだとしたら?」と訊いた時、笑うのと同時に目が鋭く光っていた。そう思い返し、時生は手応えと興奮を覚えながら話を続けた。
10
翌朝十時。日勤の刑事と交代して、時生と南雲の当番勤務は終わった。帰り支度をしていると、南雲のスマホが鳴った。あくびを堪えながら電話に出た南雲は二言三言話して通話を終え、時生に「中野坂上に行こう」と告げた。訊けば、電話の相手は昨日最初に聞き込みをしたドラッグストアの店主で、念のため連絡先を伝えたところ、たまに行くカフェで美桜を見かけたことがあるのを思い出した、と報せてくれたらしい。
電車を乗り継ぎ、中野坂上に移動した。目指す店は「ヒルトップカフェ」といい、山手通り沿いにあった。広くはないがウッドデッキを備え、通りに面した壁はガラス張りと開放的な雰囲気だ。ドアから入店すると、「いらっしゃいませ」と女性の店員が声をかけてきた。スポーティーな雰囲気の美人で、すらりとした体に白いシャツとジーンズをまとい、黒い胸当てエプロンを付けている。歳は三十代半ばか。
女性の店員に「お好きな席にどうぞ」と促されたので、時生たちは通路を進んだ。フローリングの床のあちこちに背の高い観葉植物の鉢植えが置かれ、並んだ白いテーブルには、早めのランチを摂りに来たらしいOL風の女性が何人か着いていた。
「主な客は、近所の住人とオフィスで働いている人。常連も多そうですね」
奥のテーブルに落ち着き、時生は言った。今日も暑いのでエアコンの冷気が心地いい。一方南雲はテーブルにスケッチブックを置き、メニューを取って眺めだした。
「やった、ガレットがある……知ってる? フランスのブルターニュ地方の料理で、薄く丸く焼いたそば粉の生地に、ハムや卵、チーズを載せて正方形に折り畳むんだ」
「要はクレープでしょ? ていうか、食事するつもりですか? まずは聞き込みでしょう」
時生は咎めたが南雲は、「違うよ。クレープは小麦粉だし、両面を焼くでしょ。でもガレットは片面だけを」と語りだした。そこに、さっきの女性の店員がトレイを抱えてやって来た。彼女がテーブルにおしぼりと水のグラスを置くのを待ち、時生は口を開いた。
「コーヒーとカフェラテを。それと、この女性を捜しているんですがご存じですか?」
そう訊ね、スマホの画面に表示させた美桜の写真を見せる。「さあ」と首を傾げた女性の店員だったが、写真を見直し「ひょっとして」と呟く。時生はさらに言った。
「突然すみません。この女は会社の同僚なんですが、連絡が取れないんです。この近くに住んでいたので話を聞いて回っていたら、駅前の『カインドドラッグ』の岡部さんがこちらで彼女を見かけたと教えて下さいました」
「ああ、岡部さん……そうですか。これ、カンナちゃんですよね?」
頷いてから、女性の店員は問うた。ここではカンナと名乗っていたのかと思いつつ、時生は「ええ」と返す。すると女性の店員は、「ちょっと待って下さい。店長を呼んで来ます」と告げて歩き去った。
間もなく、奥から店長の男がやって来た。背が高く彫りの深い整った顔立ちで、浅黒い肌にシルバーのピアスやネックレスが似合っている。歳は四十手前か。女性の店員と同じエプロンを着けているが、調味料などがはねているので調理担当か。左手の薬指に女性の店員とペアの指輪をはめているので、夫婦でここを切り盛りしているのだろう。
時生が立ち上がって頭を下げると、店長の男も会釈した。
「事情は伺いました。カンナちゃんは常連さんでしたけど、世間話程度しかしたことないんですよ。しばらくいらしていませんし」
眉根を寄せ、申し訳なさそうに言う。「そうですか」と落胆の表情をつくりながら、時生は質問を続けた。
「しばらくというのは、三カ月ぐらいですか? でしたら、僕らがカンナさんと連絡が取れなくなった時期と重なります」
「どうだったかな」
店長の男が首を傾げた時、コーヒーとカフェラテが載ったトレイを抱えた女性の店員がやって来て答えた。
「その通りです。最後に来てくれたのは四月末、ゴールデンウィークの前でした」
「ふうん」
南雲が呟き、時生も胸に引っかかるものを覚えた。しかし「わかりました」と返し、質問を続けた。
「最後に来た時、カンナさんは何か言っていませんでしたか? どこに行くとか、何をするとか」
「いいえ。でも、挨拶はしてくれました。『もう来られなくなりました。ありがとうございました。さようなら』って」
今度は店長の男が答え、南雲も会話に加わった。
「奥さん。写真を見た時、最初は誰かわからず、少ししてカンナさんだと気づきましたよね? あれはひょっとして、メイクのせい?」
「ええ。うちに来てくれる時はいつも可愛くメイクして、髪もアレンジしていたので。写真は、ほとんどすっぴんだったでしょう?」
「そうですか。ありがとう」
朗らかに答え、南雲は「ガレットのランチセットを二つ下さい」とメニューを指してオーダーした。
昼食を摂りながら、店主夫妻に話を聞いた。夫妻は鈴鹿英雅、優美花といい、六年前にヒルトップカフェを始めたそうだ。美桜はここでは「平野カンナ」と名乗り、近くの会社で働いていると話したらしい。いつも一人で来てランチやお茶をしていくだけだが、今年の初めから週に三、四回は通っていた模様だ。
一時間ほどで、時生たちはヒルトップカフェを出た。駅に通じる坂を上り始めながら時生が口を開こうとすると、先に南雲が言った。
「ヒルトップカフェを張り込んでみよう」
「僕も同じことを考えてました。鈴鹿優美花は、美桜が最後に来たのはゴールデンウィークの前と言いましたけど、常連とはいえ、繁盛店で女性客が多いのにはっきり覚えてるのは不自然です」
そう捲し立てた矢先、ジャケットのポケットでスマホが鳴った。取り出して見ると、画面には「伊東さん」とあった。立ち止まってスマホを構え、時生は応えた。
「小暮です」
「伊東ですけど、どうですか? 美桜がどこにいるかわかりましたか?」
勢いよく、伊東が問いかけてきた。病院の外にいるのか、車の音が漏れ聞こえてくる。
「まだ二日ですから。でも、わかったこともあります。中野坂上のヒルトップカフェという店はご存じですか?」
「知りません。そこがどうかしたんですか? 美桜が──」
と、伸びて来た手にスマホを奪われた。振り向いた時生の目に、スマホを耳に当てる南雲の姿が映る。時生が口を開くより早く、南雲は言った。
「伊東さん。あなたにレオナルド・ダ・ヴィンチのこの言葉を贈りましょう。『最高の愛は、相手を深く認識することから生まれる。もしあなたが相手を正しく認識していないなら、ほとんど、いや、まったく愛せてはいないだろう。また、もしあなたが相手を愛する理由が自分の欲望を満たすためで、美徳のためでないなら、あなたは犬と同じだ。犬は骨をくれるかもしれない人には後ろ脚で立ち上がり、尻尾を振って歓迎するものだから』」
一瞬の間があって、時生のスマホから伊東が憤慨する声が流れた。時生はスマホを取り返そうとしたが、南雲は「じゃ」と告げて電話を切った。そして時生にスマホを返し、「張り込みは今夜からやろう。車を用意して連絡して」
と告げ、車道に向き直った。そしてタクシーを停め、時生に手を振って後部座席に乗り込んだ。呆気に取られ山手通りを遠ざかって行くタクシーを見ていた時生だが、閃くものがあり、後続のタクシーを停めた。後部座席に乗り込むと運転手に南雲のタクシーを追うように告げ、シートベルトを締めた。
11
三十分ほど走り、南雲が乗ったタクシーは千代田区の神田神保町で停まった。この辺りは書店街で、広い通り沿いに大小の古書・新刊を売る店が並んでいる。南雲はタクシーを降りて歩道を歩きだし、時生も少し間を空けて倣った。
少し歩き、南雲は一軒の書店に入った。歴史を感じさせる石造りのビルで、ガラスのドアの周りには紐で縛られた本が山積みにされ、「近代西洋絵画全集全5巻 5000円」「クリムト 画集初版 3500円」といった短冊がぶら下げられている。その間を抜け、時生も入店した。
天井が吹き抜けの広いフロアに棚が何台も並び、そこに画集や写真集、学術書などが詰まっている。美術書専門の古書店らしく、洋書も多い。カビと埃の臭いをはらんだ空気が鼻を突いたが、南雲はその空気を楽しむように通路に立ち止まり、深呼吸している。
「南雲さん、いらっしゃい。この間、古閑塁さんが来てくれたんだよ」
語りかけながら、奥から店主らしき年配の男性が出て来た。南雲はにこやかに「どうも」と返し、二人は話しながら通路を進んで行った。平行して走る隣の通路に移動し、時生も続く。薄暗くしんとした店内には、他にも数人の客がいた。
通路の端まで行き棚の間から覗くと、南雲は年配の男と談笑しながら時々立ち止まり、スケッチブックを脇に挟んで棚から本を抜き取った。そして本をぱらぱらと読み、「これを買います」と言うように年配の男に渡してまた歩きだした。
時生の頭には昨夜、野中と三人で交わした会話があり、南雲が何らかの動きを見せるかとここまで尾行して来た。しかし南雲は年配の男と談笑し続け、選んだ本もリプロマーダー事件とは関係がなさそうな画集や学術書ばかりだった。
しばらくして南雲が選んだ本は十冊ほどになり、年配の男はそれを抱えてレジカウンターに向かった。一方南雲は店内を進み、奥の壁際に設えられた階段で二階に上がった。時生も続くと、二階にも本棚と通路が並んでいた。南雲の姿は前方の壁際に設置された棚の前にあり、画集らしき大判の本を手に取って眺めている。一台後ろの棚の陰からそれを覗き、時生は小さく息をついた。
あの画集も、リプロマーダー事件とは無関係だろうな。人に「車を用意して」とか言って、自分は優雅にショッピングか。そう思い、がっかりするのと同時に夜勤の疲れを感じた。家に帰って夜のために休もうと決め、最後の確認のつもりで南雲を見てはっとした。
この店は、通りに面した壁がガラス張りになっている。そこからは柔らかな外光が差し込み、二階の棚の手前に立つ南雲を照らしている。その大きな目は昨夜と同じように鋭く光り、口元にはうっすらと笑みが浮かんでいた。ぞくりと、これまでに感じたことのない寒気が背筋を走り、時生は南雲の横顔に見入った。同時に、彼が何を見ているのか確認しようと目をこらした。すると、南雲はぱたんと画集を閉じ、顔を上げた。時生は慌てて首を引っ込め、南雲は画集を棚に戻して階段に向かった。階段を下りた南雲が戻って来ないのを確認し、時生は南雲がいた棚の前に移動した。
手ぶらで階段を下りて行ったから、画集は棚に戻したはず。そう思い視線を巡らせると、並んだ本の中にそれらしき黒い背表紙を見つけた。引き抜いて眺めたところ、複数の画家の作品を収録した画集らしく、表紙の文字は英語だった。時生は画集を掴み、南雲が見ていた中ほどのページを開いた。数点の絵画が載っていたが、綺麗な風景画や人物画ばかりだ。じゃあ、あの南雲の表情はなんだったのかと考えながらさらにページを捲ったとたん、時生は、
「わっ」
と小さく声を漏らし、手を止めた。
画集の見開き二ページを使い、一枚の絵が載っていた。荒野を思わせる黄色い大地の真ん中に、おびただしい数の人間の頭蓋骨が歪んだピラミッド形に積み上げられている。頭蓋骨は横向きや後ろ向き、上下が逆さまになっているもの、顎から下がないものもあった。さらにピラミッドのてっぺんと側面にはカラスが留まり、上空を舞ったり、傍らに生えた枯れ木に留まっているものもいた。絵の下に添えられた画家の名前は、ロシア語らしき文字で書かれている。何とも不気味でおぞましい絵だが、描いた人の強い意志のようなものも伝わってくる。
間違いない。南雲さんは、これを見ていたんだ。鼓動が速まるのを感じるのと同時に湧き上がる興奮を覚え、時生は絵を見つめ続けた。
12
しばらく考え込んだ後、鈴鹿優美花は商品棚に手を伸ばした。そこに並ぶのがワインのボトルだと確認し、南雲士郎は声をかけた。
「白もいいけど、僕のお勧めは赤だな」
驚いて手を引っ込め、優美花が振り向く。「こんばんは」と南雲が微笑みかけると、優美花は戸惑ったように返した。
「こんばんは。カンナちゃんを捜してる方ですよね。お名前は確か……」
「南雲士郎です。お店に伺った際、ついでにここに寄ったら気に入ったのでまた来ました。いい店ですね。ワインの品揃えがいいし、魚の鮮度が抜群」
店内を見回し、語る。ここは中野坂上駅にほど近いスーパーマーケットで、時刻は午後八時過ぎだ。客はまばらだが、黒い三つ揃いを着て片手に表紙が深紅のスケッチブック、もう片方の手には、スーパーマーケットの店名入りのカゴを持つ南雲を不思議そうに見て行く人もいる。
納得した様子で、優美花は「そうでしたか」と頷いた。
「本当にいいお店なんですよ。こんな時間でも魚や野菜が新鮮だし。今日もおいしそうなカンパチがあったので、カルパッチョにしようかなって」
そう言って指した金属製のショッピングカートには、発泡スチロール製の皿に入ってラップされた薄赤い魚の切り身があった。
「だと思って、赤ワインをお勧めしました。魚には白ワインというのが常識だけど、カンパチやマグロ、カツオなどの脂がしっかりしてうま味も強い赤身魚には、赤ワインを合わせるのが……なんてことは、飲食のプロの優美花さんならご存じですよね。失礼しました」
蘊蓄を中断して南雲が頭を下げると、優美花は「とんでもない」と首を横に振った。
「うちでガレットを召し上がった時もお連れの方に解説されていたし、南雲さんはグルメなんですね」
「食い意地が張っているだけです」
南雲は即答し、優美花は「私も同じです」と笑った。
ヒルトップカフェを訪ねた夜から、南雲は時生と張り込みを始めた。結果、鈴鹿夫妻は店から徒歩十分ほどのマンションで暮らし、子どもは小学生の女の子が二人だとわかった。
夫妻は午前九時前に出勤し、十一時の開店から午後八時の閉店まで働く。その後、妻の優美花は帰宅し、夫の英雅は店に残って片付けや翌日の仕込みをし、午後十時前に帰るという生活を送っているようだ。しかし怪しい動きはないまま三日目となり、自分で張り込みを提案したこともあり、南雲はどうしたものかと考えた。そこでさっき閉店した店を出て行く優美花を見て、一人でここまで付いて来た。
「カンナちゃんはまだ見つかりませんか? 心配ですね」
真険な表情で、優美花が訊いてきた。チャンスと感じ、南雲は言った。
「ええ。優美花さんは、カンナさんを気にかけていたようですね。でもそれは、英雅さんに対する振る舞いへの不安、警戒という意味では? 実はカンナさんは、他の男性ともトラブルを起こしています」
「トラブルって、本当ですか?」
「はい。英雅さんはイケメンだし、カンナさんの好みなので気になって」
トラブルは事実だし、感じのいいイケメンはみんなに好かれる。独自の論理に基づき、南雲は答えた。すると、優美花は潜めた声でこう続けた。
「南雲さんのおっしゃるとおりです。はじめに店に来た時、カンナちゃんはナチュラルメイクで服もカジュアルでした。でも二回三回と来るうちに、どんどん凝ったメイクと洒落た服になっていきました。しかも、夫を見る目や話し方が露骨で。夫がカンナちゃんを相手にしていないのは明らかでしたけど、いい気持ちはしませんでした。だからもう来られないと言われた時は、正直ほっとしたんです」
「相手にしていないのは明らか? それは確かですか?」
勢いよく南雲が問うと、優美花は「ええ」と首を縦に振った。
「夫はモテるし、浮気性には苦労しています。でも私が言うのもなんですけど、すごく面食いなんです。美人が好きというか、美人以外は女じゃないと思ってるみたい」
整った顔を曇らせ、優美花はため息をつく。とたんに、南雲の頭の中に伊東真佑の顔と彼の訴え、綾部美桜を捜す過程で会った人たち、交わした会話、そして美桜の写真と、スケッチブックに描いた女の顔の絵がフラッシュバックされた。続けて一つの閃きがあって大きな衝撃が走り、頭の中が真っ白になる。と、そこに傍らからあるものが現れた。
螺旋状の骨組みに白い帆を張ったスクリューの下に、それを回転させるためのレバーが並んだ軸と円形の土台が接続された装置。南雲が師と仰ぐ芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチの手によるスケッチの空飛ぶ機械、通称「空気スクリュー」だ。CG化された空気スクリューは南雲の頭の中を悠然と横切り、どこかに飛び去っていった。これは南雲が事件のヒントを見つけたり謎を解いたりした時に起こる現象で、今回も閃きは確信に変わった。
南雲は怪訝そうに自分を見ている優美花に、
「ありがとうございました。ちなみに、カンパチのカルパッチョにはピノ・ノワールがお勧めです」
と早口で告げ、棚の中から赤ワインのボトルを一本取って差し出した。優美花は反射的にボトルを受け取り、南雲は「では」と告げて店の出入口に向かった。
13
十分で戻ると言ったのに、二十分過ぎても南雲は戻らなかった。不安になり、時生がスマホを取り出そうとした時、街灯に照らされた歩道を南雲が歩み寄って来た。
「今夜も蒸し暑いねえ。はい、これ」
助手席のドアを開けながら呑気に告げ、手にしたものを時生に差し出す。受け取って見ると、アイスキャンデー。外袋には「新発売! ゴーヤ味」とある。思わず「ゴーヤ味って」と隣を見ると、南雲が手にしているのは同じアイスキャンデーのドラゴンフルーツ味だ。どうせまた、「後で一口ちょうだい」とか言って試食だけするつもりだろ。心の中で文句を言いながら、時生は問うた。
「優美花を尾行したんでしょう? 収穫は?」
「あったよ。でも、今は教えない」
平然と答え、南雲はダッシュボードに手を伸ばした。掴み上げたのはスマホを一廻り大きくしたサイズのゲーム機で、色とりどりの四角いボタンが並んでいる。ここで食い下がったところで、「創作の過程は公にしない主義」とか何とか返されるのは明らかなので、時生は口をつぐむ。すると南雲は、アイスキャンデーを囓りながらゲーム機を構えた。
「じゃ、さっきの続きをやろうかな。でも、僕はこういう反射神経頼りのプレイは苦手なんだよね。これには、思考力や創造力を必要とするゲームは入ってないの?」
「入っていないと思いますよ。下の娘たちがぐずった時用のおもちゃですから」
「あっそう。でもこの車、すごく面白いね」
にこやかに返し、南雲は後部座席を見た。
山手通り沿いの、ヒルトップカフェから少し離れた場所に停めたこの車は、白いワンボックスだ。張り込みに署の車は使えないので、仕方なく時生のマイカーを出した。日ごろ子どもたちを乗せているため、車内にはおもちゃやぬいぐるみがたくさんあり、後部座席にはチャイルドシートが二つ並んでいる。張り込みを始めて三日になるのに、南雲はおもちゃやぬいぐるみに興味津々で、触ったり遊んだりしている。
「面白がってないで集中して下さいよ。今夜あたり、何か起きそうな気がします」
そうぼやいた時生だったが、思い直して問いかけた。
「南雲さん。そんなに面白いなら、うちに来ますか? おもちゃが山ほどありますよ。子どもたちや姉にも紹介したいし、一緒に食事しましょう」
切れ者だが変人として知られている南雲は、勤務が終わると即退庁し、刑事課の飲み会やレクリエーション等には一切参加しないことでも有名だ。そんな彼が誘いに乗るはずはないとわかっていたが、自宅に招けばあれこれ聞き出すチャンスなのでダメ元だ。
三日前は南雲が古書店を出た後、時生も彼が見ていた画集を買って帰宅した。自宅で改めて画集を眺め、パソコンで調べた結果、骸骨のピラミッドの絵はヴァシーリー・ヴェレシチャーギンという画家が一八七一年に描いた「戦争礼賛」という作品だとわかった。またヴァシーリーはロシアの従軍画家で、絵を収めた額縁には「過去、現在、未来のすべての征服者に捧げる」と記されていたという情報も得た。タイトルに礼賛と入っていることもあり、初め時生は戦果を讃える意図で描かれた絵だと思った。が、実は「戦争礼賛」は皮肉で、ヴァシーリーは平和主義者で絵は反戦のメッセージらしい。
南雲がリプロマーダーだとしたら、次の犯行の時に再現するつもりであの絵を見ていたのか? しかし大量の骸骨やカラスなど、再現の難易度はこれまでの犯行とは比較にならない。さらに、ターゲットとして狙うのは国際紛争やテロに加担している者と仮定して調べてみたが、めぼしい人物は絞り切れなかった。
と、南雲が答えた。
「考えておくよ」
「えっ!?」
驚き、時生は顔を上げた。が、南雲はゲーム機をダッシュボードに戻し、前を向いてアイスキャンデーを囓っている。
「よろしくお願いします」
とっさに会釈し、時生も前を向いた。予想外の展開だが、喜びより戸惑いが大きい。何か狙いがあるのかと疑惑を覚えつつ、三十メートルほど先のヒルトップカフェを見つめる。
南雲と時生がアイスキャンデーを食べ終えた頃、明かりが消えた店から誰か出て来た。薄暗がりに目をこらすと、ポロシャツにジーンズ姿の男。出勤時と同じ格好なので、鈴鹿英雅だ。英雅は時生たちに背中を向け、山手通りを駅方向に歩きだした。時生はワンボックスカーを出し、尾行を開始した。
英雅は、山手通りを青梅街道の交差点に向かって歩いた。昨夜も一昨日も同じようにして帰宅したので、今夜も収穫なしかという思いが時生の胸に広がる。その矢先、英雅は動いた。車道に降り、赤信号で停車していたタクシーに乗り込む。
「あっ!」
時生は声を上げ、南雲も身を乗り出す。信号が変わり、英雅が乗ったタクシーは交差点を直進し、時生も後を追った。
数台の車を挟んで尾行したところ、英雅のタクシーは山手通りを進んで渋谷駅の手前で停まった。降車した英雅は横道に入っていったので、時生も通行人の間を縫ってハンドルを切り、付いていった。
五分後。英雅は脇道沿いの建物に入った。小さな雑居ビルで、一階はしゃれたベーカリーだが店内の明かりは消えている。
「この店、知ってるよ。バゲットがすごくおいしいんだって。閉店してなきゃ買ったのになあ」
残念そうに南雲が言う。ベーカリーの手前でワンボックスカーを停め、時生は返した。
「バゲットってフランスパンのことですよね? なら、英雅は商談に来たのかも。ヒルトップカフェでフランスパンを使ったサンドイッチを食べてる客を見ました。二階が店の事務所みたいだし」
ビルの二階には明かりが点り、窓ガラスにはベーカリーの看板と同じ店名のステッカーが貼られている。
「せっかく来たんだし、しばらく張ってみようよ」
手にしたスマホを操作しながら、南雲が告げた。口調は相変わらず呑気だが確信めいたものが感じられ、時生は「はい」と応えた。
それから十分。時生はワンボックスカーを降りて英雅が入ったビルのエントランスを覗いたり、二階の窓を見上げたりしたが、動きは見られなかった。ワンボックスカーの運転席に戻ると、南雲は外の明かりを頼りに開いたスケッチブックを眺めていた。
さらに張り込むこと約三分。通りの向かいを歩いて来た女性が、ビルに入って行った。歳は二十代後半。小柄な細身で、ライトブラウンのセミロングヘア。胸元の開いたミニ丈のワンピースを着ている。
「今の女性、どこかで見たような。でも、どこだろう……南雲さん、わかります?」
首を捻りながら問いかけた時生に、南雲は返した。
「美しい。完璧だ」
「はい?」と振り向いた時生の目に、うっとりとビルのドアを見ている南雲が映る。
「今の女性がですか? ああいうタイプが好み? 確かに美人でしたけど」
すると南雲は「違うよ」と心外そうに答え、
「僕が『美しい』『完璧だ』と言ったのは、自分の推理」
と続け、スケッチブックのページを時生に向けた。そこには鉛筆で描かれた女の顔があった。「これだ!」と声を上げ、時生はスケッチブックを覗き込んだ。
「野中さんと署で話した夜に描いてた絵ですよね? だから見覚えがあったんだ……でも、なんで? 今の女性にそっくりですけど、これは民泊の運営会社の社長に頼まれた孫の似顔絵でしょ?」
「社長の孫は、小学校三年生の男の子だよ。さて、行こうか」
スケッチブックを閉じて胸ポケットに挿した青い鉛筆の位置を直し、南雲は告げた。訳がわからず、時生は「どこへ?」と問うたが、南雲はドアを開けてワンボックスカーを降りた。そのまますたすたとビルに向かったので、慌てて時生も後を追った。
南雲はドアを開け、ビルのエントランスに進んだ。狭いスペースの横の壁にアルミ製の集合ポストがあり、向かい側の壁の前にはオートロックの操作パネルがあった。操作パネルの前に立った南雲は時生が何か言う間もなく、部屋番号とインターフォンのボタンを押した。ややあって、パネルのスピーカーから「はい」と女性の声が応えた。
「運営会社の者です。そちらのお部屋に電気系統のトラブルが起きている可能性があるので、調べさせて下さい」
パネルのマイクに向かい、南雲は淀みなく語った。怪訝そうに女性が返す。
「何ともありませんけど」
「内部で漏電しているかもしれません。危険なので、念のためにお願いします」
すると女は「はあ」と応え、エレベーターホールに通じるガラスのドアが開いた。南雲は「やった」と呟いてドアの奥に進み、時生は「まずいですよ」と後を追った。
「このビル。五階の一部屋を民泊に貸してるらしいんだよ」
エレベーターホールに着いて壁の呼びボタンを押し、南雲は説明した。
「さっきスマホで調べたんですか? でも、あの女性がいるとは限らないでしょう。そもそも、あの女は」
時生が疑問を呈した矢先、チャイムが鳴ってエレベーターが一階に到着した。ドアが開き、さっさと乗り込んだ南雲が手招きをする。仕方なく、時生もエレベーターに乗った。
上昇するエレベーターの中で時生はあれこれ訊ねたが、南雲は「後のお楽しみ」と笑ってはぐらかした。すぐに五階に着き、エレベーターのドアが開いた。
薄暗い廊下に出ると、南雲は「あっちだね」と片方を指して進んだ。並ぶドアの一つの前で立ち止まり、チャイムを鳴らす。足音が近づいて来てドアが開き、さっきの女性が顔を出した。
「どうも」
笑いかける南雲に、女性は無言でドアを大きく開いた。近くで見ると、南雲が描いた似顔絵にそっくりだとわかる。南雲に続き、時生も室内に入った。狭い三和土で黒革靴を脱ぎながら、隅に男物の紺色のスニーカーがあるのをチェックする。
六畳ほどの狭いワンルームだった。手前にコンロが一口の小さなキッチン、向かいにバスルームと思しきドアがあり、奥の窓の前にベッドが置かれている。そしてベッドには、鈴鹿英雅が腰かけていた。こちらを振り向いたとたん英雅はぎょっとし、時生も驚く。一方南雲はスケッチブックを脇に抱え、英雅にひらひらと手を振った。
「先日はごちそうさま。あなたのつくるガレットは絶品」
「なんで」
とっさに立ち上がった英雅だったが、脚がベッドの前のローテーブルにぶつかる。テーブルに載っていたビールの空き缶が倒れ、乾いた音を立てた。笑顔でそれを眺め、南雲はさらに言った。
「驚くのも無理はないけど、僕らが用があるのはこっちの彼女だから……たくさん名前があるみたいだけど、取りあえず綾部美桜でいい?」
後半は後ろに立つ女性を振り向き、問う。一瞬、大きな目をさらに見開いた女性だったが、訝しげな表情で問い返した。
「誰ですか、それ? てか、そっちこそ誰? 管理会社の人じゃないでしょ?」
「正解。僕らはある人に頼まれて、きみを探してた。ある人が誰かって言うと、伊東真佑さん。知ってるよね?」
「知らないし、訳わかんないんですけど……鈴鹿さん。怖い」
怯え顔で訴え、女性は南雲と時生の脇を抜けて鈴鹿に駆け寄った。うろたえつつ、英雅はジーンズのポケットからスマホを出した。
「あんたら、なに? 警察を呼ぶよ」
「いいけど、困るのは美桜さんだよ。僕らはその警察だし」
「えっ!?」
女性が声を上げ、英雅は彼女に「どういうこと?」と訊ねる。すると女性は顔を険しくし、「ウソ。ただのはったりでしょ」と南雲を睨んだ。慌てて時生が「いえ。本当なんですけど、事情があって」と説明を始め、場は混乱する。と、タイミングを見計らったように部屋にチャイムの音が響いた。真っ先に南雲が動き、キッチンの脇の壁に取り付けられたインターフォンのパネルのボタンを押す。
「はい」
「白石だけど。伊東くんも一緒」
聞き覚えのあるその声は、確かに白石均のものだ。今度は時生が「えっ!?」と驚くと、振り向いた南雲は、「さっき白石さんから『伊東くんが捜査の進捗状況を知りたがってる』ってメールが来たんだ。面倒だし、来てもらったよ」としれっと返し、インターフォンのパネルに向き直った。そして、
「どうぞ。上がって来て」
と告げてオートロックの解錠ボタンを押した。「何すんのよ!」と声を尖らせる女性を、時生が「まあまあ」となだめる。事情はさっぱりわからないが、時生はこの女性は美桜だと悟った。そうこうしているうちに、白石と伊東が部屋に来た。時刻は午後九時過ぎだ。
ただでさえ狭いワンルームに男女が六人。流れで白石と時生が部屋の手前に立ち、ローテーブルの両脇には伊東と南雲、その奥のベッドに英雅と、その腕をしっかり掴んだ美桜が座るという配置になった。Tシャツとジーンズという格好で怪訝そうにベッドの男女を見て、伊東が問うた。
「この人たちは誰ですか? 美桜の居場所を知ってるとか?」
「いや。その女性こそが、きみが捜していた美桜さんだよ」
そう南雲が答えると、伊東は「はあ?」と眉をひそめた。
「なに言ってるんですか。違いますよ。知らない女です」
「それはこっちも同じ。私は美桜じゃないし、あなたなんか知らない」
顔を上げ、美桜も言う。隣の英雅は呆然とやり取りを聞いている。「ふうん」と呟き、南雲はスケッチブックを胸に抱いた。と、白石が時生に囁きかけてきた。
「どうなってるんですか?」
「僕もよくわからないんです。でも、このまま見守りましょう。南雲さんはいま、『ふうん』と言ったでしょう? あれは、あの人が何か気づいたり閃いたりした時のクセなんです。相棒として何度も聞きましたけど、その後ほとんどの事件を解決しています。だから、今回もきっと大丈夫です」
そう囁き返すと白石は「わかりました」と頷き、視線を前に戻した。こちらは半袖のシャツにスラックスという格好だ。時生も前を向くと、南雲は話を始めた。
「知らない女だと感じて当然。それこそが美桜さんの狙いだし……おめでとう。大成功だね」
にっこりと微笑みかけられ、美桜は何か返そうとした。それを無視し、南雲は続けた。
「経緯はわからないけど、美桜さんは自分の容姿、とくに顔の造作に強いコンプレックスを抱いていた。だからコスメを買い込んでメイクを研究し、髪型や服装も工夫したんだ。でも恋心を抱いたカフェの店主が面食いだと知り、顔を変えて別人になるしかないと決心した。つまり、美容整形だ」
「美容整形!?」
伊東が声を上げ、南雲は「そう」と頷く。驚いた英雅には美桜が、「全部ウソ。この人、どうかしてる」と訴え、さらに強くその腕を掴んだ。
「でもすべてのコンプレックスを解消するには大きな施術が必要で、多額の費用がかかる。そこで婚活アプリに登録してお金を持っていそうな男性を探し、だまし取ろうと考えた。その男性こそが、伊東さん、あなただったんです」
隣に寄り、南雲は告げた。笑顔は消え、語るほどに眼差しを強めていく。目を見開いて口をあんぐりと開け、それを見返した伊東だが言葉は出て来ない。視線を美桜に戻し、南雲は続けた。
「伊東さんから母親の治療費という名目で一千万円を奪ったきみは民泊のアパートを引き払い、カフェの店主に別れの挨拶もして姿を消し、美容整形外科で手術を受けた。そして三カ月かけて術後の腫れや赤みが引くのを待ち、新しい顔で別人として、カフェの店主に接近した。もともと浮気性の店主は何も気づかず、これ幸いとばかりに彼女と深い仲になった……ちなみに彼女、あなたには何て名乗ったんですか?」
「金森乃愛……じゃなくて、マジかよ! きみ、カンナちゃんなの?」
英雅は騒ぎ、掴まれた腕を振り払おうとした。それを阻止しようとすがりつき、美桜は言った。
「だから全部ウソだって! 信じてよ……いい加減にして。私は生まれた時から金森乃愛で、この顔なの。整形なんて、証拠があって言ってるの?」
後半は南雲を睨み、捲し立てる。すると南雲は「よくぞ訊いてくれました」と目を輝かせ、抱えていたスケッチブックを開いた。そして中ほどのページを「はい」と、向かいに突き出した。ページを見た美桜は驚き、脇から覗いた伊東も「あっ」と声を上げる。
「これを描いたのは、伊東さんに美桜さん捜しを依頼された翌日です。小暮くんと、もう一人の警察職員が証人」
南雲は告げ、時生を指した。その拍子にスケッチブックの絵が見え、それは時生の予想通り、刑事課で野中と三人で話した夜と、さっきワンボックスカーの中で見た鉛筆描きの女の似顔絵だった。目をこらし似顔絵を見た白石が「おっ」と呟き、南雲は語り続けた。
「民泊にいる時、コスメを爆買いしたでしょ? 僕は知り合いのコスメ好きにそれを使うとできるメイクを聞いて、きみがどんな顔になりたがっていたのかを予想したんだ。で、元のきみの顔をアレンジして描いたのがこの絵」
それを聞きながら、時生は慌ててポケットから手帳を出して開いた。
アイテープでまぶたを二重にして、アイライナーとアイシャドウで切れ長・ぱっちりの目に。星花堂の涙袋ライナーで涙袋をぷっくり・キュートにして、ハイライトとノーズシャドウ、細めのフェイスブラシで鼻を高く、小鼻を小さく見せる。加えてリッププランパーとリップコンシーラーを使うと、艶やかでふっくらした唇がつくれ、リフトアップテープを顎の脇や耳の後ろに貼ると小顔に見せたり、シワ・たるみを隠す効果がある。
剛田と瀬名の話をメモしたものを読み返し、同時にスマホも出して美桜の写真と照らし合わせる。確かに美桜の一重まぶたの小さな目と、低く小鼻が広がり気味の鼻、さらに薄い唇とエラの張った輪郭を、南雲の言う「なりたい顔」に変えれば似顔絵そっくり、つまり金森乃愛の顔になる。
そういうことか。合点がいき、時生が顔を上げた時、伊東が口を開いた。
「違う! この女は美桜じゃない。だって、声が違う。美桜はもっと低くて落ち着いた声だった」
美桜と南雲を交互に見て訴える。聞いた話にうろたえ、受け入れたくもないのだろう。これ幸いとばかりに美桜も、
「そうよ! それが証拠よ」
と騒ぐ。
「あっそう。でも、あまり知られていないけど声も変えられるよ。声帯や喉の骨を手術したり、注射をしたりするんだ。美桜さんは、自分の低い声もコンプレックスだったんだろうね。それに、どの病院で手術を受けたにしろ記録は残っているだろうし、どんなに顔を変えても、指紋と掌紋は変えられない。DNA鑑定だってあるし、調べれば一発だよ」
余裕綽々で告げた南雲だったが、鼻息も荒く自分を睨む伊東に気づき、言い直す。
「とはいえ、被害届が出てなきゃ警察は何もできないけど。で、今回の場合はどうするかと言うと……小暮くん。答えて」
「はい!?」
こういう展開は予想できただろうに、ノープラン? 似たような状況が、少し前にもあったよな。驚きと腹立たしさ、焦りが同時に押し寄せて来たが、この場をしのがなくてはならない。時生は必死に頭を巡らし、一つの閃きを得た。顔を上げ、言う。
「伊東さん。美桜さんの顔や体に、本人も気づいていない特徴はありませんか? 将来を誓い合った仲のあなたなら、知っているはずです」
口調は丁寧に、しかし伊東のプライドを刺激する言葉を選んで語りかける。案の定、伊東は一瞬戸惑ったような顔をした後、目を伏せて考え始めた。それを時生と南雲、英雅、さらに美桜も見守る。と、伊東ははっと顔を上げ、少し言いにくそうにこう答えた。
「……お尻の割れ目の内側。上の方の、向かって左側に小さいほくろが」
「ある!」
驚きつつ同調したのは、英雅。その言葉に伊東は呆然とし、時生は「もう言い逃れできませんよ」と美桜を追い込む。すると美桜はうんざりしたように息をつき、英雅の腕から手を放して顔を背けた。
「それ、降参ってこと?」
軽い口調で南雲が問うと、投げやりに「そうなんじゃない?」と返した。その横顔に、伊東も問いかける。
「本当に美桜なの? なんでこんなことを。美桜は十分綺麗だし、かわいかったじゃないか。僕は、ありのままのきみが好きだったんだよ」
すると美桜は鼻を鳴らし、挑むように伊東を見た。
「ありのまま? どこが? めいっぱいキャラをつくって、メイクもそれ風にしてたけど……なにが、『十分綺麗だし、かわいかった』よ。心の中じゃ、『俺にはこの程度の女でちょうどいい』『こいつには俺しかいないんだ』って考えてたクセに。私に振り向く男は、みんなそうだった。自分を諦めて妥協する口実に、私を使うの。でも私は違う。自分を諦めないし、顔を変えることで自分も変えた」
最後は誇らしげな口調になり、細く尖った顎を上げる。それを見て伊東は絶句し、英雅は怯えたように身を引いた。ぱたん、と南雲がスケッチブックを閉じた。反射的に自分を見た美桜に、こう告げる。
「残念だけど、それは違うよ。見た目をどんなに変えても、きみの中の自分は変わらないし、逃れられない。そっちの方が何倍も厄介だし、これからが地獄だよ。なにしろ、きみの中の自分は、きみの元の顔とは比べものにならないぐらい醜いからね」
いつも通りの軽く、淡々とした口調。しかしその目には、内面の怒りがはっきりと映っている。
「あんたなんかに、何が」
反論しようとした美桜を遮り、南雲は続けた。
「それに、レオナルド・ダ・ヴィンチはこう書き記してる。『自分の美しさにうぬぼれた杉の木は、周りの木々を邪魔に思い切り倒した。望み通り、杉の木の周りには何もなくなった。しかし強い風が吹くと、杉は根元から地面に倒れてしまった』……ね、地獄でしょ?」
最後に身を乗り出し、問いかける。その満面の笑みに時生は寒気を覚え、美桜もびくりとして口をつぐんだ。
その後しばらくして、美桜を残して男五人は部屋を出た。エレベーターを待ち、乗り込んで一階に下りるまでの間に、英雅は時生に問われるまま、美桜とは半月ほど前に行き付けのバーで知り合って関係を持ったこと、乃愛がカンナだとは気づかず、あのワンルームも彼女の自宅だと聞いていたことを話した。そしてビルから通りに出るなり、訊ねた。
「いろいろすみませんでした。それで、僕はどうなるんですか?」
「どうもならないし、帰っていいよ。でも、火遊びはほどほどに。それと、あなたの店のガレットは絶品だけど、カフェラテはいまいちだね。酸味が強すぎる」
テンポよく南雲に返され、英雅はぽかんとする。が、時生が「大丈夫ですよ」と促すと、「すみませんでした!」と一礼し、逃げるように立ち去った。その場に沈黙が流れ、みんなの目が伊東に向く。
部屋を出る前、「調べればすぐにわかる」と隠し持っていた自動車の運転免許証を美桜に提示させた。それによると美桜の本名は横堀恵麻、三十二歳だった。
何か言葉をかけなくてはと、時生は口を開こうとした。が、一瞬早く南雲が言った。
「伊東さん。このあいだ僕が電話で贈ったダ・ヴィンチの言葉を覚えていますか? 『最高の愛は、相手を深く認識することから生まれる。もしあなたが相手を正しく認識していないなら、ほとんど、いや、まったく愛せてはいないだろう。また、もしあなたが相手を愛する理由が自分の欲望を満たすためで、美徳のためでないなら、あなたは犬と同じだ。犬は骨をくれるかもしれない人には後ろ脚で立ち上がり、尻尾を振って歓迎するものだから』。あれには続きがあるんですよ。『しかし、もし犬が相手の美徳を知り、それを好ましいと思えたなら、犬であっても強い力で相手を愛することができるはずだ』。この言葉も、あなたに贈ります」
優しく微笑みかけた南雲だが、伊東はぽかんとする。慌てて、時生は補足した。
「また出会いがあったら、その女性を冷静に、独りよがりにならないように理解して下さい。その上で女性のいいところに惹かれたなら、今度こそ深く愛し合えるはずです」
「……わかりました。ありがとうございます」
細く力のない声だが伊東は応え、会釈した。すると南雲は、「ちなみにダ・ヴィンチは、こうも言ってて」と伊東に語り始めた。呆れながらもほっとして時生がそれを眺めていると、白石が囁いてきた。
「伊東くんのことは任せて下さい。落ち着けば、気持ちも変わるはずです」
「わかりました。よろしくお願いします」
「いろいろとありがとうございました。近いうちに必ず、お礼をしますので」
白石は告げ、深々と頭を下げた。時生が「とんでもない。先輩のお力になれて何よりです」と恐縮すると白石は顔を上げ、笑った。
「先輩なんて、僕は落ちこぼれのデカで……でも、さっきの小暮さんの『見守りましょう』『きっと大丈夫』という言葉を聞いて安心しました。南雲くんを信頼して下さっているんですね」
「いや。そんな」
信頼するどころか、連続猟奇殺人事件の犯人だと疑っていますよ。胸にそう去来し、時生は複雑な気持ちになる。南雲と伊東は、歩道の端に移動して話している。
「南雲くんはああいう性格だし、大学時代にはあんなこともあったから。警視庁に誘った手前、心配していたんです」
白石はそう続け、時生は「えっ」と返す。歩道の端に目をやりながら訊ねた。
「南雲さんは、白石さんの誘いで警察官になったんですか? なんでまた。それに『あんなこと』って──」
「小暮くん、帰ろうよ。眠くなっちゃった」
タイミングをはかったように、南雲が振り向いて言った。「お疲れ。悪かったな」と声をかけ、白石は南雲たちの方に向かった。混乱しながら、時生は話を始めた南雲と白石を見つめた。
14
約二週間後。その朝、時生は午前六時過ぎに自宅を出た。楠町西署に着き門から敷地に入ると、前方に見慣れた背中があった。
「おはようございます。早いですね。南雲さんも、訓練に出るんですか?」
意外に思いながら駆け寄り、問いかけた。今朝、署の道場では早朝術科訓練という武道の稽古が行われる。南雲は「おはよう」と応えてから肩をすくめ、こう続けた。
「まさか。柔道も剣道も、僕の好みじゃないよ。せめてフェンシングなら優雅だし、やる気になるんだけどね」
「とか言って、苦手なだけでしょ……南雲さん。相変わらず射撃も苦手なんですか? 年に一度の拳銃射撃訓練では、教養課の教官に叱られっぱなしだって噂を」
「違うよ。銃器は眺めるのも撃つのも大好き。でも、僕は左利きでしょ? 日本の警察は、利き手に関わらず右手で銃を撃つのがルールだから」
しれっと返され、時生は「はいはい」と受け流してから改めて訊ねた。
「じゃあ、何のためにこんなに早く?」
「寝るため。暑さのせいか、ベッドだと熟睡できないんだよね。で、試しに署の駐車場の車にエアコンを入れて寝てみたら、ウソみたいにぐっすり──」
「なに考えてるんですか。ダメですよ……そう言えば、伊東真佑さんが自宅近くの署に被害届を出したそうですよ。白石さんが報せてくれました」
「僕にも報せがあったよ。美桜──本名は恵麻だっけ? 恵麻はもともと東中野の冷凍機械工場に勤めていたらしいよ。で、偶然ヒルトップカフェに行き、鈴鹿英雅に一目惚れしたって流れ」
やり取りしながら、時生たちは広い駐車場を抜け、署の建物に入った。「そうだったんですか」と頷き、時生は訊ねた。
「例によって、途中で事件の真相に気づいていましたよね? 恵麻の似顔絵を描いたあたりから?」
「まあね。剛田くんたちからコスメの話を聞いた時点で、恵麻の犯行動機は美容整形の手術代だとピンと来たし、それに英雅が絡んでいるだろうとも思った。でもまさか、英雅の愛人に納まっているとはね。すごい根性、というか執念だよ」
「僕は英雅が理解できませんよ。あんなに美人で働き者の奥さんがいるのに、浮気なんて。それに奥さんはすらっとしてスポーティーですけど、恵麻は小柄でかわいいというか、ちょっと幼い感じで正反対。美人なら誰でもいいってことか」
優美花と娘たちの姿を思い出すと英雅に腹立たしさを覚え、時生は訴えた。紙コップを口に運び、南雲はあっさりと返した。
「というより、食の無限ループみたいなものじゃない? しょっぱいものを食べると、甘いものが欲しくなるでしょ。で、甘いものを食べるとまたしょっぱいものが、ってやつ。そう思って優美花さんに鎌をかけたら、大当たりだったんだ」
「はあ。いつもながら、相当突飛で強引ですね」
「結果的に上手くいったんだからいいでしょ。恵麻も相応の罰を受けることになるだろうし。偽りの美は美ではないし、それを理由に人を傷付けるなんて言語道断だよ」
最後は厳しい表情になり、南雲は階段を上がりながら空を見た。隣を歩きつつ、時生は渋谷のビルの前で交わした会話を思い出した。
「南雲さんは白石さんの誘いで、警察官になったそうですね。なんて誘われたんですか? 僕も誰かを誘う時の参考にしたいので、教えて下さい」
笑いも交え、極力さりげなく訊ねたが緊張し、鼓動も速まる。すると南雲は首を傾げ、答えた。
「そうだったかな。僕の記憶では、原宿でショッピング中に『刑事になりませんか?』ってスカウトされたんだよね。あるいは、知らないうちに友だちが警視庁に僕の履歴書を送っちゃったか」
「なんですか、それ。アイドルのデビューのきっかけじゃないんですから」
時生が突っ込むと、南雲は顎を上げて笑った。またはぐらかされたと苛立ちつつ、ということは何かあるなと手応えも覚える。
二階に着き、廊下を歩きだしてすぐに慌ただしい気配に気づいた。廊下の向こうから、刑事たちが駆けて来る。その切羽詰まった様子に、廊下を行き交う職員たちは脇に避けた。と、刑事たちの一団に井手義春と剛田力哉の顔を見つけ、時生は声をかけた。
「おはようございます。事件ですか?」
「ああ。庭梅町五丁目の空き地で、人間のものらしき頭蓋骨が見つかった」
時生と南雲の前で足を止め、井手が答える。「殺人ですか?」という時生の問いには、一緒に足を止めた剛田が答えた。
「多分。でも、ただのコロシじゃなさそうで……頭蓋骨は一つじゃなくすごい数で、しかもピラミッド形に積み上げられてるらしいんですよ。で、そこにカラスが群がって」
「『戦争礼賛』だ」
思わず言ってしまい、剛田と井手が怪訝な顔をする。はっとして時生が隣を見ると、南雲も時生を見ていた。その意図が読めない眼差しに、時生はまた緊張し、鼓動が速まった。
「とにかく臨場だ。そっちも急げよ」
早口で告げ、井手はまた歩きだした。剛田も続き、二人は他の刑事たちの後を追って階段を下りて行った。その背中を見送り、時生は混乱する。
ピラミッド形に積まれた頭蓋骨と、それに群がるカラス。間違いない、ヴァシーリー・ヴェレシチャーギンの「戦争礼賛」の模倣、リプロマーダーの犯行だ。じゃあ、やはり南雲さんは──。そう考えるとさらに緊張して鼓動は速まり、寒気に襲われた。それでも隣に向き直ろうとした時、
「行こう」
と告げ、南雲は踵を返した。かろうじて「はい」と返し、時生も続く。強ばる脚で階段に向かいながら、時生は前を行く南雲を見つめた。その華奢な背中は三つ揃いのジャケットに包まれ、色は黒。彼のお馴染みのスタイルなのに、いつもより黒が深く、濃く感じられ、時生の不安を煽る。それでも足を緩めず、時生は南雲を追いかけた。