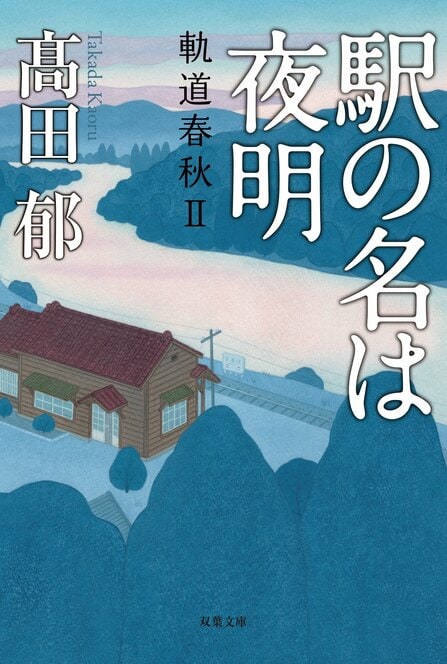夜のうちに降りだした雪は、翌朝には街をぽってりと厚く包み込んだ。
この季節の積雪には慣れているのか、人も車も戸惑う様子はない。
「ヴォティーフ教会ですか?」
ホテルのフロントマンは、外を示して、
「マダム、それならトラムを利用されては如何でしょうか」
と、交通網に麻痺がないことを、聞き取り易い英語で伝える。
いえ、と真由子は部屋の鍵を渡しながら、タクシーを呼ぶよう、再度頼んだ。
有名な教会の多くは、リンクの内側にあるが、ヴォティーフ教会はリンク外に位置する。美しいステンドグラスで有名だが、何よりもその外観が美しい。近くに在るウィーン大学と同じ設計士の手によるものだ、と徹から教わったことを覚えている。
「シェーネン・ターク・ノホ(良い一日を)」
十分とかからずに目的地に着くと、運転手は明るく言って、真由子を下ろした。
雪を纏った公園越し、蒼天を貫く二本の塔に迎えられた。ヴォティーフ教会の緻密で荘厳な外観は、ここを訪れるのが二度目にも拘わらず、圧倒される。
何て綺麗なんだろう、と真由子は広場の中ほどに立って、クリスマスツリーにも似た二本の塔を見上げた。まだ開館まで時があるのだろう、手持ち無沙汰に待つひとが多い。
「ああ、やっぱりそう」
ふいに、日本語が聞こえた。
「やっぱり、あの時のあなただわ」
声の方を見れば、頭から薄紫色のストールを被った老女が片手に杖を持ち、もう片手を少し上げて親しげに振っていた。
防寒のためのストールから覗くのは、金縁の眼鏡だけで、顔がわからない。第一、ウィーンに高齢者の知り合いが居るはずもなく、真由子はどう応じたものか、戸惑いの眼差しを相手に向けた。
老女はストールを首まで下げて、にこやかに笑ってみせる。
「覚えてらっしゃらないかしら? ほら、成田空港でテレホンカードを」
そこまで言われて、真由子はハッと気づく。
まさしく、公衆電話のコーナーで、テレホンカードを譲った相手だった。
「まぁ、こんなところで……」
思いがけない再会に、真由子もまた唇を綻ばせる。
自由行動の多いツアーでこちらに来ている、という老女と、ベンチに移って話し込んだ。
「よく私だとお分かりになりましたね」
出発前の慌ただしい時、空港でほんの少し関わっただけだった。目立つ風貌でも服装でもないのに、と不思議そうに尋ねる真由子に、老女は、
「衿もとの、そのビロードのリボンが素敵でしたから」
と、にこにこと種明かしをした。
ビロードのリボンは黒や茶などの暗い色が多く、黄色は珍しい。黄という色が魔除けになると聞いて、あちこち探し回って見つけた品だった。
娘の形見が老女の眼に留まっていたことに、母は胸を衝かれる。思わずリボンに手を遣って、ぎゅっと握り締めた。
「ちょっとごめんなさいね」
老女はそう断って、脇に置いたバッグに手を入れて、中のものを取りだした。革張りの小振りの額に写真が納まっている。茶色のスウェードのジャケットを着込んだ、白髪に白眉の老紳士が写っていた。
「お父さん、ここがヴォティーフ教会ですよ」
老女は写真に向かって優しく話しかけると、写真を教会の方へと向けた。
「亡くなった主人なの」
「そうでしたか」
遺影と一緒に旅をしているのだ、と察して、真由子はしんみりと相槌を打った。
「『金婚式にはウィーンに連れて行く』というのが、主人の口癖でねぇ。果たさぬまま五年前に亡くなりました。私ももう先が知れてますから、思いきって慰霊の旅をしています」
老女はそっと写真を自分の方へと向け、優しく撫でてみせた。
カメラを向けられて緊張しているのか、少し固い表情で写っているひと。生真面目さと誠実さが滲み出ていた。目の前の女性と並べば、本当に似合いの夫婦だろう。
「失礼な言い方かも知れませんが」
慎ましく断ってから、真由子は、
「ご主人はお幸せですね。亡くなられてからも、こんなに大切に想われて……。夢の中でも、会いに来られたりしますか?」
と、尋ねた。
「それが、あなた」
ほっほっ、と老女の口から笑い声と白い息が洩れる。
「全然なの。娘の夢枕にはちょくちょく立つらしいのだけれど、私の所には全然なんですよ」
こっちは五年も待っているのにねぇ、と老女は写真を指で軽く弾く仕草をした。恨み言でありながら、どこか朗らかな物言いだった。
そうですか、と真由子は声低く応じる。
「ひと目会いたい、と……夢でも良いから会いたい、と願う相手ほど、決して現れてくれないものなのかも知れませんね」
翳りのある表情から何か感じたのか、老女はまじまじと真由子を見た。もしかしたら、大切な誰かを喪った悲しみを、読み取ったのかも知れない。
「亡くなったあと、魂がどこへ行くのか、本当のところはわかりゃしません。だからこそ、夢で会えるなら、と願わずにはいられませんよね」
老女は、教会の塔へと視線を転じて、「でもねぇ」と続ける。
「夢枕には立ってくれなくても、今、確かに傍に居る。そうとしか思えない瞬間があるの。悲しみに溺れている時には、まるで気づけなかったけれど」
額の写真を胸にそっと抱いて、老女は穏やかに話す。
「ひとに話せば『錯覚』で済まされてしまうかも知れない。でも、確かにあるんですよ、奇跡のような瞬間がね」
日々の暮らしの中で、亡き夫の気配を感じ、温かさに包み込まれる一瞬がある、と老女は微笑みながら打ち明けた。
老女のひと言、ひと言が胸に沁みて、真由子の双眸に涙が膜を張り始めた。
開館時間を三十分近く過ぎて、漸く、教会の重い扉が開いた。待ちかねていたひとびとが、三々五々、中へと吸い込まれていく。
「すっかり冷えてしまったわ。中でお手洗いを借りないと」
夫の遺影をバッグに戻して、老女は杖を支えにベンチから立ち上がった。
「あなたはどうなさるの? もし、中を見学されるなら、御一緒しませんか」
真由子は一旦、椅子から立って、いえ、と軽く頭を振った。
「私はもう少しここに居て、それからトラムに……」
胸もとのリボンに手をあてがい、迷いを断ち切って続ける。
「トラムに乗ろうと思います」
トラムに、と繰り返すと、老女は口もとを緩めて象牙色の歯を零した。
「トラムは便利だし、風情があって良いわねぇ。私もウィーンにいる間は、沢山乗るつもりです。私くらいの年代の者には、懐かしい乗り物なの。昔はね、日本のあちこちで沢山の路面電車が走っていたから」
ではお互いにウィーンを楽しみましょうね、と老女は優しく言い添えて微笑んだ。極寒を抜けた先に咲く、辛夷の花を思わせる笑顔だった。
この続きは、書籍にてお楽しみください