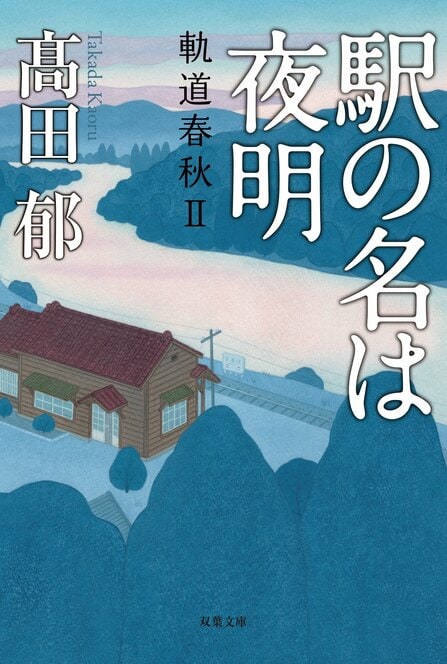トラムに乗って
「話し合う? 今さら何を『話し合う』というの?」
受話器を持つ手の震えが、どうにも抑えきれない。左の五指を右手首に巻きつけて、真由子は語調を強める。
「この一年、あなたは仕事に逃げた。由希を、あの子を、何故もっと丈夫に産んでやれなかったのか、自分を責めるしかなかった私には目もくれず、徹は仕事に逃げたじゃないの」
構内アナウンスが途切れていたせいか、真由子の声は意外なほど響いて、傍らを行くツアー客が揃って振り返った。
午前十時を過ぎた成田空港、ガラス越しに冬陽が射し込み、これから旅立つひとびとを祝福している。クリスマスが近いことも相俟って、ロビー内は高揚した空気に包まれていた。
場違いな声を発したことに気づき、真由子は口を噤む。受話器の向こうで、夫のぼそぼそとした言い訳が続いていた。
「もしもし、真由子、聞いているのか」
とにかく戻ってほしい、という徹の懇願に応えることなく、真由子は視線を転じる。
ロビーには大きなクリスマスツリーが飾られて、家族連れや恋人同士が好ましそうに仰ぎ見ていた。
ツリーの一番上には、きらきらと輝く大きな星。
あの星の名を娘に聞かれて、答えることが出来なかった。一年前、ほんの一年前だ。光が溢れて明るいはずのロビーが、ふと翳る。悲しみが足もとから膝へと這い上がるのを覚えて、真由子はぐっと奥歯を噛み締めた。
「私のサインは済ませたし、希望のない結婚生活なら解消した方がいい」
もう行くわ、と電話の向こうの夫に告げて、気持ちを断ち切るように受話器をフックに掛けた。ピピー、ピピー、と音が鳴り、テレフォンカードがゆっくりと押し出される。抜き取ったものを手に、真由子は小さく吐息をついた。
一時、日本を離れたからといって、何かが変わるわけではない。戻ればまた、自らを責め苛む日々が待つ。何もかも、よくわかっているのだが、とにかく今は全てから逃げてしまいたかった。
分厚いコートを抱え直した真由子に、背後から、
「あの、すみません」
と、呼びかける者があった。
公衆電話が並ぶ一角には、真由子の他にひとはいない。振り返って声の主を見れば、七十過ぎと思しき老女が立っていた。
灰色のコートに薄紫のストール姿。足が悪いのか杖を突いている。白髪に金縁の眼鏡がよく似合っていた。
「テレフォンカードは、何処に売ってますかしら。電話をかけたいのですが、硬貨が使えなくて」
このコーナーにある公衆電話は、全てカード式だった。探せば近くに販売機はあるのだろうが、真由子は手にしていたカードを老女に差し出した。
「良かったら、これを」
「いえ、そんな訳には」
両の掌を広げて遠慮してみせる老女に、真由子は、
「どうぞ。私にはもう必要ありませんから」
と、半ば押し付けるようにカードを渡す。
折しも、第二ターミナルに響き渡る音量で、アナウンスが入った。
「全日空二百七便、ウィーン行きをご利用のお客様にご案内を申し上げます」
搭乗予定の便のアナウンスだった。
急ぎますので、と相手に会釈して、その場を離れる。ありがとうございます、との声を背中で聞いて、真由子は足を速めた。
一度目の食事サービスのあと、窓のシェードが下ろされて、機内は薄暗い。
ウィーンへの直行便は本数が少ないせいか満席だったが、話し声もなく、換気音が響くばかりだった。
ナイトキャップに、ドライジンを頼む。
徹の好きな銘柄だった。真由子自身は強い酒は苦手なのだが、成田からウィーンまでおよそ十二時間の飛行、酔って眠ってしまいたかった。
気圧のせいもあって、少量のジンでも酔いが早く訪れた。頭の芯がとろりと溶けそうで、シェードに寄りかかって、そっと瞼を閉じる。
──にがいおクスリも、いたい注しゃも、がまんするよ。だから、由希が元気になったら、ウィーンに連れていって
──パパとママが乗ったトラムに、由希も乗るの
耳の底に愛娘の声が蘇り、真由子はハッと腰を浮かせた。膝から毛布がぱさりと落ちる。
赤い制服姿の客室乗務員が、真由子の方を気にして、ミネラルウォーターのペットボトルを持ち上げてみせた。水を求められている、と思ったのだろう。
真由子は軽く頭を振り、毛布を拾い上げてシートに身を委ねた。
胸もとにそっと手を遣る。カシミアのセーターのふんわりした質感とは異なる、厚みのある滑らかなビロードの手触り。首周りに緩く結んだそのリボンは、生前、娘の髪を飾っていたものだった。
由希、と娘の名を胸のうちで呟く。
もともと風邪を引き易かったり、よく発熱したりしていたが、内臓に異常が見つかって、たった七つで逝ってしまった。
ビロードの黄色いリボンが結ばれていた、艶やかな優しい髪を思う。その柔らかな頬、母親に向けられた眼差し、ママ、と呼ぶ声。狂おしいほどに恋しく、愛おしい。
込み上げる悲しみを辛うじて封じ、シェードに指をかけた。持ち上げて、窓の外を覗くと、眼下、凍原が夕陽に映え、朱に染まっていた。
ひとが亡くなると、その魂は何処へ向かうのだろうか。
思えば、祖父母は父方母方とも、真由子が物心つく前に他界していた。両親は健在で、それまで身内の誰をも看取ったことがなかった。初めて経験する死が、我が娘のものだったのだ。
葬儀は仏式で行い、遺骨も成田家の墓所に納めた。導師からは極楽浄土の話を聞いたが、罰当たりなことに信心の薄い真由子には、そこがどんなところか理解できない。せめて夢の中での再会を願うのだが、一年近く待っても、娘は夢枕に立つこともない。
──ママ、ウィーンの話を聞かせて
新婚旅行の写真を収めたアルバムを開いて、由希はよく話をねだった。恋愛や結婚への淡い夢を抱き始めた証だろうか、と甘やかな気持ちで、娘を膝に乗せて、かつての思い出を語った。
石畳の道を馬車が走っていたこと。本物の宮殿のこと、美術館や博物館、コンサートホールまでがおとぎ話のような美しさだったこと。城塞の跡がリンク(環状道路)になっていて、そこをトラムと呼ばれる路面電車が走っていること。結婚したばかりの父と母が終日、トラムに乗り続けたこと。
──森の方まで行くトラムもあるけれど、リンクを一周するトラムに乗れば、ウィーンの街の景色を独り占めした気分になるの。パパとママは一日中、トラムに乗っていたのよ。クリスマスが近かったから、街中がとても眩しくて綺麗だった
そんな思い出話を、由希は瞳を輝かせて聞き入った。そして、決まって、こんな夢を口にしていた。
──いつか、由希もウィーンに行く。トラムに乗って、ウィーンの街を一周するの
病を得て辛い闘病が始まったが、いつかウィーンに行くことを励みに、辛抱強く耐えていた。昨春、入院予定の病院のベッドの空きを待つ間、少しでも気晴らしになれば、と徹と話し合って娘を映画に連れていったことがあった。シンデレラ物語を下敷きにした『エバー・アフター』という作品で、由希が観たがっていたものだ。
映画館の椅子に腰かけて同じ姿勢を取るのはしんどいだろうに、由希は両親の間に挟まれて、とても嬉しそうだった。宮殿や馬車が大画面に映し出されると歓声を上げていた。王宮やシェーンブルン宮殿、それにフィアカー(観光用馬車)。写真でしか知らないウィーンを、スクリーンに重ねているようだった。
親子三人での外出は、結局、それが最後になってしまった。
元気なうちに、ウィーンに連れて行ってやりたかった。あんなに行きたがっていたのに。
ゴメンね、ゴメンね、由希。
涙の膜越し、凍原が暗く歪む。薄いグラスに唇を押し当て、真由子はジンを口に含んだ。