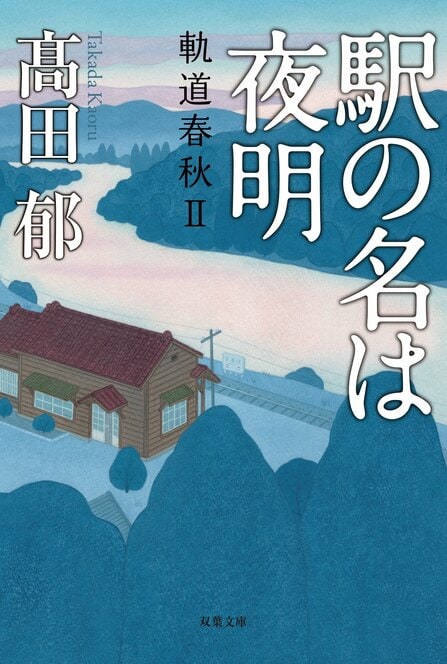およそ十二時間のフライトののち、真由子を乗せた飛行機は定刻より少し遅れて、夕映えのウィーン国際空港に到着した。
もともと十二月のウィーンはハイシーズンなのだが、今年は西暦二〇〇〇年にあたるため、さらに多くの観光客が押し寄せて、小さな空港は大層な賑わいであった。
入国審査を済ませ、スーツケースを受け取って、タクシーで市内へと向かう。ドイツ語は勿論、英語にしても決して堪能ではないが、そうした観光客が殆どだからか、ウィーンでは意思の疎通にあまり困らない。すでに日は暮れていたが、眩く幻想的なイルミネーションに照らされて、クリスマスマーケットの情景が車窓に流れていた。
予約していたホテルにチェックインして、ボーイに先導され、旧式のエレベーターで客室を目指す。案内された部屋は、オイルヒーターでほどよく暖められていた。
ボーイが去ったあと、荷を解く気力もないまま、真由子は窓の分厚いカーテンを開けた。石造りの建物に多い、アーチ形の装飾窓だった。金色のハンドルを握って捻り、そっと押してみれば、ぎぎぎっと音がして、少しだけ開いた。切りつけるような冷気を肌に受けて、真由子は窓枠にもたれる。
石畳のガッセ(小路)を行く酔っぱらいか、随分と調子はずれな歌声が石積みの壁に跳ね返って、ここまで届いていた。
♪ララ~ララ~、ララララ~♪
暫く耳を傾けていると、その節回しがヨハン・シュトラウス二世の「美しき青きドナウ」であることに気づく。随分と音痴だが、伸び伸びと気持ち良さそうだった。
『由希、聞こえる? ウィーンに来たのよ』
心の中で囁いて、真由子は胸もとに垂れ下がったリボンを手に取る。そして、娘の髪にキスをする代わりに、そっと唇に押し当てた。
十二月の現地は曇天が多いと聞いていたが、見上げる空はオレンジからライトブルーのグラデーションが美しい。
極寒の朝、吐く息は忽ち凍りついて綿菓子状になって消える。
まだ買い物客で賑わう前の静かなケルントナー通りを歩いて、オペラ座の前を過ぎる。大通りとリンク(環状道路)が交差する場所に立って、ああ、と真由子は思わず声を洩らした。
紛れもない、ウィーンだった。
十年前、徹とともに新婚旅行で訪れた時の姿と殆ど変わっていない。中世と現代とがミックスされた不思議な街並み。その美しさに、真由子は息を呑む。
──ウィーンは二十三区、東京と同じなんだけれど、ずっとコンパクトで、この一区に見どころが集中してるんだよ
十年前、同じこの場所で、徹からそう教わった。遠い日の思い出が一気に押し寄せて、真由子は立ち竦んだまま天を仰ぐ。
通勤客が真由子の傍らを通り過ぎる時に「グーテ・ライゼ(良い旅を)」と小さな呟きを残して去った。観光客が感極まっている、と思ったのだろう。
自身に掛けられた言葉と知り、真由子は視線を転じて、ダンケ、と微かに応えた。折しも、眼前のリンクの西側から、路面電車がこちらに向かってくるのが見えた。
やや縦長のシャープな車体は、上部がベージュ、下部が鮮やかな赤のツートンカラー。地元では「シュトラーセンバーン」と呼ばれるトラムだった。
運転手と目が合った。停留所はすぐ傍だったが、真由子はさり気なく視線を外した。それが旅の目的のはずなのに、どうしても、足が向かない。トラムが遠ざかるのを見送って、どこか目指す場所があるかのように、小走りでリンクを横切った。
少し歩くと、地下鉄のマークにカールスプラッツと読み取れる表示があった。確か、左に折れると、ニューイヤーコンサートで名高い楽友協会ホールがあるはずだった。新婚旅行で訪れて観光しただけなのに、土地勘が残っていることに、少なからず驚く。
──うちの百貨店は、ウィーンに支店があるんだ。僕も研修で滞在したことがある。短い期間だったけど、とても良い街だった
百貨店の外商部勤務の徹のひと言が決め手になって、夫婦となって初めて訪れる地をウィーンに決めたのだ。
見合いから半年ほどで結婚に至った二人にとって、異国での五日間で互いを深く知るのは、とても心躍ることだった。
もちろん、それまでに幾度もデートを重ねてはいたけれど、恋人同士の甘やかなものとは程遠かった。どちらかといえば周囲から望まれるまま「結婚」というゴールに向けて二人三脚で走っている感じだった。ウィーンに来て初めて、お互いにちゃんと向き合えたように思う。
タオルひとつ取っても、厚手と薄手、どちらが好みか。柔軟剤を使うか否か。習慣や好みの違いに驚いたり感心したり、と忙しかった。
個人旅行だったので、時間やスケジュールに縛られることなく、ゆっくりと好きな場所、気になったところだけを観光した。手を繋ぎ、学生時代の思い出や好きな本のこと、色々な話が出来ることが楽しかった。
何より、トラムの木製の椅子に座り、肩を寄せ合って車窓を眺める時間の愛おしかったこと。外の寒さを感じないほどに、ガラス窓から明るい陽光が射し込んでいた。
トラムは「一番」が内回り、「二番」が外回りで、どちらも三十分ほどをかけてリンクを一周する。美術史博物館、マリア・テレジア広場、自然史博物館、国会議事堂、市庁舎、ウィーン大学、ドナウ河沿いから応用美術館、市立公園と、車窓に映る景色には飽きることがない。
──今は都内も郊外も土地が高くて手が届かないけれど、こつこつ貯蓄して、いずれ一戸建てを持ちたいんだ
そんな夢も打ち明けられた。
株価が急落し、バブル景気に陰りが見え始めていたものの、地価はまだ高い。それぞれの親に援助してもらうことも出来るだろうに、それを良しとしないひとだった。そんな誠実で真っ直ぐな人柄をとても好ましく思い、ともに生きる幸せを噛み締めていた。
最終日、再訪は何時とも知れないため、ふたりしてぎりぎりまでトラムに揺られ、愛しい街を瞳と心に刻んだ。
あれから丁度、十年。
我が子を授かる喜びと、その子を弔う悲しみ、人生の天国と地獄を経験することになるとは思いもしない。
ゴメンね、由希、と真由子は胸もとのリボンに手を遣って、娘に詫びる。
トラムに乗り込む自信がない。
乗れば、人目も憚らずに泣いてしまいそうだった。
前方に、赤茶けた外観の建物を認めた。見覚えのあるそれは、楽友協会ホールだった。
取り敢えず、今日を過ごす場所を見つけて、真由子は小さく吐息をついた。