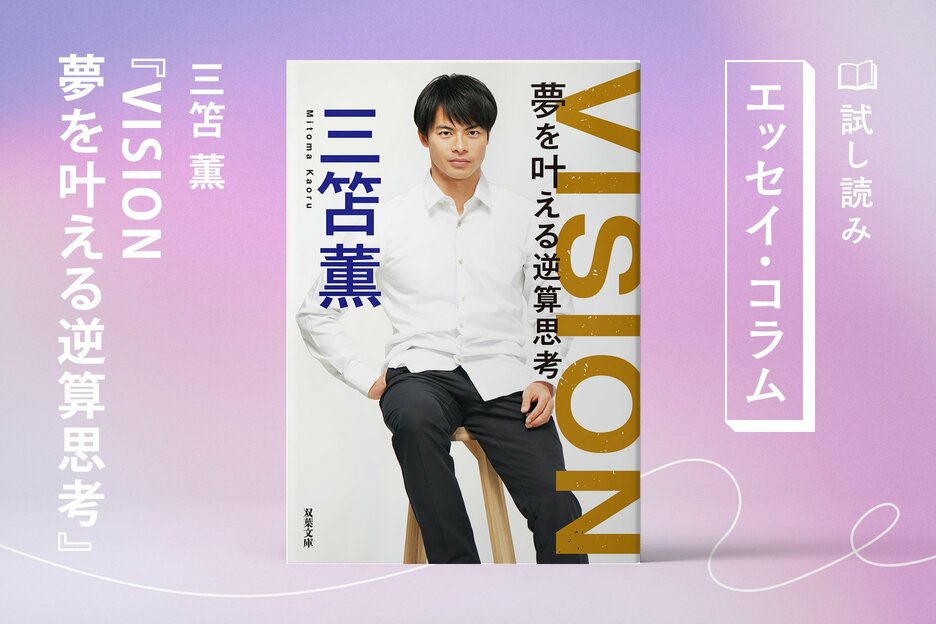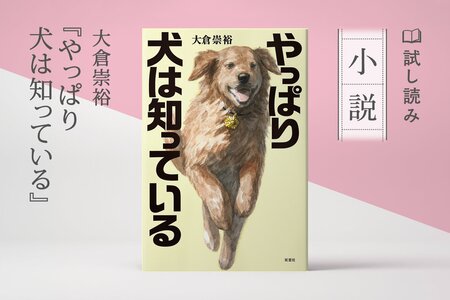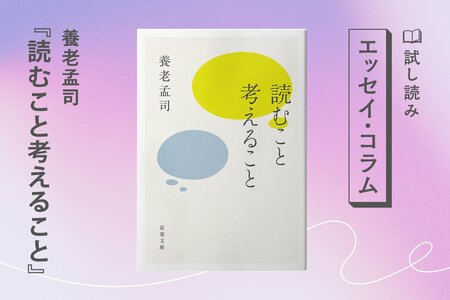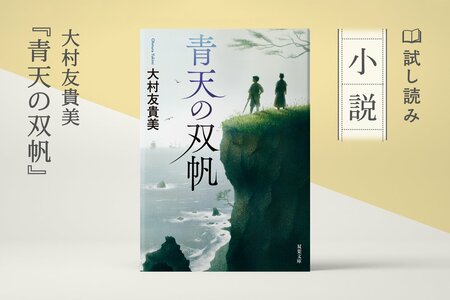三笘家の「褒める教育法」と
サッカー少年の父兄に伝えたい「“加点式”の考え方」
謙虚な三笘は「自分は自慢すべきことなどない」と言う。ただし例外はある。家族の絆と仲の良さだ。日本では一般的な「減点式」の教育法ではなく、良かったところを褒めてくれる「加点式」の教育法が、三笘を大きく成長させた──。
僕には取り立てて自慢できるものはないと思っているが、家族には感謝している。川崎フロンターレ時代のプロフィール「尊敬する人」「ホッとする瞬間」「この世で一番大切なもの」欄には、いつも両親や家族のことを書いていた。
本当に尊敬する人は両親だと思っているし、家族の仲の良さは我が家のプチ自慢だ。プロになってからも、LINEのグループチャットで、しょっちゅう連絡を取り合っていたし、その習慣は僕がヨーロッパに来た現在も変わらず続いている。
父については先に少し触れたが、母もまた、僕がサッカーをすることについてあれこれ口出しをすることはなかった。試合に向かう時、試合から家に帰る時には母が送り迎えを多くしてくれており、両親とも見守ってくれていた。
「見守ってくれた」のは試合会場でもまったく同じで、僕の試合を見に来ても目立たないようにこっそりと観戦しているような両親だった。車で送迎してもらっている時も、別に試合の話をしながら帰るというわけではなく、試合に負けてしまった時などに「あれは良くなかったね」とか、何か言われることもなかった。
むしろ、試合に負けて僕が本当に悔しい思いを抱えている時こそ、母などは優しい言葉をかけてくれた。「あのプレーが良かったね」とか、僕の良かったところを褒めてくれるのだ。試合の後、母が迎えにきてくれるとなんだかホッとしたのは、いつでもそっと僕のことを信じてただ静かに見守ってくれていたからかもしれない。
日本の子育てや教育ではどうしても“減点式”の教えが先行しているように思う。「間違えてはいけない」、「失敗してはいけない」と、ミスを避けることを教えるような傾向にあると思うのだ。でも、特に海外移籍をしてヨーロッパに来て強く思うのは、成功すれば称賛を得られる“加点式”の考え方が主流だということである。
もちろん、失敗を修正していくことは大事なことだ。ただ、修正するためには原因を見つけ出し新たなことを試みる「トライ・アンド・エラー」が必要だ。失敗をした時は「ミスを責める」よりも、良かったところを「褒めてあげる」。一緒に成長の糧を見つけられたことを喜び、物事をポジティブにとらえていけるように子供を育てたほうが良いと思う。今の僕があるのは、両親も含めて、そうした褒める考え方を実践してきたからだと思っている。
プロ選手になってから、ウェブメディアの企画で母への感謝を手紙にして渡したことがある。いつもグループLINEで連絡は取り合っているが、手紙を書くというのはなかなかないことだった。
そのウェブで公開された手紙を見た方から、「達筆ですね」とのお褒めの言葉をいただいた。「子供の頃に習字を習っていたのですか」と尋ねられたのですが、そういう経験はない。
ただ、字をきれいに書ける人は格好いいなと昔から思っていて、自分もそうなりたいと思って、丁寧に字を書くように意識してきた。家族の仲の良さと同じく、字を丁寧にきれいに書けるということも僕の数少ない自慢かもしれない。
体が小さいことがコンプレックスだった小・中学校時代
「茶そば」「パイナップル」「キウイ」で補完
体が小さかったと言う三笘。川崎フロンターレのユースに入り、“サッカー漬け”の日々が始まると、適切な栄養補給が不可欠となった。体を作る成長期に何が必要なのか。そこには母の深い愛情があった──。
母には、練習や試合の送迎以外にも、普段の生活から助けられてきたので、感謝してもしきれない。怒らずに褒めてくれた教育もそうだが、やはり「母の味」には感謝している。僕は小さい頃、なかなか身長が伸びなくて体が小さいことがコンプレックスになっていた。
小学校の頃は、1学年違うだけでもけっこうな体格差がある。僕は小柄な部類に入る子供だったので、自分より体の大きな選手とのボールの競り合いでは負けてしまって悔しい思いをすることがあった。
川崎フロンターレのU‐12(12歳以下)のチームに入ってからは、週3回くらいのペースで練習があった。通っていた鷺沼小学校で授業が終わった後、すぐに家に帰って練習用の荷物を持ち、最寄りの鷺沼駅から東急田園都市線に乗って乗り換えをして、さらにバスに乗り継いで練習場に通っていた。グラウンドに着いたらまずミーティングをして、トレーニングが終わったらバスと電車を乗り継いで家まで帰っていた。
練習に通うのには時間がかかったが、家庭で晩ごはんを食べる時間には帰ることができていた。しかし、中学生になってフロンターレのアカデミーでUー15(15歳以下)チームへと進級すると、サッカーにあてる時間が一気に増えていった。やはり授業が終わると急いで家に帰り、すぐさま練習場に向かう日が続いたのだが、小学校の頃よりも練習日が増えた。中学校時代には、「オフは月曜日だけ」というサッカー一色の生活に突入していった。
その頃は、練習後に食事を出してもらえるようになっていた。練習を終えてすぐに、体に栄養を補給するためだ。そのほうが、体力の回復に役立つということを教えてもらうなど、フロンターレでは選手の食事に関して、とても気を遣っていたのを覚えている。選手が小学生の頃から、保護者に対して食事や栄養に関する講習会を開いていたほどで、栄養士の方が講師として招かれて、選手の親御さんに対して栄養講習会を開いてくれていた。
その授業では、三大栄養素と言われるたんぱく質と炭水化物(糖質)、脂質といった要素がどのような作用を持っているかといった話や、バランスの良い食事とはどういうものなのか、食材として何が必要なのかなど、事細かに教えてくださっていたそうだ。
僕も後年は食事に気を遣うようになっていったのだが、残念ながら当時はそういうことにはまだまったく興味がなかった。でもその分、母がしっかりと栄養に関する知識を身につけてくれたのだ。
栄養についても、母からあれこれ注意を受けたりすることはなかったが、講習会で得た知識をお弁当のメニューなどに落とし込んでくれていたと思う。そうした母の深い愛情や協力があったからこそ、次第に体が大きくなっていったのだと思っている。
お伝えしたように、中学生になると練習時間が長くなり、帰宅時間が遅くなることが増えていた。練習後にユースで出していただいたごはんを食べて帰ってくると、家に着くのが夜の10時、時には11時を過ぎることもあったが、中学校に入ったばかりの頃はまだ体は小さいほうだったとはいえ少しずつ食は太くなっていたので、練習を終えて家に帰ってくると、けっこうお腹が空いていることがあった。
そんな時に嬉しかったのが、母が出してくれる茶そばだった。疲れた体には、さらにおいしく感じられて、今でも茶そばは大好物である。
そばには、人間の体の中では生成することができず、外から摂取するしかない必須アミノ酸などが含まれている。また、筋肉などを作る要素であるたんぱく質も豊富だ。
ビタミンB1、B2といった疲労回復を促す栄養素が多いことも、練習から疲れて帰ってきた僕には最適だったのかもしれない。
フルーツを出してもらうこともあった。パイナップルにはビタミンB1が含まれているし、消化も良いので、夜食にぴったりだったと思う。大学に入って自分で朝食を用意するようになった時にもパイナップルを食べていたし、骨や血管を強くするために必要なビタミンCを多く含んだキウイも食べるようにしていた。
母が作ってくれる食事には本当に助けられたと思っている。
ドリブルという「自分の武器」ができた理由
三笘といえば、今や世界中の名手が集まる最高峰のプレミアリーグにおいても注目されるドリブラーだ。日本でも、華麗に相手ディフェンダーをかわして決定機を作り出す姿が伝えられている。だが、成功の裏には多くの失敗がある。それでもブレずに勝負してきたからこそ、現在の“サムライ・ドリブラー”三笘がある──。
サッカーとはどういう競技であるか──僕はこれを先でも述べたようにイングランドのプレミアリーグなど、海外の選手たちのプレー映像を見ながら学んでいった。
一方、僕もよく見ていたスペインのバルセロナは、全盛期にはものすごいパスサッカーを展開していた。パスが細かく、かつ小気味良くつながるスタイルは、ボールを蹴る音をもじって「ティキ・タカ」と呼ばれ、世界中のサッカーファンの喝采を浴びていた。
リスクを冒しながらも全員がパスを出す相手を探し、同時に自分も最適なポジションを取る。その繰り返しでポンポンとボールがつながり続ける──。そんな「賢人」とも言われるペップ・グアルディオラ監督率いるバルセロナのサッカーを、日本のたくさんのチームも夢見て真似しようとしたものだった。
でも、そういうサッカーを披露できたのがバルセロナや、そのクラブの選手たちを中心としたスペイン代表といった、世界でもほんのひと握りのチームだけだった事実が物語るように、究極のパスサッカーというものはそう簡単にできるものではない。第一に選手全員の能力が高くなければいけないし、さらには選手全員が思い描く「絵」、「意思」が合致しないと完成されないのだ。
サッカーという競技の本質は、「最短で素早くゴールに向かうこと」なのだと思う。
もちろん、時間帯や状況によってさまざまな戦術が必要になってくるが、僕はやはり1対1にドリブルで勝ち、ゴールを決めることに重きを置きたいと考えている。それを実行して勝利と栄光をもぎ取り称賛を浴びるメッシ選手やロナウド選手の姿を見て育ってきたからだ。「そういう1対1に強い選手になりたい」と思って僕はサッカーに取り組んできたし、そこにこだわってきたからこそ、プレミアリーグでプレーすることができていると思う。
さぎぬまSCや川崎フロンターレの下部組織でプレーしていた小学生時代も、自分がゴールを決めるんだという強い意志を持って1対1のドリブル勝負を仕掛け続けていた。もちろん毎回勝てるわけではなく、ディフェンダーに止められてしまい、周りの選手たちから「どうしてパスを出さないんだよ!」と文句を言われることもあった。ただ、そうやって非難を受けても、1対1のドリブル勝負に1回でも勝利してそこでゴールを決めることができたら、そのゴールが決勝点になって試合に勝てるかもしれない。それがサッカーなのだと考えていた。
小学生の頃にはそういう気持ちを持っていた選手でも、中学・高校と進み年齢を重ねていくことで、チームプレーと自分自身の理想のプレーのバランスを取ることが、だんだんと難しくなっていく。それは、僕も経験してきたことだった。
でも、「自分が勝負を決めてやるんだ」という気持ち、また、そうしなければならないという責任感は常に持っていなければいけないと思う。周りの選手やコーチに「パスを出せ」とか「全部自分だけでやろうとするな」などと言われたとしても、1対1のドリブル勝負を仕掛けて成功させれば、その瞬間にそうした声は称賛に変わるからだ。
「1対1にこだわる」、「自分で仕掛けてやってやるんだ」というメンタリティが揺らいでしまったら、ドリブルを武器としてサイドで生きていくアタッカーは失格だと思う。そういう常にブレずに仕掛ける心構えが折れてしまったら、その時点でディフェンダーでも中盤の真ん中でもいいから、自分のポジションをコンバートしたほうがいいかもしれない。そのくらいに、「ドリブラーとしての矜持(こだわり、プライド)」は必要なのだと思う。
小学生の頃はもちろんのこと、中学・高校時代の川崎フロンターレのアカデミー、さらには筑波大学に入ってからも、色々な仲間に迷惑をかけたことは自覚している。文句を言われながらも自分を貫いた僕自身はドリブルの技術は成長するけれど、その分、他のチームメイトが成長していく時間をつぶしてしまっていたかもしれない。
それでも、たとえ1対1でドリブル勝負に勝てずに文句を言われようとも、僕は自分に「今は失敗する段階なんだ」と言い聞かせてきた。当時、体の小さかった僕は、自分がサッカーで勝ち抜いていくためにはどうしたら良いかと常に真剣に考えていた。その中で導き出した結論が、それだけ強く、「プロのサッカー選手になるにはドリブルという自分の武器を持つ」という考えだった。
僕が大好きだったクリスティアーノ・ロナウド選手も、時にはエゴが強すぎると非難されることがあった。でも、子供の頃の僕は、彼の自分を信じて勝負する姿を見て、感動や勇気をもらっていたのだ。
僕は今、ロナウド選手が所属していたマンチェスター・ユナイテッドと同じ、プレミアリーグの舞台にブライトンのユニフォームを着て立っている。次は僕が、子供たちに自分の背中を見せる番だと思っている。
この続きは、書籍にてお楽しみください