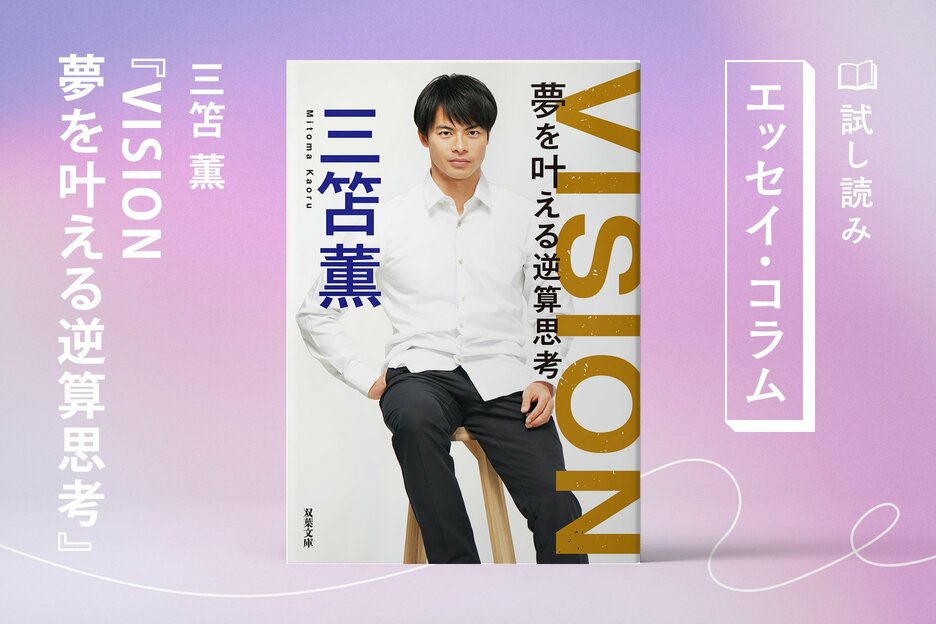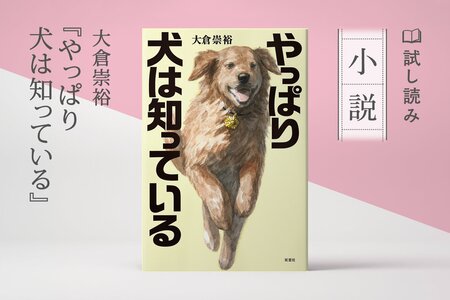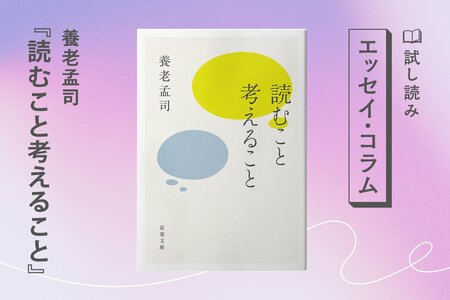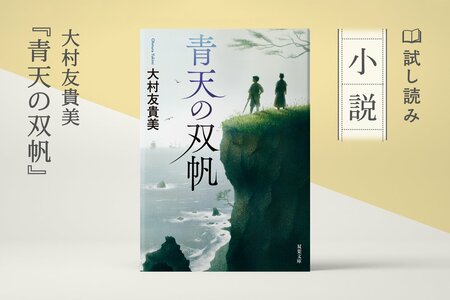さぎぬまSC時代の「基礎練習」は「リフティング」「コーンドリブル」
プロのサッカー選手といえども、最初から華麗な技術を誇っていたわけではない。また、すべての選手がエリート組織で育てられ続けてきたわけでもない。三笘の最初のサッカーキャリアも、地元にあるクラブからスタートした。だが、“普通の生活”の中にこそ、重要な要素がちりばめられている。
3歳年上の兄の影響で始めたサッカー。僕が初めてクラブに所属したのは小学校1年生の時だった。地元のさぎぬまSC(サッカー・クラブ)というチームだ。
幼稚園の頃から、アカデミーでたくさんのプロ選手を育ててきた東京ヴェルディのスクールや、東京にあるムサシサッカースクールというところでも、ボールを蹴っていた。僕が育った川崎市の宮前区は市の北部に位置していて東京に近く、ヴェルディのスクールが開催されるグラウンドまでも近かったからだ。それでも、「やはり地元が良いな」と思い、さぎぬまSCでサッカーを続けることを選んだ。
さぎぬまSCは1979年創部で、神奈川県ではそれなりに強いチームとして知られており、僕が入部する前にも、タイトル獲得こそないものの県大会で準優勝するなどの結果を出していた。
僕以外にも、その後に日本代表となる権田修一選手(現清水エスパルス)、板倉滉選手(現ボルシア・メンヒュングラートバッハ=ドイツ)、田中碧選手(現フォルトゥナ・デュッセルドルフ=ドイツ)も輩出している。
さぎぬまSCに入った当初は、ヴェルディスクールにも掛け持ちで通っていた。東京ヴェルディと言えばJリーグ草創期をけん引した名門で、スクールの指導者の方々はのちにプロ選手になる子供たちを多く見てきた経験がある。そのブランドに憧れて人が集まってくるという事情もあって、「さぎぬまSCより技術の高い子が多いな」という印象だった。ただ、さぎぬまSCにもこのクラブならではの良さがあった。父兄の方々も積極的に練習に参加するアットホームな雰囲気があって、僕たちは楽しくサッカーをすることができたからだ。
毎年夏休みには、チームで夏合宿に行っていた。その時に文集を作るのだが、僕が書いていたのはサッカーのことではなく、みんなでやったスイカ割りのことだった。チームの中で僕が最初にスイカを割ることができたので、このことを書かずにはいられなかったのだと思う。
もちろん、サッカーの練習も一生懸命だった。練習場所は、僕が通っていた鷺沼小学校のグラウンドや近くの野球場だった。人工芝や、ましてや天然芝があるはずない、普通の公立小学校の土のグラウンドだ。その校庭で週に数回、練習や試合に励んでいた。
小学生の頃は、さぎぬまSCの後に所属することになる川崎フロンターレのUー12(12歳以下)のチームでもそうだったが、「ボールを止める→蹴る」といったプレーなど、基礎的な練習をしっかりこなすことができたと思う。
練習内容も特別に凝ったものではなく、コーチに転がしてもらったボールに走り込んでシュートを打つとか、コーンを置いてその周りをボールをコントロールしながらドリブルするといったもの。本当に「どこにでもある街のサッカークラブ」といった感じの練習をひたすら繰り返していた。
僕は当時から、ボールを持って相手を抜こうとする攻撃側と、その攻め手を止めようとする守備側が個人の勝負をする「1対1」の練習が好きだった。ドリブルの練習をするにしても、動かないコーンを置いてやるよりも、誰か友だちを呼んできて1対1の相手をしてもらうことが多かったと記憶している。
練習時間はおよそ1時間半。小学生の頃は、グラウンドの広さも1チームの人数も、試合時間も大人とは違うが、サッカー本来の試合時間である90分間を意識したものだったのかもしれない。
指導者の方々には、「周囲に感謝する気持ち」や、チームスポーツであるサッカーにおける「協調性」の大切さも教えていただいた。
当時を見ていてくれた指導者の方が、僕が8歳で「ゲーゲンプレッシングのようなプレーをしていた」と、メディアの取材で話しているのを目にした。相手にボールを奪われた時に素早く取り返して、その勢いのままに前に出た相手の裏へと攻めていくという、現代サッカーで広く取り入れられている戦術であるが、「自分がそんなことをしていたなんて本当かな」と、少し照れくさく思う。話によると、「小学校低学年の子供は誰もが触りたいものだからボールの周りに群がってしまうものなのだが、僕だけ少し離れた場所に付き添うように走っていて、仲間がボールを奪われた瞬間、すぐに取り返して素早く攻撃につなげていた」ということのようだ。
さぎぬまSCでは、紅白戦をするためにチームを2つに分けた時にキャプテンを任されることもあった。そうなると、「自分がしっかりとチームを勝たせる役目をしなければいけないんだ」と、少しずつ責任感も芽生えていったように思う。
エリート教育だったわけではないが、基礎技術の徹底やチーム内での協調性、そして何より、「サッカーを楽しむこと」を教えてくれたさぎぬまSCでの時間は、僕の貴重な“原点のひとつ”だと思う。鷺沼小学校の校舎の囲いには、僕と碧の名前と「鷺沼から世界へ」の文字が刻まれた横断幕が掲げられているという。ぜひ、僕らを超えるような世界で活躍する選手が多数出てきてくれることを願ってやまない。
メッシ、C・ロナウド──世界最高のトップ選手
「プレー映像」を見て繰り返した「サッカー脳」の作り方
今では自身がサッカー少年たちのスーパーヒーローとなったが、小学生の頃の三笘にも憧れの存在はいた。彼らのプレーの映像を何度も目に焼きつけているうちに、自分の理想像が形作られ、目標がしっかりとできあがっていったという。子供の頃に目指した場所に今、三笘は立っている──。
僕は小学校の頃、海外サッカーのハイライトを扱った番組に夢中だった。当時は『すぽると!』(フジテレビ系)や『やべっちFC』(テレビ朝日系)など、海外サッカーの試合をハイライトで見せてくれる民放テレビ局サッカー番組があった。そういう番組を録画しておいて、何度も何度も繰り返し見ていた。
小学校時代の僕にとってのスーパーヒーローは、スペインの名門バルセロナでプレーしていたアルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手や、やはり世界的に有名なイングランドのクラブであるマンチェスター・ユナイテッドでゴールを奪いまくっていたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手だった。当時は、まだ2人が世界のサッカーシーンに登場したばかりの頃。その後、10年以上にわたって、世界最高のサッカー選手に贈られる個人賞であるバロンドール賞を、ほぼ独占してきた2人。その圧倒的な超スーパープレーに、心を奪われていた。
最初の頃は、マンチェスター・ユナイテッドでものすごいスーパープレーを連発するクリスティアーノ・ロナウド選手のフリーキックやドリブルを、ただただ「すごいなあ」と感心しながら何度もVTRをリプレイして見ていた。メッシ選手がいたバルセロナは、ちょうど僕が見るようになった頃が、改めて強くなり始めていくという再出発のような時期だった。
当時のペップ・グアルディオラ監督が率いるバルセロナには、スペイン代表としても活躍していたシャビ・エルナンデス選手や、2010年にはバロンドールの投票でメッシ選手に次ぐ2位になり、2018年にはなんとJリーグでプレーすることになるアンドレス・イニエスタ選手(現ヴィッセル神戸)がいた。その世界的な名手のスーパープレーを見ては、一生懸命真似をしていたのを覚えている。当時の僕はボランチなど中盤の中央でプレーすることが多かったため、バルセロナとスペイン代表で同じポジションを務めるこの2人は、とても参考になったのだ。
最初の頃は、スーパースターのものすごいスーパープレーを憧れの目で見るだけだった。しかし、何度も何度も……スーパープレーのハイライト映像を目にしていくうちに、見方が変わっていったのである。例えばボランチの選手だったら、敵、あるいは味方の選手からこぼれてきたセカンドボールを回収することが大事になってくる。そこで、当時ボランチだった僕の頭に浮かんできたのは、「どうしてシャビ選手やイニエスタ選手は、誰よりも早くセカンドボールを拾えるんだろう」という疑問だった。
そう考えて映像を見直してみると、2人ともこぼれる前からボールの行方を予測して、先に動き出していることが分かった。これは大きな発見だった。以来、「こういう状況だと、こういう場所にボールがこぼれていくものなのか、なるほど……」と、自分の中に情報を落とし込んでいくようになった。
そういう作業を重ねていくうち、いざ自分がピッチに立って直感的なプレーが求められるような場面でも、瞬間的に「たぶん、ここにいたほうがいいな」と考えられるようになっていったのだと思う。先述したゲーゲンプレッシングのような動きが頭にひらめくとか、僕にとりたててそういう才能が先天的に備わっていたのではないと思う。
ただ、おそらくサッカーを見ている“量の違い”が、“瞬時の判断の違い”につながっていったのだろうと思う。脳がそのように自然と進化していったのかもしれない。
そういった一つひとつのプレーを見ていくうちに、「どういうところからチャンスが生まれるものなのか」、さらにさかのぼって、「そのためにはどういうプレーが効果的なのか」、さらには「そもそもサッカーとはどういうスポーツであるか」といった、サッカーという競技の全体像を頭の中でイメージできるようになっていったのだと思う。
僕は小学生の頃、プレミアリーグを特によく見ていた。アレックス・ファーガソン監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが強かった時代だ。そのおかげで、「サッカー発祥の地であるイングランドではどういうプレーが称賛されるか」ということを、知らず知らずにインプットしていたのかもしれない。この時の体験が、同じプレミアリーグのピッチに立つことになった現在の僕の考え方に影響していると感じている。
もちろん、プレミアリーグにも個性が異なる選手やチームがあるし、スペインなど他のリーグのサッカーも少年時代から見ていた。おそらく、そういう多種多様な情報が蓄積されていって、小さい頃から“大人のサッカー”をしようとしていたんだと思う。
日本の選手では、『プロフェッショナル 仕事の流儀』(NHK)に登場した元日本代表の本田圭佑選手を見て、大きな刺激を受けたことを覚えている。子供ながらに、一流の選手がどういう生活をしていて、どういうメンタリティでサッカーと向き合っているかということを学んだ。本田選手の言動やメンタルの強さは衝撃で、「こういう選手がトップに行くのだな」と感化された。
毎日後悔したくないという気持ちは人一倍強いし、目標を実現するために生活しているからこそ現在の僕がある──という面もあるので、子供の頃に目標とする選手や理想とする選手を見つけられるのは幸せなことだと思う。
「VISION 夢を叶える逆算思考」は全4回で連日公開予定