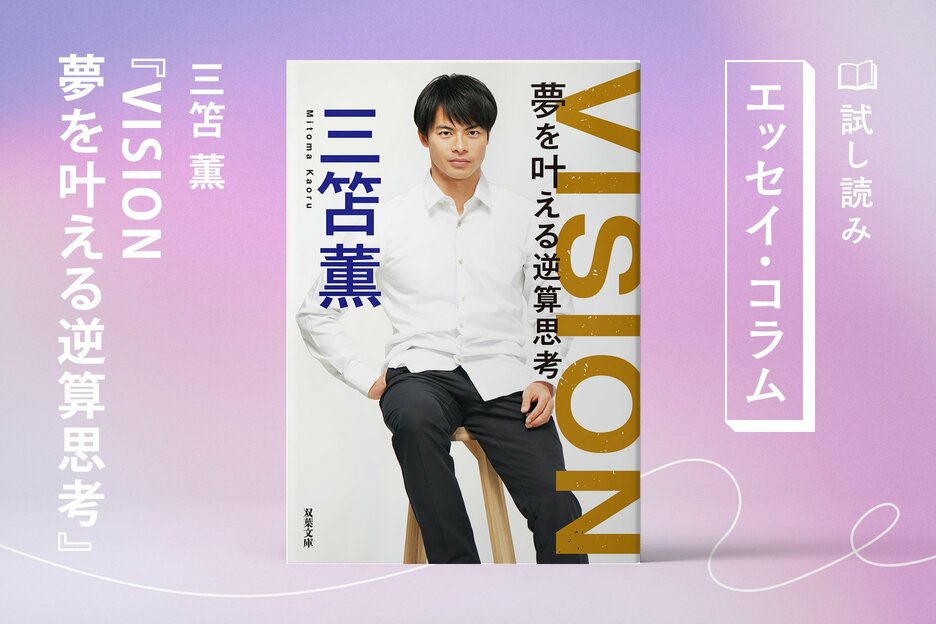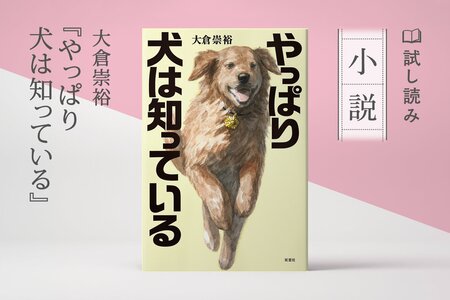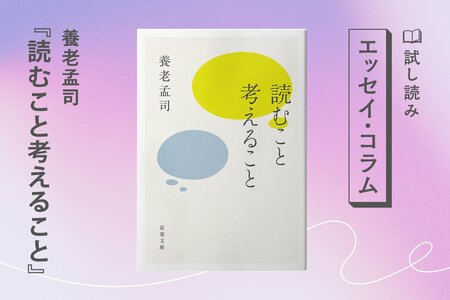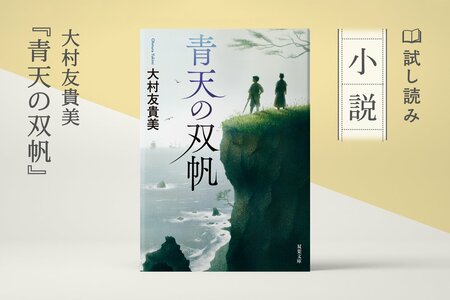自由尊重だった両親、我が家のサッカーゴール、
2002年ワールドカップ・日韓大会
プロの舞台にたどり着くまで、エリート街道を歩み続ける選手もいる。そのスタート地点が幼少期で、親によってレールを敷かれて進んでいく場合もあるだろう。だが、三笘は決して「作られた選手」でも、「育てられた」選手でもなかった──。
3歳でサッカーを始め、ずっとボールを蹴り続けていたことは、プロのサッカー選手になるうえでアドバンテージになったと思う。技術的にもそうだが、勝負事に必要な負けん気や闘争心も成長するからだ。
ただ、僕が特別な子供だったかというとそうではない。どこにでもいる普通の子だったと思う。小学校の先生からも、そう思われていたようだ。放課後はよく、みんなとサッカーをしたが、それも友だちと遊びたかったからだ。
もちろん、サッカーばかりやっていたわけではない。ゲームもよくしたし、親の目を盗んで寝る前まで布団をかぶってゲームをしていた時期もあった。当時、プレイステーション2とゲームキューブを持っていて、クリスティアーノ・ロナウド選手(現アル・ナスル=サウジアラビア)が表紙の『ウイニングイレブン 2008』や、その翌年に出たリオネル・メッシ選手(現パリ・サン=ジェルマン=フランス)が表紙の2009年版をクリスマスプレゼントでもらって、遊んでいたのを覚えている。他にも、『マリオパーティ』や『ポケモン』にも夢中になっていた。ゲームやマンガに夢中になることは、子供なら誰にでもあることだと思う。つまり、僕自身も本当にどこにでもいる普通の子供だったということだ。
ただ、とにかくサッカーに本気で夢中だった。小学校低学年の頃は、サッカーと並行して、2年弱くらいスイミング教室にも通っていた。今は陸上競技やテニス、卓球とサッカー以外のスポーツも好きだが、当時の水泳は特別好きでやっていたわけではなく、「早く終わらないかな」と考えながら、プールで泳いでいたのを覚えている。きついながらもやらされていた部分はあったので、我慢強さは身についたと思う。泳ぎ方も色々あるし、全身や関節を上手く使って前に進まないといけないスポーツのため、最初にやっていて損はないし、水泳をやっていて良かったなと思う。我慢強さや全身と関節の使い方を学べたということもあり、サッカーに与えたプラスの影響もあるのではないかと思う。その意味で、サッカーをやるうえで子供時代に「スイミング教室」に通うのも良いことかもしれない。
両親も一般的なお父さん、お母さんだったと思う。いわゆる“教育ママ”のように口うるさく何かを言われた記憶もない。どこにでもある家庭と同じように、「テレビゲームをやりすぎないように」と注意されたこと。テスト前日に勉強もせずに友だちとサッカーしていたら、「明日テストじゃないの? テスト勉強はしっかりやりなさい」と言われたことくらいだ。
父も、おおらかに見守ってくれる人だった。父もサッカーが好きだが、たまにキャッチボールもしたのを覚えている。僕がピッチャー役になって、グローブを構えた父に投げ込むこともあった。
そんな父からの忘れられないプレゼントが、「小さなサッカーゴール」だ。2002年、僕が5歳の時に開催されたワールドカップ・日韓大会を見て、一気にサッカーにのめり込んだ僕と兄のために、家の中に小さなゴールネットを作ってくれたのだ。
我が家にサッカゴールがやって来た──その日から、リビングと隣の部屋を使って、兄と夢中でサッカーをしていた。交代でゴールキーパーとキッカーを務めてPK戦ごっこをしたり、狭い場所にもかかわらず、1対1の勝負もした。ご近所さんにはドタバタ音がして迷惑をかけてしまっていたと思うが、あの小さなゴールを使ったサッカーも、僕の“原点のひとつ”なのかもしれない。
日韓大会を皮切りに、ずっとワールドカップを見続けてきた。日本代表は惜しくもベスト16でトルコに0―1で敗戦したが、ピッチに立っていなくても日本代表の選手たちと一緒に喜び、悔しい思いも味わってきた。だからこそ、「自分もいつかここでプレーしたい」と思い続けてきた舞台に立つことができた時は、言葉では言い表せないくらい感慨深いものがあった。稲本潤一選手(現南葛SC=関東サッカーリーグ1部)がベルギー戦でドリブル突破でボールを運び、相手ディフェンダーを強引にかわした強烈な左足シュートは今でも鮮明に覚えている。
僕が日本代表に選ばれた時は、両親もとても喜んでくれたが、幼い頃を思い出すと、「サッカーをやりなさい」と言ったり、何かにつけて干渉してくるというタイプではなかった。記憶にあるのは、そっと見守ってくれた姿だ。
親と子供の距離感については、ひと言でまとめるのは難しいと思う。例えば、同じアジアの選手であり、僕と同じイングランドのプレミアリーグで活躍している韓国代表のソン・フンミン選手(現トッテナム=イングランド)の場合は、お父さんが元サッカー選手で、ソン・フンミン選手が高校生になるまで、ご自分で徹底的に技術指導をされていたそうだ。その結果、プレミアリーグでアジア人初の得点王になるまでに成長していったのだと思うため、どのような距離感が正解なのか断言することはできないだろう。
家庭環境や子供や親御さんの個性によっても、違いは出てくると思う。でも僕としては、誰しも基本的には干渉されすぎると嫌になるものだと思うし、サッカーに限らず、小学生年代にはいかに自主的に物事に取り組んでいくかが大事ではないかと思う。親子といえども、一定の距離はあったほうがいいのではないだろうか。そのうえで、たまにかけてあげるひと言などがきっかけで、子供は成長したり変化したりしていくのだと考えている。だから、親御さんはお子さまをよく観察して、良いタイミングで声をかけていただくのが良いのではないだろうか。
「逆算思考法」を生む「サッカーノート」をつけるべき
サッカーを論理的に思考する。それが三笘の流儀である。子供の頃からの習慣づけが影響したというが、実は文系タイプだったという三笘の「成長の方程式」は、コーチから課された宿題から始まった──。
前述したように、僕は本当に「普通の子」だったと思う。給食のメニューではワンタンスープが大好物で、学校の授業では算数が苦手だった。僕のことを“理論派の選手”と思っている方もいらっしゃるようだが、実は数学などの理数系は、あまり得意ではなかった。どちらかというと、僕は「文系タイプ」で、もちろん体育は大好きだったが、社会の授業も好きだった。
歴史に興味があって、今でもYouTubeで偉人の本の要約動画を見たりしている。どの時代の人も同じような失敗や成功をしていて、いつの時代も人間って変わらないなと思って見ていたりもする。先人たちの知恵と経験が今につながっていることも、歴史から学べるので面白いのだ。最近は、仏教や中国の思想の動画を見ているが、自分自身を見つめ直すうえで勉強になっていると思う。昔から暗記は苦ではなかったので、テストの点数も良かった。だから自然と、社会の授業が好きになり、得意科目になっていった。
僕の文系としてのキャラクターは、サッカーにも活きるところがあった。その後、川崎フロンターレのアカデミーに入ってから、「サッカーノートを書く」という毎日のルーティンが始まったからだ。
当時は、1週間の練習を終えた後、サッカーノートをコーチに提出することが義務づけられていた。日々練習したことや、そのメニューに対して自分で考えたことをノートに書き留めていき、僕の考えに対してコーチが赤ペンで意見を書き入れてくれたり、指導をもらったりして、少しずつサッカーへの理解を深めていくというものだった。
ノートの提出は1週間に1度なので、まとめて書いても大丈夫だった。ただ、練習はほぼ毎日あるため、家に帰ってから寝るまでにその日のことを書いておかないと、次の日にはまた別の練習があり、書かなければいけないことがどんどんたまっていってしまう。
書くことが2日分たまっただけでも、「もうダメだ」となってしまいアウトだった。前の日の練習でやったこと、それについて自分が考えたことを整理する前に、また新しいことが頭に入ってくることで、忘れてしまうのだ。ノートを溜めてしまったので、「こんなものだろう」となんとなく書いて提出したこともあったが、やはりコーチには一発でばれてしまった。やはり、毎日コツコツと書き続けないといけないし、毎日続けるということが大事なんだと学んだ出来事だった。
サッカーノートを書く、しかも日課としてこなすというのは、簡単なことではなかった。時には学校が終わってから練習場に向かうまでの道中、南北に長い川崎市の中で東京都との境にある僕の家から南部の川崎駅近くにある練習グラウンドへ向かう電車やバスの中などでの時間を利用して、急いで書いたこともあった。真っ白なノートを見て「やばいな」と焦りながら、グラウンドについてから練習が始まる直前まで書いていたことも覚えている。
子供なりに、知恵を絞ったこともある。横書きのノートの両端にできるだけスペースを多く残すようにして、文章をギューッと中心に集めて行数をかせぐ、といった苦肉の策をとったこともあった。
そんなふうに苦しめられたサッカーノートだが、文章力をつけるという点からも大変勉強になったと思う。ただつらつらと書くだけでは、コーチや監督に考えが伝わらないかもしれない。相手にいかに自分の考えを正確に伝えるか、どうやって書けば分かりやすく伝わるのか……という勉強になった。
サッカーノートの書き方については、コーチから指定されていなかった。最初に「サッカーノート」という言葉と、それを書く効果を広く知らしめたのは、日本代表での大先輩でもある中村俊輔さん。選手によっては箇条書きのスタイルを取る人もいたが、僕はたまたま、文章として書くことを選んだ。
文章で書くことで、「試合の中でこうした課題が見つかった」「今日はどういう練習をして、何ができて何ができなかったか」、あるいは「こんな発見があった」、だから「次はこうしようと思う」と、自分に起こったサッカーに関するすべてを順序立てて整理することができた。それはとても大切だと思う。最後には自分なりの結論と、次に進むべき方向が明確になるからだ。そして、その課題を解決するために、日々の練習でアップデートしていくことが大事だと思う。
実際に自分の手で文章にまとめてみると、「自分の思考を整理できる」ということに気づいた。少ししてからサッカーノートを読み返す──ということはほとんどなかったが、それよりも毎日毎日、自分のことを顧みて、その日に考えたことをまとめることで、その場で反省しないといけないことが見えてきたり、「毎日の練習や試合中の自分のプレーから何か“収穫”を見つけないといけないんだ」という気持ちが湧いてきたりしたものだ。チームの約束事であり、言わば宿題ではあったが、サッカーノートを書いたことが現在の「逆算思考法」にもつながっていると思う。
プロになった現在は、サッカーノートは書いてはいない。それでも、文章を書くように思考を整理し、目標を立てる、という考え方は当時から変わらず続けている。また、試合の中で見つけた課題を日々の練習でアップデートすることを、今でも心がけている。言ってみれば僕の「ルーティン」になっているわけだ。
例えば、シーズンが始まる前には「ゴールをこのくらい、アシストはこれくらい決めたいな」と自分の中でイメージして、そのために必要なことを逆算で考えている。もちろん、すべての試合でその時にできる限りのベストを尽くしていくというのが僕のやり方なので、数字にこだわるわけではない。ただ、方向性をはっきりさせる、ということは、とても大切なことだと考えている。
そういう意識づけをするための目標設定というのは、特に小さい頃にはさらに重要になってくるのではないかと思う。プロになった現在は、毎日やるべきことが自然と分かり整理もできているが、小学生の頃はそうではないからだ。
目標を自分で決める良い点は、他にもある。そのゴール=目標に到達することで、達成感を得られるということだ。「本当にできたぞ!」という成功体験の積み重ねが自信に変わり、また新しい目標に向かって頑張っていこうという気持ちを生んでくれる。サッカーノートを書くことは、逆算思考で物事を考える習慣にもつながり、夢に近づく第一歩とも言えるだろう。
ただし、小学校の低学年など、まだ小さいうちには具体的な目標を自分で考えるというのは難しいため、周りのサポートを受けながら、段階を踏んで物事を進めていくことが重要だと思う。もしかしたら、長期的で大きな目標を設定するというのは、成長してからよりも子供時代のほうが、より重要になるかもしれない。今はもうサッカーノートを書いていない僕だが、もしかしたらまた書き始めるかもしれない。昔の自分を振り返っていたら、そんな気持ちになった──。
「VISION 夢を叶える逆算思考」は全4回で連日公開予定