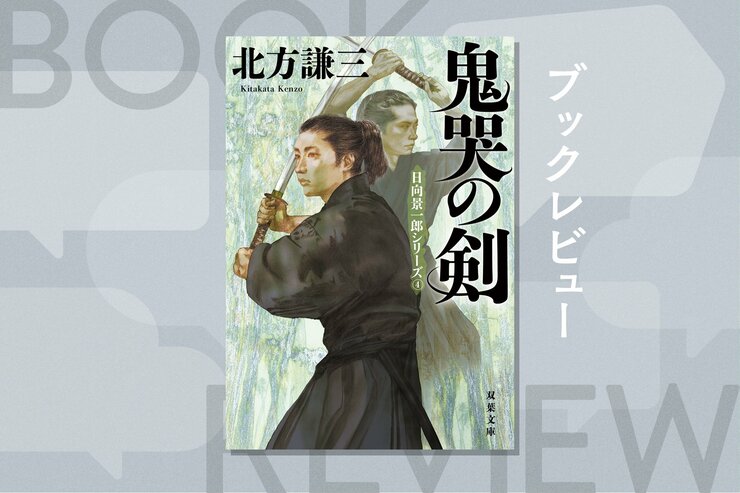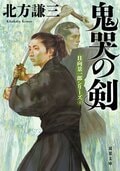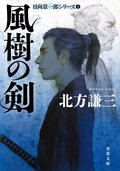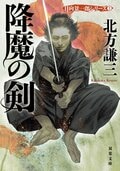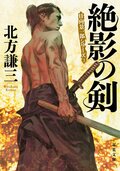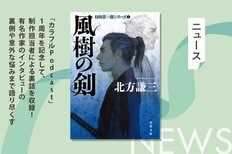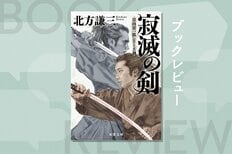2025年1月から復刊がスタートした、北方謙三氏による伝説の剣豪小説「日向景一郎」シリーズ。第4弾となる『鬼哭の剣』は主人公が兄・景一郎から15歳に成長した弟・森之助にかわる。いずれは兄と斬り合う運命にある、といわれ育ってきた森之助が、最強の敵に挑む本作の魅力を文芸評論家の池上冬樹氏が語る。
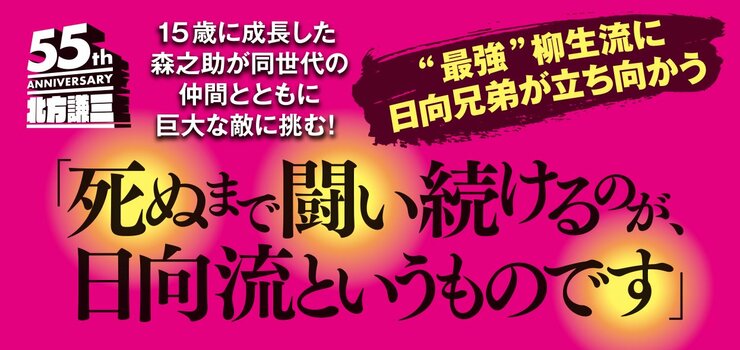
■『鬼哭の剣〈新装版〉 日向景一郎シリーズ 4』北方謙三 /池上冬樹 [評]
これは剣に命をかけた少年剣士の凄まじいまでのビルドゥングスロマンである。
ビルドゥングスロマンとは、様々な体験を通して内面的に成長していく姿を描いた教養小説(成長小説)のことだが、日向景一郎シリーズにおいては、まったく様相を異にする。あまりにも人が多く斬られ、無残にも死んでいくからである。ほとんど戦場といっていいし(前作『絶影の剣』などはまさにそうだった)、戦争小説といってもいい。
本書『鬼哭の剣』では、日向景一郎シリーズにおいて重要な主人公の一人である森之助の視点がはじめて導入される。シリーズは5年ごとの経過をたどり、第一作『風樹の剣』(1993年)は景一郎18歳、之助は中盤に生まれたばかり、第二作『降魔の剣』(97年)は25歳と5歳、第三作『絶影の剣』(2000年)は30歳と10歳、本書『鬼哭の剣』(03年)で景一郎は35歳、森之助は15歳となる。四作目の本書では景一郎は完全に後景に退き、森之助が前景にたち、柳生一族との死闘を演じる。
シリーズ四作目であるけれど、物語は完全に独立しているので、本書からシリーズに入っても問題はない。『絶影の剣』でもふれたことだが、優れたシリーズはどこから読んでも面白い。面白くないとしたら、そのシリーズは凡庸であり、読む必要はないだろう。少なくとも北方謙三は、シリーズの展開を意識しながらも、一作一作独立して、十二分に迫力にみちた物語世界を築き上げている。そしてしばしばジャンルを越え、国境を越え、時代を越えて世界の文学のいまと通じることがある。少し回り道になるが、まずはそのへんから話をはじめたい。海外ミステリの話になるが、海外ミステリのファンにこそ、読んでほしいシリーズであり、読めばかならずや満足するのではないかと思うからだ。
海外ミステリではここ10年、少女が過酷な運命を辿る物語(少女ハードボイルド)が次々に書かれている。20年前までは少年が主人公だったが、いまや少女が主流だ。
たとえば、全米ベストセラーを記録したカレン・ディオンヌの『沼の王の娘』(ハーパーBOOKS)。娘が脱獄した父親を狩る話だ。娘は沼地の電気も水道もない小屋で育ち、サバイバル術を教えてくれた父親を崇拝したが、母親が拉致監禁された被害者であり、自分がその娘であることを知って脱出。そしていま終身刑の父親が看守を殺して脱獄し、沼地に逃げ込んだ。父を捕まえられる人間がいるとしたら、沼地で生まれ育ち、父から手ほどきを受けた娘のわたし以外にいない。こうして父と娘の緊迫した究極のサバイバルゲームが始まる。娘と父の愛憎半ばの激烈な関係を、実にスリリングに劇的に描ききり、ほとんど神話的な響きさえある。力強く心を震わせるスリラーだ。
または、LS・ホーカーの『プリズン・ガール』(ハーパーBOOKS)。18年間、娘を世間から隔離し鍛え上げた父親が死んだ。監禁に近い生活だったが、父親からは軍人のように銃器の扱いと対人戦術を叩き込まれた。いったい何故そこまで徹底的だったのか。遺言執行人から逃れ、父親の遺品を奪い、父親が何者であったかを探っていく。
あるいは、アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀新人賞を受賞したジョーダン・ハーパーの『拳銃使いの娘』(ハヤカワ・ミステリ)。11歳のポリーの前に刑務所帰りの父親ネイトが突然現れ、逃亡の旅に出ることになる。ネイトが獄中でギャングを殺し、組織から処刑命令が出たのだ。母親はすでに殺され、追手はすぐそこまで来ていた。だが、父と娘は逃げるだけではなく、処刑命令を出した組織に損害を与えるため、道々で強盗をくりかえす。ポリーは次第に父親との命懸けの逃避行の中で、殺人と暴力のあふれる世界で生き延びる術を一つ一つ身につけ、悪党達に立ち向かっていく。これがもう実に恰好いい。
さらには、世界中に翻訳されたディーリア・オーエンズの『ザリガニの鳴くところ』(早川書房)。アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀ヤングアダルト部門賞ほかを受賞したコートニー・サマーズの『ローンガール・ハードボイルド』(ハヤカワ・ミステリ文庫)などもある。日本の小説では、アガサ・クリスティー賞を受賞し直木賞候補にもなった逢坂冬馬『同士少女よ、敵を撃て』(早川書房)なども少女ハードボイルドの文脈にあてはまるだろう。
そして忘れてならないのは戦争小説の文脈である。戦争が行われている海外では戦争小説はふつうに書かれているけれど、ケイト・クインのように女性作家が戦場を舞台にして緊迫感あふれる活劇と白熱した人間ドラマを生み出すようになったことである。第一次大戦下で暗躍した女スパイを描く『戦場のアリス』(ハーパーBOOKS)、第二次大戦のさなか、ドイツ占領下のポーランドにいた“ザ・ハントレス”と呼ばれた女殺人者を追及する『亡国のハントレス』(同)、第二次大戦下、390人の敵を仕留めたソ連の伝説の女スナイパーが米国で活躍する『狙撃手ミラの告白』(同)など史実を踏まえながらも大胆な設定を作り、物語に大いなる波瀾をいくつももたせ、生と死のぎりぎりの境界をどこまでもリアルに、実にスリリングに描くのである。日向景一郎シリーズの北方謙三のように。
ということで、枕が長くなってしまったが、本書『鬼哭の剣』の話になる。
物語は、森之助が越後の山の中で、一人の不思議な老婆を目撃する場面から始まる。年寄りで歩くのが難儀だから背負ってくれないかと頼まれるのだが、もうすぐ糸魚川城下に入るところで先を急いでいた。江戸湯島の薬種問屋杉屋清六の大事な使いとして、薬師菱田多三郎に50両を届けることになっていた。杉屋清六が森之助の伯父で隻腕の剣士小関鉄馬に相談したところ、鉄馬は兄の景一郎にではなく森之助に行ってこいと命じたのである。
老婆は年寄りの戯れ言だといってくれて、森之助は先を急ぐ。景一郎にならい、誰よりも歩くのが早かった。しかし森之助は、老婆が自分よりも先に城下に入り、追い越していったのを確信していた。いったい何者なのだろう。
多三郎に金を届ける役目をおえ、多三郎に誘われて、しばらく滞在することになる。城下では10数年ぶりに囚人が引き回されて首を刎ねられることになっていた。だが森之助は関心がなかった。首がとんだり、体が両断される場面など何度も見ていたし、5年前、10歳のときに、奥羽の山中で景一郎に命じられ、自分よりも小さい子供の首を刎ねたことがあったからだ。
多三郎と森之助が見ていると、馬に乗り後ろ手に縛られた罪人が奪い去られる。屋根から転がり落ちてきた男が馬に飛び乗り、走り去ったのだ。
これが冒頭である。老婆、小平太とよばれる罪人、罪人を奪った男たちの素性が明らかになり、やがて多三郎と森之助が接点をもち、後に到着した景一郎とともに、柳生一族との壮絶な血戦が開始される。前半はゆったりと森之助の性的目覚めや初体験などが海辺を舞台に語られる。北方謙三の愛読者なら、玄界灘をのぞむ港町を舞台に、網元の伜として暮らす一人の少年(中学2年生)の成長を捉えた連作短篇『遠い港』(1991年)を思い出すのではないか。普通小説であるけれど、友人や荒っぽい船子たち、ひそかな思いを寄せる女子中学生との交流を通して、性の目覚めなど大人になることの意味を静かにゆったりとリリカルに捉えた名品である。
もともと北方謙三は少年を描くのが巧い。『水滸伝』に出てくる楊令など極めて印象深いし、名作『眠りなき夜』『檻』などの脇役、「老いぼれ犬」こと高樹良文刑事の少年時代を描いた『傷痕』(1989年)も忘れがたい。太平洋戦争の終戦直後の東京で、飢えをしのぎながら、家も家族も食料もない焼跡で、必死に生き残ろうとする13歳の少年たちの物語だ。状況は、現代の少女以上に過酷。大人が子供の食料を奪うこともあり、子供は牙を剥いて生きなければならない。「幼く、弱々しかったが、心は獣だった」という一節が出てくるが、まさに生きるか死ぬかの瀬戸際なのだ。大人たちはみな狡猾。暴力、騙し、死、殺人とくぐるべき門が次々と開かれ、痛ましくも切々たる結末へと向かう。
その大人になるためのくぐるべき門がより残酷なのは、森之助のほうかもしれない。前作『絶影の剣』で、幼子の首を刎ねさせられ、景一郎によってそれを何度も思い出させられる。前作の死闘では、まだ景一郎がたえずいて、随所で助けられたが、本書では景一郎はほとんど姿を見せず、森之助の剣ひとつにかかっている。しかも相手は柳生一族で、強いのである。「はじめから、死域」、つまり生と死の間に入ることになる。何度も描かれる立合、決闘、果たし合いの場面がもうたまらない。何よりも文体の成果だろう。
北方謙三が山田風太郎との1988年の対談(『小説現代』1988年2月号所収「小説の虚構は酒中に在り」。山田風太郎『風来酔夢談』=富士見書房収録)で、「実はぼく、来年から歴史小説を書くんです」といい、山田とこんな話をしている。
北方: ぼくは、これはもう読者にとってまったく新しい人間が出てきて、すごい劇的なドラマを展開するというふうに書けば大丈夫だろうと思っているんです。
山田: いまの読者が知らないことを説明しようとすると小説の原形をまずこわしちまう。あなたのはすごいリズムで成り立っているような小説だけども、長々説明を入れたらそんなリズムがなくなっちゃう。いまじゃ、関ヶ原も説明しないとわからない読者が多くなってるから。
「読者にとってまったく新しい人間が出てきて、すごい劇的なドラマを展開するというふうに書けば大丈夫」というのは、景一郎シリーズにあてはまるだろうし、長々と説明をいれないのも本シリーズの特徴のひとつだろう。ほかの作家なら詳しく丁寧に時代背景に頁をさくのだが、北方謙三はそうしない。いきなり現場へと読者をつれていくのだ。「あなたのはすごいリズムで成り立っているような小説」だから「長々と説明を入れたらそんなリズムがなくなっちゃう」というのも、北方謙三節の要点をついた見事な指摘だ。そう文体のリズムなのだ。リズムが素晴らしくいいのである。
そのリズムとも関係するが、「説明を省略した簡潔にして直截、形容句を排除した北方節は、剣豪小説にとって目玉ともいうべきか、聖域と言える大切な場面で強烈な力を発揮する」と称賛しているのが、俳優でエッセイストだった児玉清である(以下引用は、新潮文庫版の解説より)。
決闘の場面において、「北方謙三は極端と言えるくらいに言葉数を少なくするときがある。両者の動きを的確な名詞と動詞を間隔を空けてピシッと配置し、あとは読者の想像に委ねる」が、「これが凄まじいほどリアリティを生み出し、恰も両者の息遣いを耳元に聴くようなぞくぞく感を味わえるのだ」といい、対峙したときの「気」や「斬撃」までの心の動き、さらには「皮一枚の見切り」など、「心・技・体の連繋した一連の動作を凝縮し且つあまねく表現できる術を作者は薬籠中のものとしている」「北方剣豪小説の大いなる醍醐味の一つ」と絶賛している。そう、まさにこの場面そのもの、心の動きひとつひとつを喚起させる“凄まじいリアリティ”こそが小説の醍醐味なのだ。
ここでもう一度冒頭の少女ハードボイルドの話になる。少女ハードボイルド以前のハードボイルドや冒険小説などアクションの多い物語では、もっとも傷つきやすく、それでもまだまだ立ち直ることもできて、生き残ることのできるのは少年だった。少女をヒロインにするにはまだ早かった。いたいけな少女のイメージがあり、死の危険を乗り切る物語を牽引するのにリアリティがなかった。しかしいまや少女こそが死の危険と紙一重の状況を生きる存在として最適なのである。
ただ、誤解してほしくないが、少年だからだめで少女だからいいのではない。重要なのは、なにがいちばん読者に世界を生々しく感知させるのかなのである。海外の少女ハードボイルドと同じく『傷痕』や『遠い港』がいいのは、誰もが経験する少年(少女)時代を懐かしんだり、忘れていた手触りを思い出させるからではない。いまそこにある世界、すなわち生への不安や恐れや喜びを、直接的に生々しく読者に喚起させるからである。感受性を十全に開いた主人公の生活があり、読者の各々が体験した(または体験するだろう)人生の一断面と直截につながっているからこそいいのだ。
この読者の興味のありかたは、逆にいうなら、世界中で起きている終わらない戦争や伝統的な価値観の崩壊、貧困や差別の中で、かよわき者たちがいかにタフとなり、生き抜くのかに読者の関心事があるからでもある。精神を破壊してやまない戦場で人はどうなるのかをじっくりと見てみたいのだ。大人よりもはるかに不安定でもろい10代がいいし、少年よりも少女のほうがより衝撃度があがるから少女のほうがいいのだが、では、15歳の本書の森之助はどうなのかといったら、森之助のほうがはるかに世界を生々しく体現してくれる。それは幼いころから数々の試練を与えられ、負荷をかけられ、死地をくぐりぬけてきたからである。本書でも、その試練と負荷と死地はとびぬけて多い。敵との戦いだけではなく、兄の景一郎の存在そのものが大きく影を落としているからだ。「自分を縛りつけているのは、兄ではないのか。自分は、兄に縛りつけられて、身動きもできないでいるのではないのか。(略)呪縛を断ち切る。それができなくて、自分が自分でいられるのか」(418頁)「兄がなんだ。自分より、20年ほど早く生まれただけではないのか。20年の歳月は埋められない。埋められないのは、歳の差だけだ。5年前と較べても、自分と兄の力量の差は、信じられないほど大きく縮まった。/兄に勝てるのだ。負けはしないのだ。それひとつだけを、森之助は思い続けた」(419頁)とあるのは、5年後の20歳のときに兄と真剣で立会うことになるからである。それが宿命だからだ。日向景一郎シリーズは、その戦いをもって完結するが、どういう結末を迎えるかは次回の『寂滅の剣』に詳しい。痺れますよ。
最後に余談めいたことをひとつ。「まさに疾風怒濤の森之助の青春冒険物語が展開する」「これほどワクワクして読める面白剣豪小説は、この世に、そうざらにはありませんよ」「北方剣豪小説は、有難くて、うれしくて、最高に面白い冒険小説の夢中クラス本なのだ」とは新潮文庫版の児玉清氏の言葉だが(素晴らしい解説なのでぜひ読まれたい)、剣豪小説のみならず、海外の少年・少女ハードボイルドや戦争小説にも比肩する傑作として注目してほしい。海外ミステリを原書で読んでいたほどの海外ミステリファンだった児玉清氏と対談したことがあるけれど(驚くほどの読書量、熱き言葉と優れた見識の数々には魅せられてしまった)、もしもご存命ならば、勝手な解釈といわれそうだが、僕の見方に賛成してくれたのではないか。海外ミステリファンにお薦めしたい傑作シリーズだ。