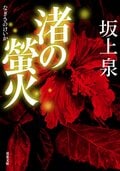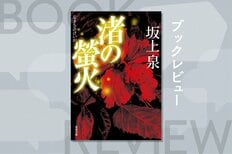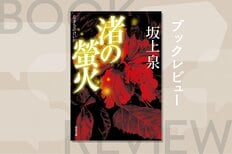坂上泉氏による昭和史×タイムリミットサスペンス小説『渚の螢火』を原作としたドラマ「1972 渚の螢火」が、10月19日からWOWOWで放送・配信される。
舞台は、1972年の沖縄。本土復帰を間近に控えたこの地で、100万ドルを積んだ現金輸送車が襲われた。アメリカ占領下の沖縄ではドルを使用していたが、本土復帰に際して円に切り替える必要があり、その金が狙われたのだ。この事件が日本政府やアメリカ政府に知られれば、重大な外交問題に発展しかねない──。
秘密裏に解決するため、琉球警察の特別対策室班長に任命された主人公・真栄田太一を演じるのは、高橋一生さん。真栄田の人物像、ドラマの見どころなどについて、お話をうかがった。
文・取材=野本由起、写真=川しまゆうこ
集団が残した記録と個人の記憶は大きく違う
──高橋さんは、「連続ドラマW 1972 渚の螢火」のどこに魅力を感じて出演オファーを受けたのでしょうか。
高橋一生(以下=高橋):この作品には、沖縄の本土復帰という歴史的背景があります。そのため、お話をいただいた時は「娯楽作品にできるだろうか」と考えました。
そこで台本を読んだところ、出自も置かれた立場も違うさまざまな人物が登場することがわかりました。思いは同じでも、出力の仕方が違うだけで大きく道を違えることもある。そういった差異がキャラクターごとに描かれていたので、きっと娯楽として成立するだろうと思いました。さらに、「平山さん(平山秀幸監督)だから大丈夫」という思いもあって出演を決めました。
──沖縄返還は高橋さんが生まれる前、1972年の出来事です。撮影に入るまで、このテーマにはどれくらいの関心がありましたか?
高橋:もともと僕は沖縄が好きで、旅行で訪れるたびにこの地の歴史を感じていました。ただ、本土復帰にあたってはわずか1日で車が左側通行になったり、信号機が替わったりしたそうです。頭ではわかっていても、芝居で疑似体験するとだいぶ違うので、その点は意識しながら演じました。
──使っている貨幣が1日でドルから円に切り替わるというのは、今の私たちからはなかなか想像がつきません。
高橋:だからこそ、当時を知る方に話を聞いてみたいと思っていたのですが、今回の撮影ではそれがとてもうまくいったんです。本土復帰当時に沖縄にいた人、コザ暴動(1970年、米兵が起こした交通事故をきっかけに、群衆が米軍関係車両を焼き討ちした事件)に参加した人、その様子を見ていた人に、たまたまお会いすることができました。
やっぱり教科書で教わったこと、自分が想像するものとは、全然違うんです。集団が残した記録と個人の記憶の違いがはっきり分かれていることを体感できて、興味深かったです。
──どのような違いがあったのでしょうか。
高橋:例えば、米軍基地に食料などを盗みに入る「戦果アギヤー」が捕まった場合、どういう制裁を受けたか想像できますか?
──いえ、どうなったのでしょうか……。
高橋:厳しく罰せられることもあれば、場合によっては殺されることもあったと想像できると思います。でも、僕が聞いたのは、それとは違う話でした。
捕まった子どもが応接室に通され、「これは大変なことになった」と思っていたら、目の前にポップコーンバケツくらいの大きなコーラを出されたそうです。そして、米軍の司令官から「これを一気飲みしたら帰してやる」と言われた、と。
──予想外の展開ですね。
高橋:いくら教科書で学んでも、実際に現地に行かないとリアルなことはわからない。しかも、相対した人によっても対応が違うでしょうから、「アメリカはこうだった」とひとくくりにすることもできません。実際は、個として向き合うわけですから。
僕はたまたま商工会議所の方から話を聞くことができましたが、その方が体感した沖縄返還前夜の世界は僕が想像しているものとは圧倒的に彩度が違いました。沖縄に入ってひと月過ごす中で、どんどん当時の沖縄がビビッドに感じられるようになっていったので、その点はとても助かりました。

真栄田は、アイデンティティが揺らいでいる人物
──今回、高橋さんが演じた真栄田はどんな人物でしょうか。役と向き合い、高橋さんは真栄田に対して何を感じましたか?
高橋:真栄田の高校の同級生で、同じ琉球警察の刑事である与那覇は、真栄田のことを「あいつは何を考えているのか、昔からわからなかった」と言います。実は僕も、かつて同じことをよく言われていましたので、その点にシンパシーを感じました。
本人としては、他意はないんです。言葉にするのが照れくさい、あまり説明したくないという思いが根底にあって、相手がどう受け取るかはどうでもいいと思っていたんでしょうね。真栄田の「あまり語るべきではないし、語ってもわかってもらえない」という思いにも共感したので、そういう一面にフォーカスして役を理解していきました。
──真栄田には、かたくななところがあるのでしょうか。
高橋:かたくなではないんです。自分が「こうだ」と信じるものはあっても、自身のアイデンティティが揺れていますし、違う価値観を持つ人が現れると気持ちも揺れ動いてしまう。
そういう意味では、真栄田はとても素直だと感じます。虚勢を張っているわけではありませんし、とてもいい人間だなと思いながら演じていきました。
──今のお話にもつながりますが、真栄田は石垣島出身で、沖縄本島で高校時代を過ごし、本土の大学へ進学し、今は琉球警察で刑事をしています。こうした出自もあって、彼は「自分は何者か」というアイデンティティを問い続けています。その点については、どう感じましたか?
高橋:もっと引いた視点で見ると、あの時代の日本は、国家としてのアイデンティティがまだ揺れていたと思うんです。ですから、真栄田という人間と当時の日本が重なるように感じました。ある意味、日本の縮図的なものが真栄田の中に詰まっていたのではないかと思います。
戦後の日本は世界情勢における立ち位置も揺れていましたし、安保闘争や学生運動が起き、思想がぶつかり合うなか、日本という国を大きく変えられるのではないかと考えていた人もいたと思うんです。そのような時代背景のなか、「日本人として生きていくためには」「うちなんちゅ(沖縄人)として生きていくためには」とそれぞれが考えていたんじゃないかと思うので、その点は意識して撮影に臨みました。
──ドラマ化にあたり「自分がどこで生まれたかによってその人の人生が最初から決まってしまいかねないレールが存在している」と、コメントされていました。さまざまな登場人物の中でも、出自が現在の価値観に特に影響を与えているのはどの人物だと思いますか?
高橋:やっぱり、沢村一樹さん演じる川平じゃないでしょうか。川平と真栄田は、対照的な存在だと思います。真栄田も、川平と同じような出自で同じ時代に育ったら、同じような道のりをたどっていたかもしれません。沢村さんとはいろいろとお話をさせていただき、セリフごと変えたシーンもありました。
──普段から、そうやってドラマを作り上げていくことが多いのでしょうか。
高橋:あまりないです。それに、セリフを変えるのはあまりやるべきではないと思っていて。ただ、ある場面で実際にその時間軸を生き、肉体を持ってその場に立った時、自分が腑に落ちるか落ちないかは非常に慎重に考えています。ごく短いシーンではありましたが、その場面は少しセリフや流れを変えさせていただきました。どのシーンなのかは、あえて明かさずにおきたいと思います。
〈後編〉に続きます。
「連続ドラマW 1972 渚の螢火」
10/19(日)放送・配信
毎週日曜午後10:00
※第1話無料放送(全5話)
出演:
高橋一生
青木崇高 城田優
清島千楓 嘉島陸 佐久本宝 広田亮平 MAAKIII 北香那 Jeffrey Rowe 藤木志ぃさー ベンガル
沢村一樹 小林薫
原作:坂上泉『渚の螢火』(双葉文庫刊)
監督:平山秀幸 脚本:常盤司郎 倉田健次 音楽:安川午朗
制作プロダクション:東北新社 製作著作:WOWOW