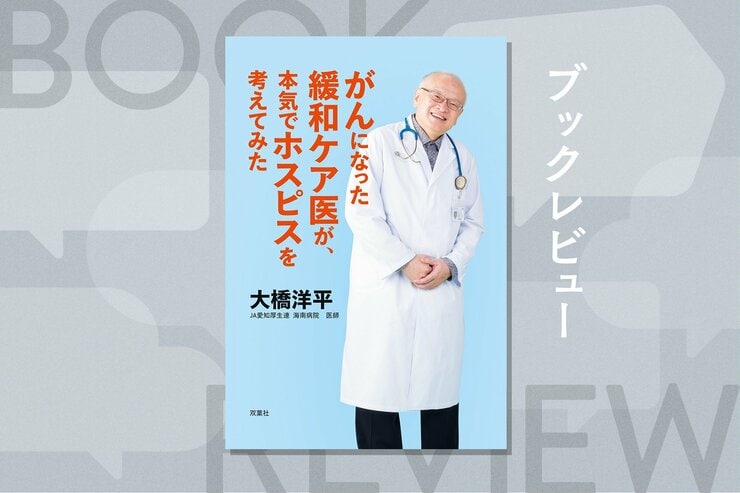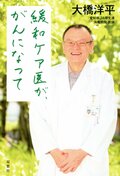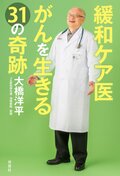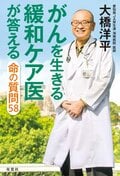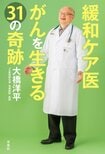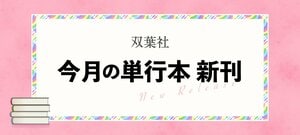一生の間に「がん」と診断される確率が、男性で6割を、女性で5割を超える時代。ただ、すべての治療を終えても、楽に生きるのをあきらめる必要はないという。
「最後までお酒やタバコを楽しみたい」「とにかく痛いのだけはイヤ」「家族に負担をかけたくない」など切実な願いを叶えてくれるルート選びを、自らもがんと闘う緩和ケア医が丁寧に指南する。
『小津安二郎 粋と美学の名言60』をはじめ、老いと人生についての深い洞察で知られる文筆家・米谷紳之介さんのレビューで、『がんになった緩和ケア医が、本気でホスピスを考えてみた』の注目ポイントをご紹介します。
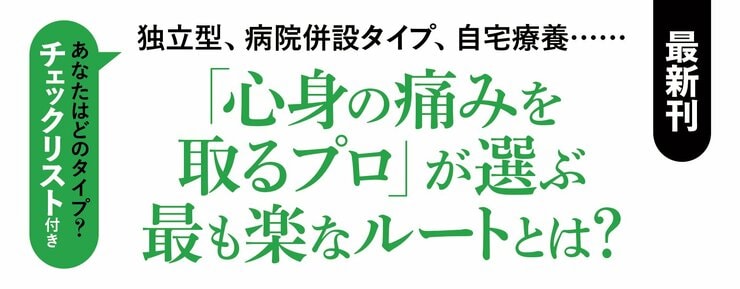
■『がんになった緩和ケア医が、本気でホスピスを考えてみた』大橋洋平 /米谷紳之介 [評]
10年ほど前だっただろうか。すでに全身がんを公表していた女優の樹木希林さんが、森の小川に気持ち良さそうに浮かんでいる正月の新聞広告に目を奪われた。
コピーがまた衝撃的だった。
「死ぬときぐらい好きにさせてよ」
この言葉が多くの人の心に刺さったのは、好きに死ぬのが難しいからだ。
ぼくに限らず、漠然と平均寿命くらいは生きると考えている人は多いと思う。そして、できることなら、それまでは元気でいて、最期はあまり苦しまずに亡くなる「ピンピンコロリ」でありたいと願っている。しかし、自分の周りを見渡しても、そんな理想通りの生き方をした人はめったにいない。
確率的に高いのは最期を病気で迎えるケースだろう。例えば、がん。一生の間にがんと診断される確率は男性で6割を、女性で5割を超える。問題はがんにかかり、治療ではどうにもならなくなって以降である。さて、どこで、どのように暮らすか。これを真剣に考えることは「死ぬときぐらい好きに」したかったら、避けては通れない。
ベストセラー『緩和ケア医が、がんになって』で知られる著者は、本書でがんの積極的な治療を終えた後のルートとして次の3つを挙げている。
① 独立型ホスピス
② 病院併設型ホスピス(緩和ケア病棟など)
③ 在宅療養
当然、それぞれメリットもデメリットもある。
ちなみに、冒頭のチェックに従えば、ぼくには②の病院併設型が向いているようだ。①の独立型も「家族の負担が少ない」、「安心・快適さが優先される」などの点では同じだが、決定的に違うのは「痛み」や「苦しみ」への対応。がんの進行にともなう苦痛や緊急時に迅速に対処できるのは、専門スタッフが常駐している②だという。
国立がん研究センターが、がん患者の遺族を対象に行った調査では、身内が亡くなるまでの1ヶ月間、患者が「体の苦痛が少なく過ごせた」と感じた割合は4割にも満たない。意外なのは排泄できないことの苦しみで、七転八倒するほどだという。甘やかされて育ち、「痛み」や「苦しみ」にはからっきし弱いぼくにはやはり②がぴったりだ。
①にも魅力を感じるのは酒やタバコなどのルールが緩やかだから。この期に及んで、酒、タバコかと思われるかもしれないが、がんが進行すると、それまでできたことが、どんどんできなくなっていく。コーヒースプーンでさえ重く感じるようになる。喫煙は愛煙家にとって自分が元気だった頃と変わらずできる数少ない行為なのだ。とっくにタバコをやめたぼくにもその気持ちは痛いほど分かる。
もちろん、③の在宅療養も有力な選択肢である。家族の負担というマイナスのカードを考慮しなければ、住み慣れた我が家で、家族と過ごしたいと思うのは自然な感情だ。
現時点でぼくはがんに罹患していないが、がんで闘病中の人にはより切実で、深刻な問題を扱った本である。しかし、重苦しさを感じさせないのは、本書の根底にホスピスは「死ぬための場所」ではなく、「生きるための場所」だという思想が流れているからだ。もう一つは著者の人柄。競馬が大好きで、医者なのにCT検査が大嫌い。ときおり関西弁が顔を出す洒脱な文章は人懐っこさもあって、すいすい読める。だから、どんなホスピスを選ぶべきか、そのポイントや現状の課題についての指摘に「なるほど」と膝を打ち、読後は関西人でもないのについ関西弁でつぶやきたくなる自分がいる。
「先生、人生を精一杯生きるためにも、いろんなホスピスに行って、ちゃんと見学してみなあきまへんな」
なお、聞くところによると著者が使うのは関西弁ではなく、三重弁らしい。