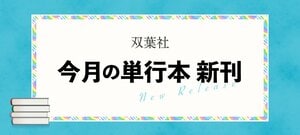※年間10万人に1~2人くらいの発症率の希少がんGIST(ジスト)に“0.001%の確率で大当たりした”と、語るのは医師・大橋洋平さん。終末期がん患者に関わる、現役の緩和ケア医である。2018年6月に胃に直径10cmもの巨大なジストを発病、抗がん剤治療を続けながら、2021年10月現在も緩和ケア医としての活動を行っている。
もっか闘病中の大橋さんが、自らを筆頭に苦しむ全てのがん患者の苦痛を和らげられたら、と彼の気付きをまとめた著書『緩和ケア医が、がんになって』(双葉社/2019)は、数多くのメディアで反響を呼んだ。
本書『緩和ケア医 がんと生きる40の言葉』は、著者が闘病の中で感じたしんどさや心の葛藤とどう向き合ってきたか、どのようにして「心の免疫力」を高めてきたかを医師としての見解も交えつつ、あくまで一個人としての言葉でまとめた、いわば「言葉の処方箋」である。
明るく、正直に、自分らしく、しぶとく生きる緩和ケア医・大橋洋平さんの著書第三弾! 本書の内容を本文から一部抜粋のうえ以下にご紹介いたします。
(※出典:国立がん研究センター希少がんセンター)
***
緩和ケアの病棟では、すべての治療を終えたがん患者さんのために、次なる一手、つまり「痛み・苦しみを和らげる医療」を施します。よく、「もはや打つ手のない患者が最後に回されるところ」といった誤解をされている方も多いですが、まったく違います。打つ手がないどころか、治療が終わった後も、楽になるためにやれることはまだまだある。長年、緩和ケア医として、おひとりおひとりのしんどさを鎮めるお薬を処方し、かつ、心の痛みに向き合ってきました。
なかでも心の痛みを取り除き、患者さんご自身の納得を生み出す威力を発揮したのが「傾聴」のスキルです。
たとえば、相手の口から“もう、生きているのがツライ”という言葉が漏れたら、普通は、慌てて声をかけたり、“悲観したらダメ! 元気出して!!”などの言葉で励ましがちですよね。でも、傾聴では、聴き手の個人的な感情を差し挟むことはありません。
生きているのがツライと思うんですね? まずはこのように返すのが鉄則。
聴き手の安易な正解を言ってはダメなのです。なぜならば患者さんにとっての正解は、ご本人のなかにしかないから。
どうにもならない状況につかまってしまった時。もがけばもがくほど、どうしていいのかわからなくなります。どれも正解のようでいて、どれも不正解のような気がしてくる。そもそも正解なんかあるものなのか。いっそどこかに売っていれば、買いたいぐらいです。緩和ケア医の私だって、いざ、主治医から治療の終了を告げられたら、身も世もなくうろたえ、取り乱すでしょう。間違いなく。
“標準治療でやれることがない。ってことは終わりってことだ。転移もどんどん広がるだろう。痛いのはイヤだ……”
痛いのは、イヤだと思ってるんですね?
“そりゃ、イヤだ。でも……”
医療者の的確な傾聴を得て、しゃべりながら考え、考えながらしゃべるうちに、ちょっとずつ見えてくるものがあります。
もう、これ以上の治療は望めないという変えられない状況と、「痛い、苦しいのは絶対イヤだ!」という自分の願い。でも、両者のズレを少しでも縮める手立ては、ないわけではない――。
そうか。オレはまだ生きてるし、いつまでかはわからないけど、これからも生きていく。そのためには、痛い、苦しいのはカンベンだ。治療はあきらめるけど、楽に生きるのはあきらめない! 頼む。痛い、苦しいのだけは全部取ってくれ――。
そんなふうに価値観が転換できたら、とっても楽になるでしょう。自分なりの正解を発見して、納得まで持っていけたからです。自分自身と折り合いがつき、心から納得できると、何かがストンと腹に落ちる感覚がありませんか? 同時に、自然と肩の力も抜けるのではないでしょうか。力みがとれると、気負いもなくなる。気負いがなくなると、不思議とやる気が戻ってきます。やる気は、生きる力と同義です。前を見るのがつらければ、無理に見なくたってかまわないと思います。みんながみんな前を向くのも、かえって気持ち悪い。後ろ向きだって、いいじゃないですか。